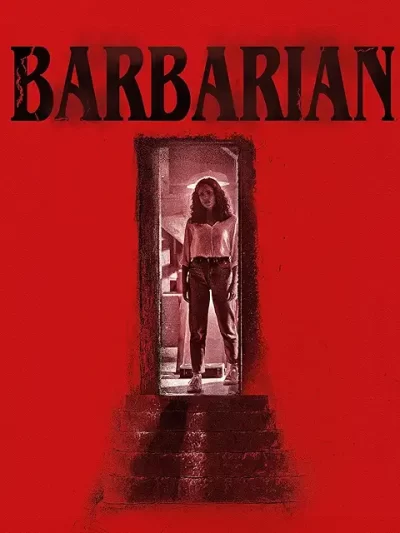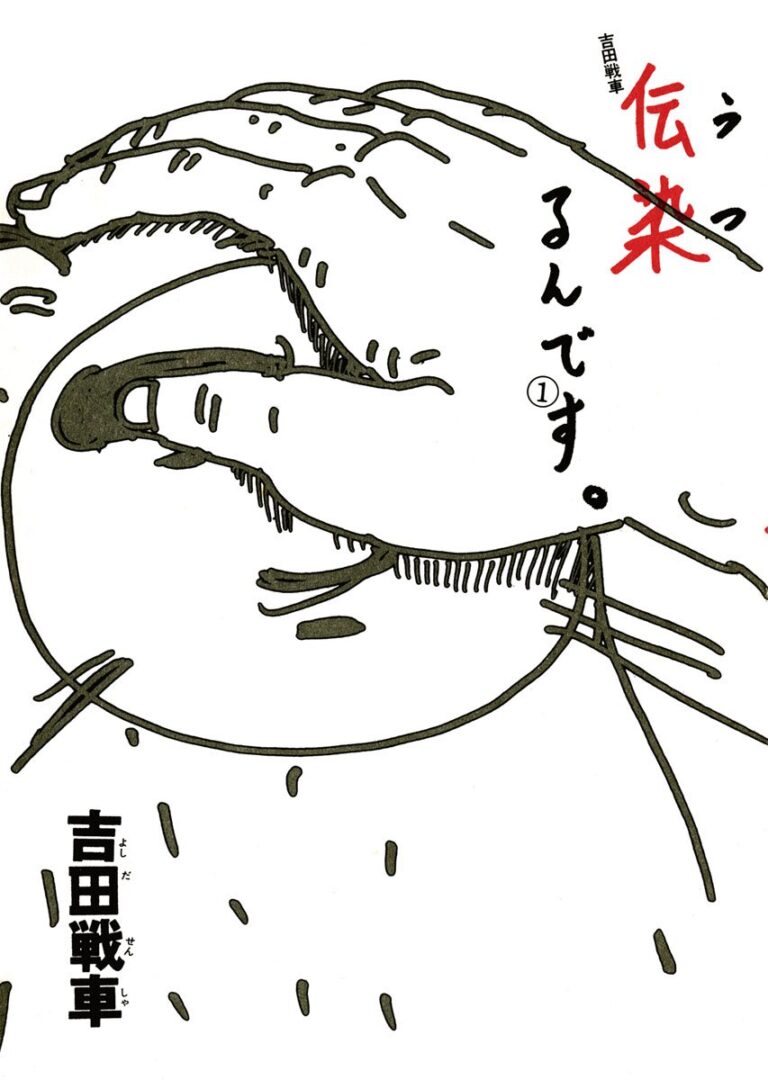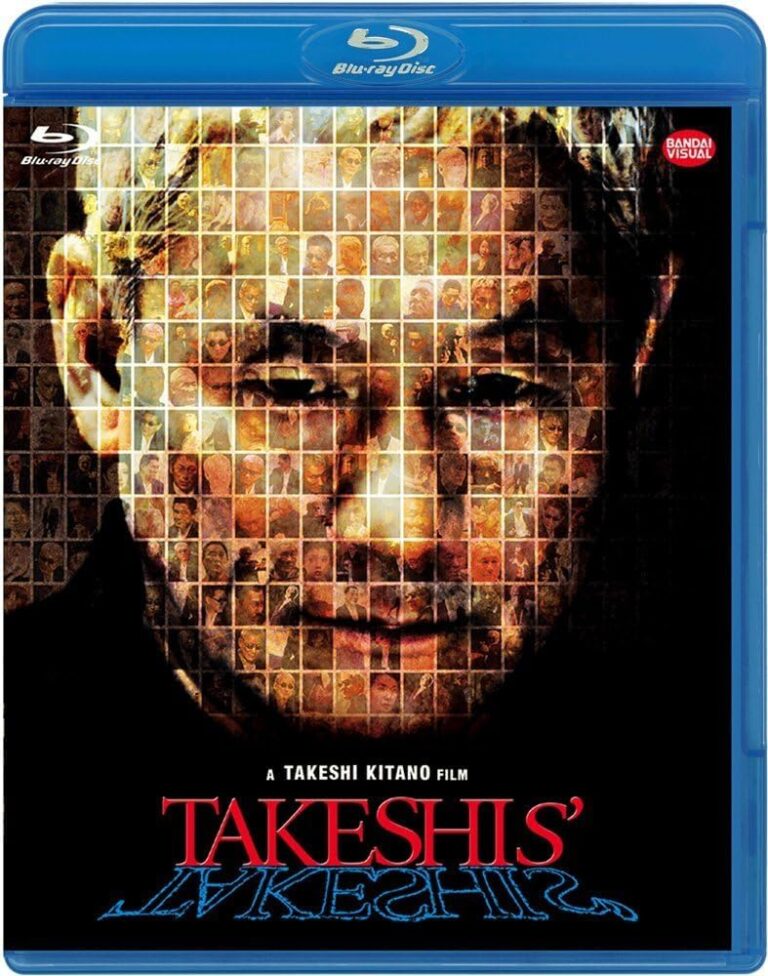『TITANE チタン』(2021)
映画考察・解説・レビュー
『TITANE チタン』(原題:Titane/2021年)は、デビュー作『RAW 少女のめざめ』で世界を驚愕させたジュリア・デュクルノー監督が、金属と肉体、そして性別という境界線を鮮やかに破壊してみせたボディ・ホラー。ジム・ウィリアムズによる不穏で荘厳な旋律が響く中、物語は生物学的な常識を逸脱した、あまりにも衝撃的な「出産」へと突き進む。これは、他者と交わることの痛みを抱えたすべての魂へ贈られた、最も過激で、最も清らかな「愛」の定義を更新する革命的な一篇。
有機と無機の不快な融合
『TITANE/チタン』(2021年)において、あらすじを語ることほど無意味な行為はない。車とセックスして妊娠して、殺人鬼が少年になりすます。そんなB級映画的なプロットは、ジュリア・デュクルノー監督が仕掛けた罠に過ぎない。
本作の本質は、ナラティブではなく、観客の皮膚感覚を直接蹂躙するテクスチャーと、音響にある。これは映画という名の、視聴覚による拷問装置であり、同時にポスト・ヒューマン時代の新たな神話を描くための、極めて洗練された宗教儀式なのだ。
ボディ・ホラーという言葉を聞けば、誰もがデヴィッド・クローネンバーグの名前を想起するだろう。『ヴィデオドローム』(1983年)や『ザ・フライ』(1986年)といった作品で見せた、肉体とテクノロジーが無機質に融合していく、あの感覚。
しかし、デュクルノーの演出は、クローネンバーグのそれとは決定的に異なる。クローネンバーグの変容が、どこか臨床的でドライな乾いた観察であるのに対し、デュクルノーの画面は徹底的にウェットだ。
アレクシア(アガト・ルセル)の身体から流れ出るのは、鮮血だけではない。乳房や性器から分泌される、ドス黒いモーターオイル。この粘着質な液体の表現こそが、本作の視覚的コアである。
撮影監督ルーベン・インペンスのカメラは、この油と血の混合物が皮膚を伝う様を、マクロレンズで執拗に舐め回す。有機物(肉体)と無機物(金属・油)が、境界を失って混ざり合う瞬間の、ぬめり。
さらに、サウンドデザインがその生理的嫌悪を加速させる。ヘアピンが頭皮を突き刺す音、皮膚が裂ける音、そして体内のチタンプレートが軋むような金属音。これらのASMR的な強調は、観客に痛みを情報の伝達としてではなく、幻肢痛のような身体感覚として強制共有させる。
デュクルノーは、観客を安全な観測者の席に座らせない。我々の神経系にジャックインし、金属と同化していくアレクシアの苦痛を、我がこととして体験させるのだ。
ジェンダーという外傷
アレクシアが、行方不明の少年アドリアンに変身する場面。このシークエンスで特筆すべきは、アレクシアが行う「変身」が、単なる逃亡のための偽装を超え、「見られる客体(女)」としての自分への処刑であるという点だ。
モーターショーのコンパニオンとして、男性たちの欲望の視線を浴び続けてきた彼女。その象徴である美貌を、彼女は自らの拳で洗面台に叩きつけ、粉砕する。鼻が折れ、顔が歪むあの鈍い音は、社会が押し付けた女性らしさという仮面を叩き割る音だ。
ここで想起されるのは、ペドロ・アルモドバル監督の『私が、生きる肌』(2011年)だ。この映画では、狂気の医師によって強制的に性別を改造される悲劇が描かれたが、『TITANE/チタン』のアレクシアは、自らが執刀医となり、麻酔なしで自分自身を改造する。ここにあるのは、痛々しいほどの主体性の暴走。彼女は“女”を辞めるために、痛みを選び取ったのだ。
対するヴァンサン(ヴァンサン・ランドン)の描写もまた、鏡像的でありながら、より哀切を帯びている。彼は消防署という、テストステロンが充満する“男の園”の長だ。老いゆく肉体に抗うため、尻にステロイドを打ち込み、過剰な筋肉の鎧を纏う。
この姿は、ダーレン・アロノフスキー監督の『レスラー』(2008年)におけるミッキー・ロークと重なる。彼らは、社会や職務が要請する「強き男」「英雄」「父」というジェンダー・ロールを維持するために、自らの肉体を薬物で漬物にし、崩壊寸前まで追い込んだ。
つまり、アレクシアが女性性の破壊者なら、ヴァンサンは男性性の過剰な守護者=ドラァグ・キングなのだ。二人はベクトルこそ真逆だが、ジェンダーという鋳型に肉体を無理やり押し込むという点において、同じ地獄を見ている共犯者なのである。
映画の中盤に登場する、ピンクとブルーのネオンが交錯する消防署のダンスシーン。ここで描かれるのは、クレール・ドニ監督の『美しき仕事』(1999年)へのオマージュとも言える、ホモソーシャルな肉体の祝祭だ。しかし、デュクルノー監督はその中心に、胸をさらしで潰したアレクシアと、薬物で膨れ上がったヴァンサンを配置する。
二つの加工された身体がぶつかり合う時、そこで発生するのはエロスというよりも、互いの傷を確認し合い、性別の壁を超えて肉体の苦痛を共有する、悲痛な魂の共鳴だ。
ヴァンサンがアレクシアの正体に気づきながらも受け入れるのは、彼女の中に「性別に呪われ、肉体を痛めつけている同類」を見たからに他ならない。
デュクルノー監督は、肉体を破壊し尽くすことで、ようやく「男」や「女」という呪縛から解放される人類の未来を、残酷なほどの希望として提示してみせたのである。
テクノ・ゴシックの宗教画
終盤、映画のトーンは一気に神話的、あるいは宗教的な荘厳さを帯びていく。
アレクシアの出産シーン。ここでデュクルノーは、エイリアン誕生のようなSF的恐怖ではなく、新たな救世主の誕生として演出している。
燃え盛る炎、消防士たちの視線、そして油と血にまみれて産み落とされる、金属の脊椎を持つ赤子。この構図は明らかに、キリスト教美術における聖母子像(ピエタ)や、降誕の図像学を引用しつつ、それをポスト・ヒューマン的な素材で再構築したものだ。
ヴァンサンがその異形の赤子を抱きしめるラストショット。ここで重要なのは、彼が理解したから愛したのではなく、理解不能なまま受容したという点だ。
カメラはヴァンサンの表情をクロースアップで捉える。そこにあるのは恐怖でも嫌悪でもない。純粋な信仰に近い慈愛だ。これは、人間中心主義(ヒューマニズム)の終焉と、機械と融合した「新しい人類」への祝福である。
デュクルノー監督は、グロテスクな特殊メイクと暴力的な音響の果てに、生物学的な繋がりを超越したアガペー(神的な愛)を出現させた。『TITANE/チタン』は、古い肉体と古いジェンダー観を焼き払い、廃油の中から新たな神を産み落とすための、現代の「創世記」なのである。
- 監督/ジュリア・デュクルノー
- 脚本/ジュリア・デュクルノー
- 製作/ジャン=クリストフ・レイモン
- 撮影/ルーベン・インペンス
- 音楽/ジム・ウィリアムズ
- 編集/ジャン=クリストフ・ブージィ
- 美術/ローリー・コールソン
- 衣装/アン=ソフィー・グレッドヒル
- TITANE チタン(2021年/フランス、ベルギー)
![TITANE/チタン/ジュリア・デュクルノー[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/818bFu6BCeL._AC_UL640_FMwebp_QL65_-e1765021403471.webp)
![ヴィデオドローム/デヴィッド・クローネンバーグ[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/51x-xirXrUL._AC_UL640_FMwebp_QL65_-e1770940888251.webp)
![レスラー/ダーレン・アロノフスキー[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/714H2qUiELL._AC_UL640_FMwebp_QL65_-e1768469085511.webp)