キューブリックとアーサー・C・クラークが挑んだ、究極の“センス・オブ・ワンダー”
優れた映像作品は、それ自体が全てを言い尽くしているものである。その典型例こそ『2001年宇宙の旅』(1968年)。
蓮實重彦氏だろうが双葉十三郎氏だろうが、誰もがこの映画の前では言葉の無力さを痛感させられてしまうことになる。ましてや一介の貧乏サラリーマンである私には荷が重すぎるというものだ。
だからこれでオシマイ!…え?短すぎるって?…たしかに。では、無理を承知で努力してみよう。修辞法なんてクソ食らえ!理論武装はその後だ。
紋切り型のクリシェではあるが、『2001年宇宙の旅』はやはり“驚異の映像体験”である。シニカルなブラック・ユーモリストであるキューブリックも、この作品に関しては一切のアイロニーを自ら封じ込んだ。リアリズムを追求した客観的視点をよく「神の視点」というが、これ以上の「神の視点」はない。
何てったって、キューブリックと原作者アーサー・C・クラークが挑んだのは「神」そのものを描くことなのだから。無機質で整然とした冷徹な「神の視点」は、あらゆる具象をアイロニカルに表現することを許さない。
一切のエモーショナルな表現を排除したこの作品は、同様にあらゆるオブジェクトも均一化される。神の前ではヒトも動物も機械も等しき存在。
音楽にヨハン・シュトラウスの『青き美しきドナウ』や、リヒャルト・シュトラウスの『ツァラストゥストラはかく語りき』といったクラシックミュージックを採用したのは、その無限に広がる宇宙の静性を際立たせる手段。
『時計じかけのオレンジ』(1971年)におけるベートーベン、『フルメタル・ジャケット』(1987年)のミッキーマウス・マーチなどのような意図的なミスマッチを狙ったものではない。
コルビジェ風インテリアに代表されるアート・ディレクションもまた同様。ラスト、老人になったボーマンが横たわっているのはアール・デコ調の寝室だったりする。宇宙船内部の、いやに白っぽくてシンメトリカルな舞台装置は、無限に広がる漆黒の宇宙空間と鮮やかなコントラストを強調させる。
猿人たちの前に突如表れる謎の黒石盤(モノリス)、反乱する人工知能HAL2000、地球を見下ろす巨大な胎児スター・チャイルド。
この映画には数多くのクエスチョンマークが存在する。しかしよく考えてみれば、かのアインシュタインすら読み解けなかった宇宙の謎が、単純明快なロジックで描ける訳がない。
21世紀になった今現在ですら、「始まりの特異点」も「ビッグバン」もすべてが謎のまま。その難解さを享受し、ただただ圧倒されることが唯一の、そして絶対的に正しい対処なのだ。『2001年宇宙の旅』は究極の“センス・オブ・ワンダー”なんである。
最後に一言。この映画はシネラマ方式と呼ばれる大スクリーンで公開された作品だ。映画の隅々にまで計算し尽された映像設計は、絶対ビデオやテレビでは伝わってこない。
是非とも映画館に観に行って、製作30年以上たっても未だ色褪せぬ 「完璧な映像」に浸って下さい。
- 原題/2001: A Space Odyssey
- 製作年/1968年
- 製作国/アメリカ
- 上映時間/139分
- 監督/スタンリー・キューブリック
- 製作/スタンリー・キューブリック
- 脚本/アーサー・C・クラーク、スタンリー・キューブリック
- 撮影/ジョフリー・アンスワース
- 美術/トニー・マスターズ
- 編集/レイ・ラヴジョイ
- 衣装/ハーディ・エイミーズ
- SFX/ウォーリー・ヴィーヴァーズ、ダグラス・トランブル、コン・ペダーソン、トム・ハワード
- キア・デュリア
- ゲイリー・ロックウッド
- ウィリアム・シルベスター
- ダグラス・レイン
- レナード・ロジター
- マーガレット・タイザック
- ロバート・ビーティ
- フランク・ミラー
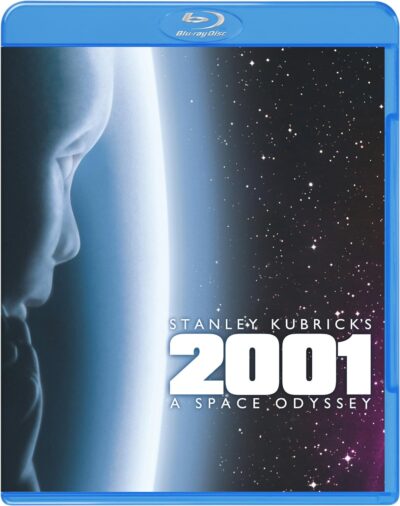
![時計じかけのオレンジ [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51xCxQ1DmcL.jpg)









最近のコメント