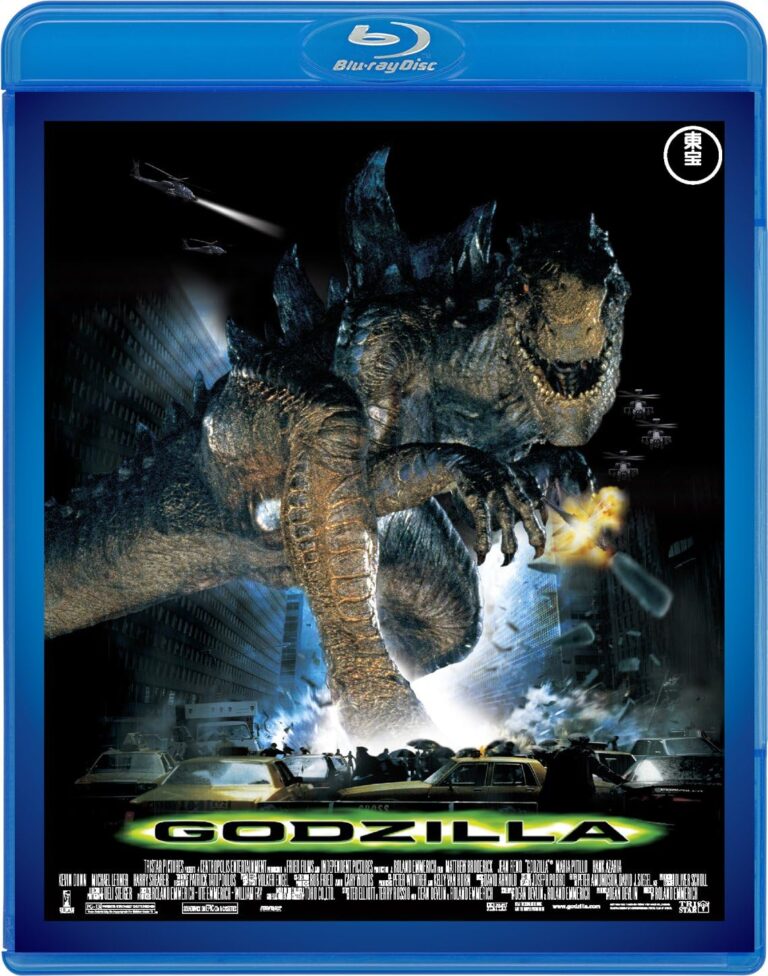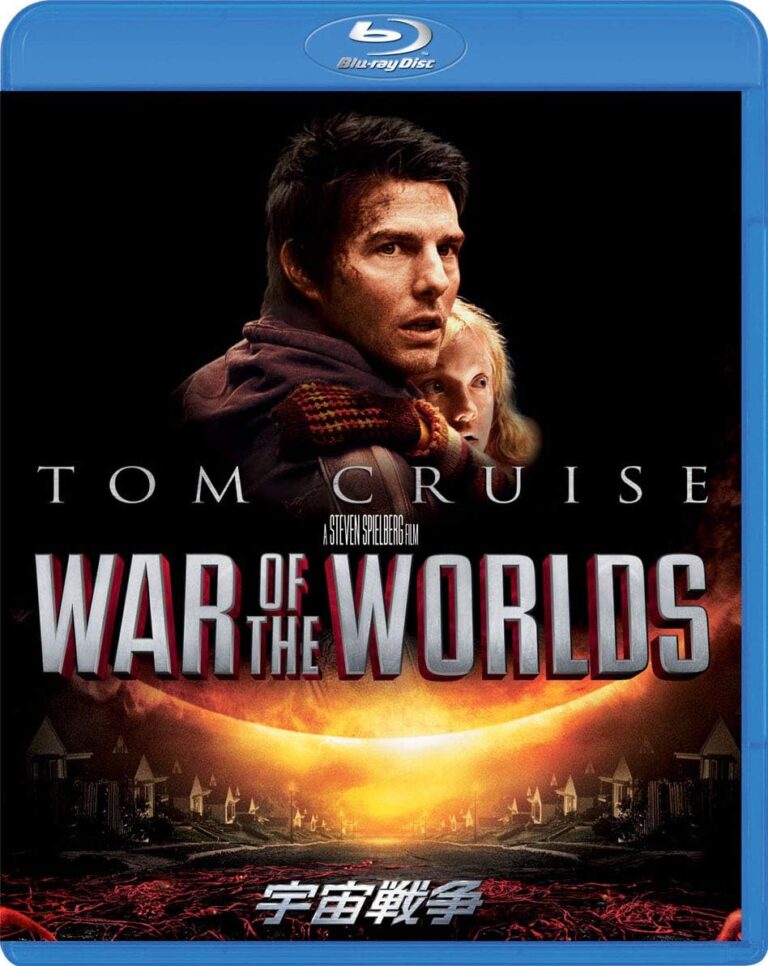『プレデター:バッドランド』(2025)
映画考察・解説・レビュー
『プレデター:バッドランド』(原題:Predator: Badlands/2025年)は、シリーズで初めてプレデターが主人公となる異色作。前作『プレデター:ザ・プレイ』で原点回帰の美学を提示したダン・トラクテンバーグ監督が、シリーズの根幹である「狩る者」と「狩られる者」の構図を根底から覆し、クリーチャーそのものを物語の主座に据えた。
落ちこぼれのプレデター
『プレデター:バッドランド』(2025年)は、1987年にアーノルド・シュワルツェネッガーがジャングルで泥を塗って以来、固定化されていた『プレデター』フランチャイズの文法を根底から覆す、コペルニクス的転回である。
これまでプレデターは常に理不尽な暴力装置であり、カメラは人間サイドに寄り添ってきた。だがダン・トラクテンバーグ監督は、『ザ・フライ』(1986年)や『キング・コング』(1933年)の系譜に連なる「モンスターへの感情移入」という劇薬を投入し、カメラを180度回転させ、あろうことかプレデター側に観客を放り込む。
本作の主人公デクは、一族の中でラント(発育不良のチビ)」と蔑まれ、父親であり族長でもあるニョールから追放された、プレデター界の負け犬。
これまでのシリーズでは、プレデターの個体差は装備の違いでしか表現されなかったが、本作では弱さとコンプレックスという人間的な感情を与えることで、キャラクターに前代未聞の奥行きをもたらした。
デクがマスクを外し、その醜悪な顎を震わせる時、観客はそこに恐怖ではなく、承認欲求に飢え、父性コンプレックスに苛まれる若者の孤独を見る。
トラクテンバーグ監督はインタビューで「『プレイ』では“ダビデとゴリアテ”を描いたが、今回は“ゴリアテの孤独”を描きたかった」と語っている。
その言葉通り、映画の前半はデクが未知の惑星ジェナの過酷な環境でサバイバルし、武器を現地調達し、傷つきながら成長していく様を丹念に追う。これはもはや宇宙版『コナン・ザ・グレート』(1982年)であり、あるいは言葉なき『ロッキー』(1976年)だ。
制作背景的にも、この挑戦はリスクの塊だった。セリフのない主人公で、しかも顔の表情が読みにくいエイリアンに、2時間近く観客を惹きつけられるのか?
そのために採用されたのが、徹底したフィジカル・アクティングと、環境音を重視したサウンドデザインだ。デクの息遣い、痛みに耐える唸り声、そして初めて獲物を仕留めた時の咆哮。これらが観客のシンクロ率を高めていく。
彼が自分の手で作り上げた粗末な槍を構える姿には、ハイテク装備で人間を蹂躙していたかつてのプレデターにはない、泥臭い生の実感が宿っている。
我々は初めて、プレデターを「それ(It)」ではなく「彼(He)」として認識し、彼の生存を応援してしまう。この視点の逆転こそが、『バッドランド』が成し遂げた最大の革命なのだ。
人間不在のヒューマニズムとウェイランド・ユタニの呪縛
『プレデター:バッドランド』を単なるプレデターの生態観察映画で終わらせず、SFとしての強度を与えているのが、エル・ファニング演じるウェイランド・ユタニ社のアンドロイド姉妹、ティアとテッサだ。
この映画には、感情移入できる生身の人間が主要キャラとしてほとんど登場しない。主役はエイリアンとロボット。人間性が完全に欠落したキャラクター配置の中で、逆説的に「人間とは何か」「魂とは何か」を問う。
エル・ファニングは1人2役を見事に演じ分けている。ティアは下半身を失い、廃棄寸前の状態でデクと出会う。彼女は壊れているがゆえに、システム(会社)の論理から逸脱し、同じくシステム(部族)から弾かれたデクと共鳴する。一方のテッサは、ウェイランド・ユタニの利益を優先する冷徹なマシーンだ。
デクとティア、言葉の通じない怪物と機械が、身振り手振りで意思疎通し、互いの欠損を埋め合わせるバディ・ムービー的な展開は、『ウォーリー』(2008年)や『第9地区』(2009年)を彷彿とさせる切なさがある。
デクはティアを道具として利用しようとし、ティアはデクを生存のための手段として利用する。しかし、共に死線をくぐり抜ける中で、そこに奇妙な信頼関係、もしくは種族を超えた共犯関係が芽生えていく。
特筆すべきは、ティアの瞳の奥でウェイランド・ユタニのロゴが起動するシーン。『エイリアン』シリーズの邪悪巨大企業が、プレデターの狩場である辺境の惑星でも相変わらず猛威を振るっていることを示す、絶望的な接続点だ。
ウェイランド・ユタニ社にとって、プレデターもアンドロイドも、等しく消耗品でしかない。この冷酷な資本主義の論理に対し、デクとティアは個としての尊厳をかけて立ち向かう。
アンドロイドのティアが流す涙(のようなオイル)と、プレデターのデクが見せる慈悲。人間よりも人間臭い彼らの姿は、我々ホモ・サピエンスがいかに傲慢な種族であるかを、皮肉たっぷりに突きつけてくる。
エル・ファニングは、CGキャラクターとの演技という難易度の高い撮影において、微細な表情の変化で機械に宿るゴーストを表現しきった。彼女の無機質な美しさが、泥と血にまみれたデクの野性味を際立たせ、映画に神話的なコントラストを与えている。
スペース・オペラへの進化とジャンルの破壊
『プレデター:ザ・プレイ』(2022年)がシリーズの原点回帰だったとすれば、『バッドランド』は完全なるジャンル破壊だ。
物語の舞台となる惑星ジェナは、奇妙な植物と荒涼とした砂漠が広がっている。さながらそれは、フランク・フラゼッタやメビウスのような、70年代サイケデリックSFアートのよう。
デクはこの惑星で、現地の生物や環境を利用して武器を作る。これは『プレデター:ザ・プレイ』のナル(アンバー・ミッドサンダー)がやったことの鏡写しだろう。
弱者が知恵を使って強者を倒すというテーマは継承しつつ、その主体をモンスター側に移したことで、物語は生存競争から、親殺し・組織殺しという革命へと変質する。
ラストシーン、デクが父ニョールに対して下す決断。そしてティアと共に新たな家族)を形成して宇宙へ旅立つ結末。これを「プレデターのディズニー化だ」「軟弱になった」と批判する古参ファンの声があるのも理解できる。
だが、シュワルツェネッガーと戦って自爆した1987年から38年。ただ人を殺すだけのマシーンとして消費され続け、『ザ・プレデター』(2018年)では迷走の極みに達していた彼らに、初めて物語と魂が与えられたことは、もっと前向きに賞賛されて良いのではないか。
『プレデター:バッドランド』が広げた風呂敷はあまりにもデカい。もはや地球のジャングルやロサンゼルスといった狭い箱庭には戻れないだろう。この映画は、シリーズを単なる怪獣パニックから、壮大なスペース・オペラへと進化させるための、荒療治にして極上の劇薬なのである。
エイリアン・ユニバースとの本格的なクロスオーバーへの布石とも取れるこの結末は、20年代後半のSF映画界における新たな台風の目となることは間違いない。
僕は断固、この映画を支持するものであります!!!!
- 監督/ダン・トラクテンバーグ
- 脚本/パトリック・アイソン、ブライアン・ダフィールド
- 製作/ジョン・デイヴィス、ブレント・オコナー、マーク・トベロフ、ダン・トラクテンバーグ、ベン・ローゼンブラット
- 製作総指揮/ローレンス・ゴードン、ジェームズ・E・トーマス、ジョン・C・トーマス、ステファン・グルーブ
- 制作会社/20世紀スタジオ
- 撮影/ジェフ・カッター
- 音楽/セーラ・シャクナー、ベンジャミン・ウォルフィッシュ
- 編集/ステファン・グルーブ、デヴィッド・トラクテンバーグ
- 美術/ラ・ヴィンセント
- 衣装/ナイラ・ディクソン
- 録音/オリバー・デュモント
- プレデター:バッドランド(2025年/アメリカ)
- プレデター:バッドランド(2025年/アメリカ)
![プレデター:バッドランド/ダン・トラクテンバーグ[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/81tErzwCjL._AC_SL1500_-e1768702253379.jpg)
![プレデター/ジョン・マクティアナン[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/81MOrEBaUyL._AC_UL640_FMwebp_QL65_-e1771288154684.webp)
![ウォーリー/アンドリュー・スタントン[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/71oeELBOsL._AC_SL1000_-e1759751076976.jpg)
![プレデター:ザ・プレイ/ダン・トラクテンバーグ[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/61jzfZRqLSL._AC_UL640_FMwebp_QL65_-e1765019068146.webp)