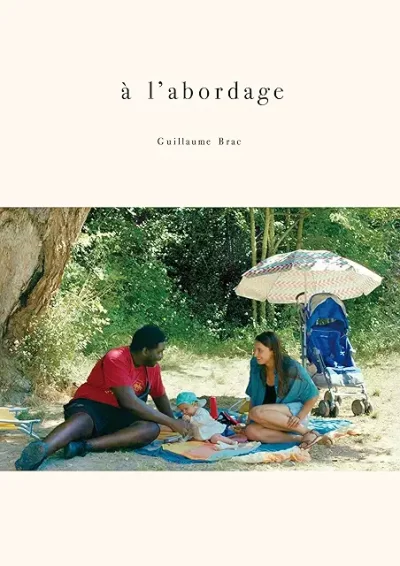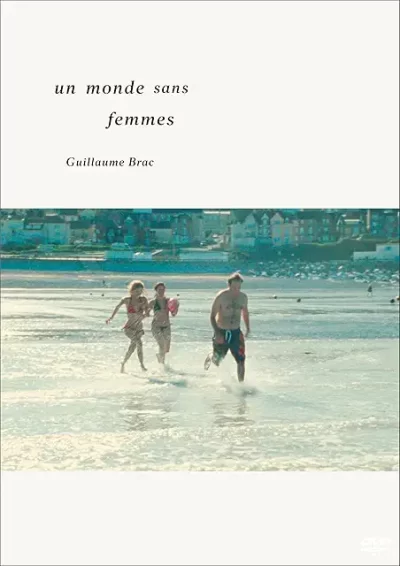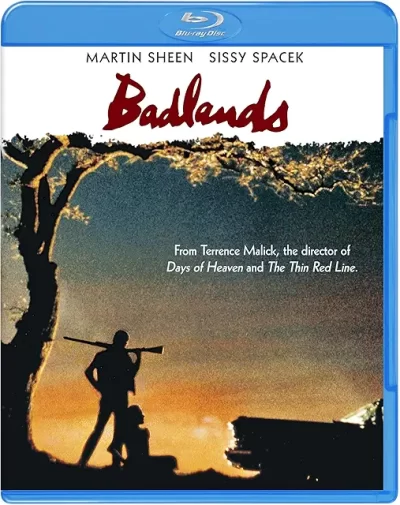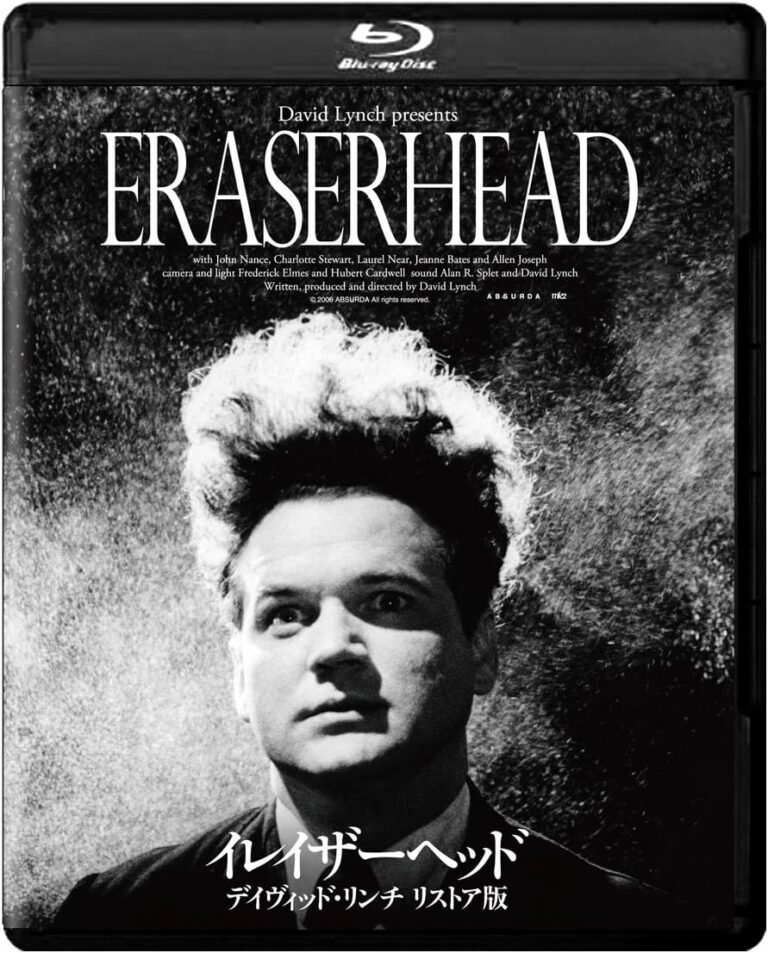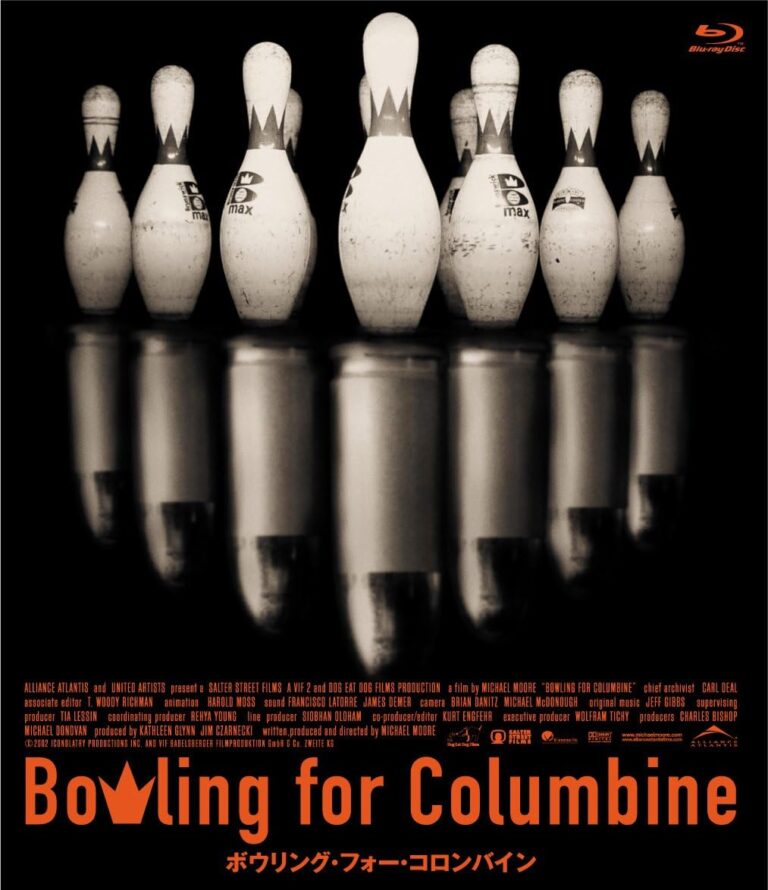『寝ても覚めても』(2018)
映画考察・解説・レビュー
『寝ても覚めても』(2018年)は、瓜二つの二人の男をめぐる女性の恋愛模様を描いた濱口竜介監督の異色ラブストーリー。朝子(唐田えりか)は自由奔放な青年・麦と出会い、強く惹かれていくが、彼は突然姿を消してしまう。数年後、彼と瓜二つの会社員・亮平と出会った朝子は、新しい関係を築こうとするも、かつての記憶に心を揺さぶられていく。東日本大震災を背景に、愛の幻影と現実の断絶が交錯する物語。
恋の高揚感、断絶の現実
美術館の静謐な空間で、東出昌大の背中を唐田えりかが追いかけていく。無言のまま距離を縮め、やがて唇が重なる。そのオープニング・シークエンスで、僕はすでに心を奪われてしまった。
人物の動線そのものがサスペンスのような緊張感を孕み、ヒッチコックの『めまい』を思わせる耽美性を漂わせる。映画はここで、恋の始まりを「避けがたい必然」として描き出す。同時に花火の音が響き、恋の祝祭性が過剰に付与される。このベタな表現をあえて正面からやることで、観客の感情は一気に燃え上がる。
だが、その陶酔は長く続かない。映画の中盤では、地震によって芝居小屋の看板が倒れ、それを東出が横向きに直す仕草が挟まれる。何気ない所作に過ぎないが、これは「震災後には、もはや以前の“正しい角度”に戻ることはできない」という寓話的宣言だろう。
濱口竜介は恋の高揚感を提示するや否や、その背後に横たわる断絶の現実を観客に突きつけるのだ。
幻影を愛するということ
この作品の核心は、朝子が「瓜二つの二人」を愛してしまうことにある。麦と亮平。名前も性格も異なるが、顔は同じ。朝子は亮平の存在に触れるたび、麦の幻影を思い出す。
彼女は、他者そのものを愛しているのではなく、他者に仮託した幻影を愛している。朝子にとって亮平は、実在の人物であると同時に、麦の幻影を呼び覚ます「記号」にすぎない。彼の顔は、失われた恋の記憶を永遠に召喚するスクリーンなのである。
言って終えば、恋に落ちるとは相手の内面を理解することではなく、ただ「顔」や「仕草」といった表層がこちらの欲望に触れてしまう出来事なのだ。瓜二つの人物を好きになるという倒錯は、恋愛が根源的に「幻影を愛する営み」であることを露わにする。
麦は幻影であり、震災前の日常に重なる。自由で奔放で、突然消え去る存在。彼は「もう戻らない世界」を象徴している。一方で亮平は震災後の日常そのものだ。真面目で安定的で、朝子の生活に寄り添おうとする。だがその顔は麦と同じであるため、朝子は常に幻影と現実の狭間に立たされる。
これはまさに震災後の日本人が直面した状況を映し出している。以前の日常は二度と戻らない。しかし、似ている「新しい日常」を生きるしかない。そこには修復の可能性と同時に、拭えぬ違和感がつきまとう。横向きに直された看板のイメージが、この不完全な修復を視覚的に象徴している。
幻影と現実の共犯関係
『寝ても覚めても』の恋愛は、幻影と現実が対立するのではなく、むしろ共犯的に絡み合っている。朝子は亮平を愛することで幻影を追い続け、幻影を追うことで現実にしがみつく。愛の純粋性と欺瞞性が表裏一体であることを、濱口は隠さずに提示する。
だからこそ、この物語は単なるラブストーリーではなく、震災後の「生のあり方」をめぐる寓話でもある。幻影に囚われながらも、現実に立ち戻らざるを得ない私たち。濱口は恋愛の物語を通じて、その不可避の二重性を描き出したのである。
- 製作年/2018年
- 製作国/日本
- 上映時間/119分
- ジャンル/ドラマ
- 監督/濱口竜介
- 脚本/田中幸子、濱口竜介
- 製作/定井勇二、山本晃久、服部保彦
- 製作総指揮/福嶋更一郎
- 原作/柴崎友香
- 撮影/佐々木靖之
- 音楽/tofubeats
- 編集/山崎梓
- 美術/布部雅人
- 衣装/清水寿美子
- 録音/島津未来介
- 東出昌大
- 唐田えりか
- 瀬戸康史
- 山下リオ
- 伊藤沙莉
- 渡辺大知
- 仲本工事
- >田中美佐子
- 寝ても覚めても(2018年/日本)
- ドライブ・マイ・カー(2021年/日本)