不惑の年齢を迎えたスパイク・ジョーンズの、真っ正直な自己告白
例えばラブドールに恋をしてしまう『ラースと、その彼女』(2007年)とか、小説のヒロインに夢中になる『ルビー・スパークス』(2012年)だとか、人間ならざるものに胸キュンする“2D擬似恋愛”は、どうしたってコミュニケーション不全の非モテ男子を救済するファンタジーにしか成りえなかった。
しかし、スマホのOSに恋をするというトンデモ設定の、『her/世界でひとつの彼女』(2013年)は、いささか様相が異なる。
そもそも、主人公のセオドア(ホアキン・フェニックス)が、非モテ男子どころか思いっきりリア充。元妻がルーニー・マーラだし、同じアパートに住む元カノはエイミー・アダムス。初デートのオリヴィア・ワイルドとはいきなりベロチューをカマす。日々代筆ライターとしてクリエイティヴ・ライフを送る、勝ち組野郎なのだ。
そんなセオドアが、スマホOSのサマンサ(スカーレット・ヨハンソン)に恋をする。仕事は有能、ユーモアのセンスもあり、その声はコンピュータと思えないほどにセクシー。
肉体がないからセックスしても子供ができる心配はないし、一人になりたければ電源を切っておけば良いし、寂しいときにはいつでも優しい言葉をかけてくれる。要は“都合のいい女”なのだ。
ソフィア・コッポラと離婚後、ミシェル・ウィリアムズや菊地凛子といったトップ女優と交際したものの、いまだ独身状態のスパイク・ジョーンズ。芸術家ならではの自分至上主義がたたって殻の中に閉じこもり、彼女たちを己の成層圏内に突入することを許さなかった故か?
そう考えると『her/世界でひとつの彼女』は、不惑の年齢を迎えたスパイク・ジョーンズが、「俺なりに改めて恋愛について真面目に考えてミマシタ!」という自己告白であり、過去の自分に対する率直な懺悔とも考えられる。
言葉のプロフェッショナルであるセオドアは、言葉によってサマンサと向き合い、言葉によって恋愛の本質、他者と関わることを思索する。そこで提示されるのは、スパイク・ジョーンズなりのコミュニケーション論だ。
退屈な会話劇になることを回避するために、彼は近未来的なSFガジェットを導入し、アーケイド・ファイアの控え目ながらも美しい音楽、ホイテ・ヴァン・ホイテマによる淡い色調に包まれたカメラで、作品全体をコーティング。
己の恋愛哲学すらも、ポップなコマーシャル・アートとして成立させてしまう手腕には恐れ入る。だが、それでも、僕的には後半やや退屈を覚えてしまった。並々ならぬポップ・センスが画面を支配しているとはいえ、ストーリー構造は
仕事の同僚として働く
→恋愛対象として意識する
→付き合う
→(疑似)セックスする
→旅行に行く
→連絡とれなくなる
→自分以外にオトコがいることを知る(そもそもOSはマルチタスキングなものなのだ!)
→別れる
という、ごく凡庸な恋愛話。『マルコヴィッチの穴』(1999年)もそうだったが、スパイク・ジョーンズには、奇想天外なワン・アイディアを2時間疾走し続けるだけの耐久力に欠けるのだ。
ロサンゼルスの朝焼けを屋上から眺めながら、エイミーはセオドアの肩にそっと頬を埋める。言葉だけで編み上げられた世界から解き放たれ、温もりを感じるセオドア。
『her/世界でひとつの彼女』によって誰よりも心の救済を得たのは、スパイク・ジョーンズ自身なのだ。
- 原題/Her
- 製作年/2013年
- 製作国/アメリカ
- 上映時間/120分
- 監督/スパイク・ジョーンズ
- 製作/ミーガン・エリソン、スパイク・ジョーンズ、ヴィンセント・ランディ
- 製作総指揮/ダニエル・ルピ、ナタリー・ファーリー、チェルシー・バーナード
- 脚本/スパイク・ジョーンズ
- 撮影/ホイテ・ヴァン・ホイテマ
- プロダクションデザイン/K・K・バレット
- 美術/K・K・バレット
- 衣装/ケイシー・ストーム
- 編集/エリック・ザンブランネン、ジェフ・ブキャナン
- 音楽/アーケイド・ファイア
- ホアキン・フェニックス
- エイミー・アダムス
- ルーニー・マーラ
- オリヴィア・ワイルド
- ポーシャ・ダブルデイ
- サム・ジェーガー
- ルカ・ジョーンズ
- スカーレット・ヨハンソン
- クリス・プラット
- ブライアン・コックス
![her/世界でひとつの彼女 [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/514LZNjtfyL.jpg)



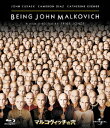






最近のコメント