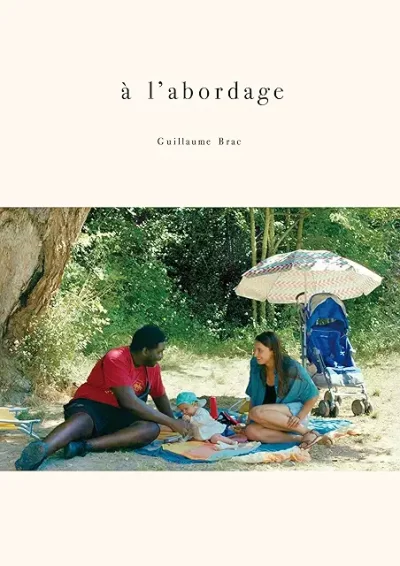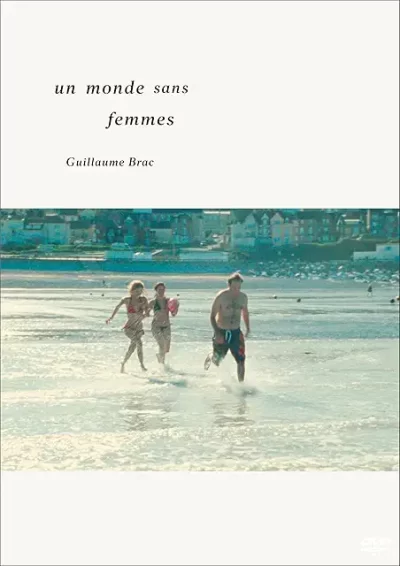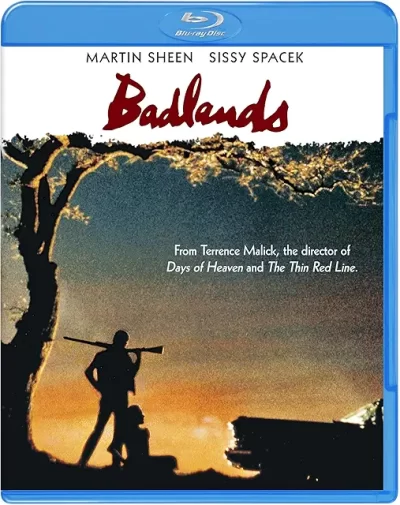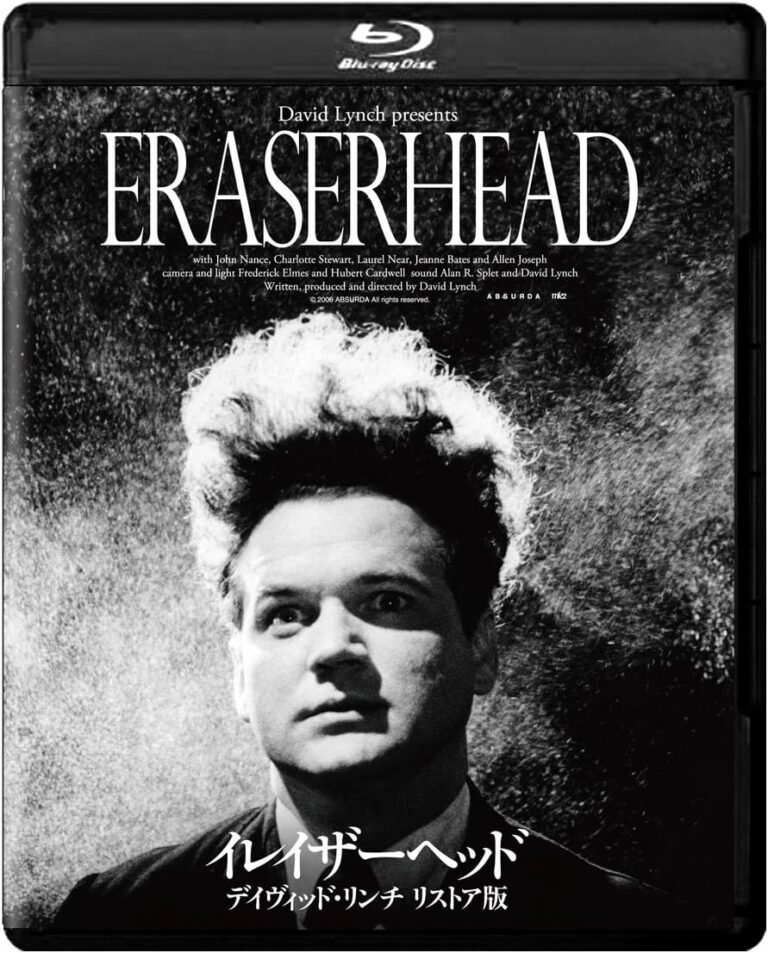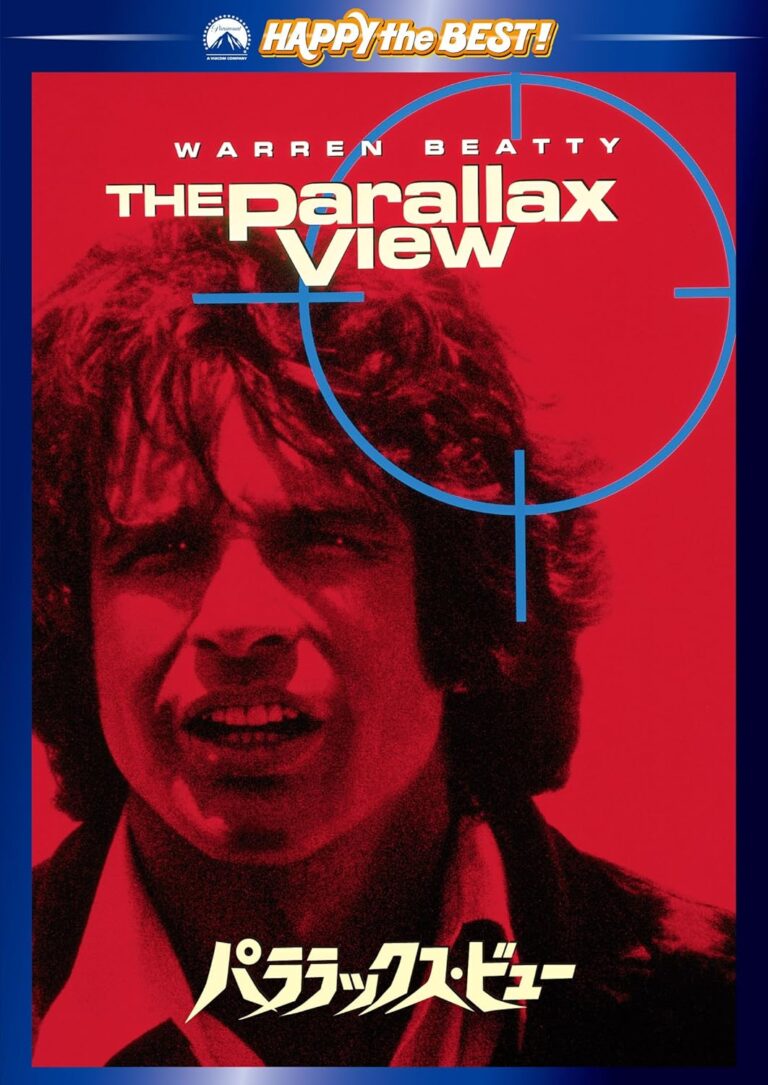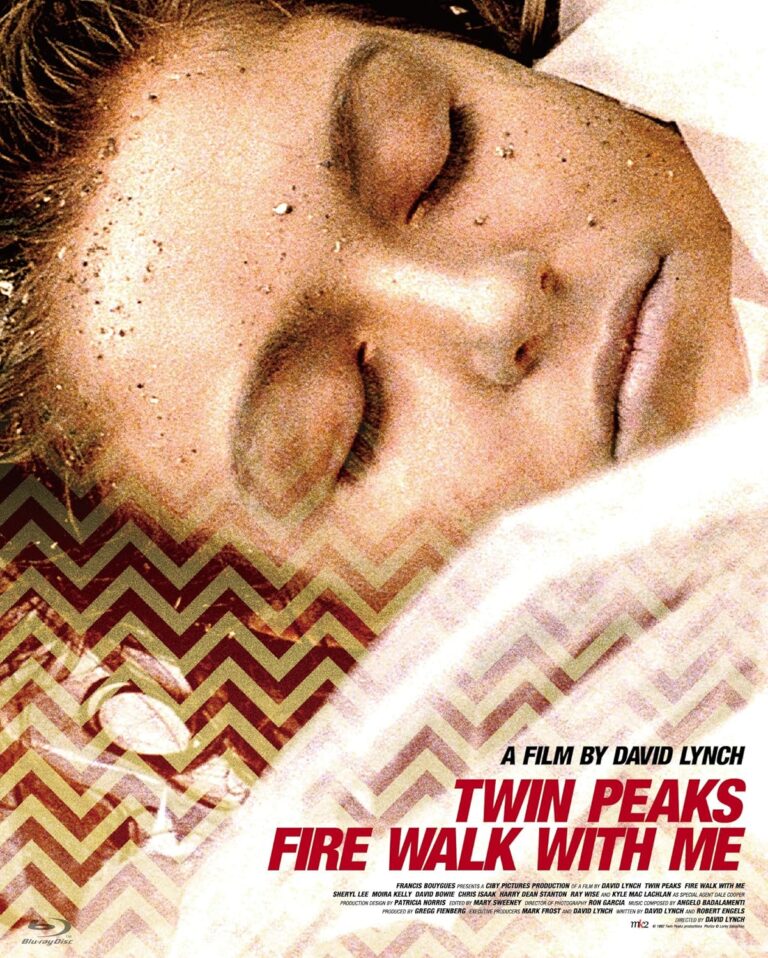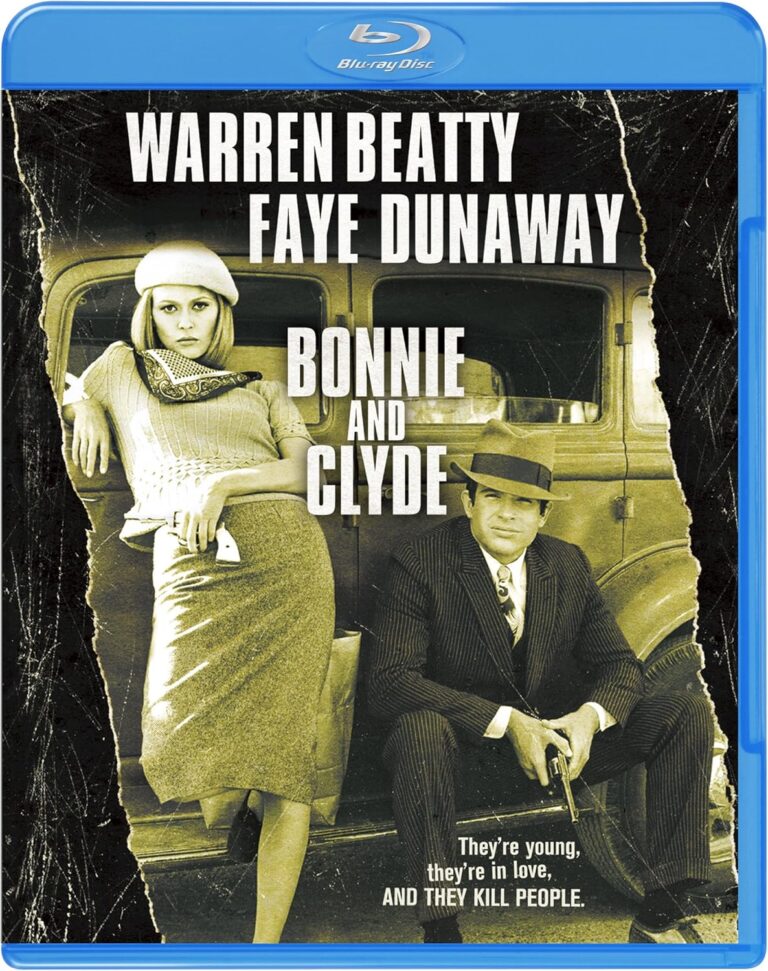『アンダーグラウンド』(1995)
映画考察・解説・レビュー
『アンダーグラウンド』(原題:Underground/1995年)は、ユーゴスラビアの激動の半世紀を背景に、地下壕での生活を続ける人々の運命を通して戦争と祝祭の狂騒を描いたエミール・クストリッツァ監督の歴史寓話。脚本はドゥシャン・コヴァチェヴィッチによる共同執筆で、主演はミキ・マノイロヴィッチ、ラザル・リストフスキ、ミリャナ・ヤコヴィッチ。ナチス侵攻から内戦までを音楽と混沌の祝祭として映し出し、第48回カンヌ国際映画祭でパルム・ドールを受賞した。
爆音と硝煙の狂宴
脳髄を直接揺さぶられるようなカオス。理屈抜きのエネルギー。カンヌ国際映画祭でパルム・ドール(最高賞)をさらったエミール・クストリッツァ監督の『アンダーグラウンド』(1995年)は、血と暴力とブラスバンドの音楽をミキサーにかけ、ユーゴスラビアという国家の死体の上にぶちまけた、狂気のごとき祝祭である。
舞台は、ナチス・ドイツの空爆が始まった1941年のベオグラードから、血みどろの内戦に至るまでの約50年間。悲劇的な歴史を、クストリッツァは極彩色のサーカスへと変貌させる。
冒頭からエンジン全開だ。酔っ払った主人公たちが銃を乱射し、ジプシー・ブラスバンドが鼓膜を破らんばかりに演奏しながらトラックと併走する。この「ウンザ・ウンザ」という独特の裏打ちのリズムを聞いた瞬間、観客の心拍数は強制的に上昇させられる。
物語の中心となるのは、共産党員のマルコと、その親友で電気技師のクロという二人の男だ。彼らはナチスへのレジスタンス活動を行い、空襲を避けるために仲間たちと地下(アンダーグラウンド)へ潜る。
問題は、戦争が終わってから。マルコは地上で英雄として権力を握る一方で、地下にいるクロたちには「戦争はまだ続いている」と大嘘をつき続けるのだ。
なんという悪辣さ。なんという不条理。地下の住人たちは、マルコの作り話を信じ込み、来る日も来る日も武器を作り続ける。その期間、なんと20年。
リアリティなんてどうでもいい。この映画におけるリアリズムとは、教科書的な整合性のことではない。人間の欲望、裏切り、そして生きることへの執着が、過剰なまでの演出でスクリーンに叩きつけられることこそが、クストリッツァ流のリアリズムだ。
戦火の中で動物園が破壊され、象や虎が街を彷徨うシーンのシュールレアリスムたるや、まさに悪夢と幻想のコラージュ。悲劇なのに笑ってしまう。笑っているうちに泣けてくる。
感情のジェットコースターなんて生易しいものではない。これは感情のフリーフォールだ。観る者は、歴史という巨大な嵐の中に放り出され、もみくちゃにされながら、それでもスクリーンから目が離せなくなる。
戦争という極限状態において、人間がいかに愚かで、いかに愛おしい生き物であるか。それをこれほどパワフルに描き切った作品が、他にあるだろうか。
地下室という名のプラトンの洞窟
この映画の構造的な白眉は、なんといっても地下世界の設定にある。マルコによって外界から遮断され、偽りの情報を与えられ続ける地下の住人たち。
これは単なる監禁劇ではない。クストリッツァが仕掛けた、強烈なメタファーだ。地下の世界は、チトー大統領による独裁体制下にあった、旧ユーゴスラビアそのものを暗示していると言われている。
かつてのユーゴスラビアは「7つの国境、6つの共和国、5つの民族、4つの言語、3つの宗教、2つの文字、1つの国家」と称されるほど、複雑なモザイク国家だった。それを強力な統率力で束ねていたのがチトーである。
彼は冷戦下において、東側にも西側にも属さない独自の路線を歩んだが、それはある種、国民に“外の世界の真実”を見せず、独自の物語(プロパガンダ)の中に閉じ込める行為でもあった。
映画の中で、地下の住人たちは、マルコが鳴らす空襲警報の嘘に怯え、彼が語る“ファシストとの戦い”という英雄譚を信じて生きている。これは、古代ギリシャの哲学者プラトンが説いた「洞窟の比喩」そのものじゃんか。洞窟の中で影絵を見せられ、それを現実だと信じ込まされている囚人たち。彼らにとって、影こそが世界の全てなのだ。
だが、クストリッツァの演出がすごいのは、この悲惨な状況を湿っぽい被害者の物語にしていないこと。地下の人々は、騙されているとも知らずに、そこで結婚し、子供を育て、宴会を開き、歌い、踊る。戦車すら自作してしまう。その生命力の逞しさたるや。
むしろ地上で政治家として腐敗し、虚飾にまみれた生活を送るマルコたちのほうが、よほど精神的に死んでいるようにさえ見える。地下(=虚構の世界)のほうが、純粋な情熱とエネルギーに満ちているという皮肉。これこそが、クストリッツァが突きつける国家と歴史のパラドックスなのだ。
やがて映画は、地下の住人たちが地上へ飛び出す展開を迎える。しかし、彼らが出て行った先は、ナチスとの戦争が終わった平和な世界ではなく、新たな内戦が始まった地獄だった。しかも彼らは、それを「まだナチスと戦っている」と勘違いして、映画の撮影現場(!)に突っ込んでいったりする。
歴史の皮肉な巡り合わせによる、虚構と現実の悪魔合体。ここで描かれるのは、もはや「何が真実か」という問いではなく、「信じ込んだ物語」のために命を懸けてしまう人間の業の深さだ。
クロは、自分を騙し続けた親友マルコを探し求め、戦火の中を彷徨う。その姿は滑稽でありながら、痛々しいほどに悲劇的だ。歴史に翻弄される個人の無力さ。だが、クストリッツァは彼らを嘲笑わない。むしろ、その愚直なまでのエネルギーを、祝祭的なリズムで肯定しようとする。
そこに流れるのは、東欧特有のブラックユーモアと、深いメランコリー。「戦争は平和だ」「自由は隷属だ」といったオーウェル的なディストピアを、クストリッツァは極上のエンターテインメントとして再構築してしまったのだ。
大地が裂けても終わらない、魂のレクイエム
物語の終盤、映画のトーンは一気に混沌の度合いを深めていく。マルコとクロ、そして彼らが愛した女ナタリア。愛憎と裏切りが入り乱れる三角関係は、ユーゴスラビアという国家の崩壊とシンクロするように破局へと向かう。
マルコは車椅子に乗りながら、自ら仕掛けた爆薬によって、地下の武器庫ごと木っ端微塵になる。クロは死んだ息子を追って井戸へ身を投げる。次々と訪れる主要人物たちの死。それは、かつて存在した一つの国が、地図上から消滅していくプロセスそのものだ。
しかし、ここで終わらないのが『アンダーグラウンド』の真骨頂。普通なら「戦争の悲劇」を訴えて幕を閉じるところを、クストリッツァは現実のルールすらねじ曲げて、奇跡的なラストシーンを用意した。
死んだはずの登場人物たちが、全員生き生きとした姿で、水辺の祝宴に集結するのだ。マルコも、クロも、ナタリアも、地下の仲間たちも、敵も味方も関係なく、一つのテーブルを囲んで酒を酌み交わす。
「許そう。だが忘れない」というセリフとともに、彼らが乗った土地は、本土から切り離され、ゆっくりとドナウ河(あるいは海)へと漂い始める。その島の上で、彼らはまたしても狂ったように踊り、演奏し続けるのだ。
このラストカットの、美しさと切なさ。大地が裂けるという物理的な分断を描きながら、そこにいる人々の魂は、音楽と記憶によって永遠に結ばれている。
ユーゴスラビアという国はもうない。現実はバラバラになった。けれど、彼らが生きた時間、愛した記憶、そしてあふれ出る音楽だけは、誰にも奪うことができないのだ。
クストリッツァはかつて「戦争とは人間の最大のコメディである」と語った。あまりにも残酷な現実を前にしたとき、人間が正気を保つためには、それを笑い飛ばし、歌い、踊るしかない。
この映画は、彼なりのギリギリの抵抗なのだろう。悲劇を悲劇のまま終わらせない。絶望の底でこそ、最大のボリュームで音楽を鳴らす。それが「生きる」ということへの最大の賛歌なのだ。
歴史がどれだけ残酷でも、祝祭は終わらない。踊ることをやめてはいけない。この映画にあるのは、圧倒的な熱量と、混沌としたエネルギーの塊だ。
- 原題/Underground
- 製作年/1995年
- 製作国/フランス、ドイツ、ハンガリー
- 上映時間/171分
- ジャンル/ドラマ、歴史
- 監督/エミール・クストリッツァ
- 脚本/エミール・クストリッツァ、デュシャン・コバチェヴィチ
- 製作/デュシャン・コバチェヴィチ
- 撮影/ヴィルコ・フィラチ
- 音楽/ゴラン・ブレゴヴィッチ
- 編集/ブランカ・ツェペラッチ、ネボイシャ・リパノヴィチ
- 美術/ミリェン・クチャコヴィチ・クレカ
- ミキ・マノイロヴィチ
- ラザル・リフトフスキー
- ミルハーナ・ヤコヴィック
- スラヴコ・スティマッチ
- エルンスト・ストットナー
- ミリャナ・カラノヴィチ
- ミケーナ・パヴロヴィック
- アンダーグラウンド(1995年/フランス、ドイツ、ハンガリー)

![アンダーグラウンド/エミール・クストリッツァ[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/81sCs7IBn-L._AC_UL640_FMwebp_QL65_-e1761951945178.webp)