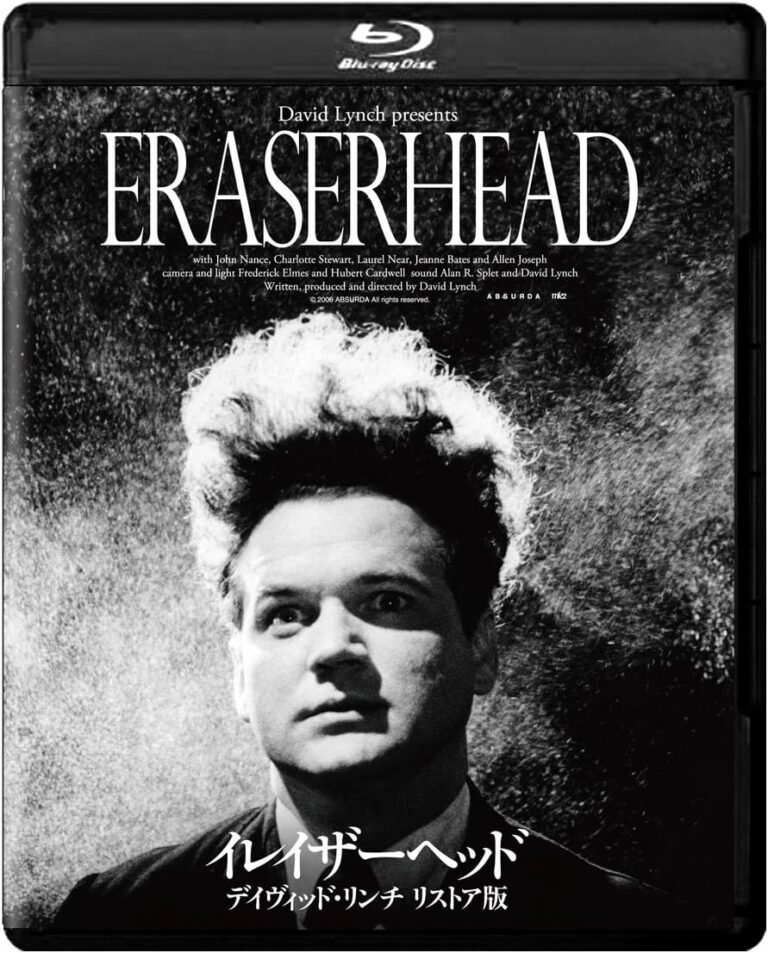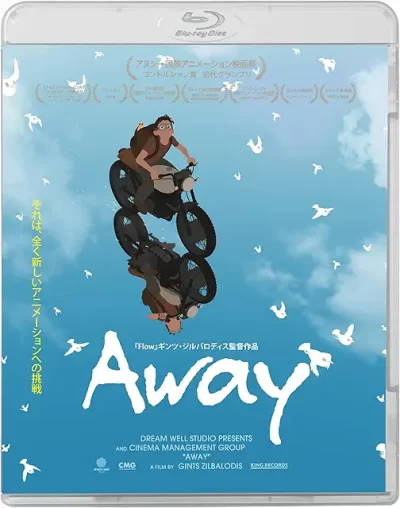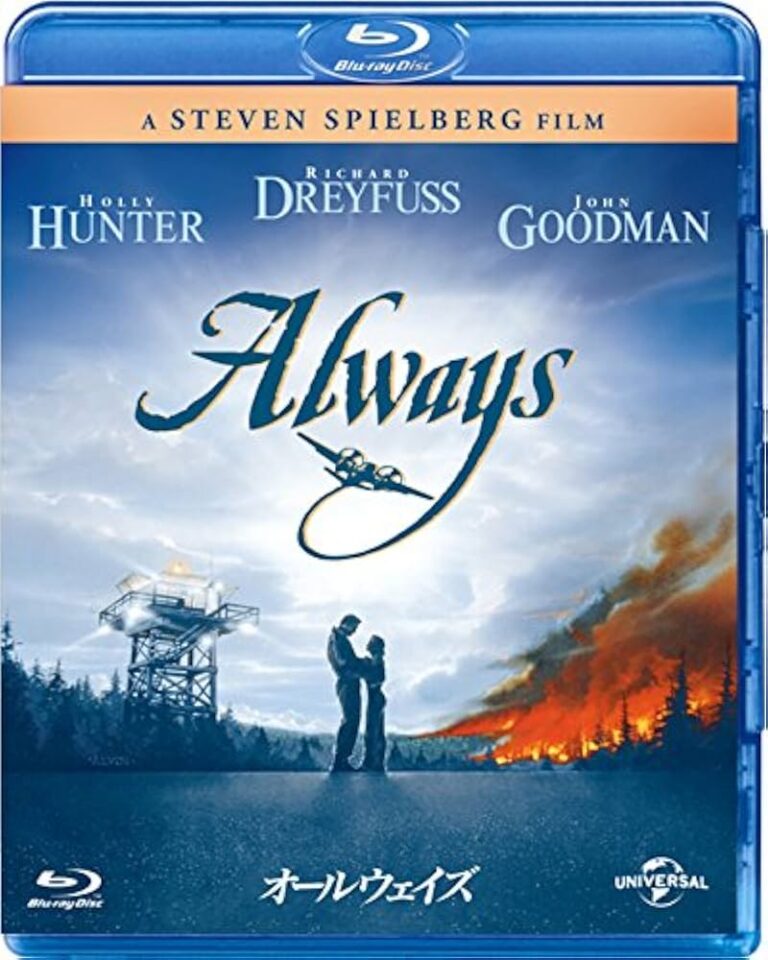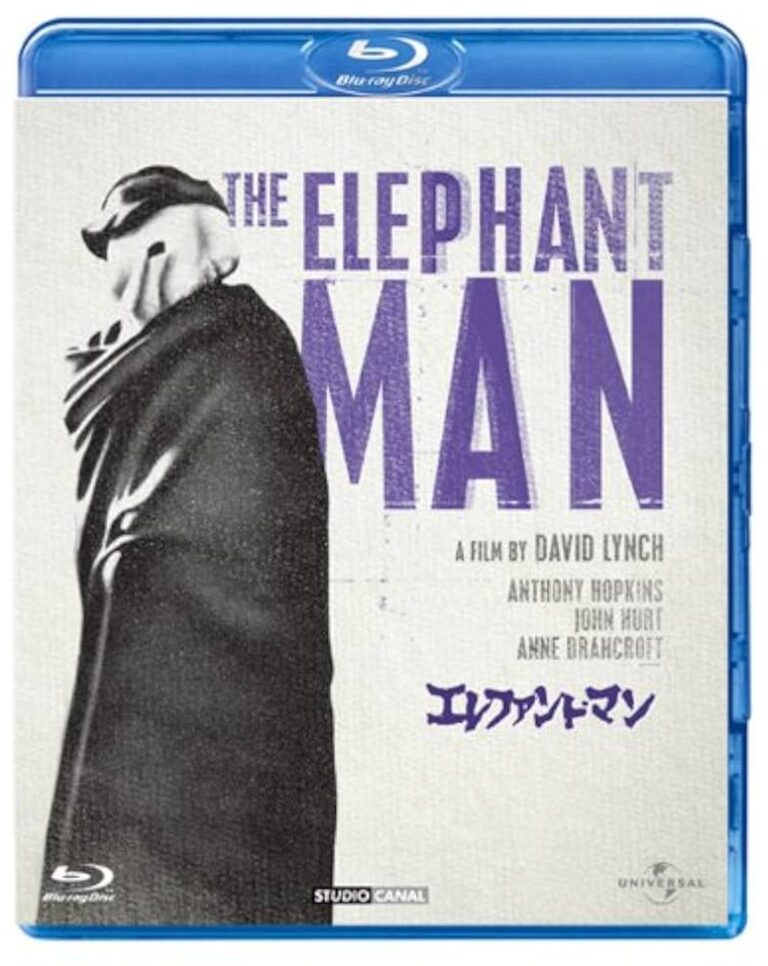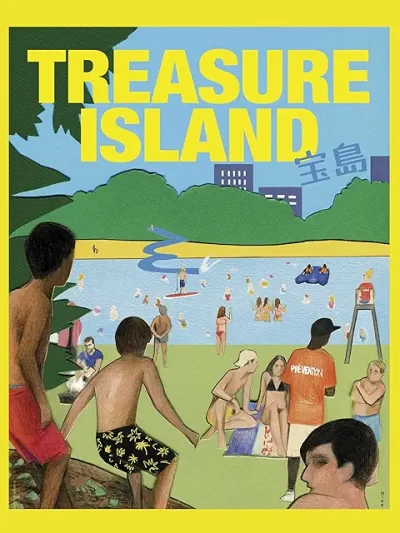『フィールド・オブ・ドリームス』(1989)
映画考察・解説・レビュー
干ばつの荒野にペンキで描いた、緑色の嘘
僕はある日、天啓のように降りてきた「If you build it, she will come(それを作れば彼女がやってくる)」という声を信じ、「なるほど、イケてるホームページを作れば、イケてない俺でも彼女ができるというシステムか!」と勝手に超解釈。
持てるWeb知識と情熱の全てを注ぎ込んで、この「POP MASTER」という城(サイト)を築き上げたわけだが、悲しいかな、現状その成果は微塵も報われていない。神様というのは、時として我々のような迷える羊に、あまりにも残酷なプレイを強いるものだ。
しかし、だ。『フィールド・オブ・ドリームス』(1989年)の主人公、レイ・キンセラ(ケビン・コスナー)は違う。彼は「If you build it, he will come(それを作れば彼がやってくる)」という謎の声を耳にするや否や、生活の生命線であるトウモロコシ畑を破壊し、野球場を建設するという暴挙に出た。
撮影が行われた1988年夏、ロケ地のアイオワ州は歴史的な大干ばつに見舞われていた。「夢のトウモロコシ畑」を描く映画なのに、現実のトウモロコシは枯れ果て、芝生は茶色く死にかけていたのだ。
だが、スタッフは近隣の小川をせき止め、新たな水路を掘って強引に水をひき、それでも色の戻らない芝生には、なんと緑色のペンキを直接散布して塗装したのである。
想像してほしい。うだるような暑さの中、枯れた大地にペンキを塗って「天国」を捏造するスタッフたちの姿を。これは劇中でレイが周囲から「狂人」扱いされながら球場を作る姿と、完全にシンクロしている。
映画とは、現実という荒野に、ペンキと狂気で「夢」を上書きする詐術だ。その「作り物の美しさ」こそが、観客を現実から引き剥がし、強制的に信じ込ませるマジックの正体なのだ。
そして、キャスティングの妙についても触れておかねばならないだろう。実は当初、主演のレイ役にはトム・ハンクスやロビン・ウィリアムズといった名前が挙がっていた。
ケビン・コスナーは直前に『さよならゲーム』(1988年)という野球映画に出演したばかりで、本人は「また野球かよ」と難色を示し、フィル・アルデン・ロビンソン監督もイメージの重複を恐れていた。だが、脚本を読んだコスナーはその完成度に震え、出演を即決したという。
結果として、これは英断だった。もしロビン・ウィリアムズが演じていたら、そのキャラクター性から「最初からヤバい人」に見えてしまったかもしれない。コスナーが持つ、ある種の凡庸なアメリカ人の善良さ、ゲイリー・クーパー的な正統派の二枚目だったからこそ、観客は「普通の男が、何かに憑かれたように狂っていく」というプロセスに恐怖し、同時に共感できたのだ。
サリンジャーの亡霊
この映画を批評的に読み解く上で、避けて通れないのが、ジェームズ・アール・ジョーンズ演じる黒人作家テレンス・マンの存在だ。
原作小説『シューレス・ジョー』(W.P.キンセラ著)において、主人公が旅に連れ出すのは架空の作家ではない。あの『ライ麦畑でつかまえて』で知られる隠遁作家、J.D.サリンジャー本人だったのだ。
原作ではサリンジャーの実名を使用していたが、現実のサリンジャーという人物は、プライバシー侵害に対して極めて敏感で攻撃的な人物だった。映画化に際し、彼は「自分の名前を使ったら訴える」という強硬姿勢を見せたため、製作陣は泣く泣く設定を変更し、架空の作家テレンス・マンを生み出した。
だが、この変更こそが怪我の功名、いや、映画のテーマをより普遍的で強固なものへと昇華させたのだ。原作のサリンジャー設定は、あくまで文学オタク的な「内輪ネタ」の域を出ない。
しかし、これをジェームズ・アール・ジョーンズという、威厳と深い声を持つ黒人俳優に変更したことで、キャラクターに公民権運動や60年代の社会変革の重みが付与された。
テレンス・マンを球場へ連れ出す旅は、単なるファンのお宅訪問ではない。ベトナム戦争や政治腐敗に絶望し、社会からドロップアウトした「60年代の良心」を叩き起こし、レーガン政権下の保守化が進む「80年代のアメリカ」へと連れ戻すための巡礼なのだ。
レイ自身も、かつては父の愛した野球を「体制側のスポーツ」として否定し、家を飛び出した60年代のリベラルな若者だった。彼がマンに会いに行く動機は、表向きは「声」に従っただけだが、深層心理では「かつて自分が信じ、そして捨て去った理想」を再確認するため。
マンが放つあの名演説、「昔から変わらないのは野球だけだ。アメリカは驀進してきた…壊しては造り、また壊しながらだ。だが野球は時をこえて残った」というセリフ。
これは単なる野球賛歌ではない。激動の歴史、革命、戦争、それらすべてを経て、結局アメリカ人が帰るべき場所は「野球(=古き良きアメリカの伝統的コミュニティ)」しかなかったという、ある種の敗北宣言であり、同時に歴史との和解の握手なのだ。
ベビーブーマー世代が自身の青春の敗北を認め、大人になるための通過儀礼。それがこの映画の隠された正体である。
言葉を超えたキャッチボールの神学
そして物語は、映画史に残る至高のラストシーンへと収束する。絶縁状態のまま死別した父ジョン・キンセラと息子レイが、時空を超えてキャッチボールを交わす場面だ。
注目すべきは、脇役として登場する老医師ムーンライト・グラハムの存在。名優バート・ランカスターの遺作ともなったこの役は、メジャーへの夢を諦め、医師として地道に生きることを選んだ人物だ。
彼は、レイの娘が喉にものを詰まらせた際、フィールド(夢の世界)から一歩踏み出し、若き日の姿から老人の医師(現実の世界)へと変貌して娘を救う。
このシーンが示唆するのは「夢からの覚醒」の尊さだ。夢の世界に留まり続ければ永遠の若さを保てるが、現実の命は救えない。グラハムは自らの夢を犠牲にして、現実の責任を果たした。この「大人の選択」が描かれているからこそ、ラストの父と子の再会が、単なる逃避ではなく、痛みを伴う赦(ゆる)しとして響く。
レイにとって父は、厳格で野球を強要した存在だった。若き日のレイは「父さんのヒーローは犯罪者(ジョー・ジャクソン)だ!」と罵って家を出た。しかし今、彼は父に「キャッチボールしないか?」と問う。
キャッチボールとは、言葉を介さずに心と心を交換する唯一の儀礼だ。白球が往復するたび、そこには「ごめん」と「ありがとう」が乗せられる。これは、アメリカという国が、分断された世代間の溝を埋めるために必要とした、美しくも切ない、集団的な禊(みそぎ)なのである。
そしてカメラが引いていくと、球場に向かって延々と続く車のヘッドライトの列が映し出される。このシーン、当時はCGなどない。実際にアイオワ州の住民たちが、なんと3000台もの自家用車で集結して作り出した、光の河なのだ。撮影監督は、地元のラジオ局を通じて指示を出し、合図とともに一斉にライトを点灯・消灯させ、あの幻想的な風景をフィルムに焼き付けた。
このエピソードは震えるほど感動的だ。「If you build it, they will come」というセリフは、映画の中だけの話ではなかった。映画という虚構を作るために、現実の共同体が動き、光を灯した。フィクションが現実を侵食し、スクリーンと観客の境界線が消滅した瞬間である。
『フィールド・オブ・ドリームス』は、失われた父権の回復であり、60年代の亡霊との手打ち式であり、そして何より、ペンキで塗られた嘘の芝生と、3000台の車のライトによって作られた集団幻覚こそが、人の魂を救うのだという、映画芸術への強烈な肯定だ。
信仰とは神のためではない。自分自身が明日を生きていくために、自分を騙し、鼓舞するための物語である。
- 原題/Field of Dreams
- 製作年/1989年
- 製作国/アメリカ
- 上映時間/107分
- ジャンル/ファンタジー、ヒューマン、スポーツ
- 監督/フィル・アルデン・ロビンソン
- 脚本/フィル・アルデン・ロビンソン
- 製作/ローレンス・ゴードン、チャールズ・ゴードン
- 製作総指揮/ブライアン・フランキッシュ
- 原作/W・P・キンセラ
- 撮影/ジョン・リンドレイ
- 音楽/ジェームズ・ホーナー
- 編集/イアン・イェーツ
- 美術/デニス・ガスナー
- 衣装/リンダ・バス
- ケヴィン・コスナー
- エイミー・マディガン
- ジェームズ・アール・ジョーンズ
- バート・ランカスター
- ギャビー_ホフマン
- レイ・リオッタ
- ティモシー・バスフィールド
- フランク・ウェイリー
- ドワイヤー・ブラウン
- フィールド・オブ・ドリームス(1989年/アメリカ)

![フィールド・オブ・ドリームス/フィル・アルデン・ロビンソン[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/51hem0tY5PL._AC_UL640_FMwebp_QL65_-e1762362505913.webp)