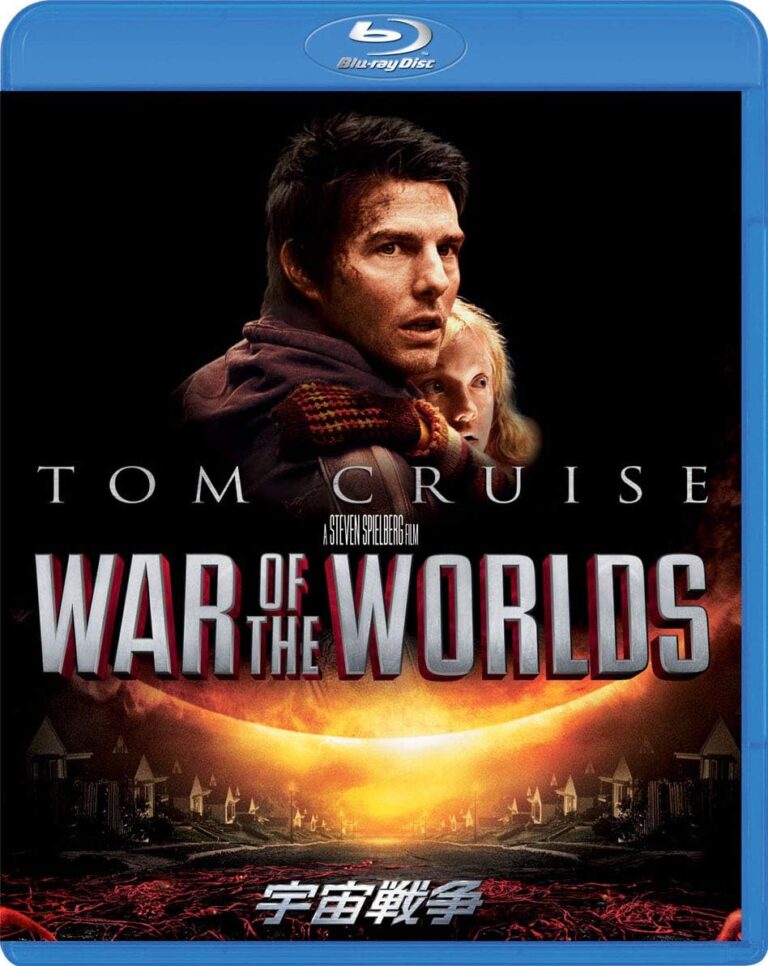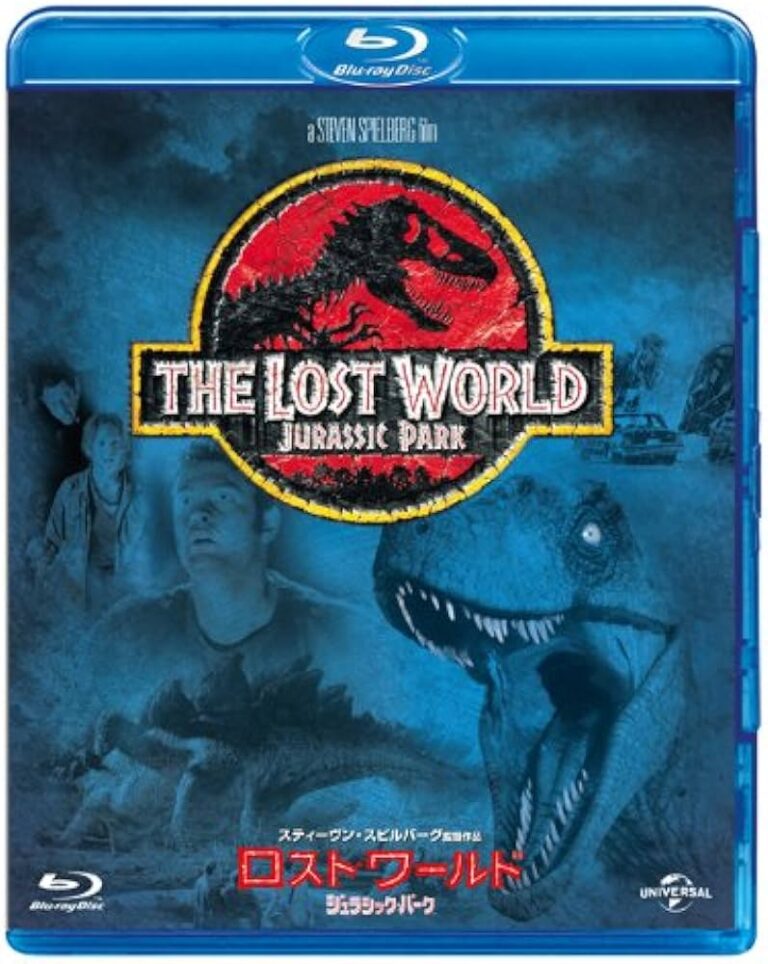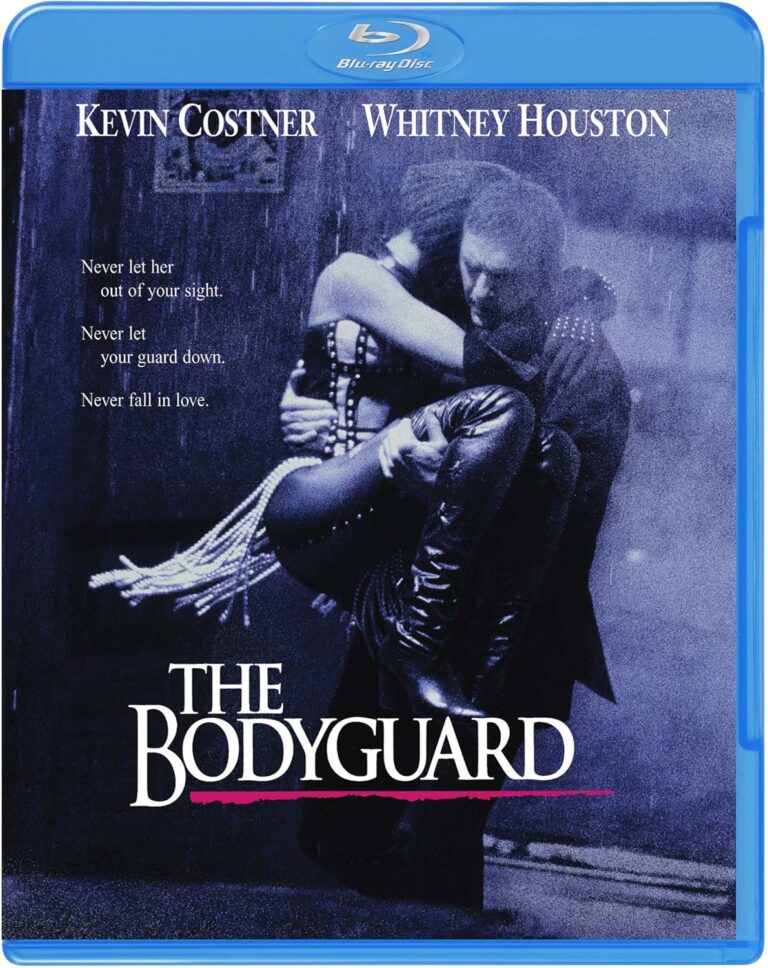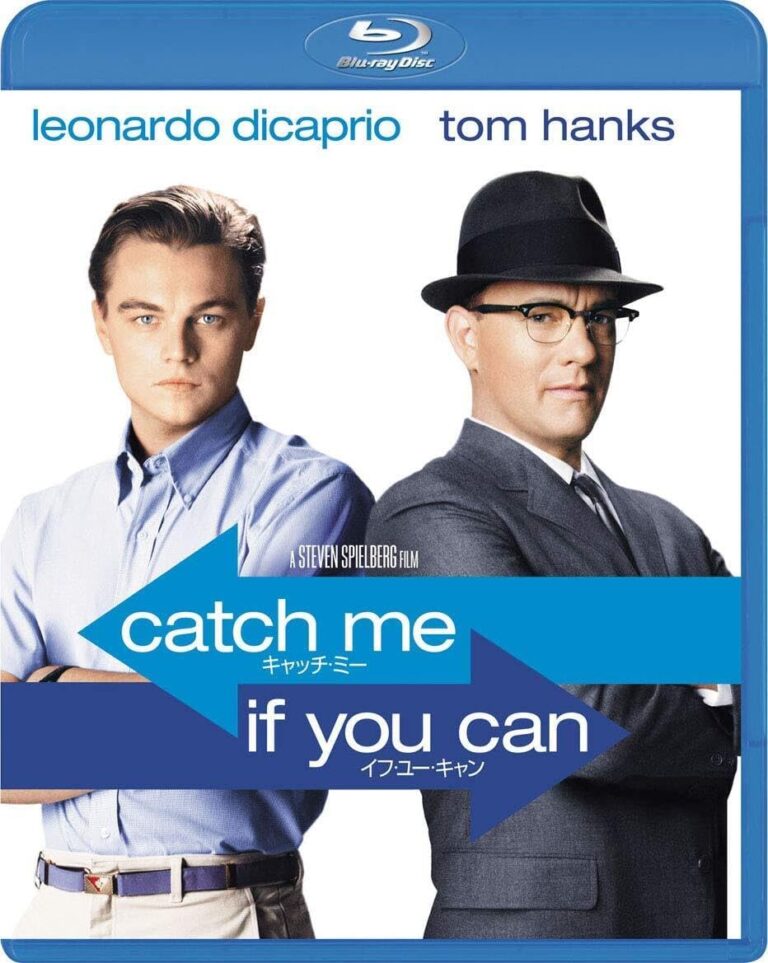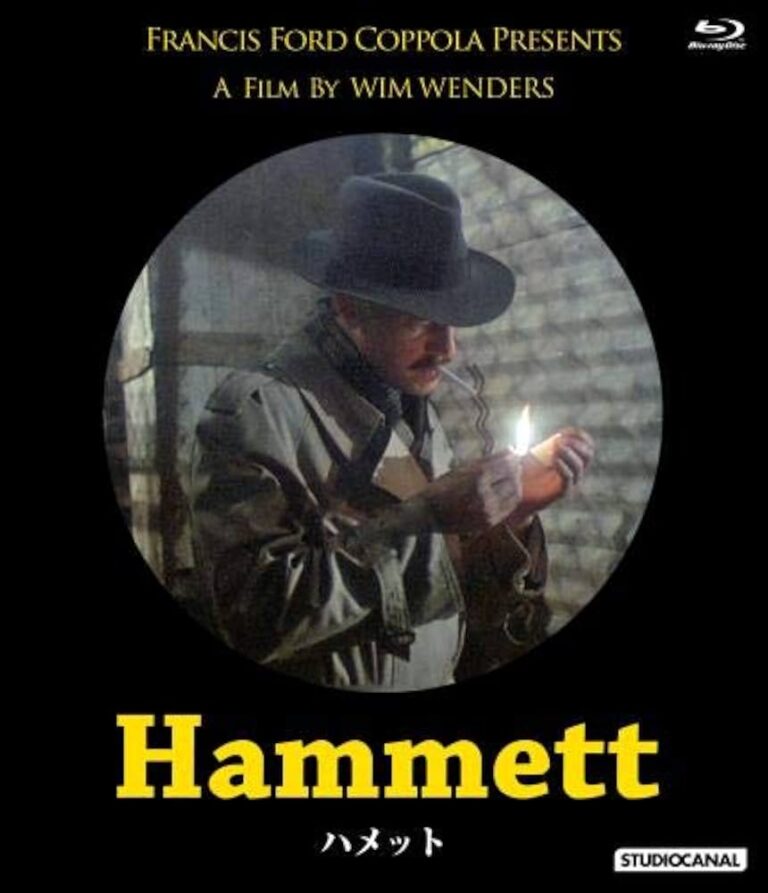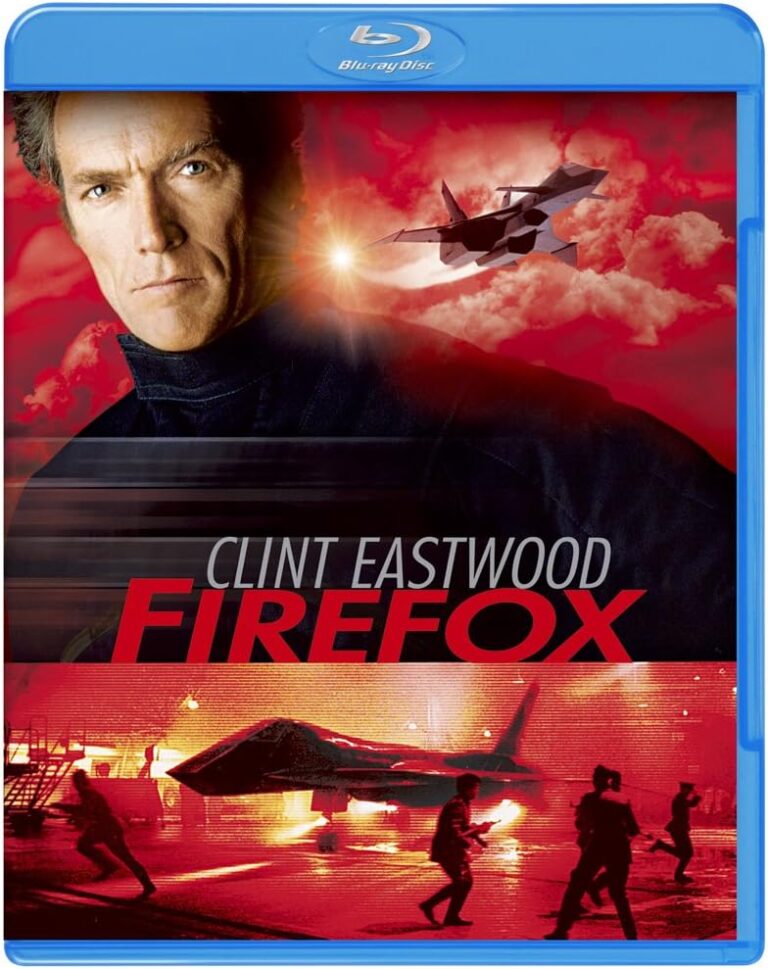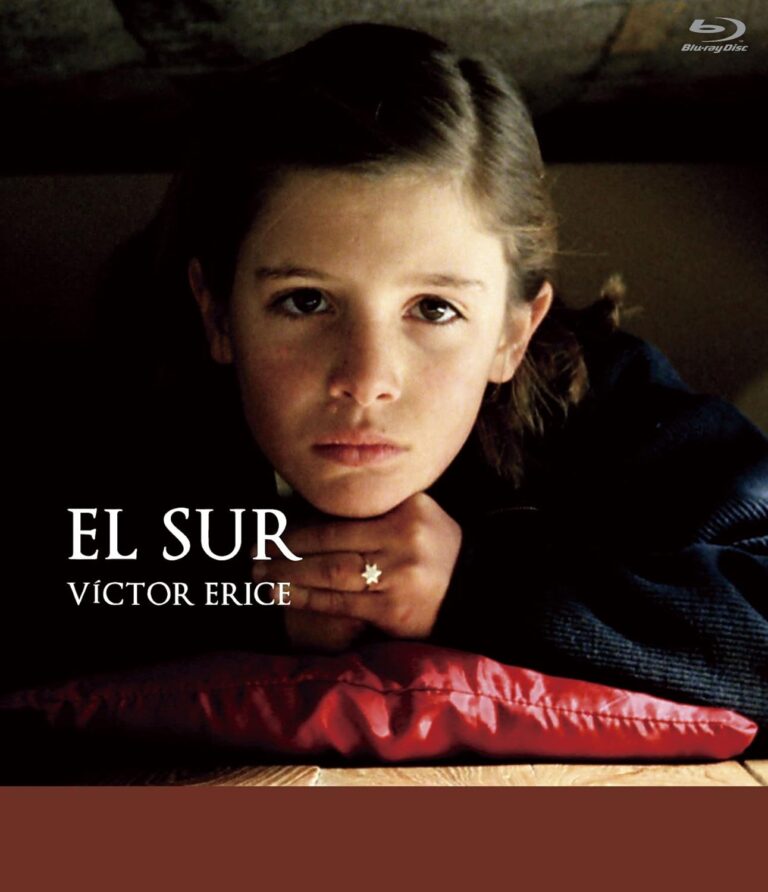『GODZILLA』(1998)
映画考察・解説・レビュー
『GODZILLA』(1998年)は、ローランド・エメリッヒ監督が東宝の名作『ゴジラ』(1954年)をリメイクしたハリウッド版怪獣映画。南太平洋の核実験によって誕生した巨大生物が、ニューヨークを襲撃する。科学者ニックと軍が対峙する中、街は破壊され、市民は混乱に陥る。
核の落とし子からマグロ食いのトカゲへの去勢
ローランド・エメリッヒ監督による『GODZILLA』(1998年)は、映画史上もっとも豪華で、もっとも味がしないお子さまランチである。
巨額の予算と最新のVFXを投じながら、そこにゴジラという存在が本来背負うべき核の恐怖と、荒ぶる神の威厳が、綺麗さっぱり抜け落ちているからだ。
オリジナルの『ゴジラ』(1954年)は、ビキニ環礁の水爆実験という現実の悲劇を背景に、人類の罪が生み出した災厄として誕生した。その足音は鎮魂の鐘であり、その熱線は業火そのものだった。
だが、このエメリッヒ版は、フランスの核実験の影響で変異したという設定こそあるものの、そこに社会的な批評性は皆無。現れたのは、ただミサイルから逃げ惑い、高層ビルの陰に隠れ、大量のマグロを貪り食う、身体能力の高い巨大イグアナに過ぎない。
キャッチコピーの「SIZE DOES MATTER」が象徴するように、本作はゴジラを単なる物理的にデカい動物へと矮小化してしまった。怪獣王としてのプライドを去勢され、米軍の通常兵器で駆除される害獣へと成り下がったその姿に、古参ファンが激怒したのは当然の反応だろう。
エメリッヒは『インデペンデンス・デイ』(1996年)でホワイトハウスを吹き飛ばした破壊王だが、彼にとってゴジラは畏怖の対象ではなく、単なるアトラクションのキャストでしかなかったのだ。
観光地めぐりと、システム崩壊の欠落
マンハッタンにゴジラ上陸。この設定だけで、本来なら映画史に残る傑作が撮れたはず。だが、エメリッヒが描いたのは、クライスラー・ビルやフラットアイアン・ビルといったランドマークを順番に壊していく、まるで過激な観光案内ビデオのような破壊劇だった。
都市のアイコンは崩れるが、そこには生活や社会が引き裂かれる痛みがない。対照的なのが、後にJ・J・エイブラムスが製作した『クローバーフィールド/HAKAISHA』(2008年)だ。
同じニューヨークを舞台にしながら、この映画には9.11以降の集団トラウマを想起させる「見えない恐怖」と、「粉塵にまみれた絶望」が描かれていた。自由の女神の首が転がるあのショットには、文明が瓦解する瞬間の生々しい痛覚があった。
さらに、日本の「平成ガメラ」シリーズと比較すれば、本作の都市描写の薄っぺらさは致命的。『ガメラ2 レギオン襲来』(1996年)において、怪獣災害は単なるビルの倒壊ではなく、通信の遮断、交通網の麻痺、自衛隊の法的な出動根拠、そして避難民の誘導といった「都市システムの機能不全」として描かれていた。
エメリッヒ版『GODZILLA』には、この視点が欠落している。選挙キャンペーンに明け暮れる無能な市長や、軽薄なテレビリポーターのドタバタ劇ばかりが強調され、大統領すら登場しない。
世界が終わるかもしれない危機なのに、画面から漂うのはテレビドラマレベルの局地戦の空気だけ。都市が持つ複雑なレイヤーを無視し、ただ派手に壊せばいいという発想は、ディザスター映画としても二流の仕事である。
ラプトルとエイリアンの劣化コピー
そして、映画ファンを最も落胆(あるいは失笑)させたのが、後半のマディソン・スクエア・ガーデンにおけるシークエンスだ。
ゴジラが産み落とした大量の卵が孵化し、ベビー・ゴジラたちが主人公たちを襲う。…っていうか、この既視感はなんだ?薄暗いホールに並ぶ卵、蒸気、ヌメヌメとした質感。これはリドリー・スコットの『エイリアン』(1979年)そのものではないか。
さらに、孵化したベビー・ゴジラの造形と動き。細長い顔、敏捷な二足歩行、集団での狩り、ドアノブを回そうとする仕草。これはスティーヴン・スピルバーグの『ジュラシック・パーク』(1993年)に登場する、ヴェロキラプトルそのまんま。
オマージュとは、元ネタへの敬意と、それを超えようとする意志があって初めて成立する。だが本作のそれは、単なる剽窃に過ぎない。エイリアンの卵室みたいな不気味さと、ラプトルみたいなスリルを入れたらウケるだろうという、安易な計算が透けて見える。
パトリック・タトプロスによるクリーチャーデザイン自体は、生物学的なリアリティを追求した優れたものだったかもしれない。だが、それを動かす演出が、過去のヒット作の劣化コピーでは、怪獣としてのオリジナリティなど生まれるはずもない。
音楽担当のデヴィッド・アーノルドも、普段は良い仕事をするが、本作では伊福部昭の重厚な「ゴジラのテーマ」を排除し、記憶に残らない汎用的なアクションスコアに終始した。
音も、姿も、魂も、すべてが「何か」の借り物で出来たキメラのような映画。それがエメリッヒ版『GODZILLA』の正体だ。もはやこれは、ゴジラ史における巨大な反面教師として、未来永劫語り継がれるべき墓標なのである。
- 監督/ローランド・エメリッヒ
- 脚本/ディーン・デヴリン、ローランド・エメリッヒ
- 製作/ディーン・デヴリン
- 制作会社/トライスター ピクチャーズ
- 撮影/ユーリ・スタイガー
- 音楽/デヴィッド・アーノルド
- 編集/デヴィッド・ブレナー、ピーター・アムンドソン
- 美術/パトリック・タトポロス
- 衣装/ジョゼフ・ポロ
- SFX/フォルカー・エンゲル
- インデペンデンス・デイ(1996年/アメリカ)
- GODZILLA(1998年/アメリカ)
- デイ・アフター・トゥモロー(2004年/アメリカ)
![GODZILLA/ローランド・エメリッヒ[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/81OxBsKfZQL._AC_SL1447_-e1758333653435.jpg)
![インデペンデンス・デイ/ローランド・エメリッヒ[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/61fxzlxK40L._AC_-e1758334178902.jpg)
![クローバーフィールド/HAKAISHA/マット・リーヴス[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/71u80hmKqkL._AC_SL1250_-e1759134334604.jpg)
![エイリアン/リドリー・スコット[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/51RZATQjZXL._AC_UF10001000_QL80_-e1755700564349.jpg)