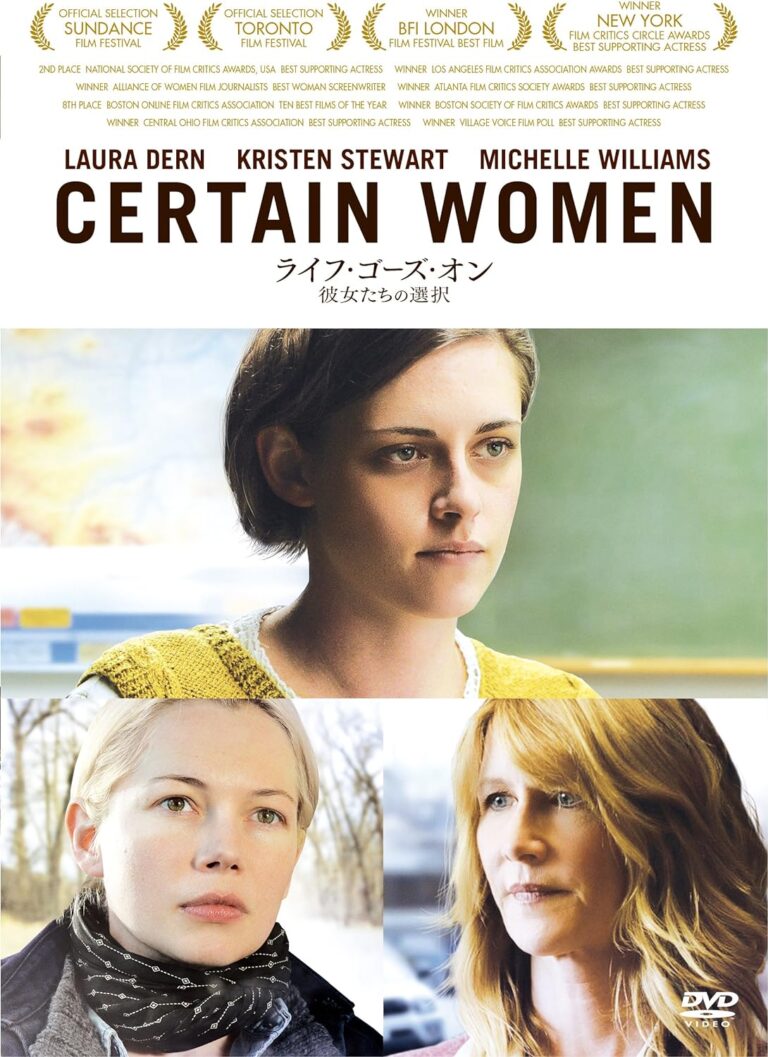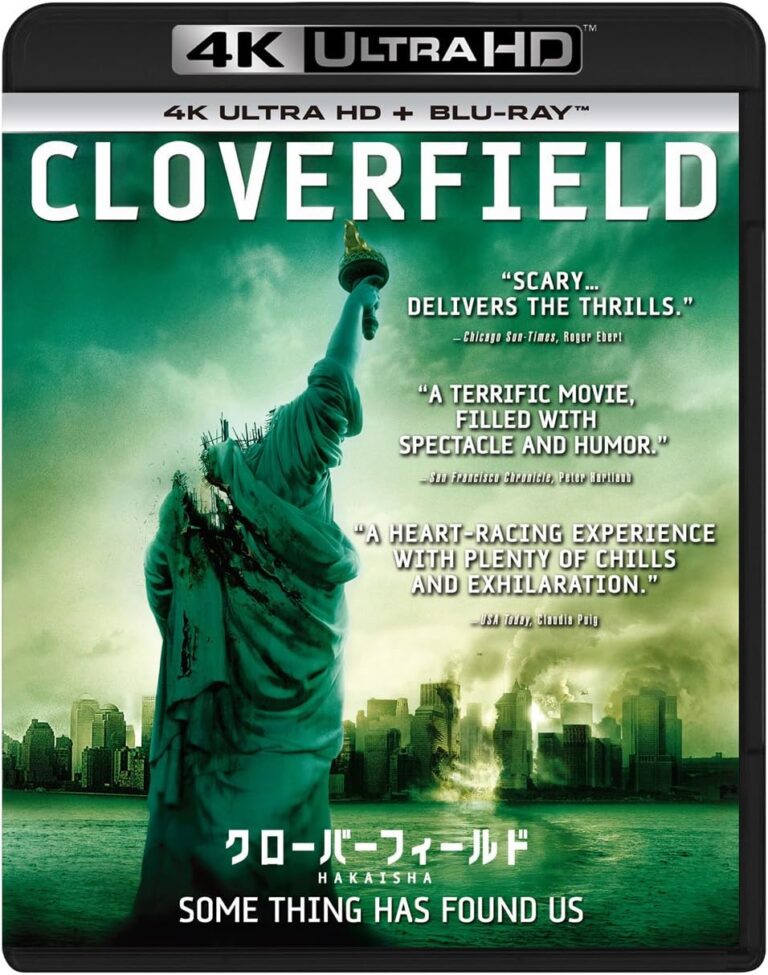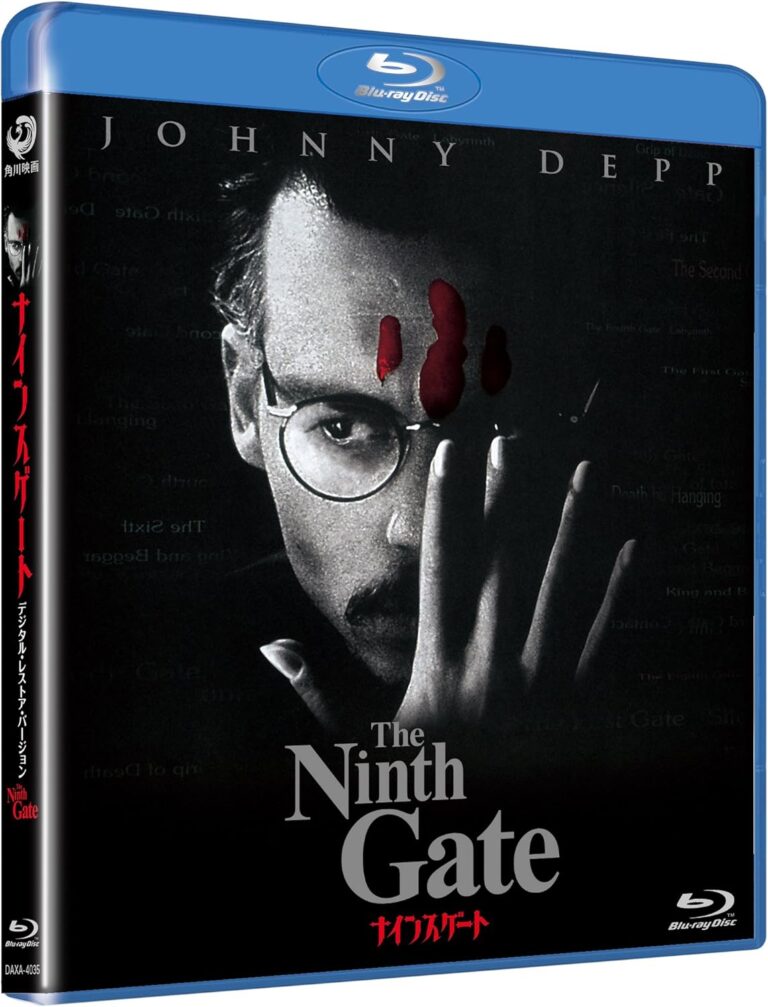『めぞん一刻』──ラブコメが現実を取り戻した瞬間
『めぞん一刻』(1980〜1987年)は、高橋留美子による長編ラブコメディ漫画。古びたアパート〈一刻館〉を舞台に、浪人生・五代裕作と未亡人管理人・音無響子の恋の行方を描く。互いに惹かれながらもすれ違いを重ね、五代が大学を卒業し社会人となるまでの年月を経てようやく結ばれる物語は、恋愛と時間の成熟を重ね合わせた構成で知られる。ヒロインを未亡人に設定するという“禁じ手”により、笑いと痛みを併存させた新しい恋愛表現を確立した。
王道ラブコメを更新した“禁じ手”の構造
ラブコメなんてものは、主人公が「好きだ!」と叫び、ヒロインが「あたしも!」と応じ、抱き合って熱烈なキスをすれば終わり。だがそんな展開では連載は続かない。だから作家たちは頭をひねり、いかに話を引っ張るかに工夫を凝らしてきた。
そこで生まれた黄金パターンが、「優柔不断だけど一途な男の子」と「美人なのに気が強くて素直になれない女の子」という組み合わせ。お互い好きなくせに意地を張り、ライバルも現れてはすれ違いを繰り返す。読者は「早くくっつけよ!」とやきもきしつつ、そのもどかしさを楽しむ──これこそがラブコメの醍醐味だ。
ところが『めぞん一刻』は、この王道をなぞりながら、あえて“禁じ手”を持ち込んだ。ヒロイン・音無響子を未亡人に設定したのである。青春のときめきを描くはずのラブコメに、亡夫という影を背負わせる──この設定は、笑いと同じ強度で痛みとためらいを読者に経験させた。
浪人生の五代裕作が大学を卒業し社会人になるまでの時間をかけてようやく結ばれる長期的構成も、この“影”があったからこそ成立した。ジャンルのセオリーを熟知した作家だからこそ成しえた離れ業である。
『めぞん一刻』が決定的に異彩を放ったのは、ラブコメの体裁を取りながら、性行為の描写をあえて挿入したことだ。ラブコメは「恋のときめき」という夢を演出する装置──それが長年の暗黙の了解だった。
だが高橋留美子は、その境界をためらいなく破壊した。恋愛を幻想から引き剥がし、ぐっと現実の地平へと引き寄せたのである。愛することは触れること、触れることは傷つくこと──そんな現実的な身体感覚を、彼女は漫画のなかで初めて可視化する。
だからこの作品は、読者に笑いと同時に痛みを体験させた。“恋愛を描く”というより“生を描く”ことへと拡張した結果、ラブコメというジャンルそのものを再定義してしまったのだ。
“恋愛=人生の時間”という地平
高橋留美子は、そもそも相反する二つのベクトルを自在に往還する作家である。一方では『うる星やつら』のようにハイテンションなギャグと非日常的ドタバタを描き、他方では『人魚シリーズ』のように死や永遠をめぐる重い主題に踏み込む。
笑いと痛み、幻想と現実──その両極を自由に行き来する作風が、『めぞん一刻』で最も鮮やかに結実した。物語全体を包むユーモアの奥には、常に“喪失”の感覚がある。
響子が亡き夫を想い続ける時間、五代が報われない恋を忍耐する時間──それらの積み重ねが、単なる恋愛喜劇ではない“生の厚み”を生み出す。高橋留美子にとって笑いは逃避ではなく、悲しみを受け止めるための形式だった。『めぞん一刻』は、喜劇を通して人生を語るという、彼女の作家哲学の到達点に位置している。
『めぞん一刻』が切り開いたリアリズムは、90年代以降の恋愛漫画に深い影響を与えた。以後、恋愛のテーマは「くっつくか否か」ではなく、「結ばれた後に何が起こるのか」「恋愛の中で何が失われていくのか」へと拡張していく。
矢沢あいの『天使なんかじゃない』や『NANA』では、恋愛は友情や仕事、夢や挫折と絡み合う現実のドラマとして描かれた。岡崎京子に至っては、『ヘルタースケルター』、『リバーズ・エッジ』で、恋愛を社会的欲望や喪失と切り結ぶテーマへと転化させ、ラブコメの甘さを徹底的に脱構築した。
東村アキコの『東京タラレバ娘』における“アラサー恋愛の焦燥と笑い”もまた、同じ文脈の延長線上にある。恋愛を日常の時間として描くこの潮流の起点に、『めぞん一刻』がある。
高橋留美子はラブコメを「恋の夢」から「人生の現実」へと引き上げた。笑いと涙、ファンタジーとリアリズムを共存させたこの作品こそ、恋愛というテーマを通じて“生きること”を描いた最初のラブコメだったのである。
- 著者/高橋留美子
- 発表年/1980年〜1987年
- 掲載誌/ビッグコミックスピリッツ
- 出版社/小学館