ジャンヌ・モローの“女性としての生理”が全てを凌駕してしまう、珠玉のヌーヴェルヴァーグ
僕のヌーヴェルヴァーグ映画(殊に60年代)に対するイメージは、「質量が軽い」という一言に尽きる。
ストーリーが軽やかで音楽で軽やかで、そして何より人間が軽やか。不可解な男女関係の機微を描いても、毛沢東のスローガンを掲げて政治を叫んでも、圧縮率が極めて高いので、「質量が軽い」のである(ちなみに僕にとって質量が重い映画の代表は、スタンリー・キューブリックの諸作である)。
あらゆる映画的制約から解放されて、まるで無重力のようにふわふわと浮かぶ、連続的なイメージたち。決して数は多くはないけれど、僕が今まで観てきたヌーヴェルヴァーグは例外なくそうだった。トリュフォーの代表作とされる『突然炎のごとく』(1962年)を除いて。
『突然炎のごとく』はなぜ軽くないのか。その原因は、古典的な「女1:男2の三角関係」にある訳ではない。トリュフォーの演出にある訳でもない。ただただ、ヒロインのカトリーヌを演じるジャンヌ・モローが重いのである。
「決して美しいわけではないが、彼女は“女”だ。男なら誰しもが夢見る“女”だ」というのは、映画内のジュールのセリフだが、僕はそれに半分は賛成。
残念ながら僕はジャンヌ・モローが全然タイプではないので、彼女に恋したりしないし、夢見たりもしない。しかしながら、彼女は間違いなく“女”だ。
ヌーヴェルヴァーグにおいては記号的ですらあった「奔放でつかまえどころのない」ヒロイン像が、ジャンヌ・モローが演じることによって、生々しいほどの女としての生理が露出している。
男装するためにヒゲを描いたり、陸橋の上を三人で駆けっこしたりと、たとえばジーン・セバーグが演じたら屈託のないファム・ファタールとして認知されるべきシーンが、ジャンヌ・モローが演じると、女としての生理がすべてを凌駕してしまう。
ゴダールの『はなればなれに』(1964年)で、主人公たちがルーブル美術館を駆けっこするシーンとは、明らかに異質の引力が働いているんである。
でもこの映画は悲劇ではない。哀しい結末をむかえるラブストーリーではあるけれど、胸をかきむしられるような悲劇ではない。カトリーヌとジューヌが非業の死を遂げた後も、ジムに表情にはどこかほっとしたような空気が漂っている。愛する女と無二の親友を失ったにもかかわらず、だ。
この二人を結びつけなければ、自分自身のバランスを失ってしまっていたであろう男の、喪失感と同時に安堵感が感じられるのである。
質量の重い映画にしたくはないが、軽い映画にもしたくない。ジャンヌ・モローの起用は強力な重石となり、この映画に程よいバランスを与えているのだと思う。
- 原題/Jules Et Jim
- 製作年/1962年
- 製作国/フランス
- 上映時間/107分
- 監督/フランソワ・トリュフォー
- 脚本/フランソワ・トリュフォー
- 製作/マルセル・ベルベール
- 原作/アンリ・ピエール・ロシェ
- 脚本/ジャン・グリュオー
- 撮影/ラウール・クタール
- 音楽/ジョルジュ・ドルリュー
- ジャンヌ・モロー
- オスカー・ヴェルナー
- アンリ・セール
- マリー・デュボア
- ヴァンナ・ユルビノ
- サビーヌ・オードパン








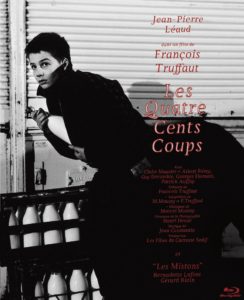


最近のコメント