アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥが仕掛けた、コミュニケーション不全を暴く現代的な神話
もともと人々は同じ1つの言葉を話していた。
シンアルの野に集まった人々は、煉瓦とアスファルトを用いて天まで届く塔をつくってシェムを高く上げ、全地のおもてに散るのを免れようと考えた。
神はこの塔を見て、言葉が同じことが原因であると考え、人々に違う言葉を話させるようにした。
このため、彼らは混乱し、世界各地へ散っていった。
(旧約聖書 創世記11章)
世界の分断。旧約聖書のバベルの塔のエピソードが、映画『バベル』(2006年)の重要なモチーフになっている。
本作では、「混乱し、世界各地へ散っていった」人間が、急速なグローバリゼーションによって「違う言葉」を話す者と遭遇するも、やはりコミュニケーション不全が生まれてしまうという、現代的な物語にアップデートされている。
となれば、「哲学的で、深淵で、ゼロ年代を代表するマスターピースなり!」と断言したいところなんだが、僕的にはエピソードの一つ一つが全て消化不良で、ちっとも映画的ダイナミズムを五感で感じることが出来なかった。いったいこれはどうしたことだろう?
文句なく役者陣は素晴らしい。ブラッド・ピットとケイト・ブランシェットは、インテリなアメリカ人夫婦の微妙な感情のひだを繊細に演じているし、聾唖の女子高生を演じた菊地凛子は、アカデミー助演女優賞ノミネートも納得の超絶演技(相手を刺すように睨みつける表情のなかに、孤独と絶望が見え隠れする)。
撮影監督ロドリゴ・プリエトによる、いかにもメキシコ人らしい鮮烈な色彩設計も素晴らしい。シャロー・フォーカスを駆使して、作中人物の内面へ肉薄せんとするカメラが、非常に劇的な効果を生んでいる。
ダグラス・クライズ&スティーヴン・ミリオンによる編集も、空間も時制も異なるエピソードを的確に繋いでいるし(ちなみにスティーヴン・ミリオンは、同じく複数の物語が交錯する『トラフィック』(2000年)の編集も担当)、グスターボ・サンタオラヤによるサウンドトラックも、異国情緒に溢れていて味わい深い。
だが、シナリオは稚拙すぎる。モロッコ人少年ユシフの天性の射撃の腕は、アメリカ人殺害未遂事件でしか発揮されないし、聾唖の女子高生の“母の不在”は、彼女の自暴自棄な行動原理を何ら説明するものでもないし、メキシコ人不法就労者アメリアが本国に強制送還されてしまうのは、単に「運が悪かった」としか言いようがない。
結局のところ、あらゆるエピソードが(かすかな因果関係は提示するものの)有機的に繋がっておらず、ドラマとして回収できていないところに、『バベル』の致命的欠陥がある。
物語の終幕では、「言語の壁=心の壁ではない。きっと、それは越境できる!」という仄かな希望を指し示す。
しかしながら、個別のエピソードのみで完結し、決して他言語・他地域のアナザー・エピソードには越境しない構造では、そのメッセージは絵に描いた餅で終わってしまうのではないか?それが僕には不満なのだ。
アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥはさるインタビューで、「箱根に行ったときに10代の知的障害の少女と一緒に歩く老人を見て、10代の聴覚障害の女の子と妻を無くした父親のストーリーを描く可能性について考えた」と語っている。
おそらくイニャリトゥは、イメージ先行型の監督なのだろう。確かに彼が紡ぐビジュアルは、えも言われぬ恍惚と、えも言われぬ哀しみに彩られている。だがイニャリトゥが周到に用意した作劇上の仕掛けは何一つ機能することなく、不発弾に終わってしまっているのだ。
- 原題/Babel
- 製作年/2006年
- 製作国/アメリカ
- 上映時間/142分
- 監督/アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ
- 製作/スティーヴ・ゴリン、ジョン・キリク、アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ
- 脚本/ギジェルモ・アリアガ
- 撮影/ロドリゴ・プリエト
- 編集/ダグラス・クライズ、スティーヴン・ミリオン
- 音楽/グスターボ・サンタオラヤ
- ブラッド・ピット
- ケイト・ブランシェット
- ガエル・ガルシア・ベルナル
- 役所広司
- 菊地凛子
- 二階堂智
- アドリアナ・バラーザ
- エル・ファニング
- ネイサン・ギャンブル
![バベル [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51zIAywtvyL.jpg)





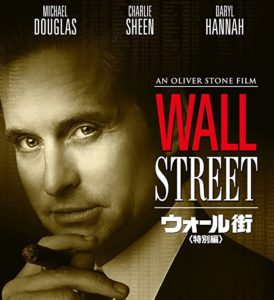

最近のコメント