宮崎駿がファンタジーの姿を借りて描く、青春の蹉跌
『魔女の宅急便』(1989年)は宮崎駿のオリジナル作品ではない。『風の谷のナウシカ』(1984年)から『千と千尋の神隠し』(2001年)に至るまで、彼のフィルモグラフィーでは極めて異質なことだが、角川栄子の童話を下敷きにしている。
彼はこの原作のどこに惹かれたんだろうか?宮崎駿によれば、「主人公のキキは魔法を使うことはできるが、それ以外はどこにでもいる普通の女の子である」 だそうである。
そんな「どこにでもいる」女の子が、見知らぬ街にやってきて悪戦苦闘する様は、現代の若者が都会に上京する様子とリンクする。
キキが用いる「魔法」は、物語内では「絵」や「音楽」や「スポーツ」と何ら変わらない、日常レベルの才能として扱われる。
10代の頃なんぞ、誰でも自らの才能に大きな不安を抱いているものだ。挫折もあればスランプもある。キキが突然魔法が使えなくなったのは、新たなステップを踏み出すために必要な試練。
そんな青春の蹉跌を、宮崎駿はファンタジーの姿を借りて描いてみせる。 『魔女の宅急便』は、宮崎駿が若い世代に送ったエールだ。
絵描きのウルスラ、パン屋のおかみさんのオソノ、そしてキキの良き理解者となる老婦人など、主要キャラクターは全て女性たち。
この映画において、男性たちは驚くほどキキの成長物語に関与しない。彼らは事態を優しく見守る観察者だ。父親にいたってはその存在感を発揮せぬまま、出番を終えてしまう。
自分自身、子供の親である宮崎駿は、「俺達が何をわめこうが、女の子は勝手に成長してどんどんたくましくなっていくんだよ…」と諭す。宮崎アニメに出てくる父親が、やたら物わかりのいいキャラクターなのは、そんな彼の信条によるものなのかもしれない。
しかーし、何も言わなくていいのに何か言ってしまいたくなるのが、この世代の習性。宮崎オジさんの「若者にエールを!!」という説教臭さが、全編で目についてしまうのは、そのせいだ。
絵描きの少女・ウルスラが、落ち込んでいるキキに投げかける言葉は、宮崎駿からのダイレクトなメッセージ。まあ僕ぐらいオトナになれば、素直に「なるほどー」と頷けるけど、反抗期真っ盛りの10代の時分にこんな説教くさいセリフを聞かされても、全く耳に入ってこない。
多くのジブリ作品がそうであるように『魔女の宅急便』もまた、現役の少年・少女ではなく、かつて少年・少女だったオトナたちが狂喜する映画なんである。
- 製作年/1989年
- 製作国/日本
- 上映時間/102分
- 監督/宮崎駿
- 脚本/宮崎駿
- プロデューサー/宮崎駿
- 原作/角野栄子
- 製作/徳間康快、都築幹彦、高木盛久
- 企画/山下辰巳、尾形英夫、瀬藤祝、セトウイワオ
- 音楽/久石譲
- 撮影/杉村重郎
- 美術/大野広司
- 編集/瀬山武司
- 作画監督/大塚伸治、近藤勝也、近藤喜文
- 色彩設計/保田道世
- 高山みなみ
- 佐久間レイ
- 山口勝平
- 信沢三重子
- 戸田恵子
- 三浦浩一
- 関弘子
- 加藤治子
- 井上喜久子
- 土井美加
- 渕崎ゆり子
![魔女の宅急便 [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41mMZFVSnXL.jpg)


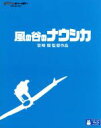
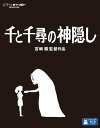







最近のコメント