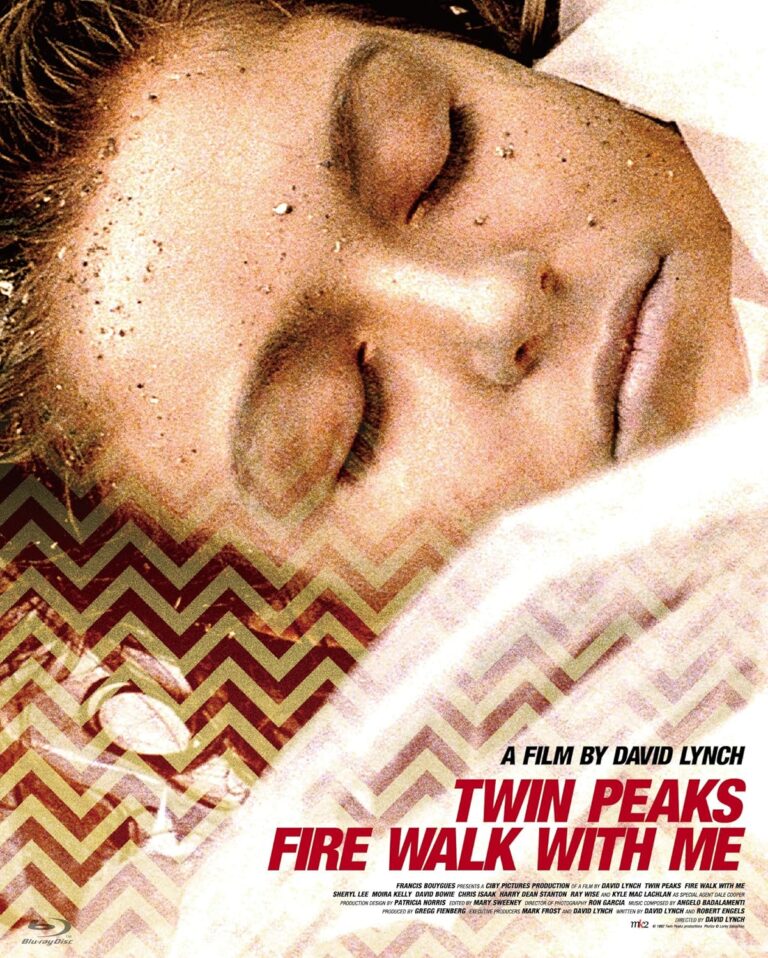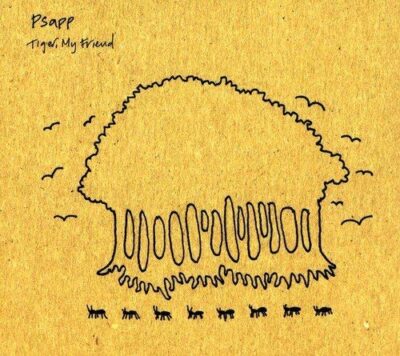『クリーピー 偽りの隣人』(2016)
映画考察・解説・レビュー
『クリーピー 偽りの隣人』(2016年)は、横浜国大で犯罪心理学を教える元刑事・高倉(西島秀俊)が、未解決事件の調査を進めるなかで、新居の隣人・西野(香川照之)とその“異様な”家族関係に違和感を募らせていくサイコロジカル・サスペンス。高倉の妻・康子(竹内結子)は、愛想の良さと不穏さが同居する西野の言動に次第に取り込まれ、夫婦の距離はゆっくりとねじれていく。一方、高倉が追う“家族全員が忽然と消えた失踪事件”は、やがて隣人の正体と恐るべき接点を露わにし、平穏な日常は気づかぬうちに崩落していく。
平凡な郊外に口を開ける奈落
2016年に公開された『クリーピー 偽りの隣人』は、黒沢清が得意とする日常と非日常の境界線を切り裂き、観客の安心感を根こそぎ奪う一本だ。原作は前川裕の小説。
だが小説のプロットに忠実に映画化した作品ではなく、黒沢清的なホラー美学と「人間そのものへの不信感」が濃厚に注ぎ込まれた作品になっている。
舞台は、どこにでもありそうな住宅街。元刑事で犯罪心理学者の高倉(西島秀俊)は、妻・康子(竹内結子)とともに郊外に引っ越してくる。そこで出会うのが、香川照之演じる隣人・西野。にこやかに挨拶を交わすその姿は、表面的にはただのご近所さんにすぎない。だが、その人懐っこさの裏に潜む異様な空気感が、映画の最初から最後まで観客をじわじわと侵食していく。
この「日常の皮膜を少しずらすと異界が顔を出す」という設定は、黒沢清が『回路』(2000年)や『叫』(2007年)で培ってきたホラー演出の核心部分だ。『クリーピー』においてはそれが、幽霊ではなく「人間の顔をした怪物」という最も身近な形をとる。
香川照之の怪演、黒沢清的な家庭崩壊譚
黒沢映画における最大のホラーは、必ずしも恐ろしい出来事そのものではない。むしろ「なぜそんなことをするのか」がわからない人物が、理解不能な行動を積み重ねていくことにある。『クリーピー』でその役を担ったのが、西野だ。
香川照之の演技は圧巻である。にこやかに笑った次の瞬間、目の奥に獣のような空虚さを宿す。その落差こそが観客の神経を逆撫でする。『香川照之の昆虫すごいぜ!』で楽しそうにカマキリ先生に扮していたのは、我々観客を騙すためのかりそめの姿だ。
黒沢清は後年『Cloud クラウド』(2024年)で、菅田将暉に「現代資本主義をそのまま体現する虚無的な主人公」を与えたが、その原型はすでに『クリーピー』の西野にあったとすら思える。
西野には動機がない。欲望もない。ただ「他者を支配する」という行為そのものを愉しんでいるかのように見える。その理解不能性こそが、この映画を恐怖映画の枠に閉じ込めず、不条理劇へと拡張している。
「え?犬にしつけするんですか?いいと思いますよ、そういうの」というイミフすぎるセリフ、最高じゃないですか。
『クリーピー』のもうひとつの軸は、夫婦の亀裂。引っ越しをきっかけにして高倉と康子の関係はゆるやかに壊れていき、妻はいつの間にか西野の「支配の輪」に絡め取られていく。
黒沢清が家庭の崩壊をモチーフとして描くのは、決して本作に限らない。『CURE』(1997年)では、主人公刑事の妻が精神的に病を抱え、夫婦関係が崩れていく過程が、猟奇事件の連鎖と地続きのものとして描かれた。
『回路』(2001年)においても、インターネットを介して人々が孤立していく様は「家族」という共同体を骨抜きにする力として示される。
さらに『岸辺の旅』(2015年)では、すでに死んでいる夫と妻が再会し、日本各地をめぐるロードムービーとして家庭を再構築する試みが描かれるが、そこには「家庭は一度壊れたら二度と元には戻らない」という冷徹な断念も漂っていた。
黒沢清の映画において、家庭は「守られるべき聖域」ではなく、「外部から侵入されることで必ず揺らぐ脆弱な構造物」として繰り返し提示されてきた。
『クリーピー』はその系譜にありつつも、夫婦の不和があまりに唐突で説明を欠き、観客を理性ではなく感情の不安に直撃させる点で、彼のフィルモグラフィーの中でも特に純化された「家庭崩壊ホラー」と言えるだろう。
郊外というホラーの舞台装置
『Cloud クラウド』が「湖畔のホラー」と「廃工場のバイオレンス」を二重構造で描いたように、『クリーピー』もまた郊外住宅街という極めて凡庸な風景をホラー化する。そこには幽霊も怪物も出てこない。ただ「隣人」という最もありふれた存在が、最も得体の知れない恐怖へと変貌する。
この視点の転倒は、黒沢清の持ち味であると同時に、アメリカ映画の「郊外ホラー」の伝統とも共鳴する。例えば、ウェス・クレイヴンの『エルム街の悪夢』(1984年)は、どこにでもある中産階級の住宅街で、超自然的殺人鬼が跳梁するスラッシャー・ムービー。
リチャード・フライシャー監督の『10番街の殺人』(1971年)は、元警察官の温厚な男が実は恐ろしい連続殺人鬼で、新しくアパートに引っ越してきた一家を毒牙にかける物語だった。
さらに近年では『ゲット・アウト』(2017年)が、アメリカ郊外の裕福な家庭を舞台に人種差別ホラーを展開し、「郊外=安全」という幻想を鮮やかに裏返してみせている。
黒沢清は、こうした「郊外の皮膜を破る」物語を日本の風景に置き換えた稀有な作家。日本の住宅街はどこも似通い、匿名性に覆われている。
その匿名性ゆえに、隣人の素性は逆に見えにくく、そこに無限の不安が忍び込む。『クリーピー』は、こうした郊外ホラーの系譜を受け継ぎつつ、日本独自の息苦しさをスクリーンに定着させた作品だと言えるだろう。
『クリーピー 偽りの隣人』は、Jホラーの枠を飛び越えた「人間不信の映画」である。幽霊よりも怖いのは、目の前で笑っている隣人かもしれない。動機や欲望を欠いた人間の存在そのものがホラーである。この作品はその真理を徹底的に突きつける。
黒沢清のホラー作家としての顔と、人間の虚無を描く実存主義的映画作家としての顔。その両面を濃厚に味わえるという点で、『クリーピー』は「お得な2 in 1 Pack」的作品である。
- アカルイミライ(2002年/日本)
- LOFT ロフト(2006年/日本)
- クリーピー 偽りの隣人(2016年/日本)
- Cloud クラウド(2024年/日本)

![クリーピー 偽りの隣人[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/911jGUwfmPL._AC_SL1500_-e1757662832810.jpg)