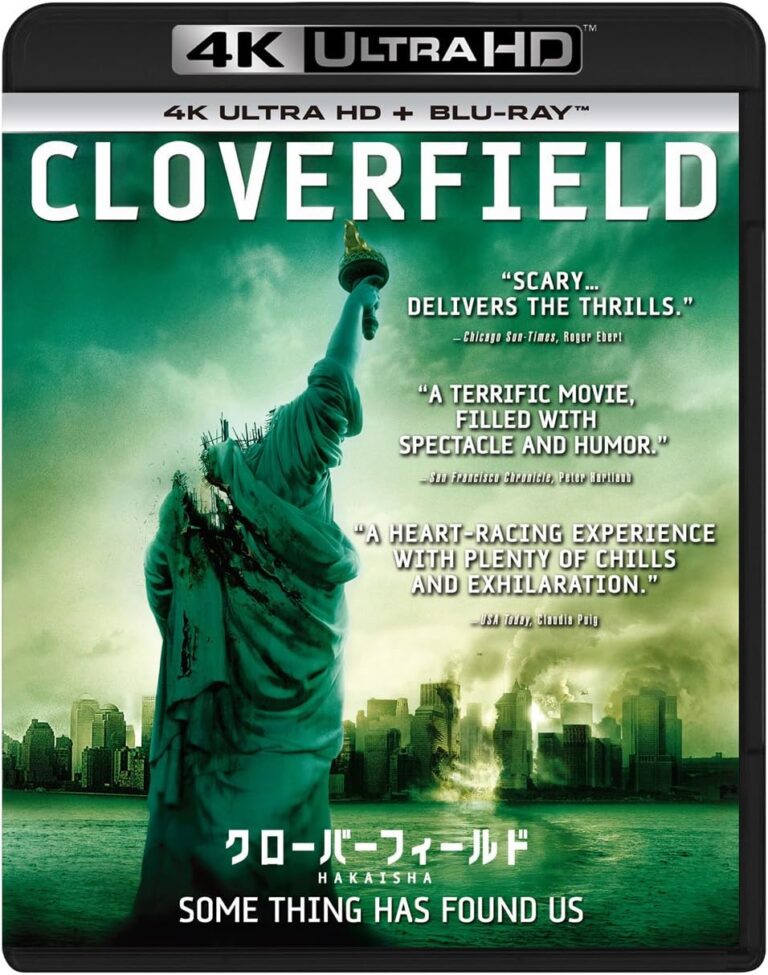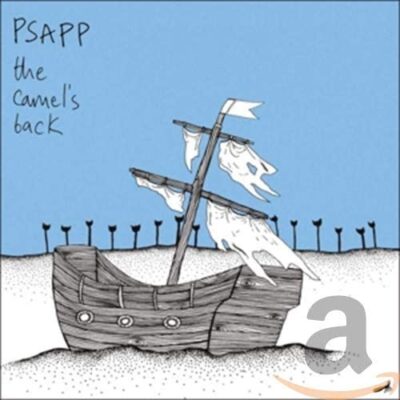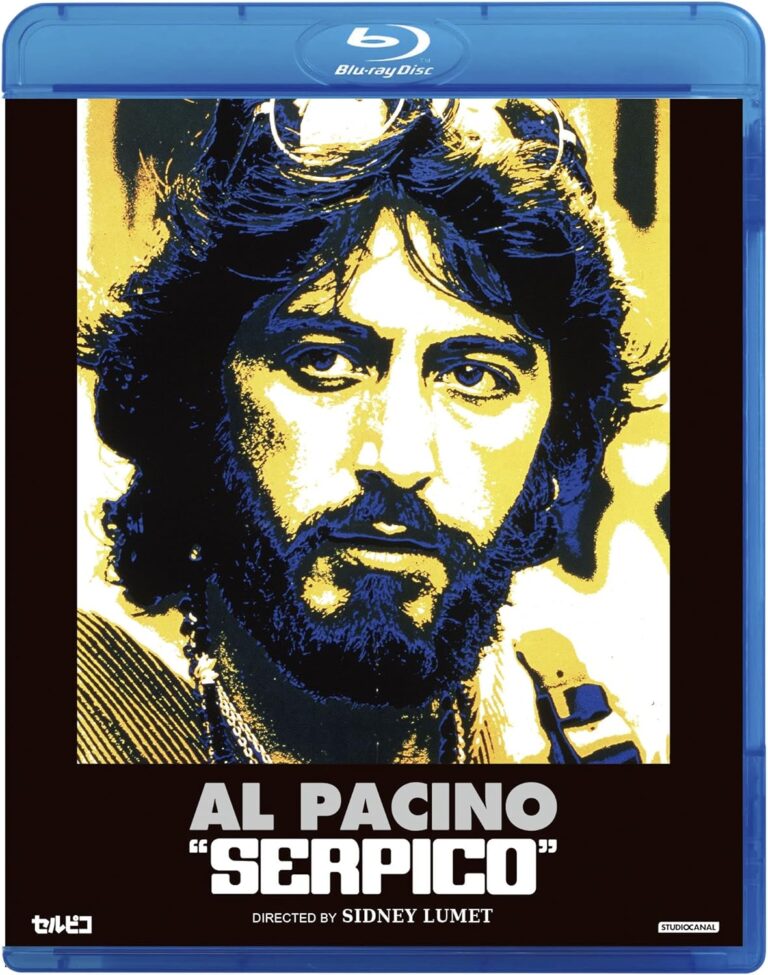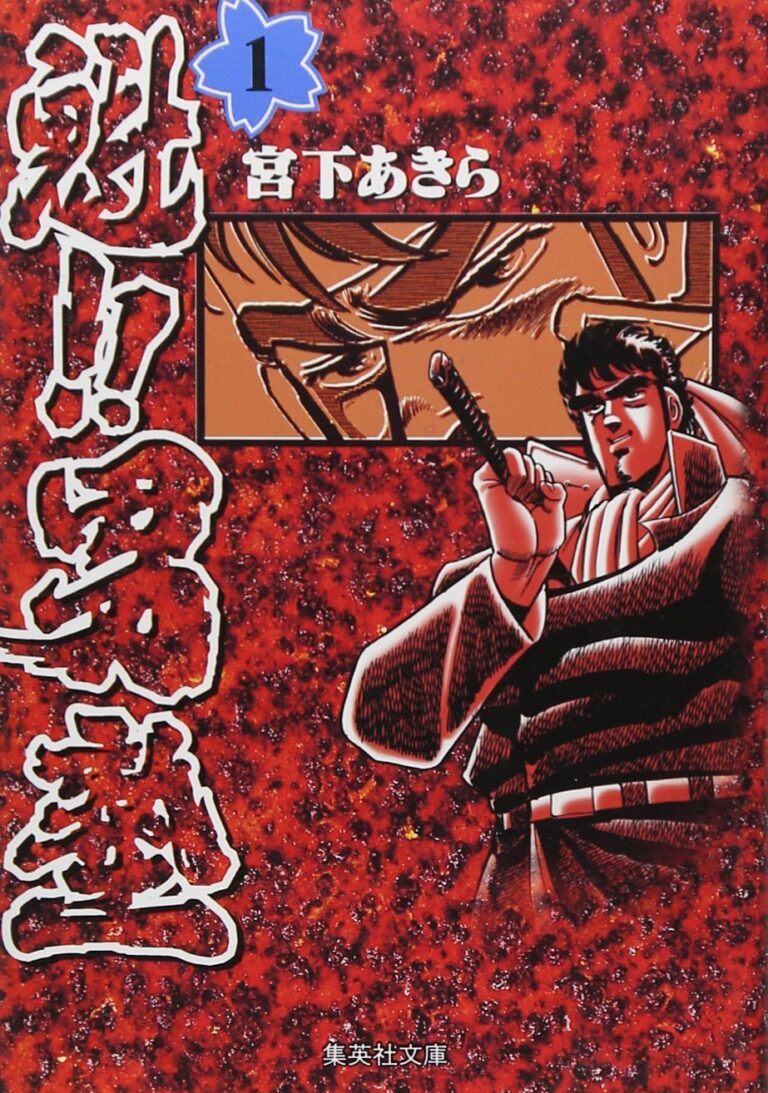『エンド・オブ・デイズ』筋肉と悪魔、世紀末の一騎打ち
『エンド・オブ・デイズ』(1999年)は、ピーター・ハイアムズ監督がアーノルド・シュワルツェネッガーを主演に迎え、世紀末のニューヨークを舞台に“悪魔そのもの”との戦いを描いた黙示録的アクションである。信仰と筋肉、終末と救済──その矛盾を横長の暗闇の中に封じ込めた、映画的終焉の寓話だ。
千年紀の闇──“筋肉神話”の終焉としての『エンド・オブ・デイズ』
宇宙人、殺人マシーン、コマンドー部隊。これまでアーノルド・シュワルツェネッガーは、様々な敵と対峙してきた。だが本作『エンド・オブ・デイズ』(1999年)で彼が相まみえるのは、最強にして最古の敵──“悪魔そのもの”である。
世界の終焉を目前にしたニューヨークを舞台に、堕落した男が再び信仰と戦闘の意味を取り戻すという物語は、ある意味で彼のキャリアにおける最終的な儀式のようでもある。
世紀末的モチーフ、バチカン、黙示録、処女受胎、悪魔憑依──そのあまりの“詰め込み感”に強引さを感じなくもない。しかしホラーとアクションという異なるジャンルを、シュワルツェネッガーという俳優の肉体を媒介に接合させたその試み自体が、90年代アメリカ映画のジャンル実験の象徴だった。
監督はピーター・ハイアムズ。『カプリコン・1』(1977年)や『アウトランド』(1981年)で、シネマスコープの横長画面を駆使して孤高の男と巨大な権力構造との対峙を描いてきた“職人作家”だ。彼がこの映画に持ち込んだのは、単なるエンタメ的興奮ではなく、“終末のリアリズム”とでも呼ぶべき冷徹な視覚秩序だった。
終末の都市──閉ざされた神話空間としてのニューヨーク
ハイアムズが本作で構築するのは、宗教都市ローマではなく、世俗の迷宮ニューヨークである。そこでは高層ビルが教会の鐘楼に代わり、地下鉄が冥界への通路となる。都市そのものが“地獄の門”として描かれているのだ。
彼のカメラは常に暗く、光源が限定されている。霧、炎、影、反射──それらが画面を満たす。ハイアムズが得意とするロングレンズ撮影により、空間は圧縮され、人物は逃げ場を失う。『アウトランド』で描かれた宇宙ステーションの閉塞感は、この終末都市にそのまま転写されている。
ニューヨークという人工の洞窟において、悪魔は人間社会の最奥から出現する。バチカンではなくウォール街、修道士ではなく株式仲介人──ハイアムズは“信仰の堕落”をこのような舞台転換で象徴する。神の不在を宣告するのは、十字架ではなくネオンサインである。
悪魔の顔──ガブリエル・バーンという「虚無の俳優」
悪魔を演じるのはガブリエル・バーン。冷ややかな眼差しと計算された抑制演技で、彼は超自然的存在を“知的虚無”として体現する。教典的威厳やホラー的誇張に頼らず、都市のエリートの姿のまま人間の肉体に宿る悪魔──その造形が現代的恐怖を喚起する。
バーンが演じる悪魔は、暴力ではなく言葉で人間を誘惑する。「神はお前を見捨てた」と囁くその声は、火炎放射器よりも破壊的だ。ハイアムズはこの“言葉の悪魔”を、宗教的存在というよりも心理的ウイルスとして描く。90年代末という、宗教とテクノロジーが交錯する時代において、悪魔はもはや赤い角を持たない。彼はネクタイを締め、携帯電話を手にして現れる。
バーンの演技は、やがて“堕落した神”のような寂寞を帯びていく。恐怖よりも虚無、悪意よりも疲労。ハイアムズのカメラはその表情を長回しで捉え、観客に悪魔の“人間的哀しみ”を覗かせる。ここに、単なるホラーではない、宗教寓話としての深みがある。
筋肉の終焉──シュワルツェネッガーの“信仰”と肉体の崩壊
シュワルツェネッガー演じる主人公・ジェリコは、家族を失い、自殺未遂を経て、もはや信仰も希望も失った男として登場する。この設定は、彼のキャリアにおける自己解体の試みでもある。超人ヒーローから人間への転落。だが残念ながら、その“落差”は十分に表現されていない。
彼の悲嘆は筋肉の陰に隠れ、心理的苦悩はアクション的爆発によって中和されてしまう。涙よりも弾丸、祈りよりも銃撃。シュワルツェネッガーという俳優は、依然として“解体不能な肉体”の象徴であり続ける。ハイアムズのリアリズムがそこに倫理を与えようとするものの、彼の身体はあまりにも神話的で、現実を拒む。
だが逆説的に言えば、この“失敗”こそが映画の魅力でもある。神を信じられない男が、神の不在の中で悪魔と戦う──それはまさに、ポスト冷戦時代におけるアメリカ的アイデンティティの象徴だ。
信仰の代わりに筋肉を信じ、祈りの代わりに銃を構える。『エンド・オブ・デイズ』は、そんな信仰なき時代の祈りの映画なのである。
“愛の力”という終末──ジャンルの衝突が生んだ寓話
クライマックス、ジェリコは悪魔に憑依された肉体を自らの犠牲によって封じ、“愛の力”で世界を救う。この展開はあまりにも古典的で、あまりにも凡庸だ。だが、ハイアムズはその陳腐さを逆手に取る。彼が描く“愛”とは、宗教的救済ではなく、絶望に抗うための最後の筋肉運動に過ぎない。
火と光に包まれるラストの構図は、ハイアムズ特有の陰影構成の頂点であり、同時に“映画的終末”のメタファーでもある。画面の横幅いっぱいに広がる火柱と、孤立した人間のシルエット。彼の映画では常に、広さが孤独を意味する。ワイドスクリーンとは、神のいない世界での十字架なのである。
『エンド・オブ・デイズ』は、完璧な作品ではない。だがそれは、筋肉と信仰、アクションとホラー、肉体と魂──あらゆる矛盾を抱えたまま、時代の終わりに生まれた一篇の黙示録的映画である。
ハイアムズはこの作品で、アクションの終焉と映画の終焉を重ね合わせる。終末に立ち尽くすシュワルツェネッガーの姿は、もはや救世主ではない。彼は、映画という信仰の最後の信徒だったのだ。
- 原題/End Of Days
- 製作年/1999年
- 製作国/アメリカ
- 上映時間/122分
- 監督/ピーター・ハイアムズ
- 製作/アーミアン・バーンスタイン、ビル・ボーデン
- 脚本/アンドリュー・ダブリュ・マーロー
- 音楽/ジョン・デブニー
- 美術/リチャード・ホランド
- 撮影/ピーター・ハイアムズ
- 編集/スティーヴン・ケンパー
- 衣装/ボビー・マニックス
- アーノルド・シュワルツネッガー
- ガブリエル・バーン
- ロビン・タニー
- ロッド・スタイガー
- ケビン・ポラック
- CCH・パウンダー

![エンド・オブ・デイズ/ピーター・ハイアムズ[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/71U22xvzRQL._AC_SL1240_-e1759059138595.jpg)