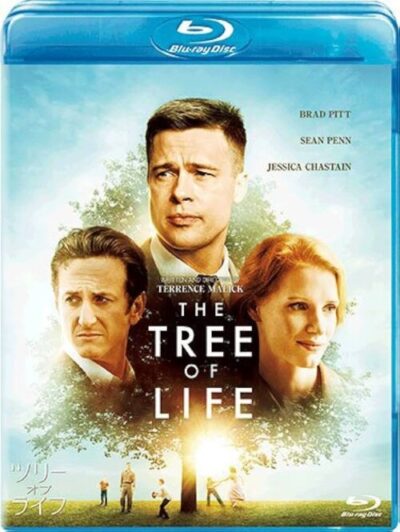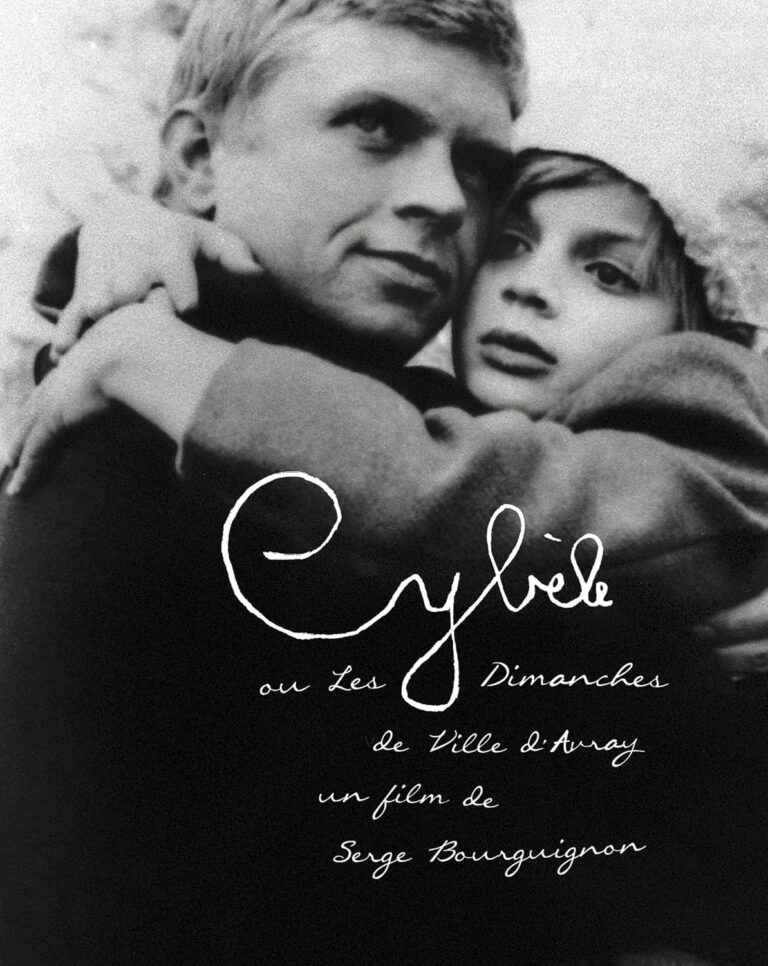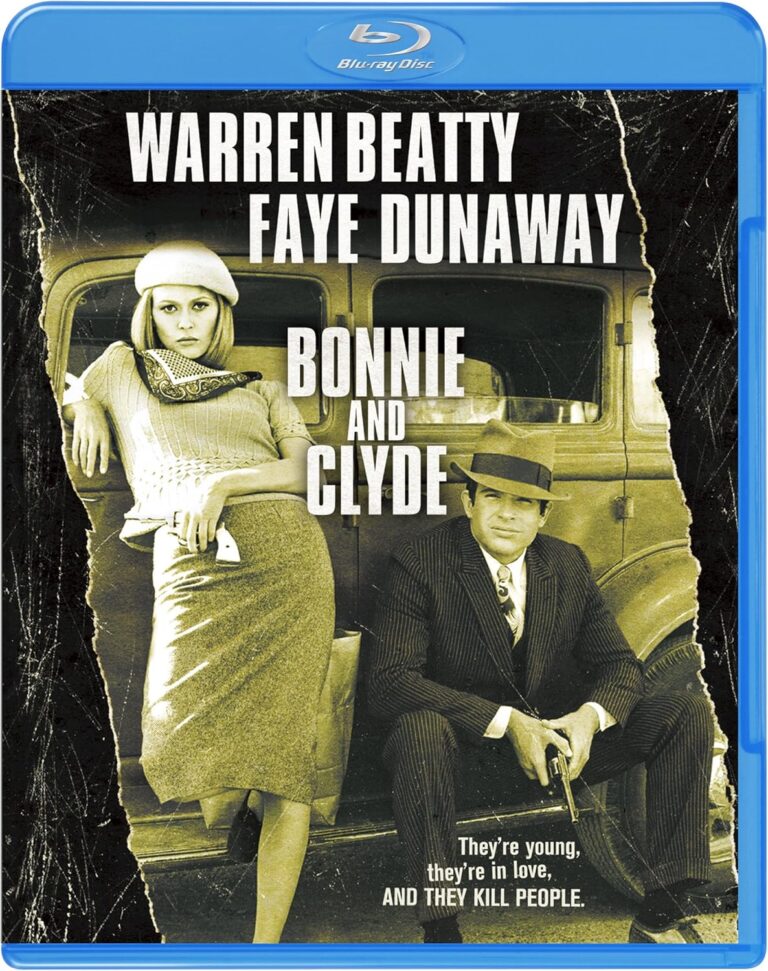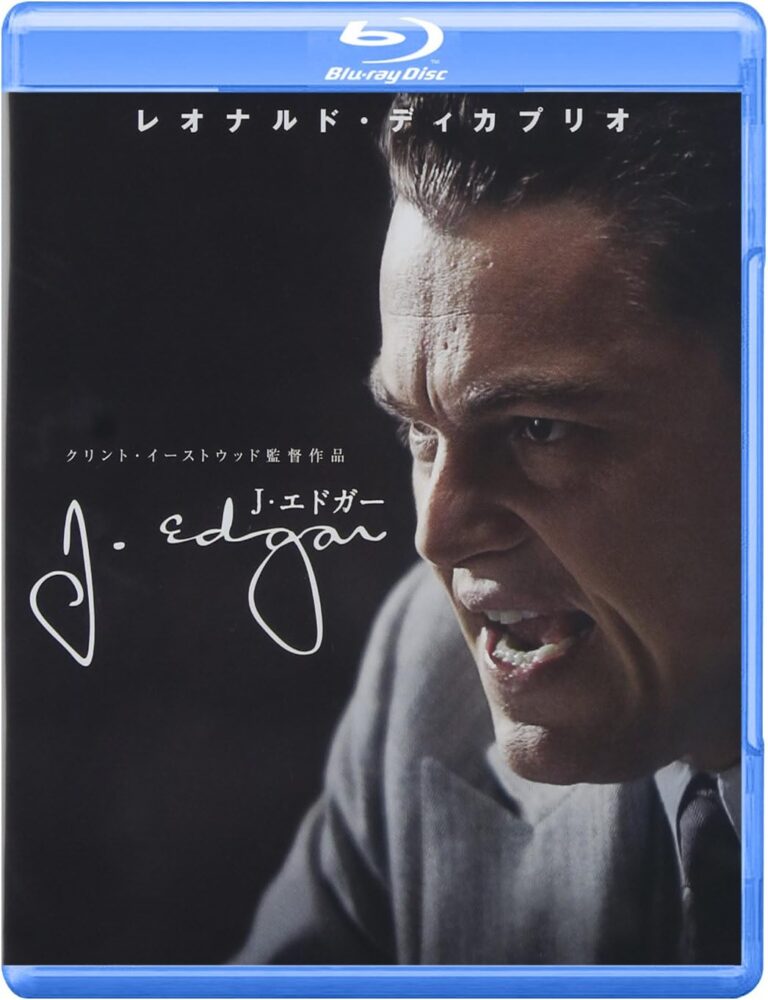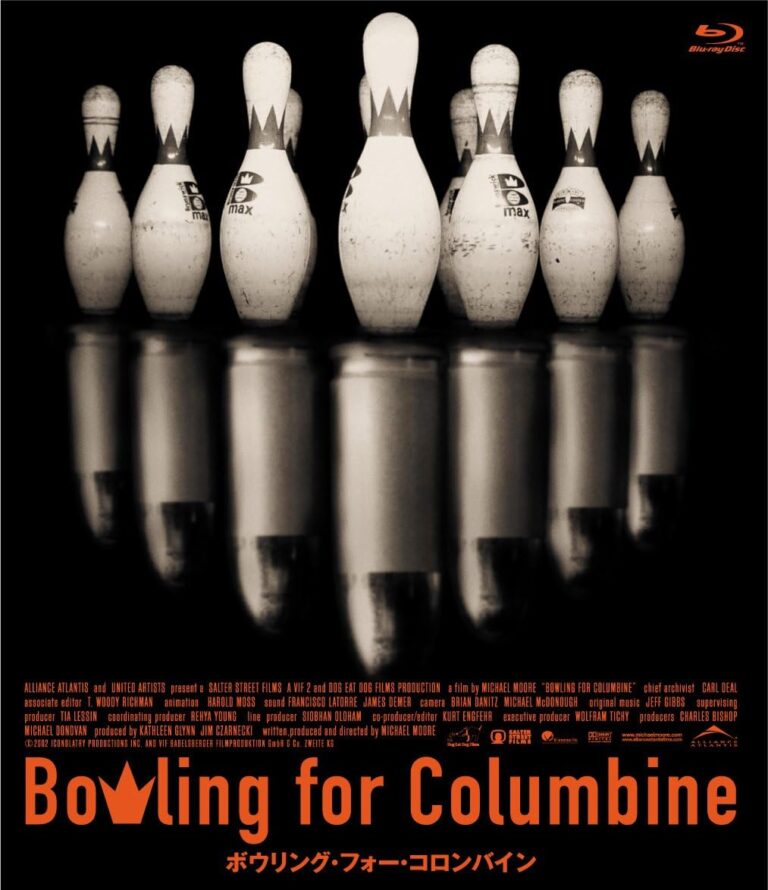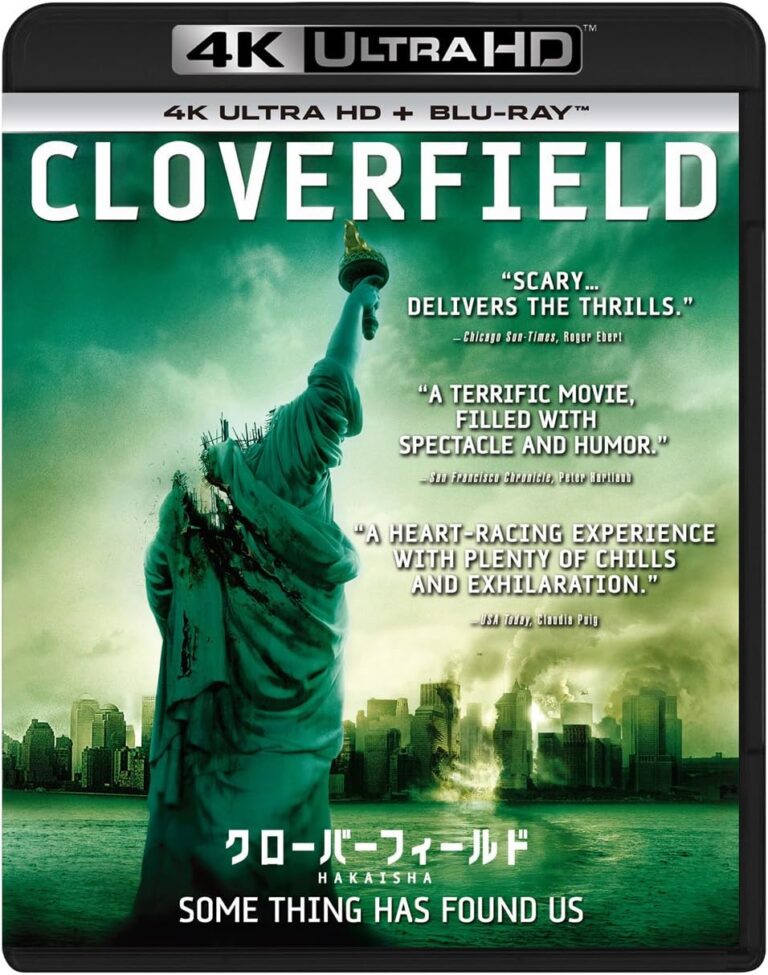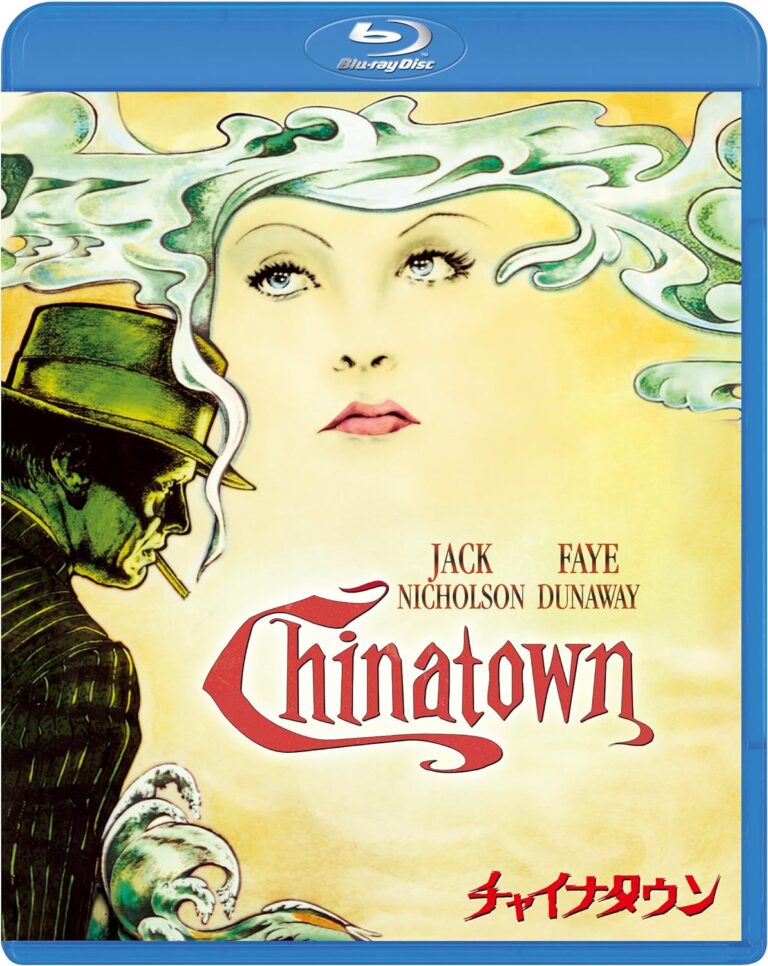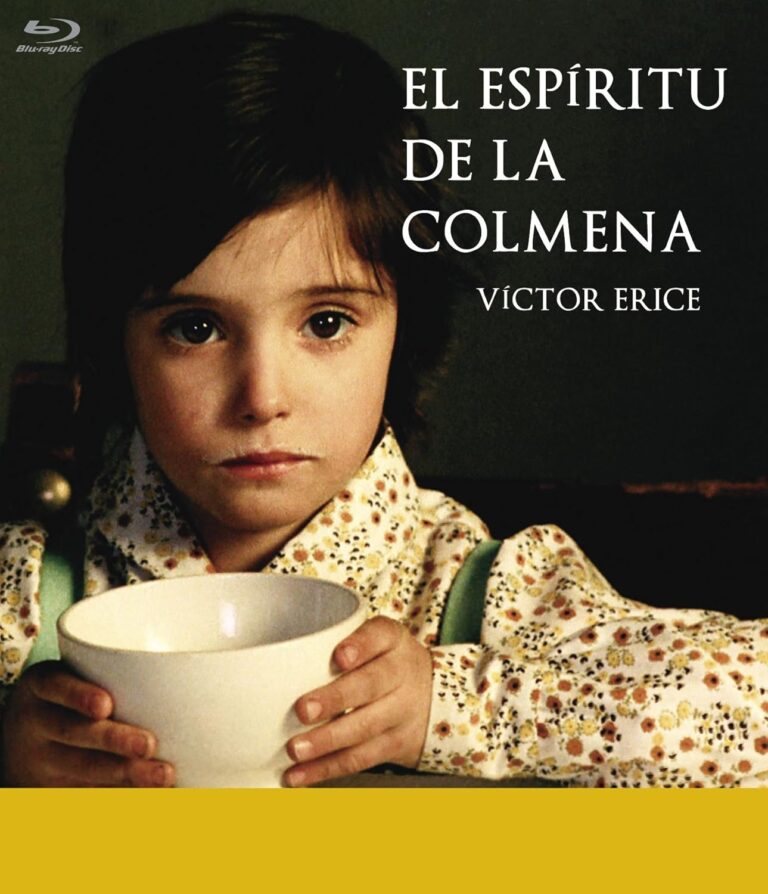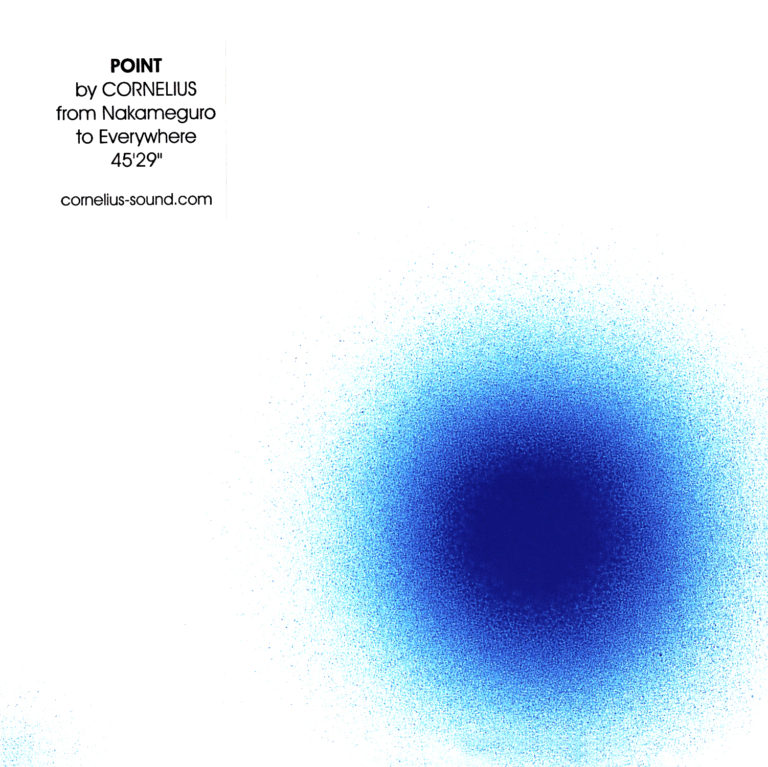【ネタバレ】『獲物の分け前』(1966)
映画考察・解説・レビュー
『獲物の分け前』(原題:La Curée/1966年)は、ロジェ・ヴァディム監督がゾラの小説『はらわた』を下敷きに描く不倫劇である。舞台はパリのブルジョワ社会。若い妻ルネと年上の夫、そして愛人マクシムの三角関係が、金と欲望の連鎖の中で崩壊していく。豪奢な屋敷と温室の光が、愛と制度の歪みを照らし出し、やがて誰もが快楽の罠に囚われていく。
メタ・エロティカが暴く支配と被写体
タイトル『獲物の分け前』(1966年)と聞いて、血の匂いがプンプン漂うギャング映画を想像した、そこのお前!アラン・ドロンやジャン=ポール・ベルモンドが葉巻を咥えて、マシンガンをぶっ放すマッチョなフレンチ・ノワール……かと思いきや、大間違いだ!
稀代のプレイボーイ監督ロジェ・ヴァディムがここで提示するのは、19世紀の文豪エミール・ゾラの自然主義文学を下敷きにした、退廃と官能が渦巻くドロドロの不倫悲劇である。
舞台は1960年代、狂乱のパリ・ブルジョワ社会。莫大な金と果てしない欲望が交錯する閉鎖空間で、人間関係がまるで狩りの「獲物」のように容赦なく解体され、冷酷に分配され、そして消費され尽くしていくのだ。
原作が持つ重苦しい社会批判の視点を引き継ぎながらも、エロスの魔術師ヴァディムの狙いは全く別の場所にある。彼は道徳や教訓なんかより、圧倒的な官能をスクリーンのド真ん中に据え付けたのだ。
そこでは、ブルジョワの抑圧された欲望が制度の外側へとドバドバと溢れ出し、強烈な視覚的快楽が倫理観をドロドロに侵食していく。映画は、上流社会が生み出す「美」と「退廃」のギリギリの均衡を、きわめて変態的で映像的な筆致で炙り出していくのである。
そして何より、主人公の若き人妻ルネを演じるのは、当時ヴァディムの実の妻であったジェーン・フォンダだ。彼女の瑞々しい身体は、夫である監督の舐め回すようなレンズによって、徹底的に極上のオブジェとして消費されていく。
名カメラマンであるクロード・ルノワールが捉える温室に射し込む柔らかな光、水面の妖しいゆらめき、そして幾度となく繰り返される不気味な鏡像。ヴァディムは妻の肉体を執拗に撮ることで、被写体と撮影者の間にある「支配と服従」の倒錯した関係性を、これでもかと可視化しているのだ!
劇中の愛の場面は、常に演出過剰で異常なまでに装飾的である。フォンダが惜しげもなく美しい肌を露わにするたび、愛という純粋な感情は、ヴァディムのドス黒い映像的欲求へと強制的に変換されていく。
つまりこの映画は、夫が妻を美しい被写体として完全に支配するポルノグラフィー的構造そのものであり、同時にその歪んだ構造自体を批評する高度なメタ・エロティカとして機能しているのだ!
フォンダの虚無的で無表情な眼差しが示すのは、満たされない快楽の空虚である。彼女が求めているのは愛ではない。「愛されることの演出」なのだ。欲望ではなく、「欲望を演じること」なのだ!
彼女はヴァディムのカメラに「撮られる」ことを通じてのみ、ギリギリのところで自身の存在意義を確認しているのである。最高に歪んでいて、最高に美しいぜ!
仮面劇と化したブルジョワの不倫
物語の主戦場となるのは、冷酷な初老の夫アレクサンドル(ミシェル・ピコリ)の豪邸だ。そしてルネが禁断の恋に落ちる相手は、なんと夫の先妻の息子である若きマクシム(ピーター・マクネリー)である。
この背徳の恋人たちが密会するマクシムの部屋を覆い尽くしているのは、異様なチャイニーズ・テイストの装飾、どこからともなく聴こえてくるエスニックな旋律、そして壁に飾られた不気味な京劇の仮面だ。
ヴァディムがここで唐突に導入するトンチキな東洋趣味は、決して異文化への深いリスペクトなどではない。エロスの表面をひたすらデコラティブに装飾するための、チープでキッチュな意匠に過ぎないのだ。
ジェーン・フォンダが顔面パックを施してベッドに横たわり、そこにマクシムがド派手な京劇の衣装を着て迫りくる異常な場面。ここは間違いなく本作における狂気の象徴的頂点である!サッパリ分からない!
だが、この滑稽なコスプレごっこによって、二人は「仮面を被った者たち」として交わるのだ。そこでは生々しいはずの肉体の触れ合いさえもが、完全に空々しい演技へと変わってしまう。大量の文化的引用が、彼らの間にある「本当の感情の不在」を必死に覆い隠しているのである。
この過剰な異国趣味は、男女の情念を燃え上がらせるどころか、ぽっかりと空いた感情の空洞を彩るただのハリボテだ。ヴァディムは、「愛の消費社会化」という極めて現代的なテーマを、この悪趣味なセット美術によって視覚的に表現し切ってみせたのだ!
中国風の調度品や音楽は、愛という神聖なものが異文化の仮面を被ることで滑稽化し、チープなゲームへと成り下がっていく過程を残酷に映し出す。エキゾチシズムとは異文化の理解ではない。自分たちの空っぽな欲望を演出するための、都合のいい文化利用にほかならないのだ!
物語の帰結はあまりにも単純で残酷である。若い妻は金持ちで権力者の年上の夫を捨て、同世代の若き愛人との愛にすべてを賭けて走る。だが、愛人マクシムは結局のところ、ルネを裏切り、自分と同じ階層の金持ちの娘との堅実な結婚をあっさりと選んでしまうのだ!
すべてを失ったルネは完全に孤立し、行き場のない欲望の熱に一人で焼かれながら崩れ落ちていく。だが、ヴァディムの関心はそんな陳腐なメロドラマの因果応報にはない!
彼が冷徹なカメラで暴き出すのは、愛という一見ピュアな感情が、ブルジョワジーの制度の中でいかにして形式化され、そして無惨に商品化されていくかという絶望的なシステムそのものなのだ。
彼らにとって愛とは契約であり、暇つぶしの消費であり、社会的ポジションを再生産するためのツールに過ぎない。フォンダ演じるルネは、その強固な制度からうっかりはみ出してしまった瞬間に、見事に自我を喪失して破滅する。
つまり、この映画には「愛の主体」など最初からどこにも存在しないのだ!あるのは、愛という美しい言葉の響きを利用して、自己の欲望を必死に演出する人間たちの空しい虚構だけである。
ゾラの自然主義文学が19世紀の社会構造の暴力をペンで暴き出したように、ヴァディムは20世紀の「映像の暴力」をもってその惨劇をスクリーンに再現してみせた。彼にとってエロティシズムとは、単なるお色気ではない。社会的腐敗を最も美しく可視化するための、最強の武器なのである!
永遠に封じ込められた美神
物語が終局へと向かう中、ヴァディムの冷酷なカメラは最後までルネの愛を救済しようとはしない。彼女が狂おしいほどに求めた快楽の代償は、あまりにも重い。
愛欲の舞台となった温室の光はやがて凍りつくように冷たくなり、精神を破壊されたフォンダの美しい身体は、もはや生きた被写体ではなく、ただの抜け殻のような「残像」と化してしまうのだ。
美は残酷なまでに消費し尽くされ、はみ出した快楽は結局のところ、冷徹な夫アレクサンドルが支配する強固なブルジョワ制度の中へと完全に回収されてしまう。
すべてが終わった後にスクリーンに残されるのは、空っぽで虚ろな静寂と、映像という名の牢獄の中に永遠に封じ込められた一瞬の肉体の輝きだけだ。
ロジェ・ヴァディムがこの映画で成し遂げた最大の恐るべき達成とは、「愛」と「映像」の完全なる同一化である!愛というものは、カメラのレンズを通してフィルムに定着させられたその瞬間に、標本のように死んでしまう。それこそが『獲物の分け前』という映画が突きつける、底知れなく冷たい核心なのだ。
エミール・ゾラが19世紀のパリで暴き出したブルジョワジーのドス黒い偽善を、ヴァディムは1960年代のポップでエロティックな「20世紀的欲望の様式」として見事に再構築してみせた。
この映画の中で輝く圧倒的な美しさは、実は人間性の腐敗が始まっていることの危険な兆候なのだ。そして画面に横溢する官能は、もはや死に体となったブルジョワ制度を無理やり延命させるための、人工心肺装置のようなものである。
ラストシーンで、すべてを失ったフォンダの顔からふっと微笑みが消え去るその瞬間、我々観客は背筋の凍るような真実を理解する。人間の快楽や美しさというものは、現実世界では一瞬で腐り落ちてしまう儚い幻影に過ぎない。
それは常に「映像」という虚構の箱の中でのみ、永遠の命を与えられて生き延びることができるのだと!本作は、ただの不倫映画でも、単なるアイドル女優のヌード映画でもない。
映画というメディアが人間の愛と欲望をいかにして搾取し、標本として保存するかを描き切った、残酷なまでに美しい映像ドラッグなのだ。ジェーン・フォンダというミューズを極限まで消費し尽くしたヴァディムの異常な執念に、ただただひれ伏すしかない。
断言しよう、これほどまでに退廃の美学を極めた映画は、後にも先にも存在しない。
- 監督/ロジェ・ヴァディム
- 脚本/ロジェ・ヴァディム、ジャン・コー
- 製作/ロジェ・ヴァディム
- 製作総指揮/エミール・ゾラ
- 撮影/クロード・ルノワール
- 音楽/ジャン・ブシェティー、ジャン・ピエール・ブルテール
- 編集/ヴィクトリア・メルカントン
- 獲物の分け前(1966年/フランス)
![獲物の分け前/ロジェ・ヴァディム[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/51uolFCwsxL._AC_UL640_FMwebp_QL65_-e1762657184435.webp)