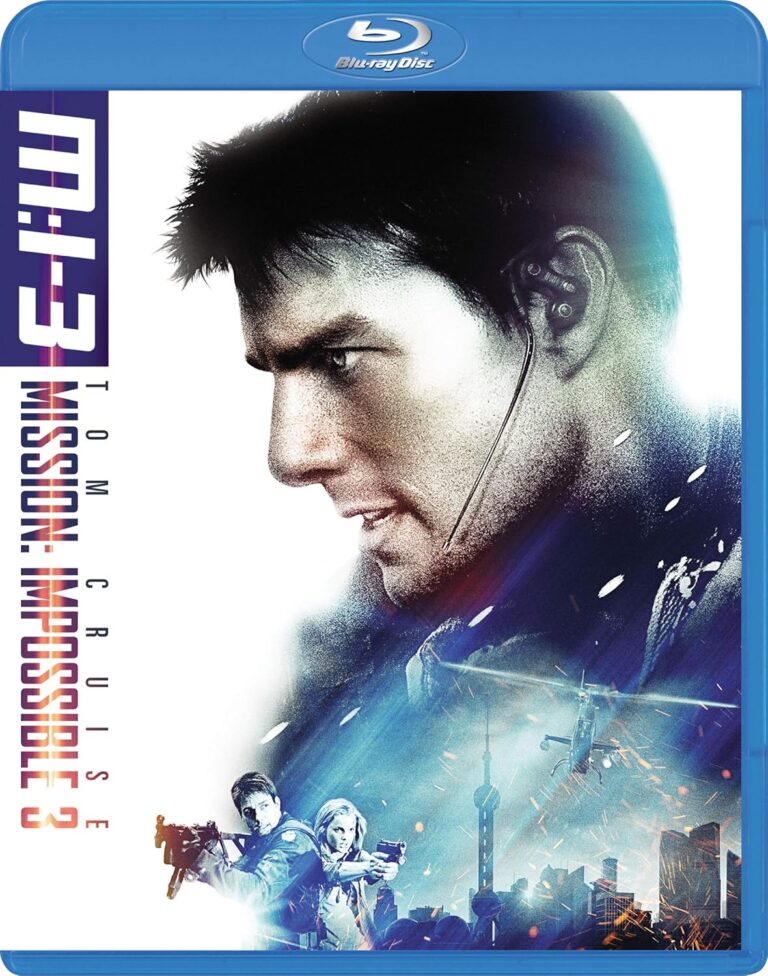『無常』(1970)
映画考察・解説・レビュー
『無常』(1970年)は、実相寺昭雄監督が手がけた劇場映画で、地方の寺院を舞台に、複数の家族関係や人間関係が交錯する物語。僧侶の家に暮らす青年・俊道は、姉の美也や母ミツとの複雑な関係に翻弄され、周囲の大人たちの思惑に巻き込まれていく。寺の檀家や住職の関係者は、家業の継承や寺のあり方をめぐって意見を交わし、俊道の行動は家族だけでなく地域の人々にも影響を与え始める。俊道は外部の女性・克子とも関わりを持つようになり、その関係が新たな対立を生む中、寺にまつわる人々の意識や態度が揺れ動き、複数の家庭と寺院を巡る状況が緊張の方向へ向かっていく。
宗教性と仏教的モチーフ
姉弟相姦に母子相姦に3P、これまさにアンチ・モラルの無限地獄!
『無常』(1970年)は、琵琶湖近くの旧家という日本的風土のなかで、ハードコアな濃厚エロスが醸成される激ヤバムービー。さすがは実相寺昭雄、劇場用映画第一作となる『無常』から、トンデモな映画をドロップしてしまった。
『無常』というタイトル自体が示すように、本作は徹底的に仏教的な思考と結びついている。主人公・正夫(田村亮)は、父の家業=現世的義務を拒絶し、仏像制作に取り憑かれる。彼にとって仏像は信仰の対象ではなく、自らの存在を投影するものだ。ここで重要なのは、仏像そのものが「無常」を体現するオブジェとして提示される点にある。
正夫は姉・百合(司美智子)と関係を結び、師の妻とも交わり、「これが自然なんや」とのたまう。世俗のモラルなんぞアウト・オブ・眼中。それは快楽主義でも放埒でもなく、むしろ宗教的枠組みの転倒。彼にとって“自然”とは、倫理を超えた「存在そのもの」の肯定であり、そこに罪も罰も存在しない。性愛は宗教的な「空」を実証する手段にすぎないのだ。
この宗教とエロスの結合は、日本映画史的にも重要な意味を持つ。大島渚『愛のコリーダ』(1976年)が実在事件をもとに「性愛=死の聖域」を描き出す以前に、実相寺はすでに性愛を仏教的な「無」と結びつける実験を行っていた。宗教的秩序を維持するのではなく、性愛を通じて宗教を「無化」する。『無常』はその倒錯的で過激な実験の第一歩なのである。
エロティシズムの系譜
『無常』を単なるエロ映画として語るのは容易だ。この作品は、姉弟相姦、母子相姦、3Pと、性的タブーを、これでもかと並べ立てている。しかしその本質は、決して官能の提供ではない。むしろ観客に「タブーの無化」を突きつけ、道徳的秩序の外へと放り出すところにある。
ここで比較すべきは澁澤龍彦の思想だろう。澁澤は『快楽主義の哲学』において倒錯と悦楽を文化史的に正当化し、快楽を祝祭として称揚した。だが実相寺は祝祭性を完全に欠いている。彼の性愛は決して楽しくも祝祭的でもなく、ただ「存在そのものを確認する実験」でしかない。
つまり澁澤が「快楽を美学化」したのに対し、実相寺は「快楽を哲学化」した。結果として『無常』は日活ロマンポルノの官能映画とは一線を画し、日本映画史における“哲学的エロス映画”という独自ジャンルを切り拓いたのである。
哲学的読解の可能性
正夫の「地獄も極楽も存在しない」という言葉は、単なる無神論的放言ではなく、実存主義的徹底の表現だ。いやいや、サルトルかよ!彼が「実存は本質に先立つ」と宣言したように、正夫は倫理や宗教の枠組みを超えて「存在そのもの」を肯定する。
その存在肯定は、姉弟相姦や母子相姦といった極端な実践として現れる。ここで観客は二重の不快を味わうことになる。ひとつは、道徳的禁忌の侵犯に対する本能的嫌悪。もうひとつは、不気味なほど徹底された、禁忌を侵犯する彼の論理だ。
この論理の徹底性は、カフカの不条理文学を想起させる。『審判』や『城』の登場人物たちは、理由もわからぬまま裁かれるが、その背後に合理的秩序は存在しない。正夫もまた、性愛という行為を繰り返しながら、その背後に「神も罰も存在しない世界」を提示する。その徹底ぶりは、まるでベケットの『ゴドーを待ちながら』のようだ。
つまり『無常』は、エロス映画であると同時に、日本映画における“不条理劇”の一形態でもある。性という人間の根源的行為を通じて、不条理な存在のあり方を剔抉しているのだ。
大島渚、ブニュエル、パゾリーニとの比較
大島渚と実相寺昭雄は、1960〜70年代の日本映画において、ともに“性愛を武器にした破壊者”だった。ただしそのベクトルは大きく異なる。
大島は『日本春歌考』(1967年)や『愛のコリーダ』(1976年)において、性愛を社会秩序の批判のために用いた。性愛は社会的規範を破壊する装置であり、検閲制度や家父長制、戦後民主主義そのものへの攻撃だったのだ。
対して実相寺は、性愛を社会ではなく宗教と哲学の解体装置として用いる。すなわち、「極楽も地獄も存在しない」という宗教的虚無を証明するための論理的実験。社会批判ではなく存在論的破壊なのだ。
それはむしろ、ルイス・ブニュエルやピエル・パオロ・パゾリーニといった、同時代の監督たちとの共振といえるかもしれない。
ルイス・ブニュエルは『銀河』(1969年)で、カトリック教義を徹底的に脱構築し、宗教的虚無を寓話化した。実相寺の「地獄も極楽も存在しない」という論理は、まさにブニュエル的反宗教精神の日本的翻訳である。
パゾリーニの『テオレマ』(1968年)は、超越的存在が一家の秩序を性愛を通じて破壊する物語。性愛と宗教を直結させる点で、『無常』と響き合う。さらに『ソドムの市』(1975年)では、性と暴力を極限まで突き詰め、倫理を完全に無化する。これは『無常』のタブー破壊の延長線上に位置づけられる。
すなわち『無常』は、孤立した日本映画ではなく、ブニュエル、パゾリーニと並んで、“国際的アンチ・モラル映画運動”の一翼を担っていたと見るべきなのだ。
キャスティングの異化効果
それにしても映画の冒頭近く、野武士の格好をして乱入してきた小林昭二はいったい何だったのだろう。実相寺昭雄が監督をしていた『ウルトラマン』(1966年〜1967年)繋がりのキャスティングだったにせよ、あのムラマツキャップがキチ◯イ系の役で数秒だけ出演、というのは、逆に殺傷力ありすぎ。
当時の子どもや親世代にとって彼は「父性的権威」の象徴だった。その彼が突如、狂気を帯びた役で登場すること自体が、観客の認識を破壊してしまう。
仏像師のドラ息子役は、『宇宙戦艦ヤマト』(1974年〜1975年)の主題歌でもお馴染みの佐々木功。さすが、若い頃からいい声している。義母とセックスするシーンで、どこからか「次は胸の運動~」なんていうラジオ体操が流れてくるシーンはちょっと笑ってしまったが。
深読みすれば、実相寺は「役者の既知のイメージ」を意図的に裏切るために、このようなキャスティングをしたのかもしれない。観客にとって親しみ深い彼らをアナーキーな文脈に投入することで、作品全体が「安心の解体装置」として機能する。単なる配役ではなく、映画の主題そのものをキャスティングで体現したのかもしれない。
’60〜’70年代アナーキー文化との共鳴
1970年前後の日本社会は、学生運動の終焉と共に大きな転換点を迎えていた。東大安田講堂事件(1969年)を象徴とするように、政治的イデオロギーの敗北が若者に強い幻滅を与えた。理念を掲げた闘争が挫折し、残されたのは虚無感と「体制に対する漠然とした不信」だった。
『無常』における正夫の姿勢──「極楽も地獄も存在しない」という断言──は、この時代精神と強く共鳴する。宗教的秩序だけでなく、戦後民主主義が提示してきた“進歩”“理性”“正義”といった理念もすべて無効化される。つまり彼の言葉は、単なる宗教批判ではなく、当時の社会そのものに対する「存在論的な拒否宣言」だったのである。
松竹ヌーヴェルヴァーグは大島渚や吉田喜重らによって社会批判の鋭利な矢を放ったが、『無常』はその終焉期に制作された。だがそれは後退や模倣ではなく、むしろ「政治的アナーキーが文化的アナーキーに転換した瞬間」を刻印している。政治の言葉が無力化した後に残された“実存的アナーキー”──その映画的表現が『無常』なのだ。
そう、つまりこの映画は、実相寺昭雄が放ったアンチ・モラルの宣言なのだ。
性愛と宗教、モラルと虚無、テレビ的映像感覚と哲学的討論。その後の『曼陀羅』(1971年)、『哥』(1972年)へと連なる実相寺の系譜を開き、大島渚や澁澤龍彦との思想的対話に位置づけられ、さらにブニュエルやパゾリーニと共鳴する。『無常』は、日本映画の中で最も孤独で、そして最も世界的な“アナーキー映画”なのである。
- 製作年/1970年
- 製作国/日本
- 上映時間/143分
- 監督/実相寺昭雄
- 脚本/石堂淑朗
- 製作/淡島昭
- 撮影/稲垣涌三、中堀正夫、大根田和美
- 音楽/冬木透
- 編集/柳川義博
- 美術/池谷仙克
- 録音/大沢哲三、泉田正雄、広瀬浩一
- 照明/佐野武治、林光夫、加藤慶一
- 田村亮
- 司美智子
- 岡田英次
- 花ノ本寿
- 田中三津子
- 佐々木功
- 菅井きん
- 小林昭二
- 寺田農

![無常/実相寺昭雄[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/41APDlH89AL._AC_.jpg)