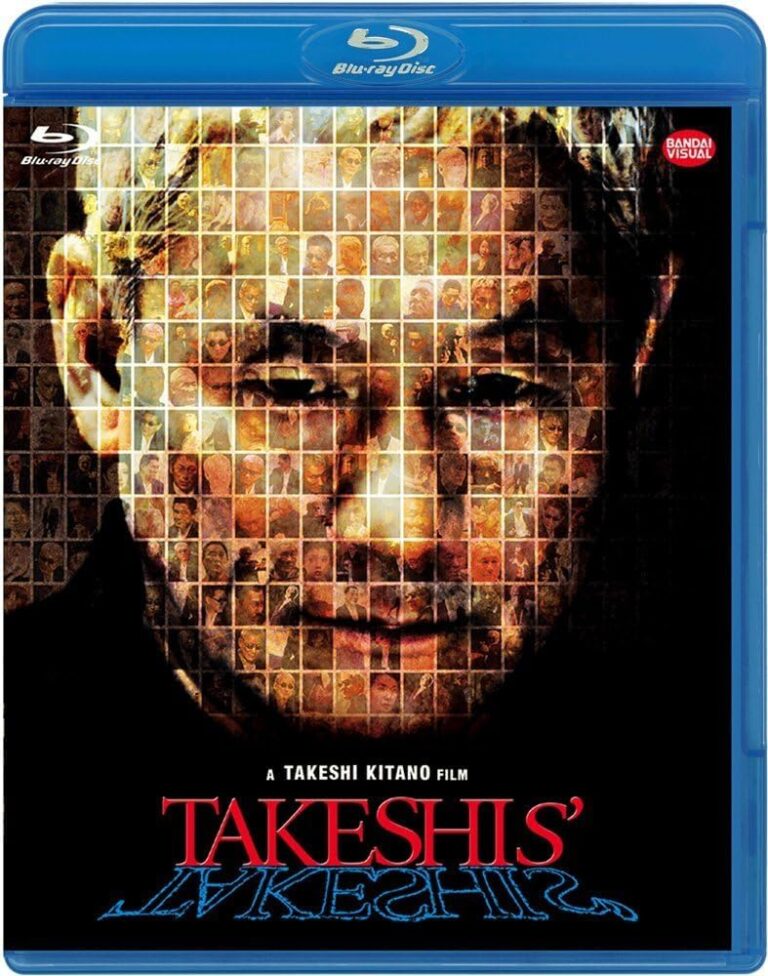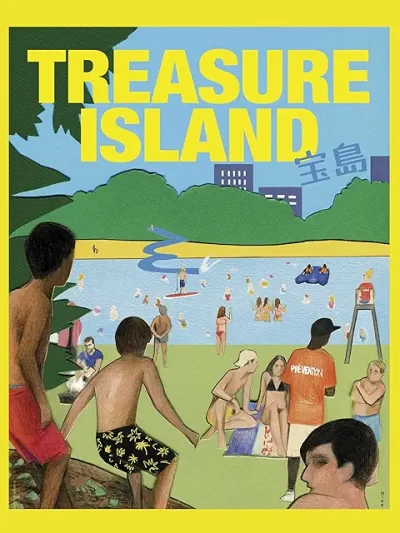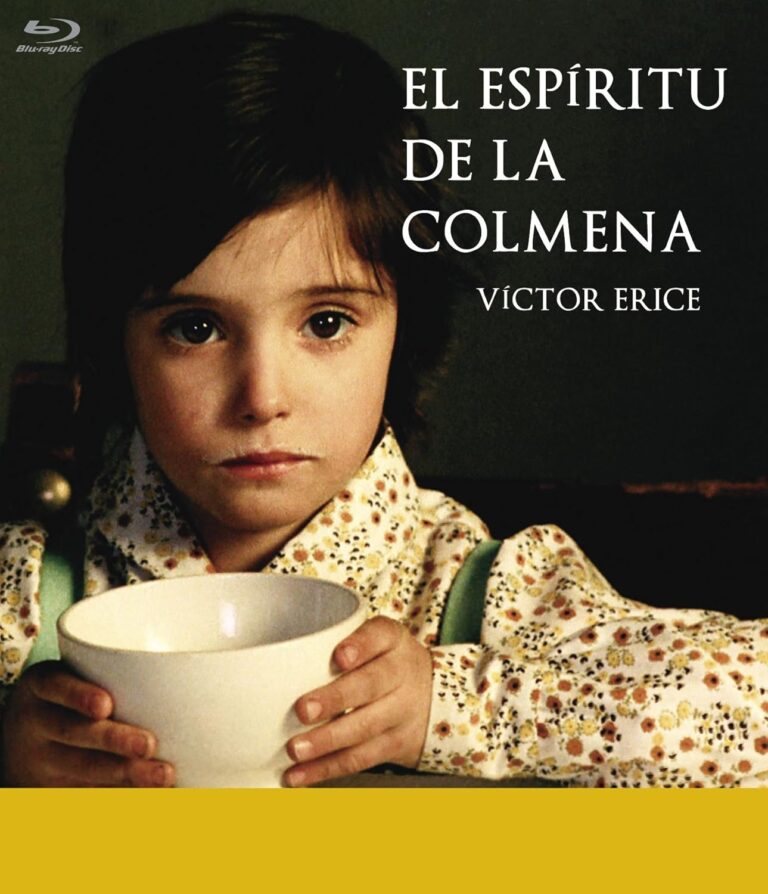『スパイダーマン』──B級魂でアメコミ映画を救ったサム・ライミ
『スパイダーマン』(原題:Spider-Man/2002年)は、サム・ライミ監督によるマーベル・コミックス実写映画化作品。冴えない高校生ピーター・パーカーが、遺伝子操作クモに噛まれたことをきっかけに超人的な力を得て、悪と戦うヒーローへと成長する。学園生活の葛藤や恋愛、そして正義との狭間で揺れる青春が描かれる。
アメコミ的感性とB級映画的悪ノリを併せ持つ、サム・ライミ
サム・ライミという監督は、ハリウッドにおいてきわめてユニークな軌跡を描いてきた作家だ。
ホラー映画史に残る低予算カルト作『死霊のはらわた』(1981年)でデビューを飾り、その後『ダークマン』(1990年)や『キャプテン・スーパーマーケット』(1992年)といった、ホラーとコメディを軽妙にミックスさせたオバカ・ヒーロー譚を次々と世に送り出しす。
アメコミ的感性とB級映画的な悪ノリを、恐るべきスピード感と演出の妙でまとめ上げてしまう圧倒的(&変態的)スキル。それがライミ監督の十八番であった。
そんな彼のもとに舞い込んだのが、マーベル・コミックスの看板ヒーロー『スパイダーマン』というビッグ・プロジェクト。ハリウッドのスタジオ・システムが全面的に資金を投下し、世界的ヒットを目論む一大企画。従来のB級テイストの作家が、この巨大な知的財産をどう料理するのか。ここにこそ、当時の映画ファンやアメコミオタクの関心が集まっていた。
ライミが導きだした答えは、意外にもシンプルかつ直球なものだった。彼は『スパイダーマン』(2002年)を「少年の成長物語」として正面から描くことにしたのである。
パーマンからアメリカン・スクールカーストへ
物語の中心に据えられるのは、冴えない高校生ピーター・パーカーだ。クモに噛まれたことから超人的な力を授かり、やがて街を守るヒーローへと成長していく。展開そのものは単純明快だが、ライミはここに「学園青春ドラマ」の要素を徹底して投入する。
たとえば藤子・F・不二雄の『パーマン』のように、平凡な少年がヒーローの仮面を手に入れるというプロットを下敷きにしながら、同時にアメリカ的スクールカーストの力学を色濃く反映させる。
いじめられっ子として疎外されてきたピーターが、突如として力を得ることによって「選ばれし者」へと変貌する──この二重構造こそが、作品全体を青春群像劇へと変貌させている。
レンタルビデオ店のジャンル分けで言うならば、本作は「アクション映画」の棚ではなく「青春ドラマ」の棚に置いた方がしっくりくるほどだ。
その青春映画的テイストはキャスティングにも顕著に表れている。主人公ピーターを演じたトビー・マグワイアは、いかにも冴えないヤサ男ぶりを全開にし、観客に「地味な少年が突然ヒーローになる」説得力を与えている。
対してヒロインのMJ役キルスティン・ダンストは、『チアーズ!』(2000年)で見せた陽気で少し小生意気なカマトトぶりをそのまま持ち込み、学園コメディ的な軽快さを画面に漂わせる。
「イケメンしか相手にしないのよ!」といった彼女の振る舞いは、アメリカのスクールライフのリアリティを漂わせると同時に、当時の観客にとって非常に現代的に映った。
スクリーンの裏側で二人が交際していたこと、そしてすぐに別れてしまったことはゴシップ的な余談だが、それもまた「学園青春ドラマ」的なテクスチャを強化するエピソードだったといえる。
グリーン・ゴブリンの不在感
しかし本作には弱点もある。悪役グリーン・ゴブリンの存在感の薄さだ。演じるウィレム・デフォーの怪演自体は悪くないのだが、彼の行動原理は最後まで曖昧で、パンフレットを読んで初めて「世界征服」という目的を知った観客も少なくないのではないか(少なくとも僕はそうだった)。
ティム・バートン版『バットマン』(1989年)におけるジョーカーのように、悪役のキャラクター造形が作品全体を牽引するのに比べると、グリーン・ゴブリンは単なる添え物に終わってしまっている。
結果として後半はカッティングも雑になり、小競り合いが延々と続くヒーロー映画的クリシェに回収されてしまう。せっかくの「青春群像劇」という独自路線が瓦解し、凡百のアクション映画に近づいてしまうのは惜しい。
爽快感の映画的達成
とはいえ、本作を語るうえで欠かせないのは、摩天楼を縦横無尽に飛び回るスパイダーマンの映像表現だ。カメラがビルの谷間を疾走し、観客の視点がピーターとともに宙吊りになる瞬間の爽快感──これこそがライミ演出の真骨頂である。
2000年代初頭のハリウッドは、まさに「デジタル革命」の渦中にあった。『マトリックス』(1999年)の“バレットタイム”や『スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス』(1999年)のCGキャラクター=ジャー・ジャー・ビンクスが象徴するように、デジタル映像技術が一気に拡張していたのである。
『スパイダーマン』における摩天楼アクションも、その延長線上にある。ただし重要なのは、サム・ライミが“完全なCGの身体”と“実際の俳優の身体”のバランスを徹底的に探った点だ。
スパイダーマンはCGキャラに置き換えられる瞬間が多いにもかかわらず、ワイヤーワークや実写スタントの身体感覚が組み合わさることで、観客は違和感なく「都市空間を移動する肉体」として受け止めることができる。これは、単に最新技術のショーケースではなく、ヒーロー映画における身体表現を更新する試みだったといえるだろう。
そして、ライミのトレードマークである「突進カメラ」(ラピッド・ズームや疾走感を伴った視点ショット)。これは、『死霊のはらわた』の森の中を這う邪悪な存在を可視化するために使われたものだった。
つまり、突進カメラは本来「恐怖の主観」を観客に強制する技法だったのである。これを『スパイダーマン』ではポジティブな方向に転用せてみせた。
摩天楼を飛び回る視点ショットは、恐怖ではなく「爽快感」へと変貌した突進カメラ。ライミの作家性はブロックバスターに吸収されることなく、自身のスタイルをアップデートしてきちんと刻み込まれている。
『死霊のはらわた』の森を駆け抜ける悪霊のスピードが、ニューヨークの高層ビル群を飛び回るヒーローの疾走感に変換されたのだ。
9.11以後のヒーロー映画として
もうひとつ、本作の歴史的な文脈を見逃してはならない。2001年9月11日の同時多発テロによって、ワールド・トレードセンターが崩壊したことで公開が延期された事実だ。予告編には摩天楼の双子の塔が登場していたが、テロのショックによって急遽差し替えられた。
だが奇妙なことに、この作品のポジティブなエネルギーは、むしろ9.11以後の観客にとって大きな癒しとなった。都市の高層ビルを舞台にヒーローが躍動する姿は、崩壊の記憶と正面から対峙しながらも、それを上書きするような爽快さをもたらしたのである。
『スパイダーマン』の公開は、アメコミ映画史においても重要な転換点だった。『ブレイド』(1998年)がジャンル復権の端緒を開き、『X-MEN』(2000年)がシリアスな群像劇の可能性を提示したあと、本作が「青春群像劇」としてのアメコミ映画の新しい地平を切り拓いた。ここからマーベル映画は次第に拡張し、のちの「シネマティック・ユニバース」へとつながっていく。
結局のところ、『スパイダーマン』は「爽快さ」の映画である。学園的ノリと青春的な葛藤、そして都市空間を疾走するアクション。これらが渾然一体となって観客にポジティブな体験を提供する。
だが同時に、本作はピーター・パーカーがまだ「少年」であるからこそ成立した物語でもある。大人になったスパイダーマンをサム・ライミがどう描くのか。青春路線を貫けない第二弾以降にこそ、作家としての試練が待ち受けているだろう。
その予感を孕ませつつ、この第一作は一つの青春映画としてきらめいているのである。
- 原題/Spider-Man
- 製作年/2002年
- 製作国/アメリカ
- 上映時間/ 121分
- 監督/サム・ライミ
- 製作/ローラ・ジスキン、イアン・ブライス、アヴィ・アラド
- 製作総指揮/スタン・リー
- 脚本/デヴィッド・コープ
- 撮影/ドン・バージェス
- 音楽/ダニー・エルフマン
- 美術/ニール・スピサック
- 編集/ボブ・ムラウスキー
- トビー・マグアイア
- キルスティン・ダンスト
- ウィレム・デフォー
- ジェームズ・フランコ
- クリフ・ロバートソン
- ローズマリー・ハリス
- ランディ・ポッフォ
- ジョー・マンガニエロ
- マイケル・パパジョン
- テッド・ライミ
- ブルース・キャンベル