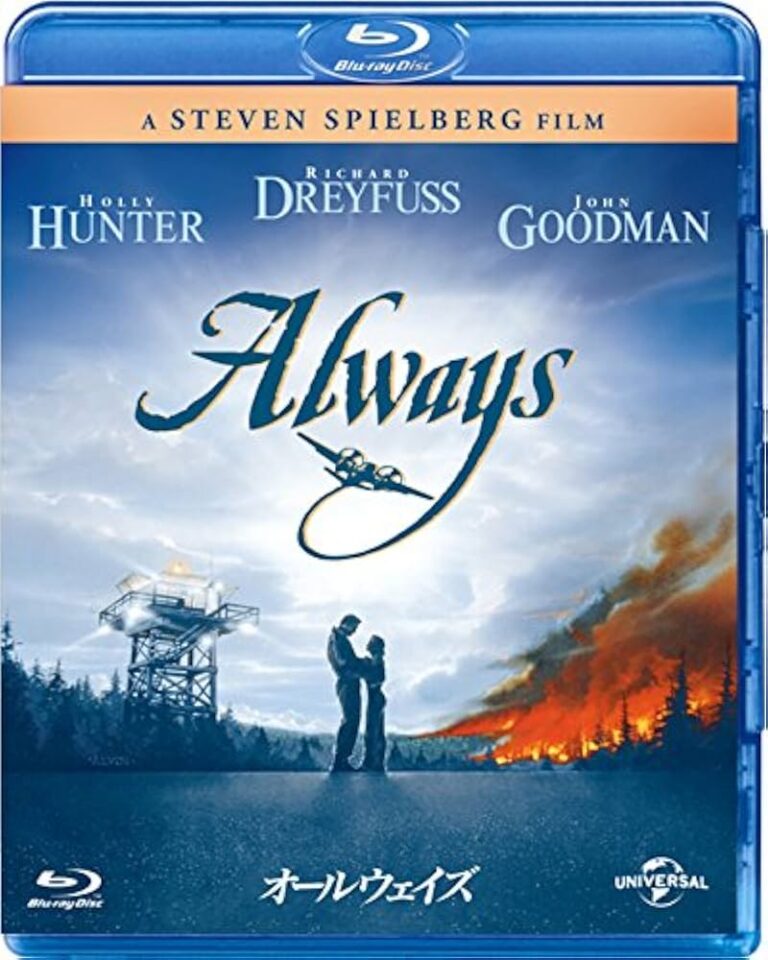『Everybody Digs Bill Evans』──沈黙と光が交錯する、内省のピアノ美学
『Everybody Digs Bill Evans』(1958年)は、ビル・エヴァンスがマイルス・デイヴィス・セクステット在籍後に録音したピアノ・トリオ作品で、1958年12月15日にセッションが行われた。リズム・セクションにはサム・ジョーンズ(ベース)とフィリー・ジョー・ジョーンズ(ドラム)が参加。ジャケットにはマイルス・デイヴィス、ジョージ・シアリング、アフマッド・ジャマールらによる賛辞が掲載され、当時の評価の高さを物語っている。
孤独なピアニストに寄せられた賛辞の重み
『Everybody Digs Bill Evans』(1958年)というアルバムタイトルには、どこか照れくささすら滲む。
レコードジャケットには、マイルス・デイヴィス、ジョージ・シアリング、アフマッド・ジャマール、キャノンボール・アダレイといった名だたる音楽家が賛辞を寄せており、若きビル・エヴァンスに向けられた期待と敬意の大きさが、そのまま視覚化されている。
しかし、当のエヴァンス本人はその厚遇にどこか距離を置き、「どうして母親のコメントは載せなかったのか?」と冗談を口にしたという。
過剰な称賛を嫌い、音楽そのものの内側に閉じこもるように生きた男の、静かな皮肉。そのひと言だけで、彼の美学の一端が見えてくる。
1958年12月。ビル・エヴァンスは、マイルス・デイヴィス・セクステットを離れ、ソロ・アーティストとして歩み始めたばかりだった。
『Milestones』と『Kind of Blue』のあいだに広がる、ジャズ史の断層のような数年。その“揺れ”の真只中で、エヴァンスは誰よりも繊細な耳で変化の気配を掴み、その感受性をピアノに沈めていった。
「Peace Piece」──透明な時間を刻む、世界で最も静かな革命
このアルバムは多くの名演を収めているが、あらゆる論考は最終的に「Peace Piece」に帰着する。圧倒的で、無音に近く、そして美しい。世界の雑音が完全に沈黙した瞬間にだけ聴こえる、あの“透明な光”のような曲。
左手の二和音が静かに往復し、右手の旋律が水面に落ちる光の粒のように変形し続ける。その構造は、後年のミニマル・ミュージックを先取りしながらも、同時に東洋的な静謐と余白の美を湛えている。
音と音の間に漂う“呼吸”。触れれば崩れてしまうほどの脆さ。そして、その脆さ自体が美の中心に据えられていること。
クラシック音楽で培われたポリフォニーの感覚は、ドビュッシーやラヴェルの影をほのかに映し出す。『月の光』の柔らかな光彩や、『夜のガスパール』の揺らぎのような色彩感。一音ごとの濃淡が、ただの即興ではなく“音の絵画”として浮かび上がる。
「Peace Piece」を聴くと、世界は一度静止する。内側に沈む時間が、外側の時間を上書きし、身体はどこか遠くへ連れ去られる。この曲が“世界で最も美しい”と人々が語るのは、技法や構造の問題ではなく、音が触れる精神の深さの問題なのだ。
ハードバップの土台と、孤独なピアニズム──内側へ向かう音の力学
本作に集ったリズムセクションは、フィリー・ジョー・ジョーンズ(ドラム)とサム・ジョーンズ(ベース)という強靭な布陣だ。
ハードバップの骨格を知り尽くし、鍛え抜かれたビートを刻むふたりに対して、エヴァンスは決して力で対抗しない。むしろ、彼らの強さを“静けさで受け止める”ように音を置く。
M-2「Young and Foolish」や「Lucky to Be Me」は、バップの伝統をなぞりながらも、エヴァンス独自の“周縁のピアニズム”が際立つ。
旋律を中央で奏でるのではなく、あえて周囲の余白をふらつくように進む。コードの陰影は深く、ひとつの音が次の音の影を引き連れていく。その影の連鎖が美学を形成する。
エヴァンスの音は、強靭なリズムの上ですら、孤独な方向へ歩いていこうとする。外へではなく、内へ。光の中心ではなく、光と影が触れ合う縁(ふち)へ。
ビル・エヴァンスは、マイルス・デイヴィスのグループに在籍した短い期間で、革命前夜のモード・ジャズを誰よりも深く吸収していた。
『Milestones』録音時、モードの語法はまだ曖昧で、バップの末端がほつれ始めたばかりだった。しかしエヴァンスは、そのほつれの中に広がる“新しい自由”を、静かに、しかし確信を持って見つめていた。
『Everybody Digs Bill Evans』は、その探究の萌芽として聴くと、俄然輝きを帯びる。ビバップの速度と技巧を相対化し、内省と和声の思索へ舵を切る。
ピアノ・トリオを“ひとりの精神の探検装置”へと変貌させる。その全ての始まりが、この1958年の記録の中に刻まれているのだ。
エヴァンスは、 loudness ではなく quietness を武器とし、激情ではなく静かな持続で音の世界を変えた。このアルバムは、ピアニストの美学が初めて輪郭を露わにした“誕生の証言”である。
- アーティスト/ビル・エヴァンス
- 発売年/1959年
- レーベル/Riverside
- Minority
- Young and Foolish
- Lucky to Be Me
- Night and Day
- Epilogue
- Tenderly
- Peace Piece
- What Is There to Say?
- Oleo
- Epilogue
- Some Other Time