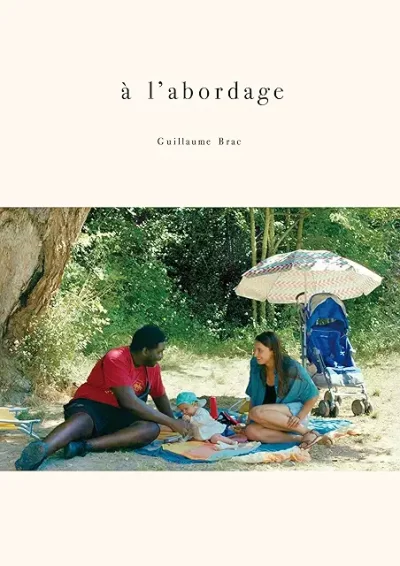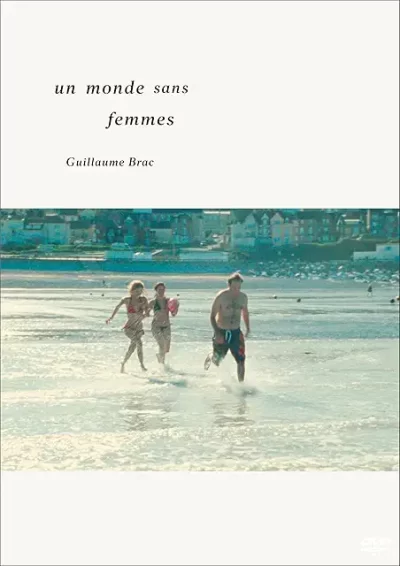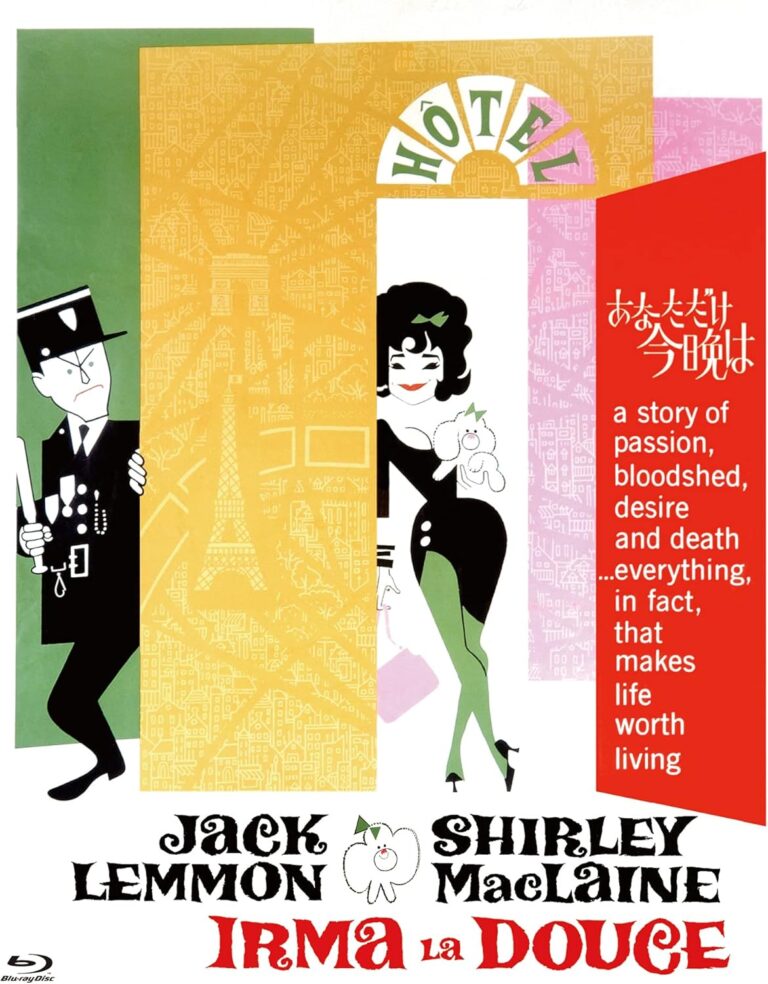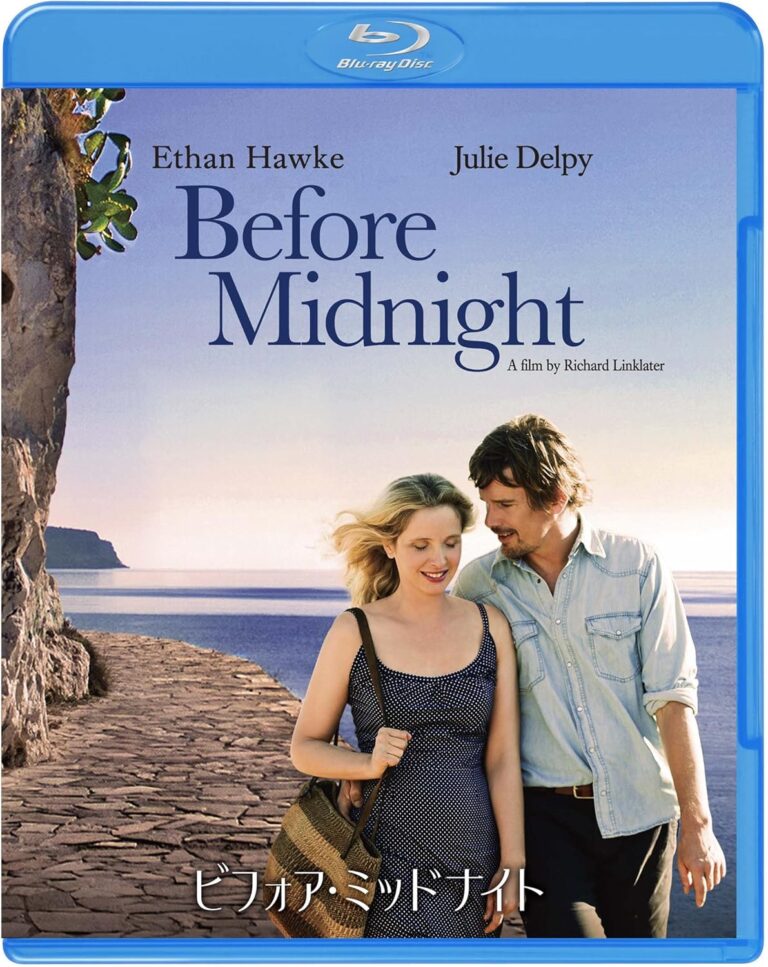『12人の優しい日本人』(1991)
映画考察・解説・レビュー
『12人の優しい日本人』(1991年)は、シドニー・ルメット監督の名作『十二人の怒れる男』(1957年)を下敷きに、三谷幸喜が“日本的合議文化”の可笑しさと不条理を巧みに描き出した密室コメディ。初めて導入された陪審制度を前に、理性や証拠ではなく、空気や遠慮、思い込みによって意見が揺れ動く陪審員たちの議論は、やがて予測不能な方向へ転がり始める。表向きの「慎重な話し合い」の裏に潜む集団心理の脆さと、議論そのものの滑稽さが、会話劇のテンポとともに鮮やかに浮かび上がっていく。
オリジナルを反転させた、日本的密室劇の誕生
もともとはシドニー・ルメットが監督したサスペンス映画の傑作『十二人の怒れる男』(1954年)に三谷幸喜がインスパイアを受け、東京サンシャインボーイズのために書き下ろした戯曲が、『12人の優しい日本人』。
1990年の初演、2005年の再演、そして1991年の映画化を経て、この作品は三谷幸喜の代表作として日本演劇史に確かな足跡を残した。
【1990年 初演】
陪審員1号 小原雅人
陪審員2号 相島一之
陪審員3号 阿南健治
陪審員4号 小林隆
陪審員5号 かんみほこ
陪審員6号 一橋壮太朗
陪審員7号 梶原善
陪審員8号 斉藤清子
陪審員9号 西村雅彦
陪審員10号 宮地雅子
陪審員11号 野中功
陪審員12号 伊藤俊人
【2005年 パルコ公演】
陪審員1号 浅野和之
陪審員2号 生瀬勝久
陪審員3号 伊藤正之
陪審員4号 筒井道隆
陪審員5号 石田ゆり子
陪審員6号 堀部圭亮
陪審員7号 温水洋一
陪審員8号 鈴木砂羽
陪審員9号 小日向文世
陪審員10号 堀内敬子
陪審員11号 江口洋介
陪審員12号 山寺宏一
ルメット版『十二人の怒れる男』は、ひとりの陪審員が理性と論理で“真実”を掘り当てる社会派ドラマだった。だが三谷版は、同じ密室劇の枠組みを保ちながら、構造を見事に反転させている。『十二人の怒れる男』が「確信を求める物語」だとすれば、『12人の優しい日本人』は「迷いを共有する物語」だ。
ルメット版の陪審員8号は孤立を恐れず真実を訴えるが、三谷版の陪審員たちは“場の空気”に敏感すぎるほど敏感で、誰もが確信を語れない。論理よりも共感、正義よりも調和を重んじるその構図が、まさに日本社会の縮図として機能している。
「もしも日本に陪審員制度があったら」という仮定を通して、三谷は“日本的合議文化”の可笑しさと危うさを、笑いに包んで描いているのだ。
笑いの中に潜むミステリー的構築
三谷幸喜の脚本は、笑いを緻密な論理のうえに構築している。会話のテンポ、論点のすり替え、誤解の連鎖といった構成の妙は、後年の『古畑任三郎』にも通じる“論理のユーモア化”という三谷独自のスタイルの萌芽だ。セリフひとつひとつが無駄なく、キャラクターの性格と日本人の社会性を同時に露わにしていく。
中原俊の演出も見事。サスペンス出身の監督らしく、笑いよりもむしろ“間”の緊張を重視。カメラは陪審員たちの沈黙や視線のズレをじっと見つめ、言葉にならない圧力を可視化する。その“沈黙の演出”によって、コメディでありながら不思議な緊張感を保つ密室劇が成立している。
そして三谷幸喜にとって、知的ゲーム=ミステリーとは単なる“謎解き”の構造ではない。それは、論理と感情、秩序と混沌のせめぎ合いを可視化するための装置なのだ。
『12人の優しい日本人』では、陪審員たちの議論が一種の“集団推理劇”として展開し、論理的に真実を導く過程そのものが笑いの源泉となっている。言い換えれば、本作の笑いは推理のメカニズムの中に内包されているのだ。
その作劇術は後の『古畑任三郎』や『ラヂオの時間』にも受け継がれた。三谷の作品群では、論理的構築が常にユーモアと共存している。観客は笑いながら、登場人物たちの言葉の中に“推理のロジック”を読み取ることを要求される。
そこにこそ、彼がミステリーという形式を用いて追求してきた“人間の矛盾”がある。本作は、三谷作品におけるミステリー的構築の出発点であり、笑いと論理が最も純粋な形で融合した記念碑的作品なのだ。
キャストが支える知的コメディの精度
映画版では、舞台系の俳優が中心のキャスティングで、どの人物にも“芝居の呼吸”がある。それは単なる演技の巧拙ではなく、呼吸の共有によって生まれるアンサンブルの妙。限られた空間の中で、セリフのテンポと間合いを呼吸でつなぐ――この“舞台的なリアリズム”が、本作の空気を作っている。
中でも上田耕一の演技は圧巻だ。普段は強面の役が多い彼が、気弱で理屈っぽい男を飄々と演じる。その姿は、まるで“怒れる男”の正反対――権威ではなく臆病、理屈ではなく戸惑い。
彼が醸し出す“ためらいのリズム”が、映画全体のトーンを決定づけている。威圧ではなく間(ま)で引きつける俳優。まさに中原俊の「沈黙を撮る演出」と完璧に呼応している。
ブレイク前の豊川悦司が放つ存在感も忘れがたい。彼の若さにはまだ演技の粗さがあるが、その不安定さが逆に陪審員という立場の“揺れる個”を体現している。
無名時代ゆえの純粋さが、作品に瑞々しい緊張を与えているのだ。群像の中に潜むスター性――それが画面の重心をわずかにずらし、議論劇にダイナミズムを生んでいる。
俳優たちは、いずれも舞台出身でありながら、映画的な間合いを心得ている。セリフを“語る”よりも、“聴く”芝居に重点が置かれているのが特徴だ。誰かが話す時、他の十一人がどう反応しているか――その沈黙のリアクションが、議論の呼吸を決定する。
つまり、この映画のリアリティはセリフの外側の芝居にある。それは演技を“見せる”コメディではなく、“呼吸を合わせる”コメディなのだ。
【映画版】
陪審員1号 塩見三省
陪審員2号 相島一之
陪審員3号 上田耕一
陪審員4号 二瓶鮫一
陪審員5号 中村まり子
陪審員6号 大河内浩
陪審員7号 梶原善
陪審員8号 山下容莉枝
陪審員9号 村松克己
陪審員10号 林美智子
陪審員11号 豊川悦司
陪審員12号 加藤善博
この面々には、いわゆる“スター俳優”はいない。だが、それこそが本作の強み。誰か一人が主張するのではなく、全員が“群としての人間”を演じ。一人ひとりが平均的で、際立たない――その匿名性が、この映画を成立させている。
つまりこのキャスティング自体が、“日本的合議制の寓話”なのだ。そしてその中で、塩見三省の沈着、梶原善の軽妙、山下容莉枝の温かさ、相島一之の小賢しさが、微妙な均衡を生み出していく。
“翻案=創造”を証明した、日本的パスティーシュの到達点
『12人の優しい日本人』は、単なるオマージュではなく、翻案(アダプテーション)という創作行為の成功例である。
原作への敬意を保ちながら、日本的社会構造や集団心理を織り込み、独立した意味を獲得した。その意味で、この作品は“翻案=創造”の可能性を示した稀有な日本映画であり、90年代邦画の中でも特異な輝きを放つ。
欧米では、古典を笑いに転化するパスティーシュや翻案が、ひとつの文化的伝統として定着している。メル・ブルックスの『ヤング・フランケンシュタイン』は、ユニバーサル版『フランケンシュタイン』をモノクロ撮影で完全再現しながら、原作の悲劇性を笑いへと転倒させた。ティム・バートンの『マーズ・アタック!』は1950年代のB級SF映画群を引用し、ジャンルそのものをカーニバル化した。
だが、日本ではこうした“他者の作品を再構築する”試みはきわめて少ない。翻案は往々にして「模倣」と誤解され、オリジナリティ信仰の中で軽んじられてきた。
その中で『12人の優しい日本人』は、明確に「引用」から出発しながら、文化を横断して新たな文体を創造した稀有な成功例である。つまり本作は、単なるリメイクでもパロディでもなく、“日本的パスティーシュ”というジャンルを成立させた先駆的作品なのだ。
『十二人の怒れる男』が正義を信じる男たちのドラマだったのに対し、『12人の優しい日本人』は、正義を信じきれない人々の優柔不断を愛おしく見つめる。そこには、三谷幸喜の人間観がある。理屈ではなく、情と空気で動く日本人の姿を笑いに変えながら、同時にやさしく批評する。このバランス感覚こそ、三谷の真骨頂。
笑いと論理、風刺と温度、そのすべてを兼ね備えたこの作品は、まさに“優しさ”という名の知的コメディである。
- 製作年/1991年
- 製作国/日本
- 上映時間/116分
- ジャンル/コメディ、ミステリー
- 監督/中原俊
- 脚本/三谷幸喜、東京サンシャインボーイズ
- 製作/笹岡幸三郎、垂水保貴
- 撮影/高間賢治
- 編集/冨田功、冨田伸子
- 美術/稲垣尚夫
- 録音/志満順一
- 塩見三省
- 相島一之
- 上田耕一
- 二瓶鮫一
- 中村まり子
- 大河内浩
- 梶原善
- 山下容莉枝
- 村松克巳
- 林美智子
- 豊川悦司
- 加藤善博
- 久保晶
- 近藤芳正
- 12人の優しい日本人(1991年/日本)

![12人の優しい日本人/中原俊[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/81jy795IeaL._AC_SL1500_-e1759087953851.jpg)