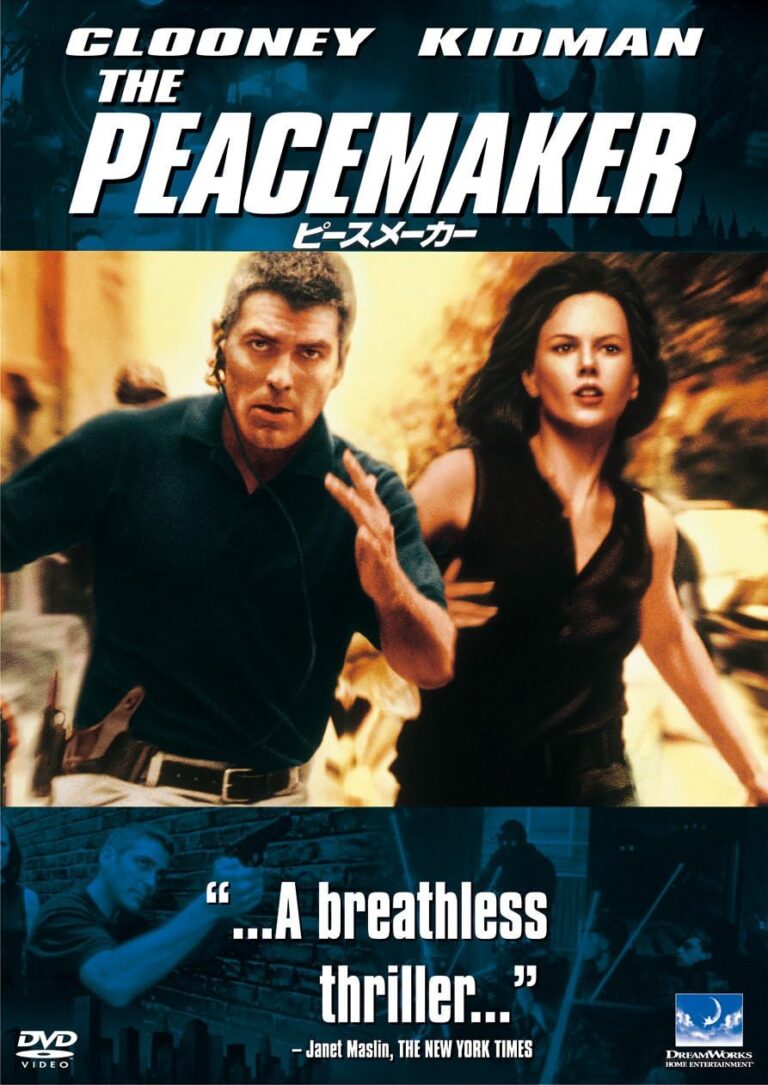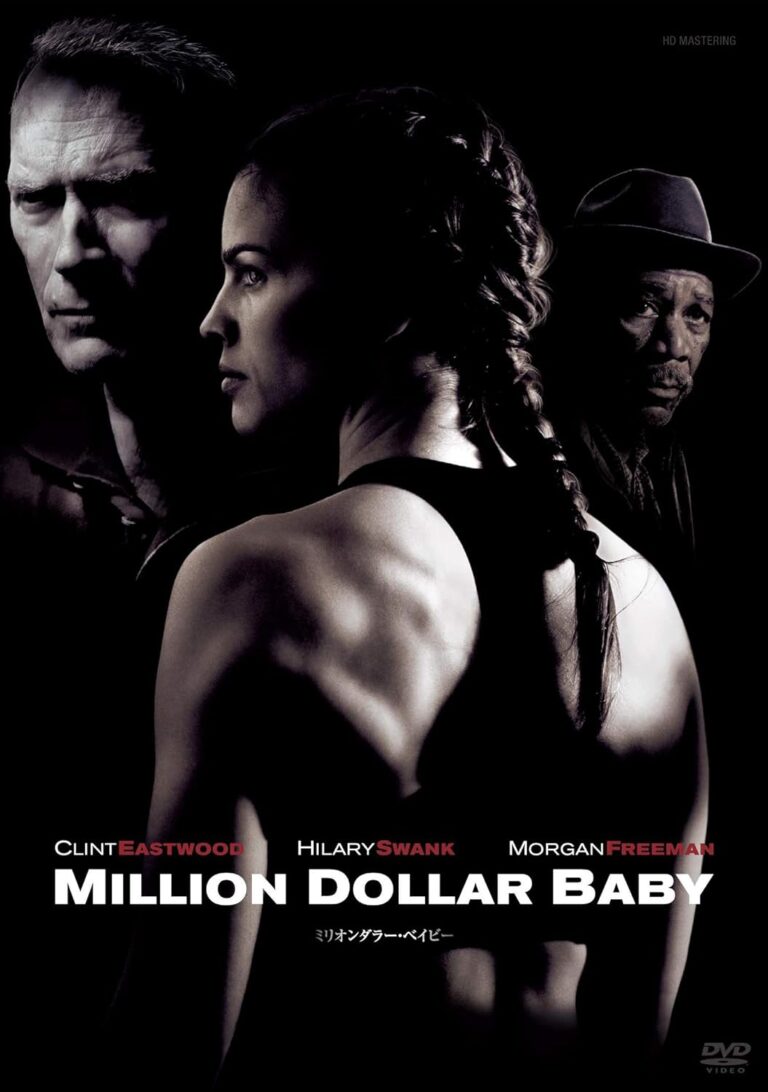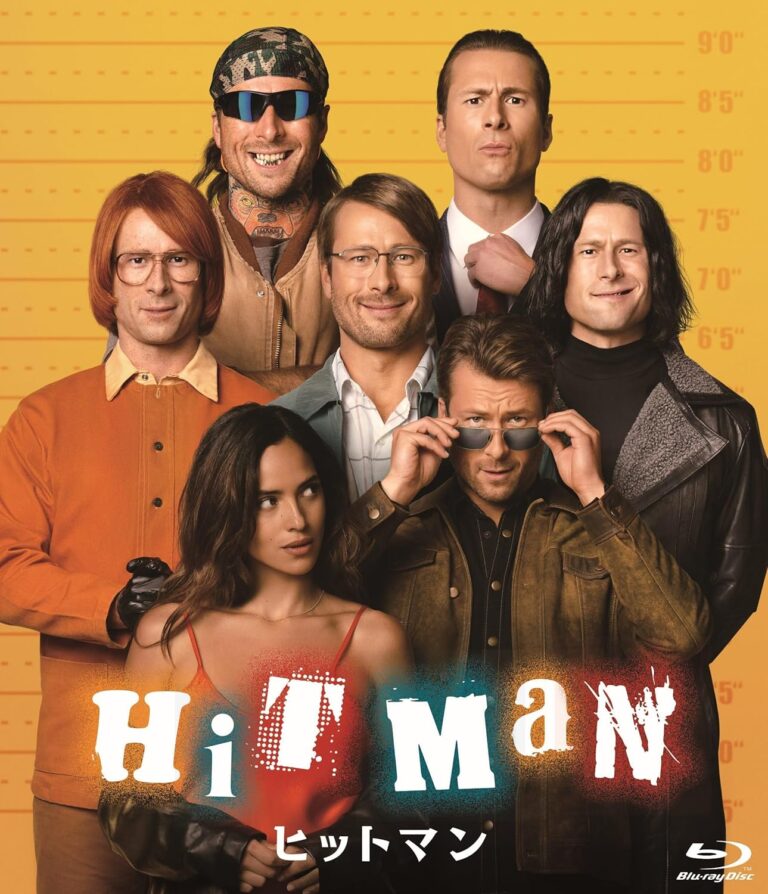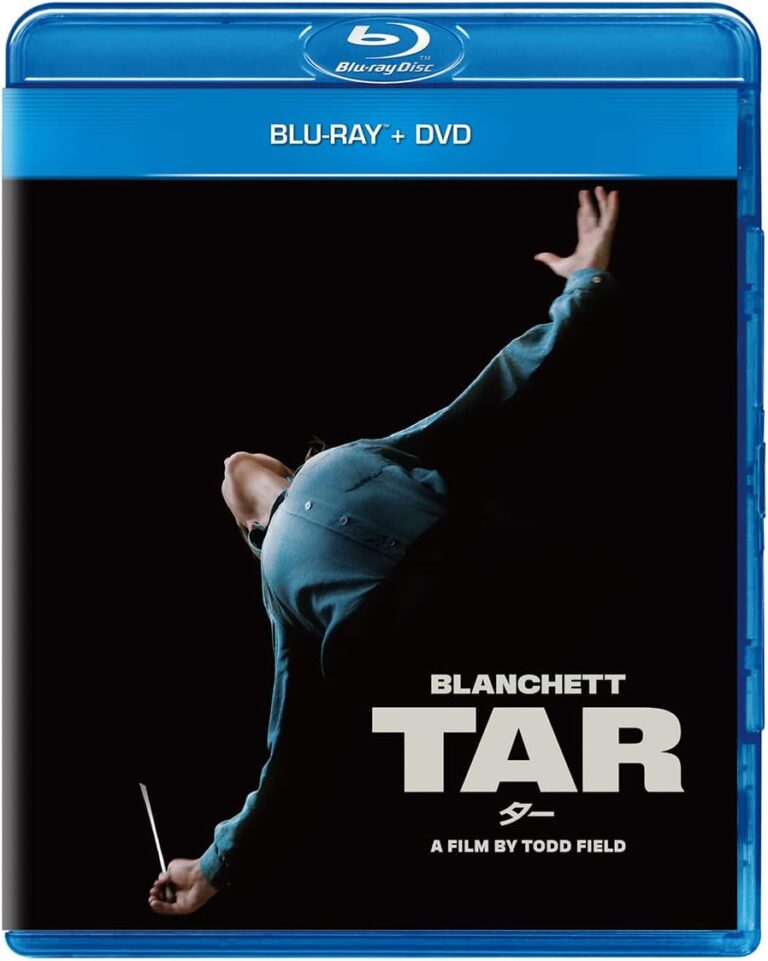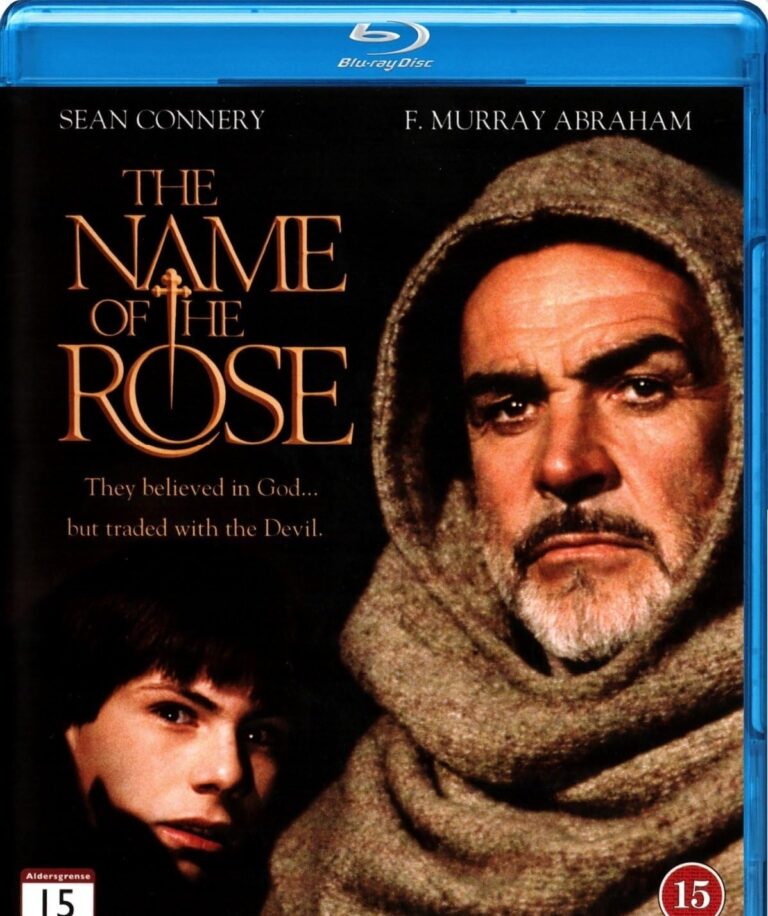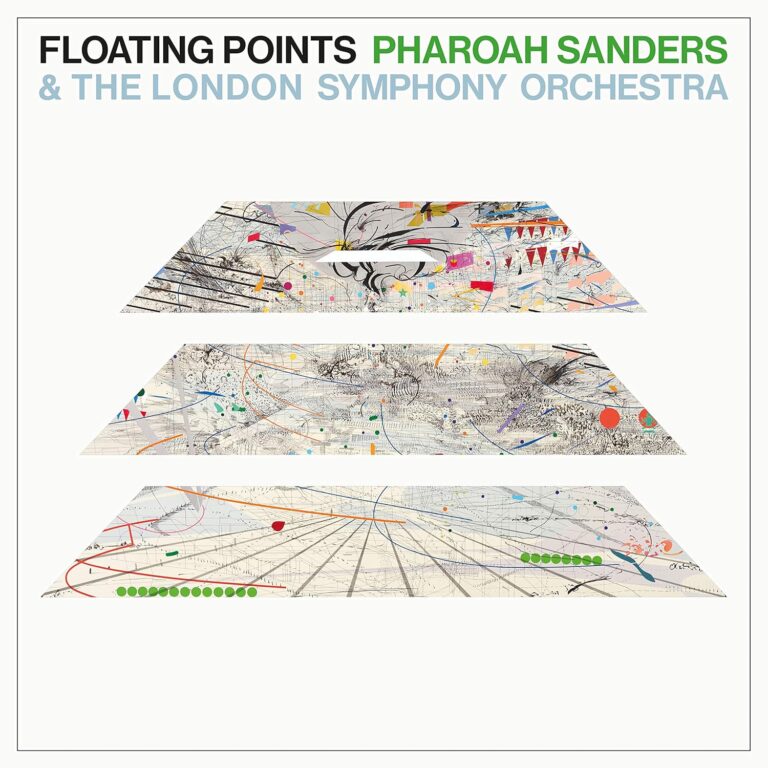『ダークマン』──サム・ライミが仕掛けた“ハッタリ”の美学
B級の仮面をかぶったポスト・ノワール
スプラッターの旗手として知られるサム・ライミが、全編をウソ臭いハッタリで突き通した異色のヒーロー映画、それが『ダークマン』(1990年)である。
『悪魔のはらわた』シリーズで独自の残酷ユーモアを確立したライミが、今度はコミック的誇張とメロドラマ的激情を融合させ、独自のジャンル混成を試みた。結果として生まれたのは、ホラーでもアクションでもない、“ポスト・ノワール的ヒーロー映画”だった。
主人公ペイトンを演じるのはリーアム・ニーソン。後年『シンドラーのリスト』(1993年)や『スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス』(1999年)で名声を得る彼だが、本作では完全に別路線。知的な演技派俳優が、まだキャリア初期にこんな荒唐無稽な作品に出演していたこと自体、ある意味で映画史的事件である。
怪人としてのヒーロー──“顔のない男”の誕生
『ダークマン』の設定は単純だ。実験中の事故で顔を焼かれた科学者ペイトンは、人工皮膚の研究によって自らの肉体を再生し、復讐の怪人へと変貌する。
ただし、その人工皮膚は一時間しか持たない。時間が過ぎれば、顔は溶け、地獄のような素顔が露出する。つまり、主人公は“時間制限付きの自己再生者”であり、ヒーローであると同時に自己崩壊を宿命づけられた存在だ。
このタイムリミット設定は、古典的スリラーの装置であると同時に、アイデンティティの不安を寓話化したものだ。どんな顔にもなれるが、永続できない――それは「人格を仮面として演じる現代人」のメタファーでもある。
サム・ライミはこの構造を、過剰なカメラワークと古典的照明演出で視覚化する。驚愕の瞬間には極端なズーム、緊張の場面ではトップライトで陰影を強調。まるで1940年代ノワール映画の語法を、B級特撮のテンションで再現しているかのようだ。
“ハッタリ”の映画術──古典演出のパロディと継承
『ダークマン』の最大の魅力は、ライミの映像操作にある。
人物の感情をそのままカメラの動きに変換し、観客の視覚を強引に引きずる。被写体が怒りを爆発させれば、画面は唐突に斜めに傾き、照明は人工的にきらめき、音楽は一段階ボリュームを上げる。
この徹底した“演出の可視化”は、いわばハリウッド的リアリズムへの反抗である。感情をリアルに再現するのではなく、あえて“演技”として提示する。観客に「これは映画である」と突きつける自己言及的手法なのだ。
このスタイルは『スパイダーマン』(2002年)へと繋がる。ライミはのちにアメコミ映画の巨匠として再評価されるが、その原型はすでに『ダークマン』にあった。アクションと感情を物理的に同期させる演出法――それこそライミ映画の本質である。
遊園地のシーンに見る過剰の快楽
本作の白眉は、遊園地での一幕だ。主人公ペイトンが的当てゲームで景品のぬいぐるみを獲得するが、店員に「線をはみ出した」とケチをつけられて没収される。すると彼は怒りを爆発させ、理性を失う。
この場面こそ、映画全体の縮図だ。ライミは人間の感情がどこで理性を超えるか、その境界線を“ギャグ”として描く。ペイトンの怒りは過剰であり、滑稽であり、しかし同時に悲劇的だ。観客は笑いながらも、そこに痛みを感じる。
“過剰”を恐れず、“感情の暴走”を演出として楽しむ――ライミのハッタリズムは、この場面に凝縮されている。リアルな人物心理ではなく、映画的エネルギーの純粋な放出としての怒り。ここに『ダークマン』の奇妙なカタルシスがある。
スプラッター出身監督の転位──暴力のコメディ化
スプラッター映画で名を馳せたライミだが、『ダークマン』では暴力の描き方が大きく変化している。『悪魔のはらわた』における肉体破壊の快楽はここでは控えめで、むしろ“痛みの演出”として転化されている。
グロテスクな表現も存在するが、観客を嫌悪させるのではなく、アクション的リズムの一部として処理される。ホラー的恐怖を“スーパーヒーローの悲劇”へと接続することにより、ライミは暴力をジャンル横断的な装置へと再定義した。
この“ホラー的ヒーロー像”は後のダーク・スーパーヒーロー作品(『ブレイド』『ヴェノム』など)に先駆けるものであり、『ダークマン』が時代を先取りしていたことを示している。
リーアム・ニーソンとフランシス・マクドーマンド──異質な組み合わせの妙
ペイトンの恋人を演じるのはフランシス・マクドーマンド。『ファーゴ』(1996年)以前の彼女が、ヒーロー映画のヒロインに起用されたという事実自体が異例だ。
ハリウッド的美貌とは無縁のリアリズムをまとった彼女の存在は、作品全体に奇妙なバランスを与えている。ニーソンの誇張された演技とマクドーマンドの抑制的な演技の対比は、映画の“トーンの不一致”をそのまま魅力に変えている。
つまり『ダークマン』は、登場人物たちの演技スタイルまでもが“仮面”として機能する構造になっている。全員がそれぞれ異なるジャンル映画から迷い込んだかのような異物感。それこそがライミが意図的に生み出した異化効果だ。
仮面の下の映画愛──セルフパロディとしての終幕
ラストシーンで主人公が群衆に紛れながら新しい仮面を被るとき、観客はその顔に“ブルース・キャンベル”を見出す。
『死霊のはらわた』シリーズの盟友である彼を、ラストでカメオ出演させる演出は、ライミによるセルフパロディであり、映画そのものへのウインクである。
この結末が示すのは、“ヒーローとは誰でもない存在である”という皮肉な真理だ。顔を変える者は、結局のところ誰の記憶にも残らない。『ダークマン』の仮面とは、ハリウッド映画そのものが被り続ける商業主義の象徴でもある。
サム・ライミは、B級ヒーロー映画の形を借りて、映画の「虚構性」そのものを暴き出した。全編に漂うウソ臭さは、単なるギャグではない。リアリズムの欺瞞を見透かした上で、映画の“演技性”を極限まで突き詰めた結果なのだ。
ハッタリの彼方にある真実
『ダークマン』は、誠実さよりもハッタリを信じた映画である。だが、だからこそ誠実だ。
サム・ライミは、観客をリアルに引き込むのではなく、“映画を映画として楽しませる”という最も原初的な映画的快楽を提示した。
CGも整合性もない時代に、誇張と過剰を信じてカメラを動かした監督のエネルギー。その無鉄砲さこそが、現代の“計算され尽くしたヒーロー映画”にはない生命力を持っている。
『ダークマン』は、ヒーロー映画のフォーマットを借りた“映画そのもののパロディ”であり、サム・ライミのキャリアにおける最初の総括である。ウソを突き通したそのハッタリの向こうに、彼の映画愛の真実が見える。
- 原題/Darkman
- 製作年/1990年
- 製作国/アメリカ
- 上映時間/96分
- 監督/サム・ライミ
- 原案/サム・ライミ
- 製作/ロバート・タパート
- 脚本/サム・ライミ、チャック・ファーラー、アイヴァン・ライミ、ダニエル・ゴールディン、ジョシュア・ゴールディン
- 撮影/ビル・ポープ
- 音楽/ダニー・エルフマン
- 美術/ランディ・セル
- 衣装/グラニア・プレストン
- リーアム・ニーソン
- フランシス・マクドーマンド
- ラリー・ドレイク
- コリン・フレールズ
- セオドア・ライミ
- ニール・マクドノー
- ブルース・キャンベル