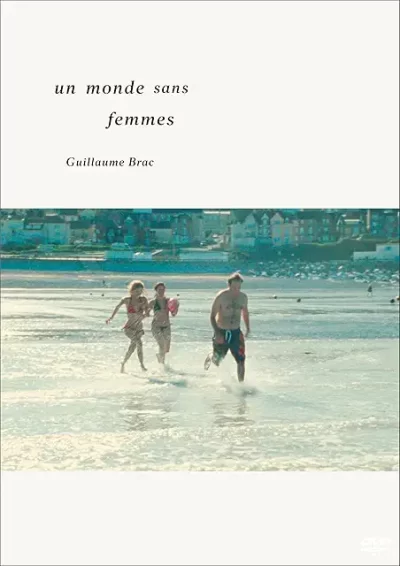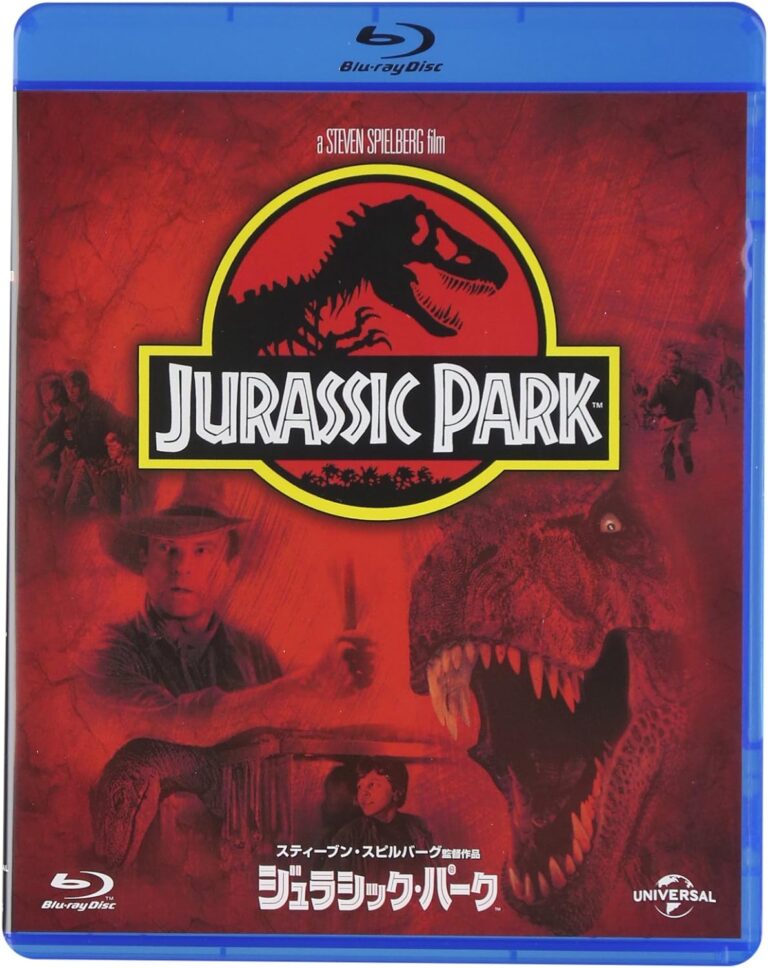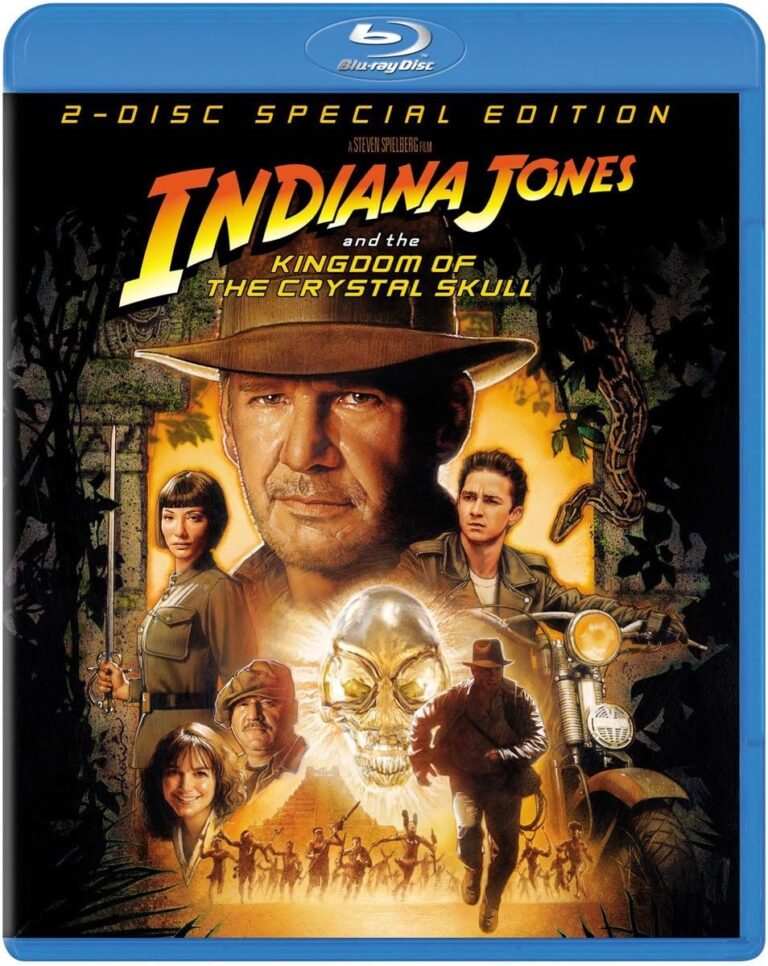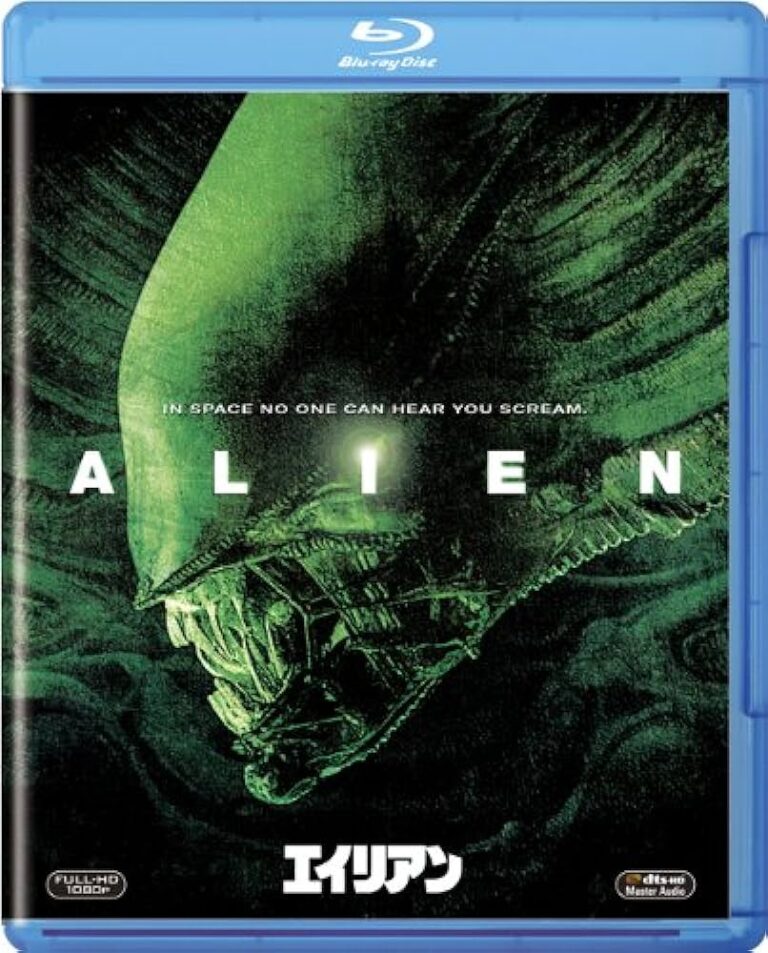『HANA-BI』──“世界のキタノ”が生まれた瞬間
『HANA-BI』(1997年)は、刑事の西が、病に倒れた妻を支えながら生と死のはざまを彷徨う姿を描いた北野武の代表作である。かつて仲間を死なせた罪悪感を抱えながら、彼は限られた時間を静かに妻に捧げる。第54回ヴェネツィア国際映画祭で金獅子賞を受賞。
ロマンチシズムの氾濫
北野武が1994年にバイク事故を起こすまでに撮った初期四部作──『その男、凶暴につき』(1989年)、『3-4×10月』(1990年)、『あの夏、いちばん静かな海。』(1991年)、『ソナチネ』(1993年)は、徹頭徹尾「照れ」に支配された映画群であった。
照れゆえにセリフは極端にそぎ落とされ、照れゆえにカメラはスタティックに均一化され、照れゆえに物語は性急なほど「死」に執着する。そうして作品は徹底的に純化され、暴力は様式美へと昇華される。第一期キタノ映画は、ミニマリズムの緊張感によって絶対的な強度を勝ち得ていたのだ。
しかし事故を経て「死」を身をもって体感した北野は、映画作りを「己と正対する行為」と認識せざるを得なくなったのではないか。照れを脱ぎ捨て、自身の内面をさらけ出すことが映画作家の宿命であると悟ったのだろう。
復帰作『キッズ・リターン』(1996年)で“生きる痛み”を語った彼は、続く『HANA-BI』(1997年)でついに照れを振り切り、抑制されていたロマンチシズムを全面に解放する。
『HANA-BI』には、初期作の硬質な寡黙さを凌駕するほどのウェットな情感が満ちている。久石譲による甘美なメロディーは饒舌に流れ、不治の病に冒された妻(岸本加世子)との何気ないやりとりはホームドラマ的な温もりを帯びる。観客のこちらが照れくさくて直視できないほどに。しまいには愛娘が凧を揚げる光景で物語が閉じられるのだ。
これをロマンチシズムと呼ばずして何と呼ぼう。下半身不随となった堀部(大杉漣)が生きる意味を見出す点描画を、北野自身が手ずから描いていること自体、照れを突破して制作に臨んだ証左である。
ゴダールとの近似と差異
大胆なカットの省略や、破滅へと突き進む男女の逃避行というモチーフ──『HANA-BI』のフォーマットは、ジャン=リュック・ゴダールの『気狂いピエロ』(1965年)に驚くほど近い。形式的には、唐突な省略編集や、死を予感させるプロット構造を踏襲しているといってよい。
だが、決定的に異なるのは「情感のあり方」だ。ゴダールがモダニストとして、徹底的に感情を突き放し、記号化された映像のコラージュとして「映画という形式そのもの」を提示しようとしたのに対し、北野武はあくまで“浪花節”の人間だ。彼の映画には、形式の冷徹さを装いながらも、義理人情に涙する日本的メンタリティが深く刻まれている。
『気狂いピエロ』において死は観念的で、モダニズムの果てに訪れる「必然の終末」だった。対して『HANA-BI』での死は、愛する人を守るために選ばれる「義理の果ての犠牲」である。つまり、ゴダールにとって死は“映画そのものの実験”の到達点であり、北野にとって死は“人情の極み”として位置づけられているのだ。
また、両者の「クール」の質もまるで違う。ゴダールのクールさは、アメリカン・ニューシネマ的なジャズの即興演奏のような自由さに近い。北野のクールさは、むしろ「照れ隠し」としての沈黙であり、感情を押し殺した結果として生まれた硬質さである。その照れを振り切ったとき、彼の映画は一転して、暴力と死に覆われていたミニマリズムから、ハートウォーミングな人間ドラマへと変貌した。
『HANA-BI』に溢れるロマンチシズムは、ゴダールのモダニズムとは真逆のベクトルを示している。北野武は、映画的形式を更新するためではなく、人間の心の襞をさらけ出すために「照れ」を超えたのだ。
だからこそ本作は、実験映画の系譜ではなく、浪花節的な情感に支えられた“人間の物語”として観客に届く。
世界のキタノへ、そしてその代償
『HANA-BI』は第54回ヴェネツィア国際映画祭で金獅子賞を受賞し、フランスの『カイエ・デュ・シネマ』が大々的な特集を組むなど、北野武を一躍「世界のキタノ」へと押し上げた。
国際映画祭の場で認められたことは、単に一人の映画監督の成功にとどまらず、日本映画が久しく失っていた“世界的存在感”を取り戻す出来事でもあった。北野武は黒澤明の後継者として扱われ、ヨーロッパ批評界からは「東洋のモダニスト」と称えられることになる。
だが、この国際的成功は同時に「名声の肥大化」という副作用をもたらした。以後の北野は、フェリーニのように自己神話化された作家として振る舞わざるを得なくなり、作品世界もまた自己言及的な傾向を強めていく。
『HANA-BI』を頂点とする評価の重圧は、彼に「世界のキタノ」というペルソナを演じ続けさせる宿命を課したのだ。
その作風の変化は『菊次郎の夏』(1999年)に顕著である。病妻や仲間の死を描いた『HANA-BI』のウェットな情感は、今度は親子愛や子供の視線にシフトし、叙情性をさらに強める。
ここには、照れを突き破ったロマンチシズムの必然的な帰結がある。暴力と沈黙の代わりに、メロディアスな久石譲の音楽とロードムービー的な叙情が物語を支配していくのだ。
「照れ」を突き破る
しかし、初期のミニマリズムを愛する僕にとって、この変化は必ずしも歓迎すべきものではなかった。『その男、凶暴につき』から『ソナチネ』に至るまでの作品が放っていたのは、緊張と停滞のあいだに漂う独特の“無”の感覚であり、それこそが純粋映画としての強度を担保していた。セリフを削ぎ落とし、感情を抑圧し、暴力を様式化することで立ち上がっていた美学は、ロマンチシズムの流入とともに希薄化していく。
つまり、『HANA-BI』によって「世界のキタノ」となったことは、日本映画にとって誇るべき快挙であると同時に、初期キタノ映画の孤高の純度を手放す瞬間でもあったと、個人的には思っている。
名声が作家を開かれた場所へと押し出す一方で、その名声は同時に“狭い閉じられた世界”でしか成立し得なかった緊張感をも解体してしまったのではないか。
『HANA-BI』は、北野武が「照れ」を突き破り、内面をさらけ出した最初の作品である。死の影を漂わせた初期四部作から、浪花節的ロマンチシズムへ──その転換点に立つ『HANA-BI』は、彼を世界的作家へと押し上げると同時に、初期の純度を懐かしむ者に複雑な感情を抱かせる一本でもある。
- 製作年/1998年
- 製作国/日本
- 上映時間/118分
- 監督/北野武
- 製作/森昌行、鍋島寿夫、吉田多喜男
- 脚本/北野武
- 撮影/山本英夫
- 特殊メイク/原口智生
- 美術/磯田典宏
- 衣裳/斉藤昌美
- 編集/北野武、太田義則
- 音楽/久石譲
- 助監督/清水浩
- ビートたけし
- 岸本加世子
- 大杉漣
- 寺島進
- 白竜
- 薬師寺保栄
- 逸見太郎
- 矢島健一
- 芦川誠
- 大家由祐子
- 柳ユーレイ
- 渡辺哲


![キッズ・リターン [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51JUtm7OMkL.jpg)
![気狂いピエロ [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51XdRoXNR6L.jpg)