パトリス・ルコントらしからぬ、ハッピー・チャームなスウィート・ムービー
『仕立屋の恋』(1989年)しかり、『髪結いの亭主』(1990年)しかり、無償の愛が報われずに悲劇的なエンディングを迎えてしまうのが、パトリス・ルコントの流儀。それだけに、『橋の上の娘』(1999年)も最後はどーなることか、とハラハラして観ていたんだが、まさかこんなにハッピー・チャームなスウィート・ムービーだったとは。
「一途な純愛は報われない」がルコントの信条であること確信していた僕は、ダニエル・オートゥイユがヴァネッサ・パラディにナイフを投げつけるたびに、ギャーギャー叫んでました。実は過去のフィルモグラフィー自体、ナイフ投げのシーンをスリリングするための伏線だったか。一杯食った。
コントラストの効いたモノクロでキッチュな映像が、作品の寓話性を際立せる。オートゥイユとパラディがお互いテレパシーで意思伝達ができちゃうという、かなりアクロバティックな設定も「アリ」なのは、ルコント監督のトリッキー演出のおかげ。
もちろんルモンドと言えば洋菓子、ルコントと言えば官能な訳で、エロいシーンも無きにしも非ずなんだが、最もエロいのはナイフを投げられて恍惚とした表情を浮かべる、ヴァネッサのバスト・ショットだろう。
ナイフ投げの的である自分が、その恐怖と同時に得がたいエクスタシーを得る瞬間である(それにしても『キミには的としての素質がある』なんて言われても、普通は、ねえ。そんな文句じゃどんなアホ女もついていかないと思うんだが)。
ナイフ投げの男が的である女の生死を支配するという、そのギリギリの信頼関係がセックス以上の高揚感と充足感をもたらし、人生負け組だった彼らを光輝く場所へと導く。彼らが劇中セックスはおろかキスすらも交わさないのは、プラトニックな関係を遵守しているからではなく、すでに肉体を超えて精神的に超エロい状態にあるからだ。
ナイフ投げはさしずめ前戯。切削部が彼女の心臓に突き刺さった瞬間、オーガズムはMAXの状態に。真のエロスは、死と隣り合わせにあるのだ。うーん、とってもやらしいニャー。
ヒロインのアデルを演じるヴァネッサは、いい按配のすきっ歯加減が薄幸そうな感じに拍車をかけており、いい男を見るとすぐ寝たくなっちゃうという尻軽女を好演。イタイ役だが、撮影当時ですでに27歳だった彼女に、20歳そこそこの役柄をキャスティングさせるってのもちょっとイタイ。
できれば10年前のヴァネッサに演ってほしかったね。『白い婚礼』(1989年)の頃は小悪魔的魅力全開で、僕も当時そのフレンチ・ロリータぶりにゾッコンだったんだが。あー『Be My Baby』を歌っていた頃が懐かしい。
最後は、きちんと観客の予想通りのハッピエーンドに収まるのも嬉しい。お決まりのパターンで終着するのは、物語の構造が寓話的だからだ。観終わってと~ってもいい気持ちになれる、フランス映画には珍しいタイプの作品と言えよう。
- 原題/La Fill Sur Le Pont
- 製作年/1999年
- 製作国/フランス
- 上映時間/90分
- 監督/パトリス・ルコント
- 脚本/セルジュ・フリードマン
- 撮影/ジャン・マリード・ルージュ
- 美術/イヴァン・モーシオン
- 編集/ジョエル・アッシュ
- 衣装/アニー・ペリエ
- 製作代表/クリスチャン・フェシュネール
- ヴァネッサ・パラディ
- ダニエル・オートゥイユ
- イザベル・プティ=ジャック
- ナターシャ・ソリニャック
- イザベル・スパッド
![橋の上の娘 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51mZN7J1BQL.jpg)
![仕立て屋の恋 -デジタルリマスター版- [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51-yBT5Z-XL.jpg)








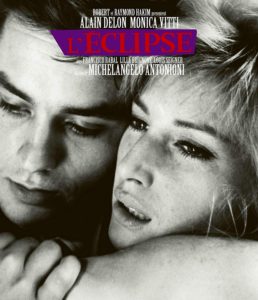
最近のコメント