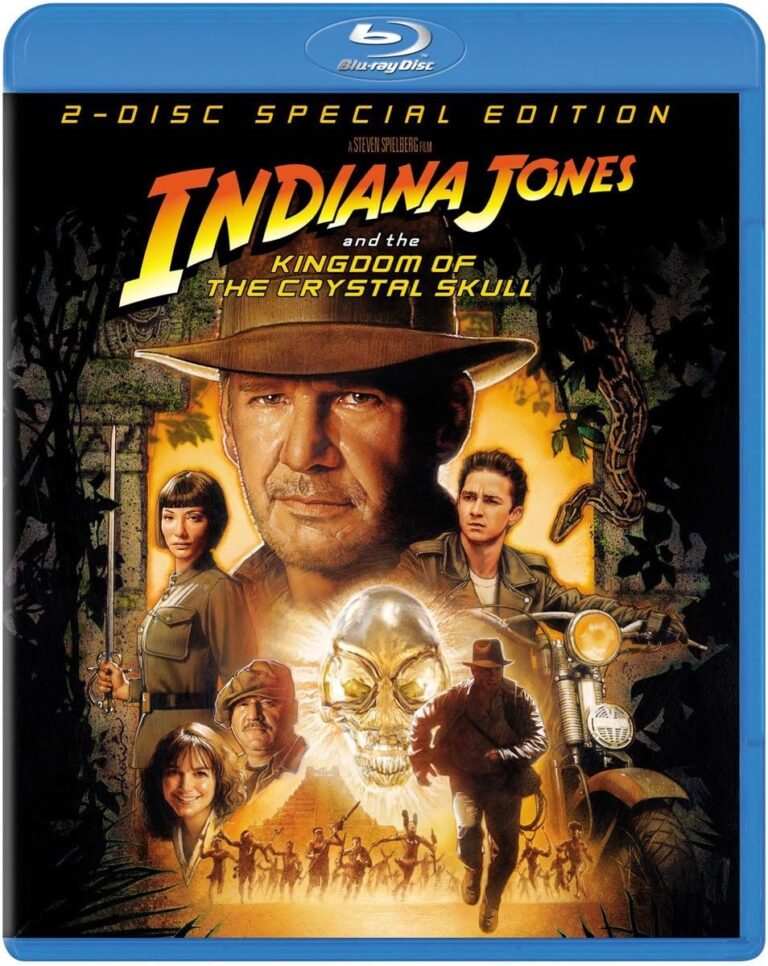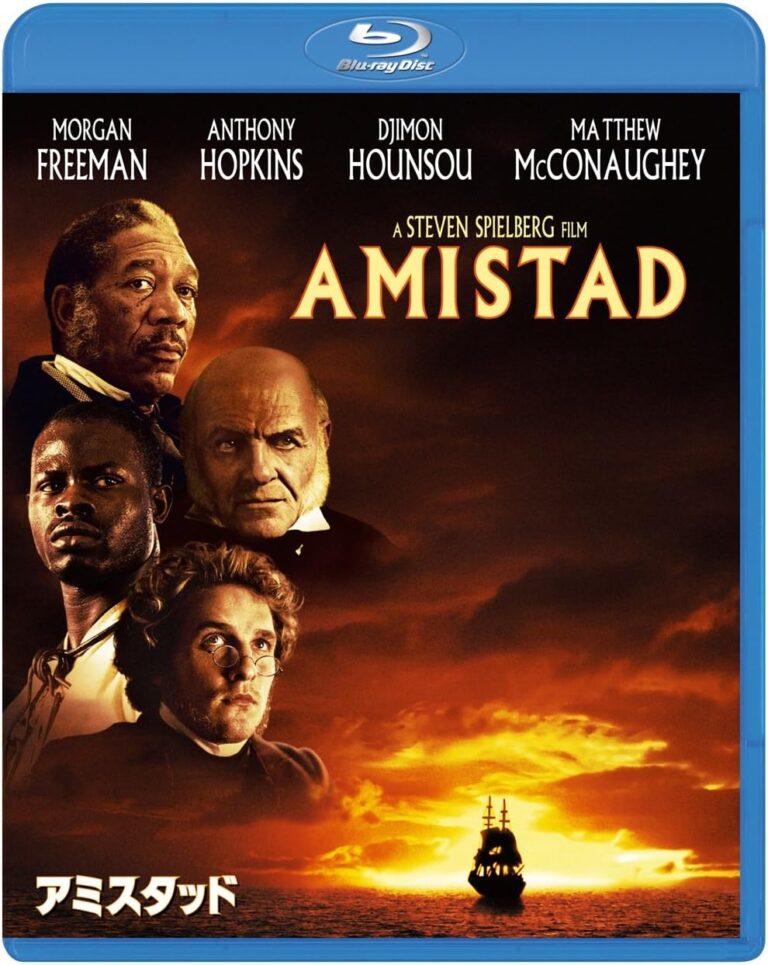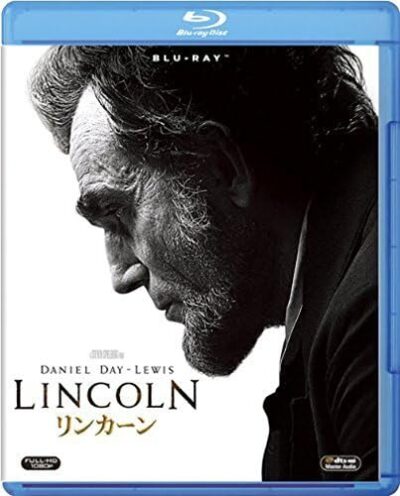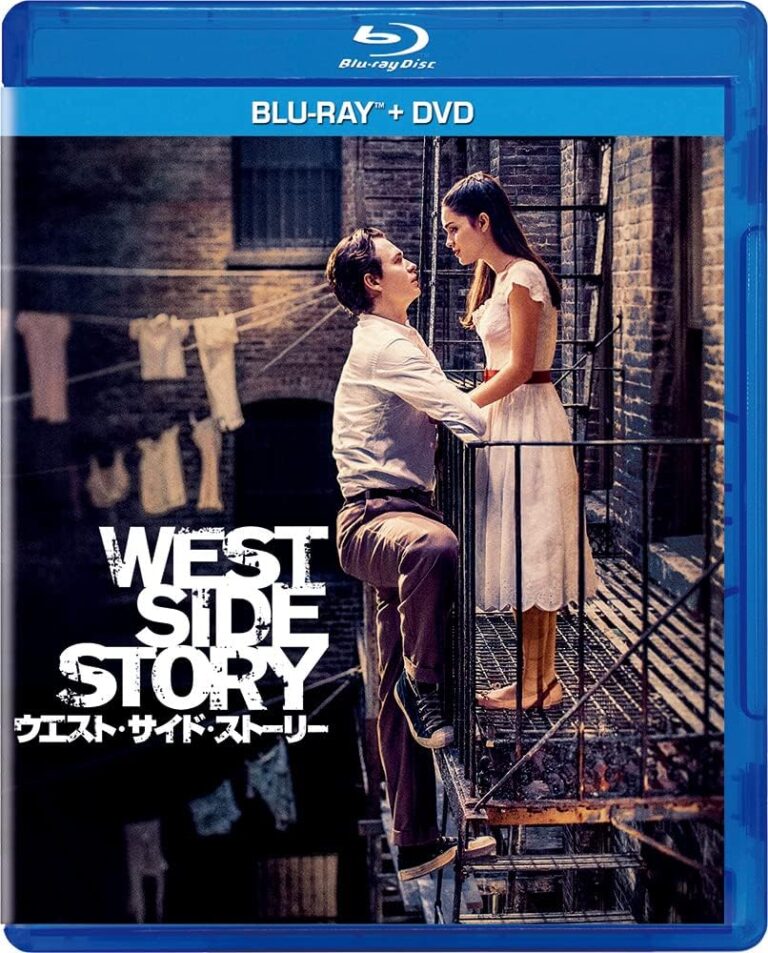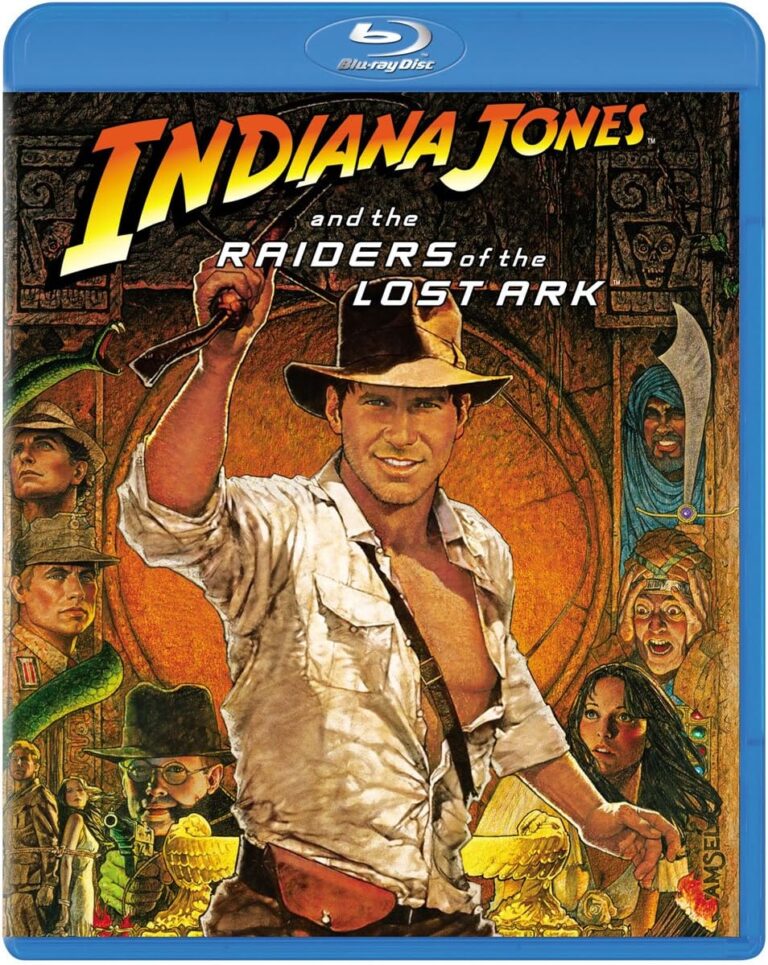『ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク』(1997)
映画考察・解説・レビュー
『ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク』(原題:The Lost World: Jurassic Park/1997年)は、スティーヴン・スピルバーグ監督によるシリーズ第2作。恐竜復活という前作の興奮を受け継ぎつつ、今度は“子を奪われたTレックス”が中心となる。人間ではなく恐竜に共感を抱かせる異色の構造が、スピルバーグ作品に通底する“捨て子”というテーマを露わにする。娯楽映画の枠を越えた家族喪失の寓話として、彼のキャリアの中でも特異な位置を占める一本。
永遠の“捨て子”たちの凱旋
スティーヴン・スピルバーグは、映画監督の仮面を被った、永遠の迷子だ。
彼は世界で最も成功したヒットメーカーとして、冒険、SF、ファンタジーの煌びやかな世界を我々に提供し続けてきた。だが、そのフィルムの裏側、いや、そのど真ん中に横たわっているのは、血の滲むような“家族の不在”と、泣き叫ぶ“捨て子”の姿に他ならない。
彼のフィルモグラフィーを貫く最大の通奏低音、それは「見捨てられる恐怖」だ。『未知との遭遇』(1977年)を思い出してみよう。バリー少年は宇宙人から選ばれた存在だが、母親からすれば、理不尽に引き剥がされた捨て子である。
『E.T.』(1982年)の主人公エリオット少年も、父親の不在を抱えていた。皺くちゃの愛すべき異星人は、宇宙から来た友達である以前に、父親に去られた少年の心の穴を埋めるための、あまりにも切実なピースだったのだ。
この強迫観念とも呼べるモチーフは、彼のキャリアにおいて執拗に繰り返される。『太陽の帝国』(1987年)におけるジェイミーの戦時下の孤独、『キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン』(2002年)におけるフランクの詐欺師としての逃避行。
これらはすべて、家庭崩壊によって「居場所」を失った子供たちの悲痛な叫びだ。電気技師の父とピアニストの母、そして幼少期に訪れた両親の離婚。この原体験こそが、スピルバーグの映画を駆動するエンジンの正体である。
彼にとって映画を撮るという行為は、単なるエンターテインメントの創出ではない。自らの魂に刻まれた捨て子という傷口を、何度も何度も反芻し、確かめるための儀式なのだ。
ある意味で我々は、ポップコーンを片手に、一人の男のセラピーを目撃させられているのかもしれない。
恐竜に仮託されたトラウマ
そう考えると、『ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク』(1997年)は、なかなかの問題作である。前作『ジュラシック・パーク』(1993年)が、革命的なCG技術で恐竜を現代に蘇らせた「センス・オブ・ワンダー」の結晶だったとするなら、この続編は、スピルバーグの作家性が暴走し、物語を食い破ってしまったのだから。
タイトルこそアーサー・コナン・ドイルの傑作『失われた世界』を冠しているが、中身は完全に別物。スピルバーグはあろうことか、捨て子という聖なるテーマを、人間ではなくティラノサウルス(Tレックス)へと託してしまったのだ。これは「子供を人間に奪われた親Tレックスが、復讐のために暴れまわる話」なのだ。
主人公であるジェフ・ゴールドブラムやジュリアン・ムーアは、仲間の人間が無残に食い殺されても、どこか無関心。そのくせ、傷ついたTレックスの幼体には、異様なまでの愛着と献身を見せ、命がけで治療を試みる。
優先順位がグッチャグチャな感じ、これこそがスピルバーグなのだ。彼にとって“傷ついた子供”は、それが爬虫類であろうと何であろうと、全世界を敵に回してでも守り抜かねばならない絶対的な存在なのである。
この歪みは、映画のスリラーとしての機能を完全に破壊した。『ジョーズ』(1975年)がなぜ怖かったか? それは巨大鮫という絶対的な暴力と、それに対峙する人間社会の対立構造が強固だったからだ。
しかし『ロスト・ワールド』において、観客の無意識の同情は、人間ではなく、子を奪われた恐竜へと流れてしまう。人間たちが襲われるシーンで、我々は恐怖するどころか、恐竜側に同情してしまう。スリラー映画において、恐怖の対象にシンパシーを抱かせてどうすんねん!
だが、スピルバーグは止まらない。クライマックス、サンディエゴの街をTレックスが蹂躙するシーン。かつて『キング・コング』(1933年)では、摩天楼の頂上で野獣が文明に敗北し、悲劇的な死を遂げた。
しかし、スピルバーグのTレックスは死なない。最後まで生き延び、勝利する。なぜなら、スピルバーグにとって捨て子は、絶対に殺されてはならない聖域だからだ。
物語の整合性よりも、スリラーとしてのカタルシスよりも、自らのトラウマの救済を優先させた結果、この映画は奇形的なまでの、恐竜擁護映画へと変貌を遂げたのである。
捨て子というオブセッション
捨て子のモチーフの暴走は、後続の作品でさらに純度を高めていく。『A.I.』(2001年)の主人公デイヴィッドは、もはや人間ですらなく、愛をプログラムされたロボットだ。しかし、彼が母親の愛を求めて二千年の時を彷徨う姿は、スピルバーグ映画史上最も残酷で美しい、捨て子の極致だろう。
そして『シンドラーのリスト』(1993年)における、赤いコートの少女。彼女はゲットーという閉鎖空間に取り残された、共同体的規模での捨て子の象徴だ。個人的な孤独は、やがて歴史的な絶望へと接続されていく。そうした文脈の中に『ロスト・ワールド』を置くと、この映画が持つ特異な魅力が浮かび上がってくる。
世間的には、ラズベリー賞にノミネートされ、スピルバーグ本人さえも製作に嫌気がさしたと公言。失敗作の烙印を押されている。確かに脚本は穴だらけだし、登場人物の動機は破綻している。
結局のところ、『ロスト・ワールド』は完璧な娯楽大作ではない。しかし、巨匠スピルバーグが捨て子という自らのオブセッションを制御しきれず、恐竜にまでそれを投影してしまったがゆえに生まれた、愛すべき事故現場なのだ。
我々は、整ったストーリーラインを追うのではなく、画面の端々から滲み出る監督の執念と、制御不能なエネルギーの奔流をこそ楽しむべきだろう。
- 原題/The Lost World: Jurassic Park
- 製作年/1997年
- 製作国/アメリカ
- 上映時間/129分
- ジャンル/SF、パニック
- 監督/スティーヴン・スピルバーグ
- 脚本/デヴィッド・コープ
- 製作/キャスリーン・ケネディ、ジェラルド・R・モーレン
- 製作総指揮/キャスリーン・ケネディ
- 原作/マイケル・クライトン
- 撮影/ヤヌス・カミンスキー
- 音楽/ジョン・ウィリアムズ
- 編集/マイケル・カーン
- 美術/リック・カーター
- SFX/スタン・ウィンストン
- ジェフ・ゴールドブラム
- ジュリアン・ムーア
- ピート・ポスルスウェイト
- アーリス・ハワード
- リチャード・アッテンボロー
- ヴィンス・ヴォーン
- ヴァネッサ・リー・チェスター
- ピーター・ストーメア
- ハーヴェイ・ジェイソン
- リチャード・シフ
- トーマス・エフ・ダフィ
- レイダース/失われたアーク《聖櫃》(1981年/アメリカ)
- E.T.(1982年/アメリカ)
- ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク(1997年/アメリカ)
- アミスタッド(1998年/アメリカ)
- プライベート・ライアン(1998年/アメリカ)
- マイノリティ・リポート(2002年/アメリカ)
- ミュンヘン(2005年/アメリカ)
- インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国(2008年/アメリカ)
- タンタンの冒険 ユニコーン号の秘密(2011年/アメリカ)
- リンカーン(2012年/アメリカ)
- レディ・プレイヤー1(2018年/アメリカ)
- ウエスト・サイド・ストーリー(2021年/アメリカ)
- ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク(1997年/アメリカ)
- ジュラシック・ワールド/復活の大地(2025年/アメリカ)

![ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク/スティーヴン・スピルバーグ[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/51D1cynz0XL._AC_UF10001000_QL80_-e1707304614762.jpg)
![未知との遭遇/スティーヴン・スピルバーグ[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/813MEbIWnvL._AC_SL1500_-e1756663860162.jpg)
![失われた世界 (光文社古典新訳文庫)/アーサー・コナン・ドイル (著)、伏見威蕃 (翻訳)[本]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/811RxEiYUbL._SL1500_-e1768837157749.jpg)
![シンドラーのリスト/スティーヴン・スピルバーグ[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/51lHyZ4KP-L._UF10001000_QL80_-e1754898172436.jpg)