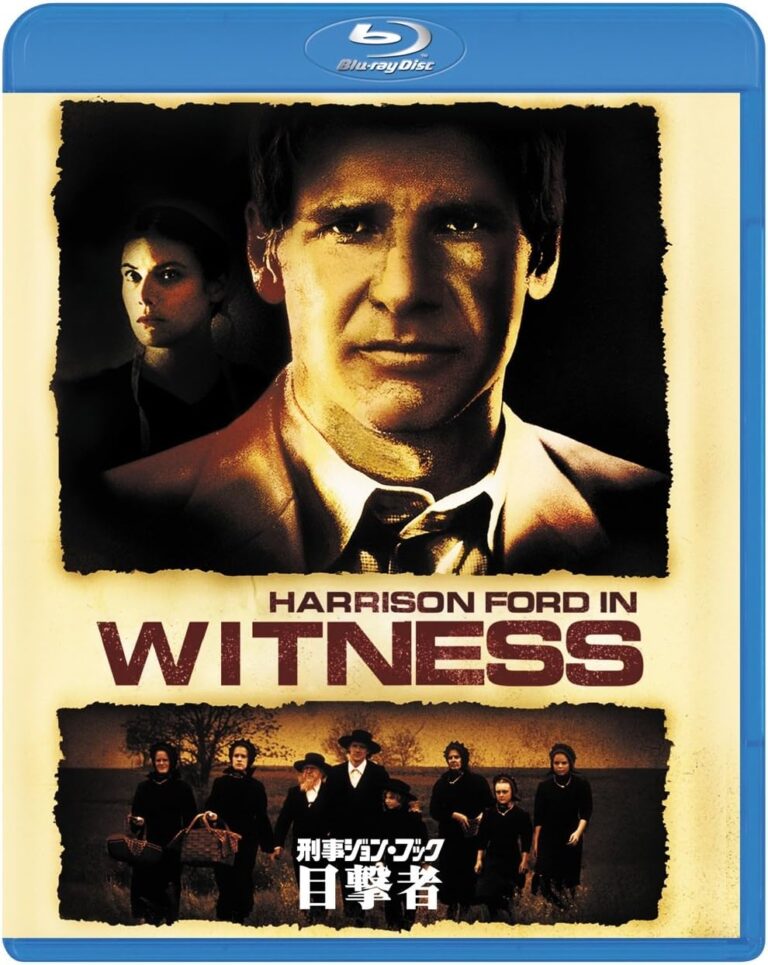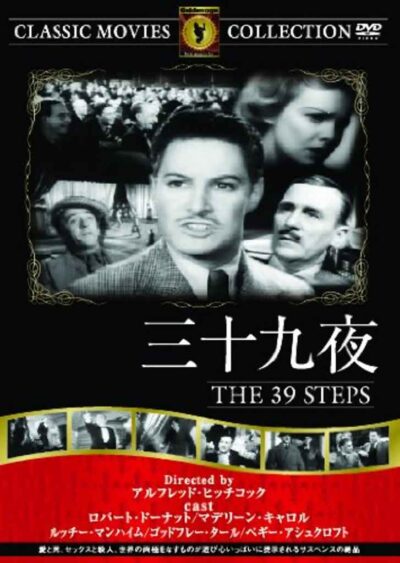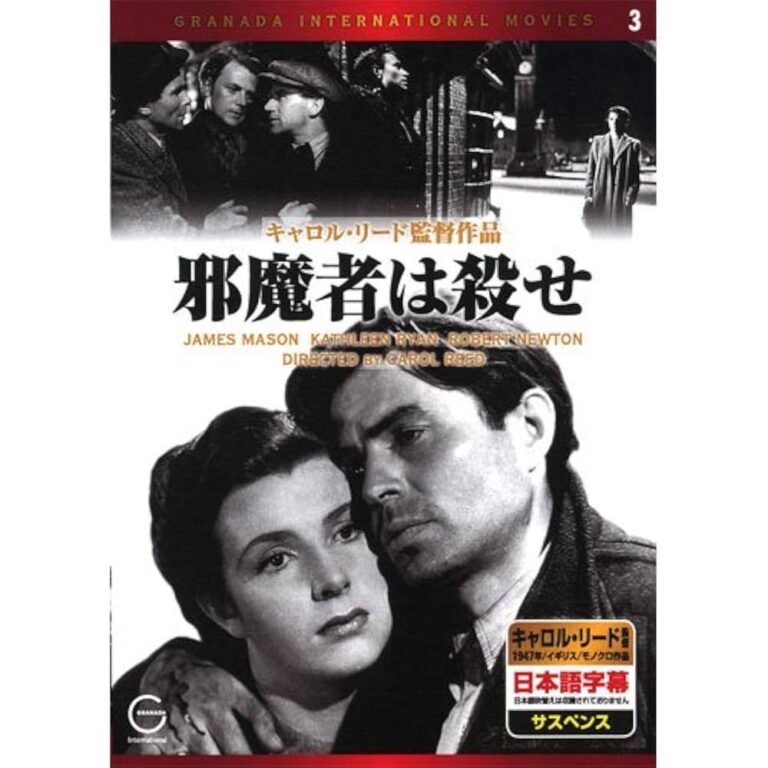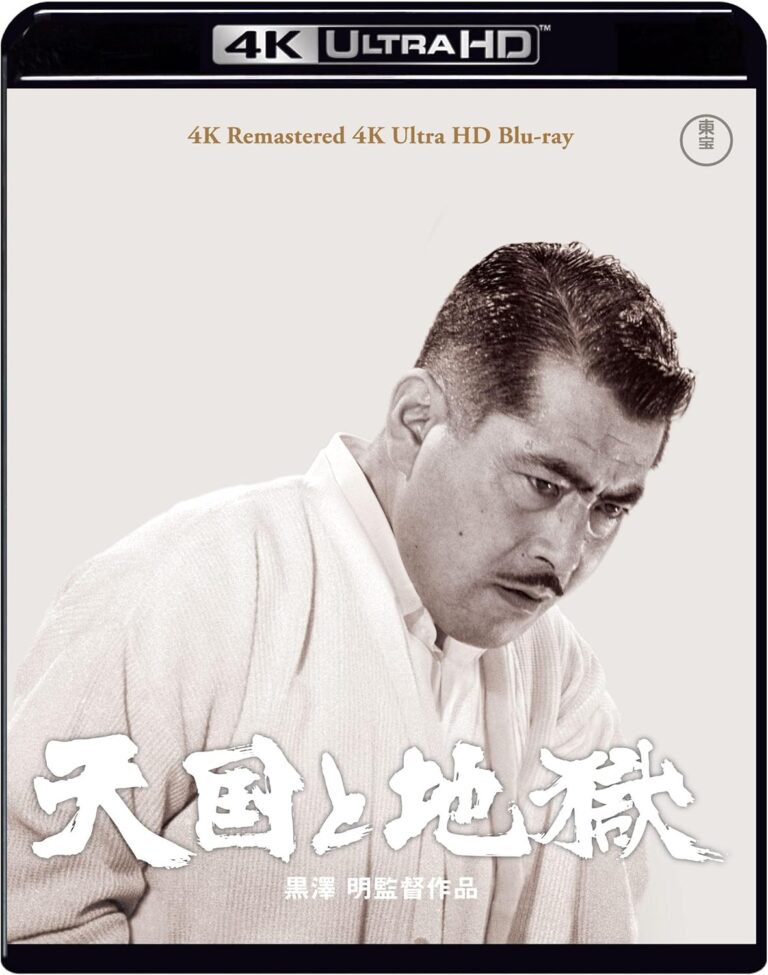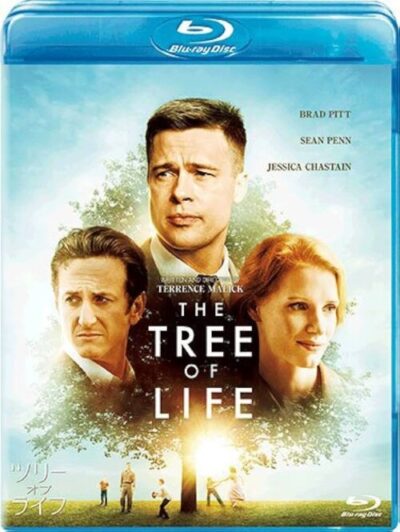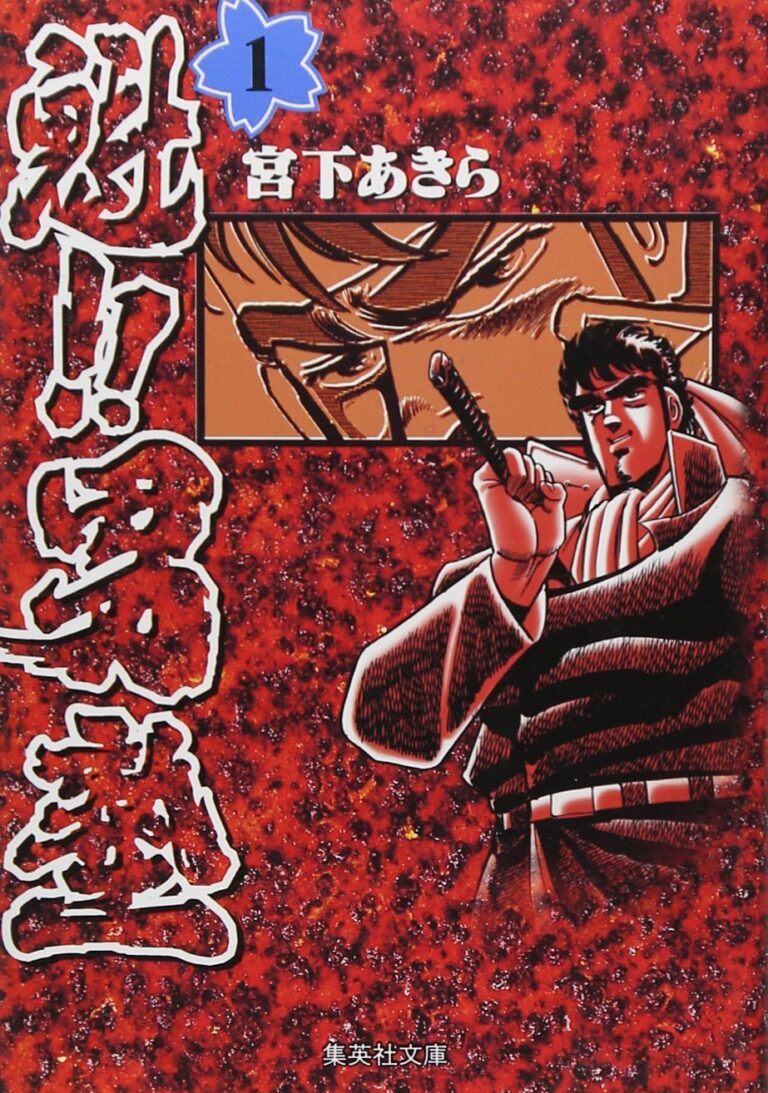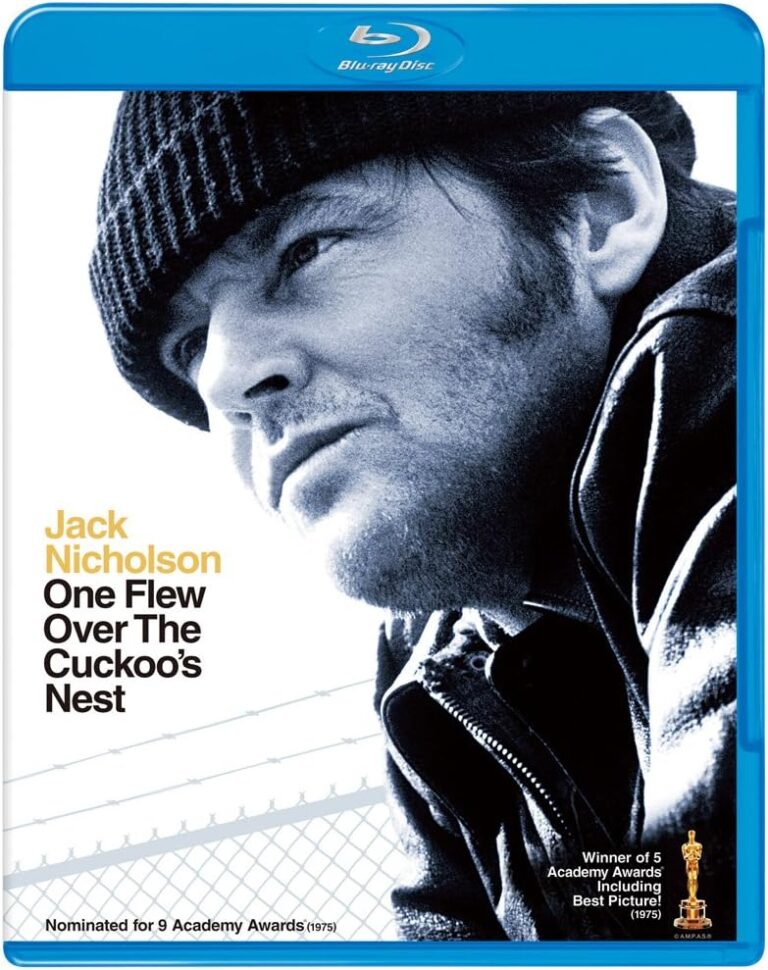『マラソンマン』(1976)
映画考察・解説・レビュー
『マラソンマン』(原題:Marathon Man/1976年)は、ジョン・シュレシンジャー監督が元ナチスの歯科医と若き大学院生ベイブの対峙を軸に、信頼の崩壊と恐怖の連鎖を描いたサスペンスである。ニューヨークで平穏な日々を送っていたベイブは、兄ドクの死を機に謎の男たちに追われ、国家の闇へ巻き込まれていく。狂気を宿した歯科医ゼルが放つ「Is it safe?」という台詞は、暴力の前触れであると同時に、70年代アメリカが抱えた不安と不信の象徴でもある。逃走、尋問、疑念が折り重なる中、善悪の境界は曖昧となり、日常は音もなく破壊されていく。
ウィリアム・ゴールドマンの冷徹な計算と、70年代ニューヨークの腐臭
映画史の起点をリュミエール兄弟にまで巻き戻すなら、映画とは本質的に運動を記録する芸術だ。そう考えると『マラソンマン』(1976年)は、走るという最も原始的な運動を通じて、1970年代アメリカの病理とパラノイアをスクリーンに定着させた記念碑的作品といえるだろう。
本作の骨格を形成しているのは、原作者であり自ら脚本も手掛けたウィリアム・ゴールドマンによる、“計算し尽くされた言葉の刃”だ。彼は『明日に向って撃て!』(1969年)でハリウッドの頂点に立った天才だが、原作小説は最初から映画化権を高く売るために、サスペンスの構造を逆算して執筆されたという極めてシニカルな出自を持つ。
自身の内面から絞り出した小説を、再び自らの手で映画というスクリプトに書き換える。この純粋な自己翻訳の構造が、物語に一切の破綻を許さない幾何学的な冷たさを与えている。
主人公のベイブ(ダスティン・ホフマン)は、ニューヨークの大学で歴史を学ぶ傍ら、ひたすらセントラルパークを走る若きマラソンランナーだ。
だが、彼の走りは決して健康的なスポーツではない。彼の父親は、かつてマッカーシズムの標的にされ、絶望の中で自殺した悲劇の知識人だった。
ベイブが歴史の博士論文に取り組むのも、そして心臓が破裂するほど走り続けるのも、父を殺した国家の暴力というトラウマを代謝し、己の正気を保つための過酷な儀式なのだ。
一方、エリート・ビジネスマンを装う兄のドク(ロイ・シャイダー)は、実は政府の極秘エージェントであり、冷酷なスパイ戦の真っ只中で血を流している。
この“無垢で観念的な弟”と“汚濁にまみれた実務者の兄”という対比が、ベトナム戦争の泥沼化とウォーターゲート事件によって完全に引き裂かれた、当時のアメリカの二面性を鮮やかに浮き彫りにする。
『真夜中のカーボーイ』(1969年)で知られるジョン・シュレシンジャー監督は、イギリス人という「外部の視点」から、ゴミが散乱し、犯罪が日常化した1970年代のニューヨークをドキュメンタリータッチで切り取った。
国家と個人の間にあった“信”が崩れ去ったこの荒廃した都市で、ベイブの無防備な日常は、兄の死を決定的なトリガーとして、表層に潜んでいた歴史の腐臭によって容赦なく侵食されていくのである。
メソッド演技vs英国演劇の激突が生んだ痛覚の神話
本作を単なる政治スリラーから、映画史に永遠に刻まれる倫理的ホラーへと昇華させた最大の要因は、間違いなくローレンス・オリヴィエ演じる元ナチス歯科医、クリスチャン・ゼルの存在だ。
アウシュヴィッツの死の天使と呼ばれたヨーゼフ・メンゲレをモデルにしたこの怪物は、権力や高尚な理念など一切信じていない。彼が信仰するのは、ユダヤ人から奪い取ったダイヤモンドと、他者の肉体的な痛みだけ。人間の身体をただの物質や商品として扱うその冷徹な姿は、20世紀最大の暴力の記憶そのものだ。
椅子に縛り付けられたベイブに対し、ゼルが歯科用のドリルを近づけながら幾度となく繰り返す「Is it safe?」という問い。これは単なる尋問ではない。誰もが信用できない現代社会に対する、極めてアイロニカルな哲学の問いかけである。
ゼルの冷たく気品のある声音と、ドリルの甲高いモーター音が響くたび、観客はスクリーン越しに自分自身の口腔をこじ開けられ、神経を削られるような錯覚に陥る。
イデオロギーも、愛も、知性も、歯の神経を直接ドリルでえぐられる痛みの前では何の意味もなさない。痛覚という絶対的な生理現象をサスペンスの頂点に据えたゴールドマンの着眼点は、あまりにも残酷で天才的だ。
そして、この拷問シーンの裏側には、映画史に残る伝説的な演技論の激突があった。徹底したメソッド演技法を信奉するダスティン・ホフマンは、拷問されるベイブの疲労と恐怖をリアルに表現するため、実際に何日も風呂に入らず、一睡もせずに撮影現場に現れた。
そのボロボロの姿を見た英国演劇界の至宝ローレンス・オリヴィエは、静かにこう言い放ったという。
親愛なる君、なぜただ演技をしようとしないんだ? その方がずっと楽だぞ
この逸話は、肉体を酷使して現実に同化しようとするアメリカの若きリアリズムと、圧倒的な技術と品格で虚構を支配するヨーロッパの伝統という、二つの文化の衝突を見事に象徴している。
この背景を知ることで、二人が対峙する密室のシーンは、単なるキャラクターの対立を超えた、役者同士の魂の殺し合いとして凄まじい緊迫感を放ち始める。
ダイヤモンド街の白昼夢と、虚無を駆ける実存のランナー
シュレシンジャーの演出は、物語が佳境に入るにつれて、感情的なカタルシスを徹底して拒絶していく。彼は暴力を安易なハリウッド的スペクタクルとして消費することを許さない。
その真骨頂が、クリスチャン・ゼルがニューヨークのユダヤ人街を歩く終盤のシークエンスだ。白昼堂々、ナチスの戦犯が、かつて収容所で彼に身内を殺されたホロコーストの生存者たちとすれ違う。
一人の老婆が彼に気づき、「あいつよ! 白い天使(Der Weisse Engel)よ!」と絶叫しながら群衆の中を追いすがる。暗い密室ではなく、太陽が照りつける大通りで展開されるこの凄絶なサスペンスは、過去の歴史的悲劇が、現代の都市のど真ん中に突如として亀裂を入れる恐るべき瞬間を見事に映像化している。
警察や政府機関がすべて敵と通じていると悟ったベイブは、裸足でニューヨークの街を疾走する。そしてセントラルパークの貯水池で、ついにゼルと最終的な対峙を果たす。
ベイブはゼルを殺す代わりに、彼が執着していた無数のダイヤモンドを、ゴミのように水の中へ投げ捨てる。富への執着、歴史の亡霊、そして腐敗した権力システムそのものを、根底から拒絶する行為だ。
『ダーティハリー』(1971年)や『フレンチ・コネクション』(1971年)が国家権力側からの法の限界を描いたとすれば、『マラソンマン』は徹底して無力な個人の内側から、その底知れぬ絶望を描き切っている。ラストシーン、すべてを終わらせたベイブは、誰にすがることもなく、ただ一人でカメラから遠ざかるように歩き出す。
彼は生き延びたが、父を奪った国家も、兄を殺した組織も、何一つ根本的な解決などしていない。「Is it safe?」という問いに対する答えは、永久に「No」のままだ。
『マラソンマン』は、観客の神経を直接削りながら、70年代アメリカが抱えた癒えぬ傷痕を、今なお冷徹に突きつけ続けている。
- 監督/ジョン・シュレシンジャー
- 脚本/ウィリアム・ゴールドマン
- 製作/ロバート・エヴァンス、シドニー・ベッカーマン
- 原作/ウィリアム・ゴールドマン
- 撮影/コンラッド・L・ホール
- 音楽/マイケル・スモール
- 編集/ジム・クラーク
- マラソンマン(1976年/アメリカ)
![マラソンマン/ジョン・シュレシンジャー[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/71etEmSQ26L._AC_SL1280_-e1706982230685.jpg)
![真夜中のカーボーイ/ジョン・シュレシンジャー[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/91lomgQ88aL._AC_UL640_FMwebp_QL65_-e1766826097763.webp)
![フレンチ・コネクション/ウィリアム・フリードキン[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/81iix01kZjL._AC_UL640_FMwebp_QL65_-e1766820521314.webp)