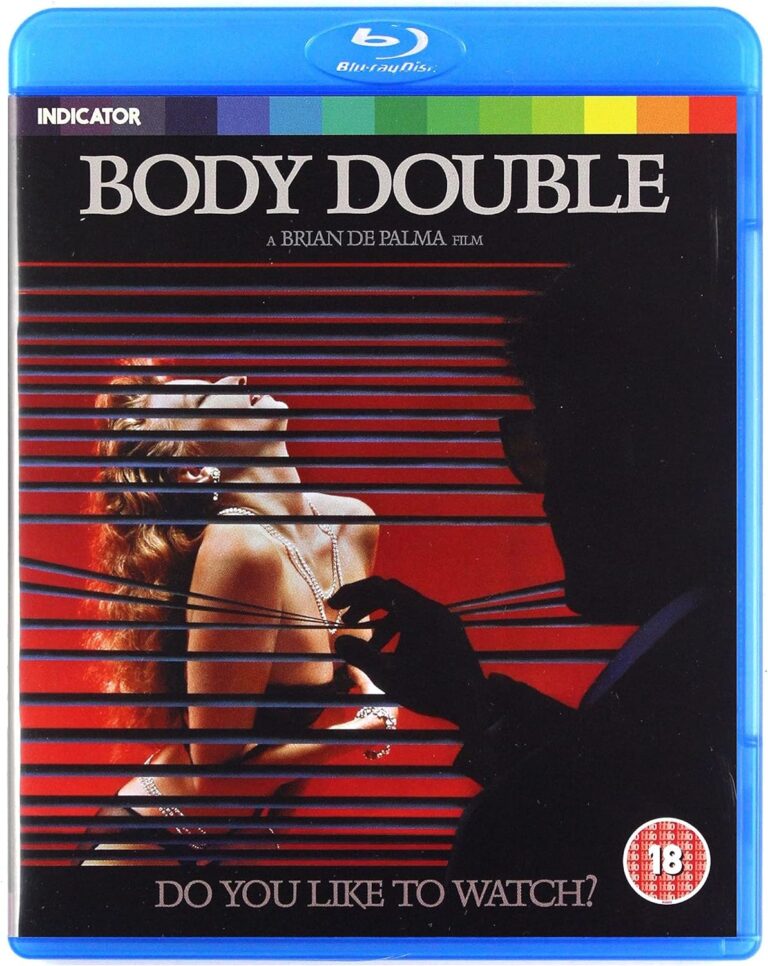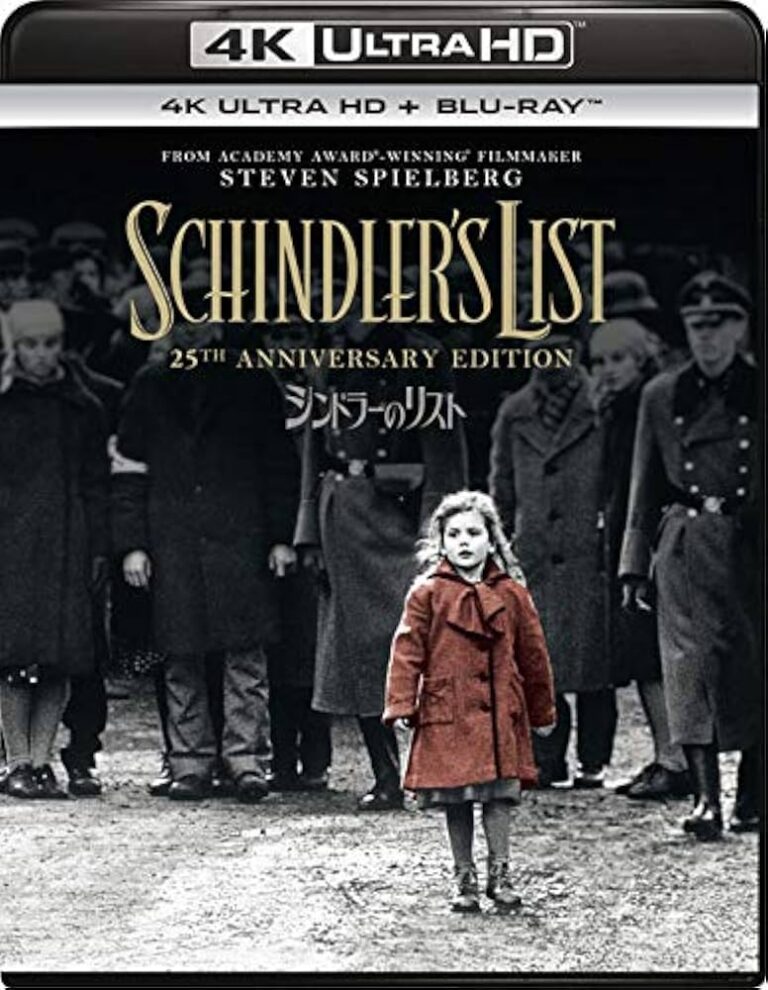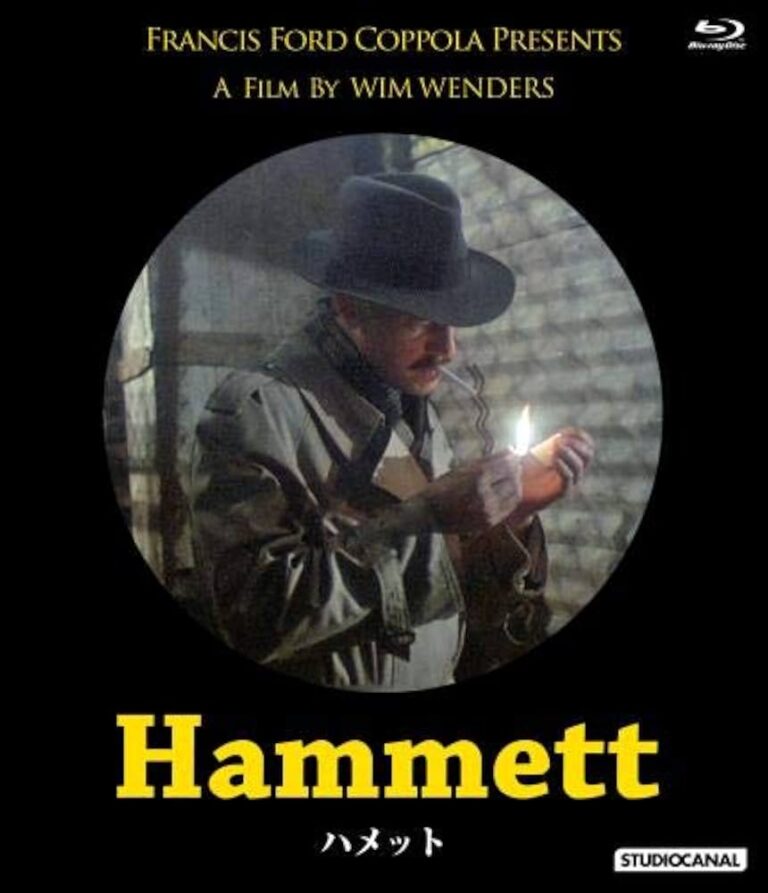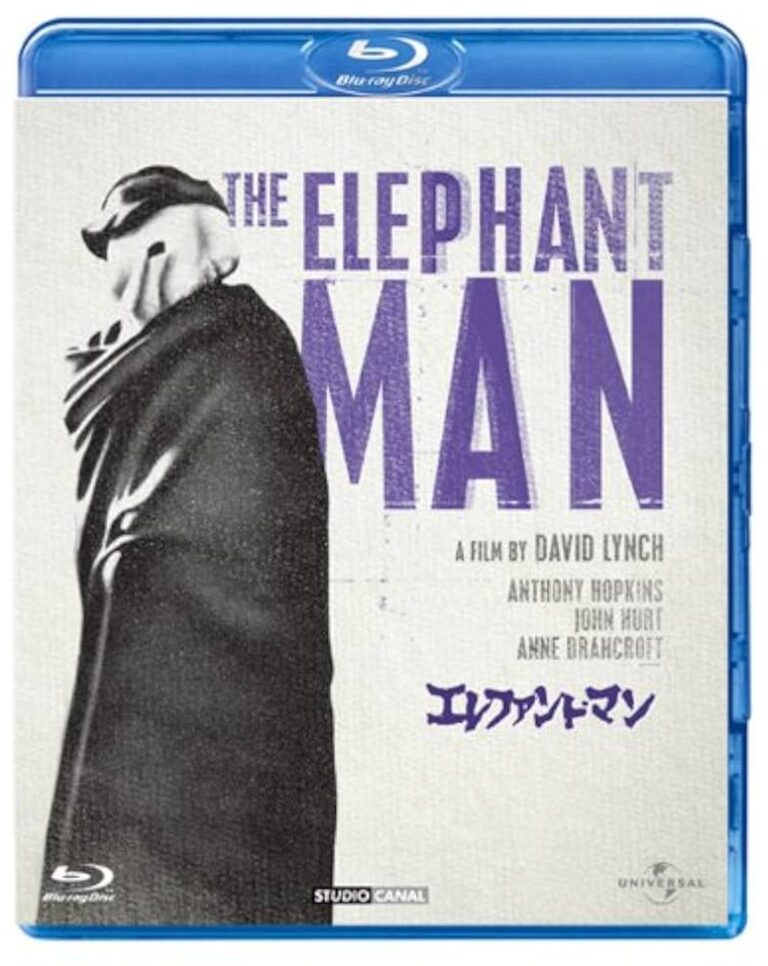『スカーフェイス』(1983)
映画考察・解説・レビュー
『スカーフェイス』(1983年)は、ブライアン・デ・パルマ監督がアル・パチーノ主演で放った暴力と欲望の黙示録である。コカインと血にまみれたアメリカン・ドリームの崩壊を描き、80年代カルチャーの象徴として今も生き続ける。
『スカーフェイス』(原題:Scarface/1983年)は、ブライアン・デ・パルマ監督、アル・パチーノ主演によるギャング映画の金字塔。公開当時は「FUCK」ワード206回や電動ノコギリ拷問など過激描写で酷評を浴びたが、やがて評価は逆転し、現在ではヒップホップやストリートファッションに多大な影響を与えたカルチャー・アイコンとして語り継がれている。本記事では、1932年版『暗黒街の顔役』との関係、パチーノの野獣的演技、そして80年代アメリカを象徴する過剰さの魅力を徹底考察する。
リメイクから始まった数奇な企画
『スカーフェイス』(1983年)の起点は、プロデューサーのマーティン・ブレグマンが深夜放送でハワード・ホークス監督の『暗黒街の顔役』(1932年)を観たことに遡る。
この映画の製作総指揮を務めたのは大富豪ハワード・ヒューズ。禁酒法時代のシカゴを舞台に、アル・カポネをモデルとした主人公トニー・カモンテ(ポール・ムニ)が血と暴力で暗黒街を支配していく姿が描かれた。
当時としては異例のバイオレンス描写は大きな論争を呼び、全米各地で上映禁止や再編集を求められる事態に発展。映画に副題「The Shame of a Nation(国の恥)」をつけ、社会告発の色を前面に出すことでようやく公開にこぎつけたという逸話もある。
とはいえ、ホークス特有の疾走感ある演出と、トンプソン・マシンガンを駆使した銃撃戦のイメージは強烈で、ギャング映画の新たなスタンダードを確立したことは間違いない。
主人公トニーが妹に異常な執着を見せるという、血縁と欲望が入り混じるその設定は、のちの『スカーフェイス』(1983年)においても繰り返されている。ホークス版は単なる古典ではなく、デ・パルマ版の核心的モチーフをすでに孕んでいたのだ。
ブレグマンは、この古典をアル・パチーノ主演でリメイクすることを決意し、企画を始動させる。監督には名匠シドニー・ルメットが選ばれ、彼はアル・カポネを題材にしたクラシックなギャング譚を、現代の「コカイン社会」へと翻案することを提案。
しかしそこに、自身もコカイン中毒経験のあるオリバー・ストーンが脚本に参画したことで、物語は一気に過激さを増す。結果としてルメットは降板し、最終的にブライアン・デ・パルマが監督の座へ就くことになる。かくして、後に“悪逆無道ムービー”と評される新たな『スカーフェイス』が誕生したのである。
公開当時の評価 ――酷評とスキャンダル
公開直後の評判は最悪だった。なにしろ本作では「FUCK」という単語が台詞の大半を覆い尽くしており、その回数は206回。上映時間170分弱で平均すると1分に1回以上のペースで罵声が飛び交うという、当時としては前代未聞のギネス級の多用ぶりだった。
さらに、浴室での電動ノコギリによる拷問シーンは悪趣味の極みとされ、観客と批評家をドン引きさせた。だが問題視されたのはそれだけではない。
机いっぱいに積もったコカインへ顔を突っ込みラリまくるトニーの姿、妹ジーナに対する近親相姦的とも言える執着、愛人エルヴィラを「ヤクをやりすぎて子宮が腐ってる」と罵倒する場面――いずれも当時のハリウッド映画の常識を逸脱した“下品さ”として受け止められた。
クライマックスの銃撃戦もまた、血しぶきと肉体の破壊を過剰なまでに強調しており、「Say hello to my little friend!」と叫んでM16を乱射する場面は、カタルシスと同時に批評家に「悪趣味の見本市」と断じられる要因となった。
こうしてオリジナル版『暗黒街の顔役』が持っていたノワール的風味は完全に消し飛び、批評家はこぞって酷評。ついにはラジー賞のワースト監督賞まで受賞し、意気軒昂にハリウッドへ乗り込んだブライアン・デ・パルマの期待は無惨に打ち砕かれたのである。
しかし、時が経つにつれて評価は逆転する。かつて悪趣味と罵られた過剰さこそが80年代アメリカの虚飾と欲望を象徴するものと再解釈され、今や『スカーフェイス』はギャング映画の新たなスタンダードとして語り継がれるに至った。映画史の皮肉はここに極まれり、である。
アル・パチーノの演技 ――野獣と化すアンチ・ヒーロー
この映画を語る上で、アル・パチーノのトニー・モンタナ抜きにはあり得ない。妹ジーナに手を出したマニーを知った瞬間の、血走った眼差し。銃弾を浴びながら、「貴様らのクソ弾なんか屁でもねえ!」と絶叫する姿。
その全身から噴き出すエネルギーは、もはや“人間”を超えた“野獣”の域にある。庭で飼われる虎がその象徴であり、彼の存在感はマフィアのボスというよりも、欲望と破壊衝動に突き動かされる猛獣そのものだ。
ここで注目すべきは、同じマフィア映画『ゴッドファーザー』(1972年)における演技との落差。マイケル・コルレオーネは寡黙で冷徹、怒りも野心も内側に押し殺しながら、氷のような視線で相手を支配する存在だった。
それに対してトニー・モンタナは、感情を隠すことを一切せず、欲望も怒りも破滅も全てを剥き出しにする。低音で囁くように語る『ゴッドファーザー』のパチーノに対し、『スカーフェイス』では怒鳴り、唾を飛ばし、顔の筋肉を震わせる。まさに対極の演技スタイルであり、彼の俳優としての振れ幅を証明している。
さらに特筆すべきは、その“過剰さ”が80年代という時代の空気と呼応していた点だ。アメリカ経済の拡張主義、ドラッグ文化の蔓延、ヒスパニック移民の社会的葛藤――パチーノのトニーは、それら全てを一身に背負い、欲望と破滅のアイコンへと昇華した。
抑制の効いたクラシックなギャング像から、ラテン移民のアンチ・ヒーローへと変貌することで、ギャング映画は新たな世代の観客に届いたのである。
口元を震わせ、血管を浮き上がらせる彼の表情は、半世紀を超える俳優人生においても屈指のハイライトだろう。アル・パチーノのキャリアにおいて、マイケル・コルレオーネが「静の頂点」だとすれば、トニー・モンタナは「動の極北」。
両極を演じ切ったからこそ、彼は映画史に残る偉大なアクターとして不動の地位を築いたのだ。
サブカルチャーへの影響 ――ヒップホップが選んだアイコン
『スカーフェイス』は単なる映画を越えて、文化的現象となった。マイアミの土産物屋にはトニー・モンタナのTシャツやフィギュアが並び、彼の姿はヒップホップやブラック・カルチャーにおいて“アンチ・ヒーローの象徴”として参照され続けている。
パフ・ダディが「俺はこの映画を63回は観た」と豪語した逸話は有名。Jay-ZやNasをはじめとする数多くのラッパーがリリックでトニーを引用し、その豪邸やライフスタイルを“成功の記号”として模倣した。
その影響はファッションにも波及する。白いスーツや葉巻といったトニーのアイコンはヒップホップ・ファッションのスタイル源となり、ナイキやシュプリームが「Scarface」デザインのコラボアイテムを発表するなど、ストリートブランドのモチーフとして定着した。トニー・モンタナはラップ界だけでなく、ストリートのアイコンへと変貌したのである。
映像文化への影響も絶大だ。『GTA: Vice City』(2002年)は『スカーフェイス』を下敷きにしており、2006年には『Scarface: The World Is Yours』がリリースされ、「もしトニーが生き延びていたら」というIFストーリーまで描かれた。テレビドラマ『ブレイキング・バッド』最終回のM60乱射シーンも、『スカーフェイス』クライマックスへの明白なオマージュである。
さらに、トニー・モンタナが“移民の成り上がり”という設定を持つことから、ラテン系や黒人コミュニティでは「アメリカン・ドリームの裏返し」として熱狂的支持を集めた。成り上がりの象徴でありながら破滅の化身でもあるトニーは、マイノリティの複雑なアイデンティティを投影する対象となった。
そして今日では、映画のポスターや名台詞「Say hello to my little friend!」はポップアートやストリートアートの題材としても消費され続けている。アンディ・ウォーホル風に加工されたモンタナの肖像や、壁画に描かれるその姿は、すでに一個の「カルチャー・アイコン」として独立しているのだ。
ミシェル・ファイファー演じるエルヴィラの虚ろな魅力や、ジョルジオ・モロダーによる安っぽいシンセ・サウンドもまた、80年代の享楽と虚無を象徴するエッセンスとして文化に刻み込まれている。『スカーフェイス』は、映画であると同時にカルチャー全体を覆い尽くした神話なのである。
悪趣味が時代を撃ち抜いた
結論から言えば、『スカーフェイス』は血と暴力に彩られた悪逆無道ムービーである。しかし、その過剰さこそが80年代アメリカの虚飾と欲望を最も的確に映し出し、今日まで語り継がれる所以となった。
「俺はこの映画を63回観た」と語ったパフ・ダディのように、本作は何度でも繰り返し鑑賞され、語られる運命にある。デ・パルマの十八番にして、アル・パチーノが野獣と化した瞬間を刻み込んだ唯一無二のギャング映画――『スカーフェイス』は、まぎれもなくサイコーなのである。
- 原題/Scarface
- 製作年/1983年
- 製作国/アメリカ
- 上映時間/169分
- ジャンル/アクション、クライム
- 監督/ブライアン・デ・パルマ
- 脚本/オリバー・ストーン
- 製作/マーティン・ブレグマン
- 撮影/ジョン・A・アロンゾ
- 音楽/ジョルジオ・モロダー
- 編集/ジェラルド・B・グリーンバーグ、デイヴィッド・レイ
- 美術/エドワード・リチャードソン
- 衣装/パトリシア・ノリス
- アル・パチーノ
- ミシェル・ファイファー
- F・マーレイ・エイブラハム
- スティーヴン・バウアー
- メアリー・エリザベス・マストラントニオ
- ロバート・ロジア
- ハリス・ユーリン

![スカーフェイス/ブライアン・デ・パルマ[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/71638EfRnL._AC_SL1289_-e1707308760125.jpg)