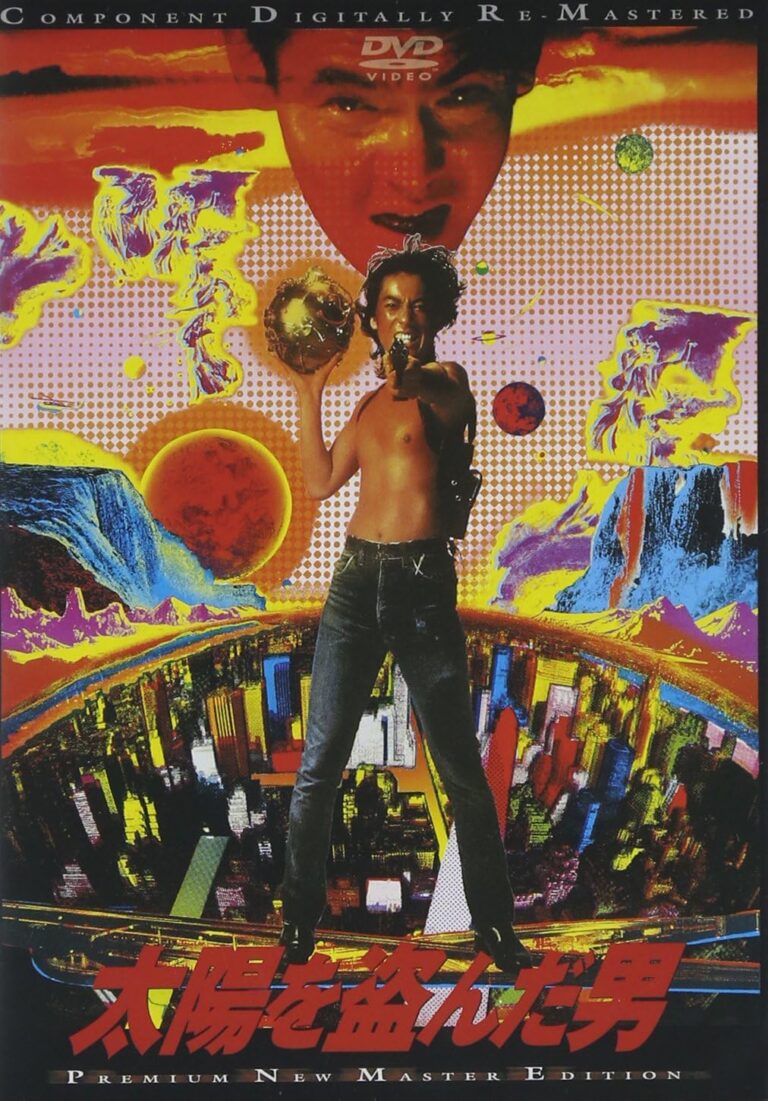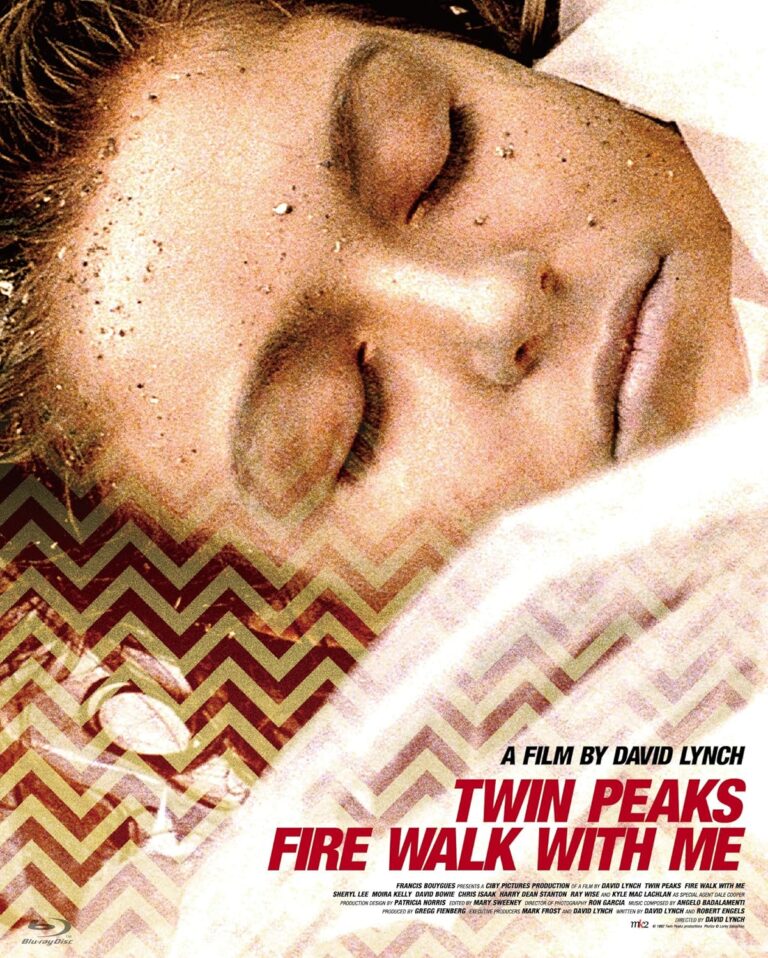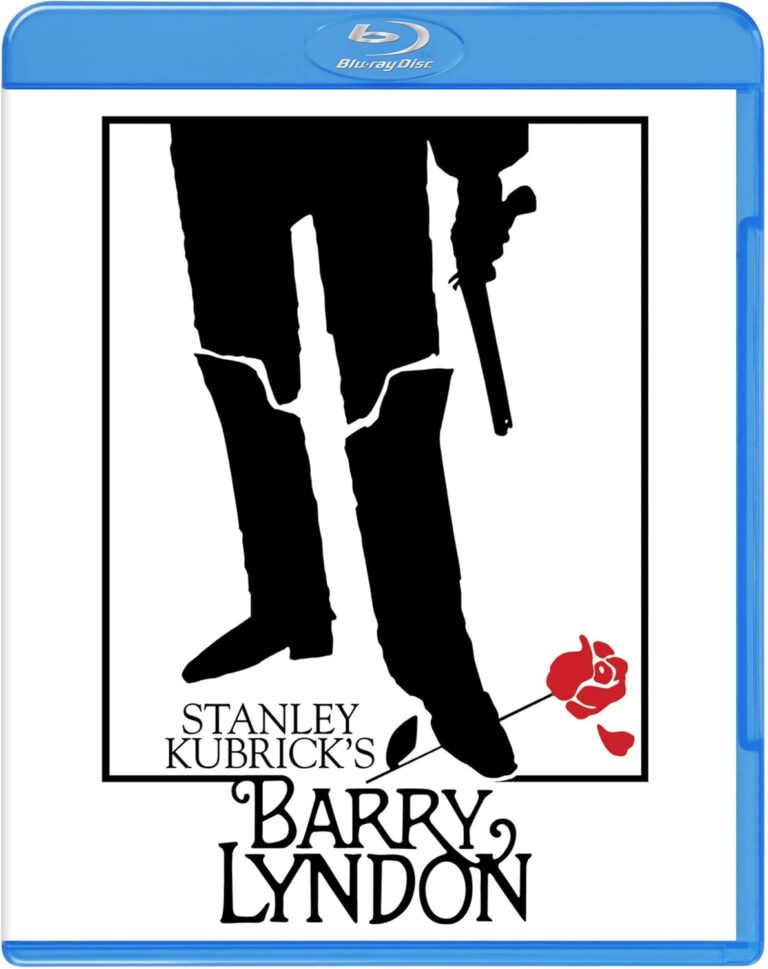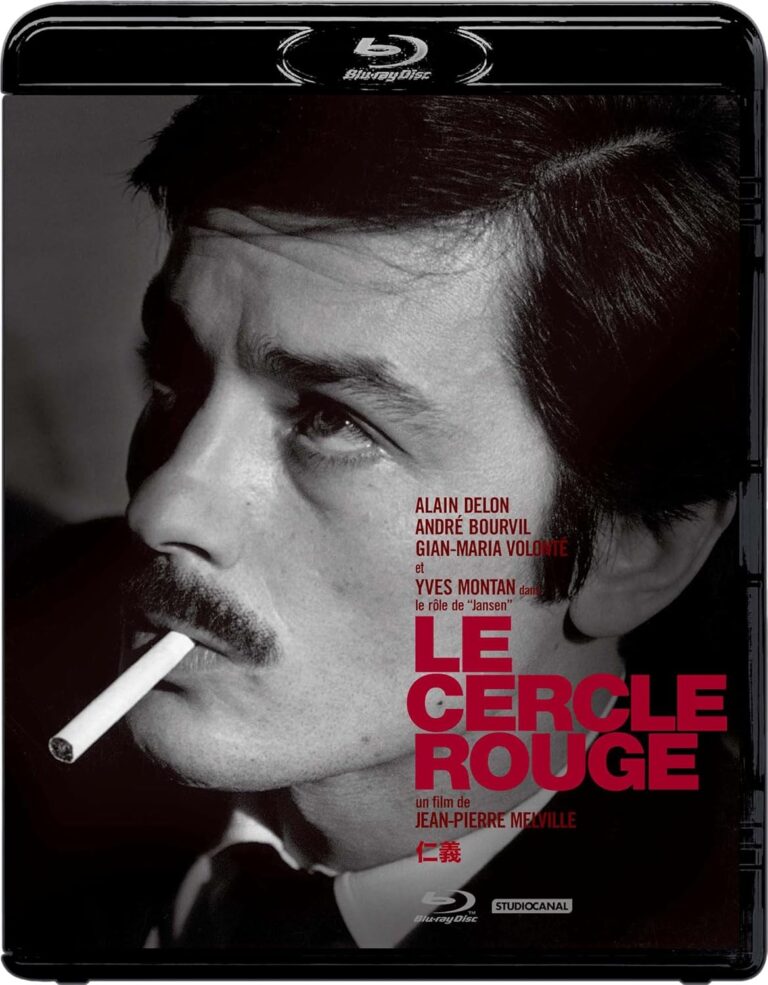『聖なる鹿殺し キリング・オブ・ア・セイクリッド・ディア』(2017)
映画考察・解説・レビュー
『聖なる鹿殺し キリング・オブ・ア・セイクリッド・ディア』(2017年)は、ギリシャの奇才ヨルゴス・ランティモスが、カンヌ国際映画祭脚本賞をかっさらった不条理スリラーの怪作。心臓外科医の平穏な家庭が、一人の少年の出現によって「神話的呪い」に侵食されていく様を描く。コリン・ファレル、ニコール・キッドマン、そしてバリー・コーガンという豪華キャストが、感情を去勢されたような演技で繰り広げる、戦慄の家族解体ショー。
神話的因果律──「目には目を」という絶対零度の恐怖
『聖なる鹿殺し キリング・オブ・ア・セイクリッド・ディア』(2017年)には、幽霊も出なければ、ジェイソンのような殺人鬼も出ない。ここに存在するのは、あまりにもシンプルで、だからこそ逃れようのない恐怖がある。
主人公スティーブン(コリン・ファレル)は、成功した心臓外科医だ。美しい妻アナ(ニコール・キッドマン)と二人の子供、豪邸、高価な腕時計。
全てを手に入れたかに見える彼だが、過去に犯した「医療ミス」という罪を隠している。そこに現れるのが、謎の少年マーティン(バリー・コーガン)だ。彼はスティーブンにこう告げる。「君が僕の父親を殺した。だから君の家族も一人死ななければならない。バランスを取るために」。
これは脅迫ではなく、自然法則の宣告だ。ランティモス監督は、この不条理な設定を現代のアメリカに持ち込むにあたり、エウリピデスのギリシャ悲劇『アウリスのイフィゲニア』をモチーフに選んだ。
かつてミケーネ王アガメムノンが女神アルテミスの聖なる鹿を殺した罰として、自らの娘を生贄に捧げることを強要されたように、スティーブンもまた血の代償を支払わねばならない。
本作の恐ろしさは、この呪いが超自然的な現象としてではなく、まるでインフルエンザのように淡々と進行する点にある。子供たちの足が動かなくなり、食欲を失い、目から血を流す。医学的説明は一切ナシ。
現代科学の粋を集めた病院で、CTスキャンを何度撮ろうが原因不明。スティーブンは「科学的合理性」の象徴として、この非科学的な呪いを否定し続ける。だが、マーティンという「神の代行者」が突きつける因果律の前では、最新医療など無力なのだ。
ランティモス特有の、抑揚のない棒読み演技が、この恐怖を加速させる。登場人物たちはパニックに陥るべき事態でも、まるでロボットのように無機質な会話を続ける。
「脚が動かないの」「そうか、じゃあ這って行け」。この感情の欠落こそが、観客の不安を極限まで煽る。我々は、スクリーンの中の彼らが人間なのか、それとも神の実験台にされたモルモットなのか、サッパリ分からなくなってくるのだ。
広角レンズと不協和音が刻む生理的嫌悪
ヨルゴス・ランティモスの映画には、常に居心地の悪さが充満しているが、本作におけるその濃度は致死レベルだ。撮影監督ティミオス・バカタキスが作り出した映像世界は、美しく、清潔で、そして吐き気がするほど不気味である。
まず注目すべきは、極端な広角レンズ(10mmレンズ等)の使用だ。カメラは病院の長い廊下や、豪邸の広すぎるリビングを、空間ごと歪ませて映し出す。
登場人物たちは、この広大すぎる空間の中にポツンと配置され、常に何かに見張られているような孤独感を漂わせている。 さらに、スタンリー・キューブリックの『シャイニング』(1980年)を彷彿とさせる、地面を這うようなトラッキングショット。だがキューブリックのそれが「何かが起こる予感」だとするなら、ランティモスのカメラは「逃げ場のない閉塞感」を執拗に追い回す。
そして、「神の視点」とも言うべき極端なハイアングル撮影。病院のエントランスや手術室を真上から見下ろすその構図は、人間たちが盤上の駒に過ぎないことを冷酷に示唆している。
特に冒頭、実際に拍動している心臓のクローズアップ映像に、シューベルトの「あべこべ通信」が流れるシーン。グロテスクな生体反応と、崇高なクラシック音楽の悪趣味な融合! 開始数秒で「この映画はヤバい」と本能が警報を鳴らす演出なのだ。
音響設計もまた、精神攻撃のレベルに達している。会話の背後で常に鳴り響く、金属を引っ掻いたような不協和音。あるいは、アコーディオンの音が呼吸困難に陥ったかのように途切れ途切れに響く。
この映画には安らぎという瞬間が1秒たりとも存在しない。清潔なリネン、整えられた食卓、完璧な手術着。それら「文明的で綺麗なもの」が、すべて暴力を隠すための包装紙に見えてくる。
ランティモスは、現代社会の無菌室のような暴力性を、視覚と聴覚の不快指数をマックスにすることで表現してみせたのだ。
スパゲッティの怪物──バリー・コーガンという必然
『聖なる鹿殺し』を映画史に残る怪作たらしめている最大の要因、それは間違いなくバリー・コーガン(マーティン役)の存在だ。当時まだ無名に近かったこのアイルランドの若手俳優は、本作で「映画史上最も礼儀正しく、最も胸糞悪いヴィラン」の一人となった。
マーティンは決して声を荒げない。怒鳴りもしなければ、ナイフを振り回すこともない。彼はただ、スティーブンの職場に現れ、ぎこちない笑顔で「脇毛を見せてくれませんか?」と頼んだり、自分の母親とスティーブンをくっつけようとしたりする。その純粋さと邪悪さの境界線が完全に溶解している佇まいは、まさに「人間界に降りてきた異物」だ。
特筆すべきは、伝説となった「スパゲッティを食べるシーン」である。 スティーブンの妻アナに対し、マーティンが自分の勝利(=呪いの進行)を確信しながら、ただひたすらにスパゲッティを貪り食う。
ソースを口の周りにベッタリとつけ、下品な音を立ててすする。 実はこのシーン、脚本には「食べる」としか書かれていなかったという。コーガンは本番で突然、獣のように汚く食べる演技を選択した。
その瞬間、アナ(ニコール・キッドマン)の表情に浮かんだ嫌悪感は、演技を超えた本物の生理的拒絶だったに違いない。彼は言葉ではなく「咀嚼音」で、この家族を支配したのだ。
物語のクライマックス、スティーブンは家族の誰を殺すか選べず、目隠しをしてライフルを持って回るという「ロシアン・ルーレット」ならぬ「人間ルーレット」を行う。
リビングでぐるぐると回る父親、逃げ惑う家族。あまりにも滑稽で、あまりにも残酷なこの地獄絵図こそ、ランティモスが描きたかった“決断できない現代人の末路”ではないか。
ラストシーン、ダイナーでフライドポテトを食べる生き残った家族。そこにマーティンが入ってくる。言葉は交わされない。ただ視線が交錯するだけだ。彼らは救われたのか? いや、違う。彼らは神の算術によって、魂の一部を永遠に欠損したまま生きていくのだ。
ケチャップをたっぷりとつけたポテトを頬張るマーティンの、あの虚無的な瞳。それを目撃したとき、我々は知る。この世には、人間の理屈など通用しない、聖なる理不尽が存在するのだと。
- 原題/The Killing of a Sacred Deer
- 製作年/2017年
- 製作国/イギリス、アイルランド
- 上映時間/121分
- ジャンル/サスペンス、スリラー
- 監督/ヨルゴス・ランティモス
- 脚本/ヨルゴス・ランティモス、エフティミス・フィリップ
- 製作/エド・ギニー、ヨルゴス・ランティモス
- 製作総指揮/アンドリュー・ロウ、ダニエル・バトセック、サム・ラベンダー、デヴィッド・コッシ
- 制作会社/A24、Film4、エレメント・ピクチャーズ
- 撮影/ティミオス・バカタキス
- 編集/ヨルゴス・マヴロプサリディス
- 美術/ジェイド・ヒーリー
- 衣装/ナンシー・スタイナー
- 録音/ジョニー・バーン
- コリン・ファレル
- ニコール・キッドマン
- バリー・コーガン
- ラフィー・キャシディ
- サニー・スリッチ
- アリシア・シルヴァーストーン
- ビル・キャンプ
- 聖なる鹿殺し キリング・オブ・ア・セイクリッド・ディア(2017年/イギリス、アイルランド)
- 哀れなるものたち(2023年/イギリス)
- 憐れみの3章(2024年/アメリカ、イギリス)
![聖なる鹿殺し キリング・オブ・ア・セイクリッド・ディア/ヨルゴス・ランティモス[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/81e8fxhWePL._AC_UL640_FMwebp_QL65_-e1767198893917.webp)