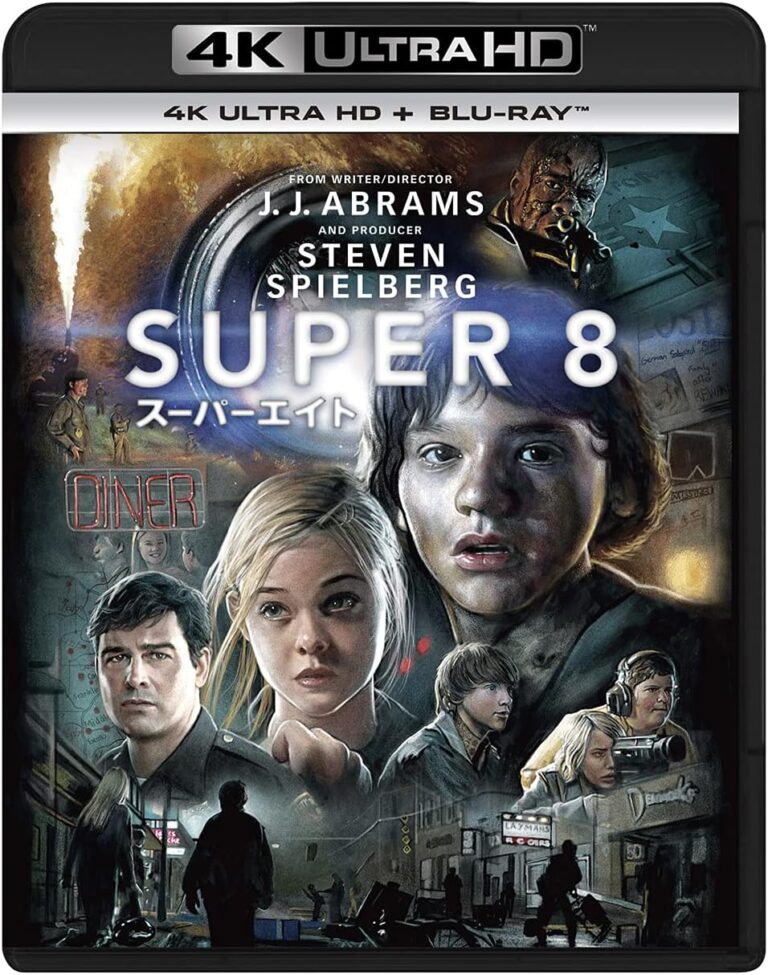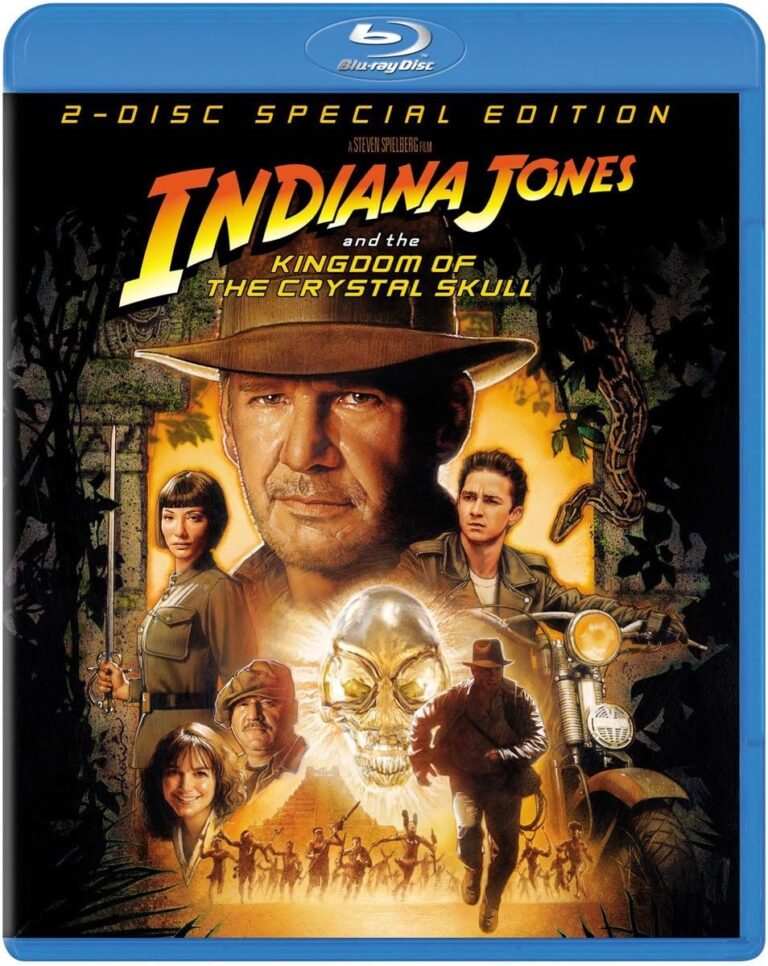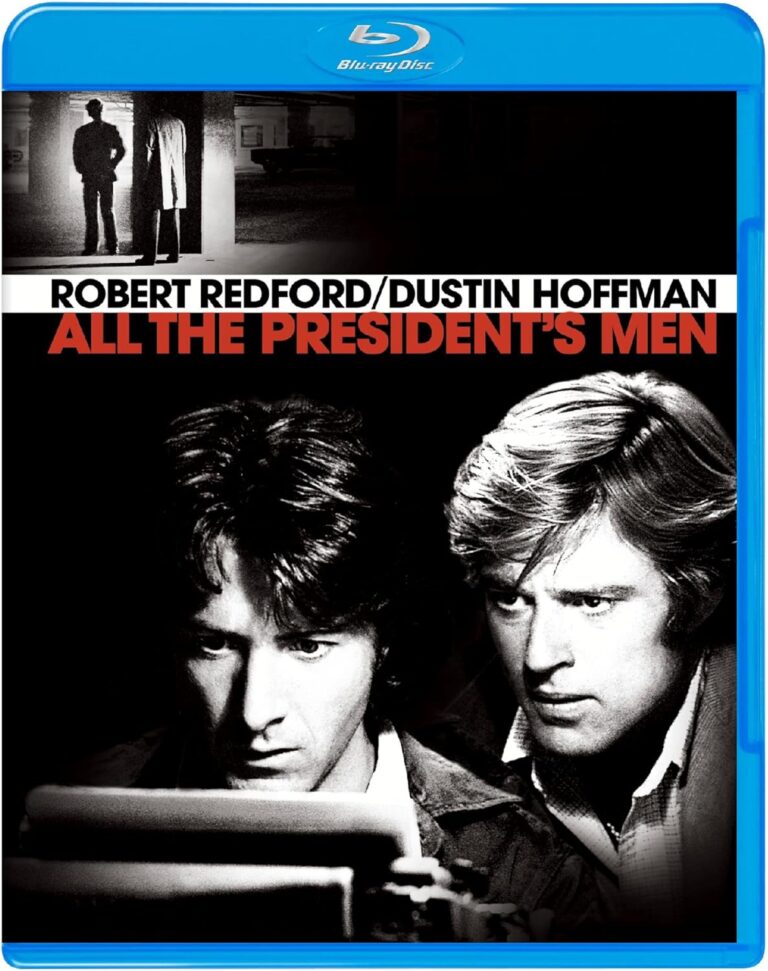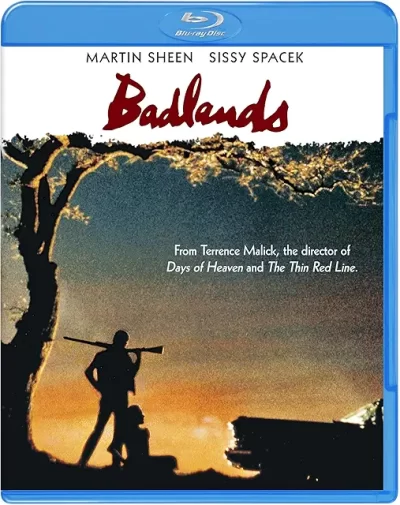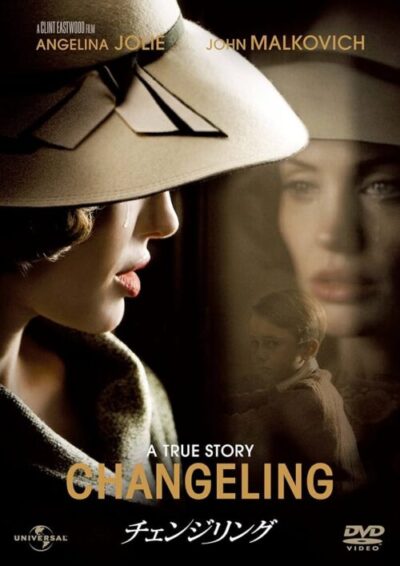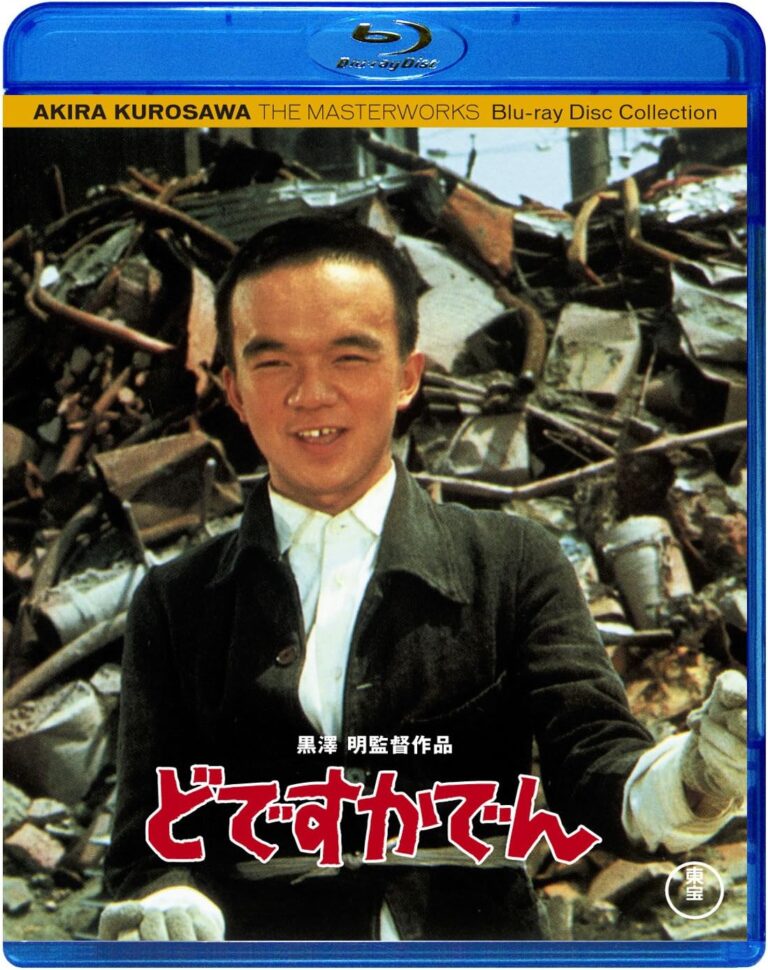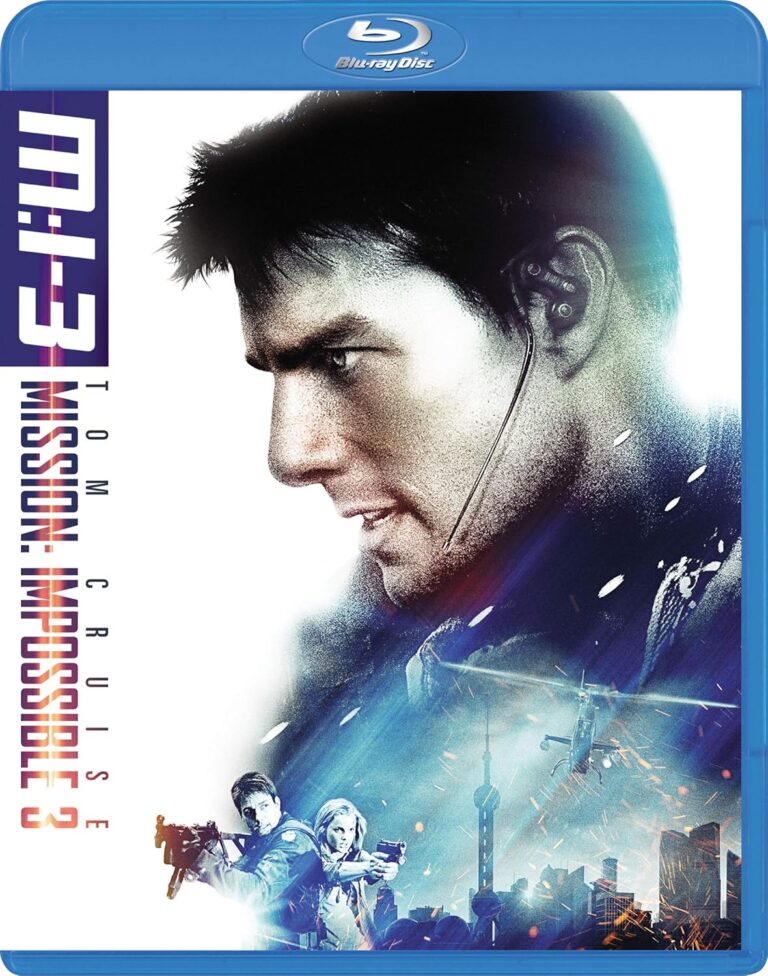『天使と悪魔』──時間と信仰のアポリア
『天使と悪魔』(原題:Angels & Demons/2009年)は、ダン・ブラウンの同名小説を原作とする、ヴァチカンを揺るがす連続誘拐と爆破予告事件を描いた宗教ミステリー。ラングドン教授が古代科学と信仰の象徴を辿りながら、四大元素を鍵にローマの街を奔走する。枢機卿暗殺と反物質の脅威が迫る中で、時間と理性の限界を賭けた闘いが展開する。
情報の洪水を「時間」に変換する
筆者は前作『ダ・ヴィンチ・コード』(2005年)のレビューで、「映画というフォーマットで、原作の膨大な情報量をどのように詰め込んでいくのかが最大の難問だった。しかし、そんなのどうしたって負け戦に決まっている」と書いた。
ダン・ブラウンの小説世界は、宗教史・美術史・暗号学・数学・神秘主義を縦横無尽に引用しながら構築されており、その情報密度は文学的にも構造的にも過剰。したがって、映像化の瞬間に“編集”という名の犠牲を強いられる宿命を背負っている。
だがその続編『天使と悪魔』(2009年)は、その構造的欠陥を逆手に取り、むしろ“映画的制約”を推進力に変えることに成功している。ロン・ハワードは、情報の洪水を時間軸のドラマに変換することで、前作を超えるリズムと緊張を獲得した。
時限装置としてのプロット
『天使と悪魔』の物語は、精密に設計された“時限プロット”によって進行する。
次期ローマ教皇候補である枢機卿四人が誘拐され、秘密結社イルミナティから「一時間ごとに枢機卿を殺害する」という予告が届く。そして四人全員が殺害された後には、「反物質」を使ってヴァチカンを爆破するという最終宣告が下される。
時計が進むごとに命が消える——この明快な構造が、観客の時間意識を物語の内部へと巻き込む装置として機能している。ロバート・ラングドン教授(トム・ハンクス)は、古代科学の象徴である四大元素〈土・空気・火・水〉に対応した殺害現場を推理し、次の死を阻止すべくローマの街を疾走する。いわば“学者版『24 -TWENTY FOUR-』”である。
このリアルタイム的プロットは、物語に確固たる駆動力を与え、観客を知的な迷宮から肉体的なサスペンスへと誘導する。ロン・ハワードは情報を削るのではなく、情報を「時間の圧縮」として再編した。学問の探求が思索ではなく“走ること”として描かれる時、知性は肉体を獲得するのだ。
本作の撮影は、ヴァチカン市国そのものの撮影許可が得られなかったため、イタリア国内に実寸大のセットを構築するという異例の規模で行われた。
結果として、実在のローマよりも“映画的に設計されたローマ”が誕生する。彫像、教会、地下墓地——それぞれの空間が象徴として連鎖し、都市そのものが巨大な暗号機械のように作動する。
ハワードは、都市空間を宗教的記号体系として扱いながら、観客の視線を導く。移動と切断、光と影、石と炎。映画のリズムはそのまま都市の脈動と同期する。
ここに、ハワードの空間演出の精度が表れている。『ダ・ヴィンチ・コード』では美術館という静的空間に情報を詰め込んだが、『天使と悪魔』では街路と時間の流れを結合させることで、映像の流動性を獲得した。
ラングドンの思考はもはや講義ではなくアクションであり、推理は肉体運動としてスクリーンに可視化される。
信仰と科学の対立構造
本作の核心は、“信仰”と“科学”という二項対立の再検証にある。イルミナティという名の秘密結社は、啓蒙思想の残滓であり、教会が抑圧してきた科学者たちの怨念の集合体として描かれる。
一方、ヴァチカンは伝統と秩序の象徴であり、世界を超越的原理によって統べようとする権威そのものだ。ラングドンはその狭間に立つ。彼はどちらの側にも属さず、知性を媒介として世界を解釈する者——すなわち「中間者」として機能する。
ハワードの演出はこの構図を単純化しない。科学の暴走も、信仰の暴力も、同じように“人間の傲慢”の帰結であることを示す。反物質という存在はその象徴だ。
創造と破壊、光と闇、天使と悪魔——それらは対立ではなく、補完関係にある。爆破予告のタイマーが刻む一秒ごとに、映画は宗教哲学的な命題を更新していく。つまり、時間の経過そのものが神の審判を可視化しているのだ。
『天使と悪魔』のもうひとつの成功は、脚本段階での取捨選択にある。前作のように登場人物を過剰に詰め込むことを避け、プロットの骨格を際立たせている。情報の削減は単なる省略ではなく、“知のドラマ化”への意志である。
ラングドンの知識は今回は万能ではなく、時間とともに更新され、時に誤る。その不完全さが映画的リアリティを生む。トム・ハンクスの演技もまた、学者然とした無表情から一歩進み、肉体の焦燥を纏っている。思考と走行のバランスが、キャラクターを“観念”から“人間”へと引き戻す。
脚本は主要人物を大胆に削ぎ落とし、物語の重心をラングドンと新教皇庁カメルレンゴ(ユアン・マクレガー)との対話に集中させる。この構成変更によって、映画は単なる謎解きから“倫理の選択劇”へと変貌した。誰が神の意志を代弁しうるのか——それが物語の最終審問である。
唯一の不満を挙げるなら、ヒロインである科学者ヴィットリア・ヴェトラ(アイェレット・ゾラー)の描写が希薄すぎるところか。原作において彼女は、ラングドンと対等な知的パートナーとして機能し、「ヨーガの達人とベッドを共にした経験もないでしょ?」という強烈なセリフをカマす存在していた。
だが映画ではその要素が徹底的に削がれ、ラングドンの補助的存在に矮小化されている。時間制限の中で、性的ニュアンスや情感を描く余裕がなかったのは理解できるが、その結果、作品から“身体のリアリティ”が失われてしまっている。
知的サスペンスとしての完成度は高いが、ハワード映画に通底する“人間の温度”は希薄。『ビューティフル・マインド』や『バックドラフト』で見られた“他者との共鳴”の瞬間が、この作品には欠けているのだ。
“知性”の炎に焼かれながら
『天使と悪魔』は、宗教と科学という二項を単純に対立させるのではなく、その間に生じる“思考の火花”を描いた映画だ。
知識とは、理解ではなく闘いであり、信仰とは、救いではなく迷いである。ロン・ハワードは、この二つの概念をエンターテインメントとして成立させるために、あえて理性の限界を演出した。時限爆弾のカウントダウンとともに、人間の理性もまた焼かれていく。
ラングドンは最終的に何も“信じない”のではなく、“信じすぎない”ことを選ぶ。その冷静さこそが、現代における新しい信仰の形なのかもしれない。
『ダ・ヴィンチ・コード』が“知の迷宮”だったとすれば、『天使と悪魔』は“知の爆発”である。情報の洪水を恐れず、理性の炎を手に、映画は疾走する。ロン・ハワードのフィルモグラフィーの中でも、最も知的で、最も肉体的な作品である。
- 原題/Angels & Demons
- 製作年/2009年
- 製作国/アメリカ
- 上映時間/138分
- 監督/ロン・ハワード
- 脚本/デヴィット・コープ、アキヴァ・ゴールズマン
- 製作/ブライアン・グレイザー、ロン・ハワード、ジョン・コーリー
- 原案/ダン・ブラウン
- 製作総指揮/トッド・ハロウェル、ダン・ブラウン
- 撮影/サルヴァトーレ・トチノ
- 美術/アラン・キャメロン
- 編集/ダニエル・P・ハンリー、マイク・ヒル
- 視覚効果/アンガス・ビッカートン
- 衣装/ダニエル・オーランディ
- 共同製作/キャスリーン・マクギル、ルイザ・ヴェリス、ウィリアム・M・コナー
- 音楽/ハンス・ジマー
- トム・ハンクス
- ユアン・マクレガー
- アイェレット・ゾラー
- ステラン・スカルスガルド
- ピエルフランチェスコ・ファビーノ
- ニコライ・リー・カース
- アーミン・ミューラー=スタール
- トゥーレ・リントハート