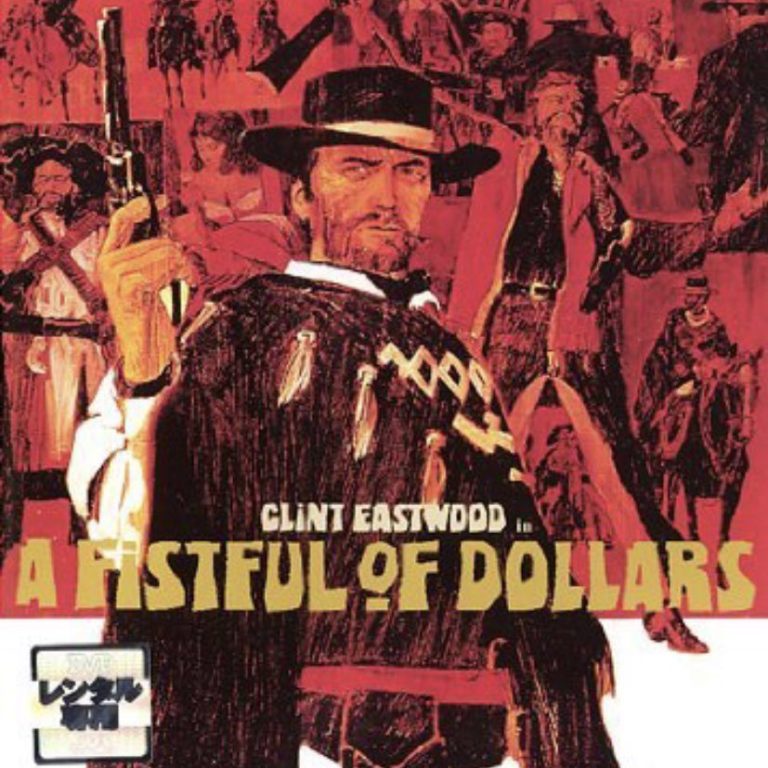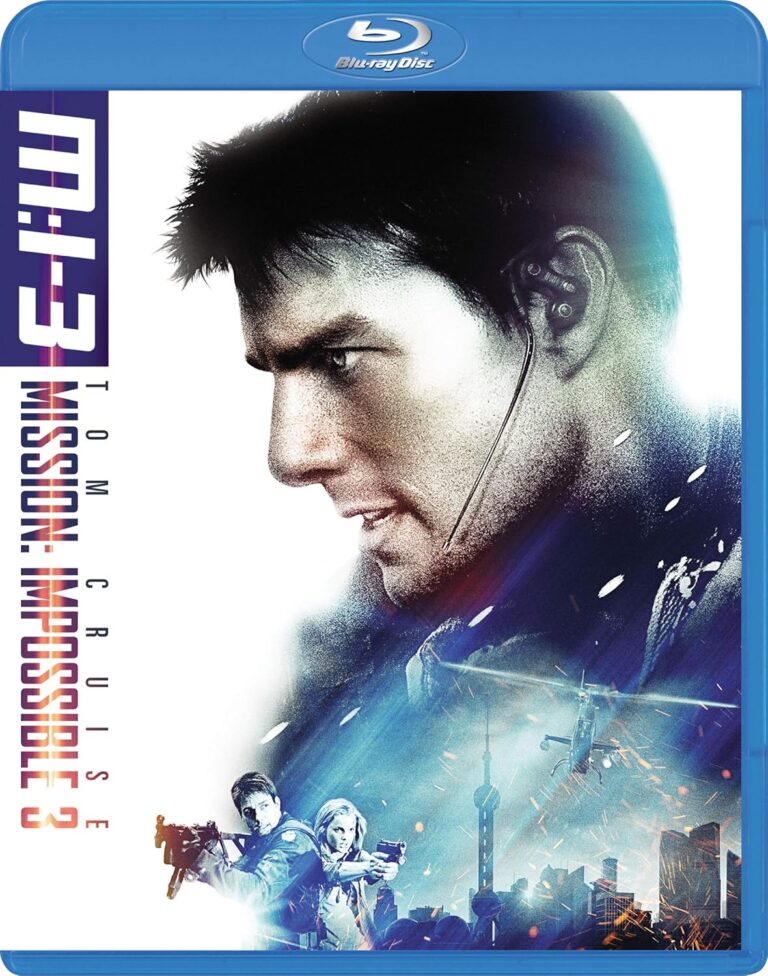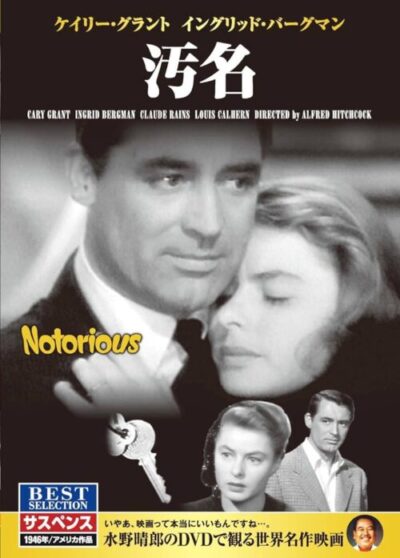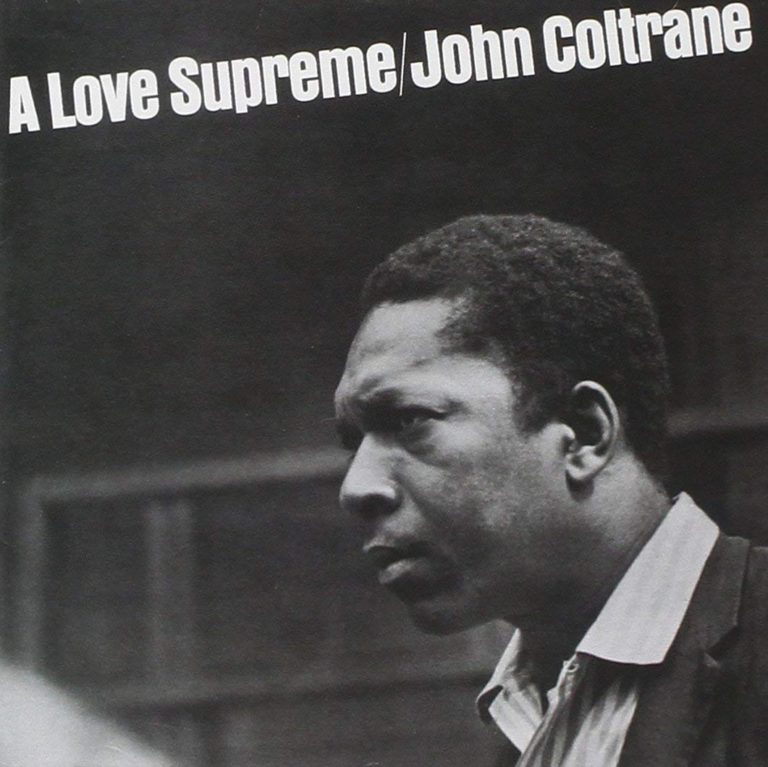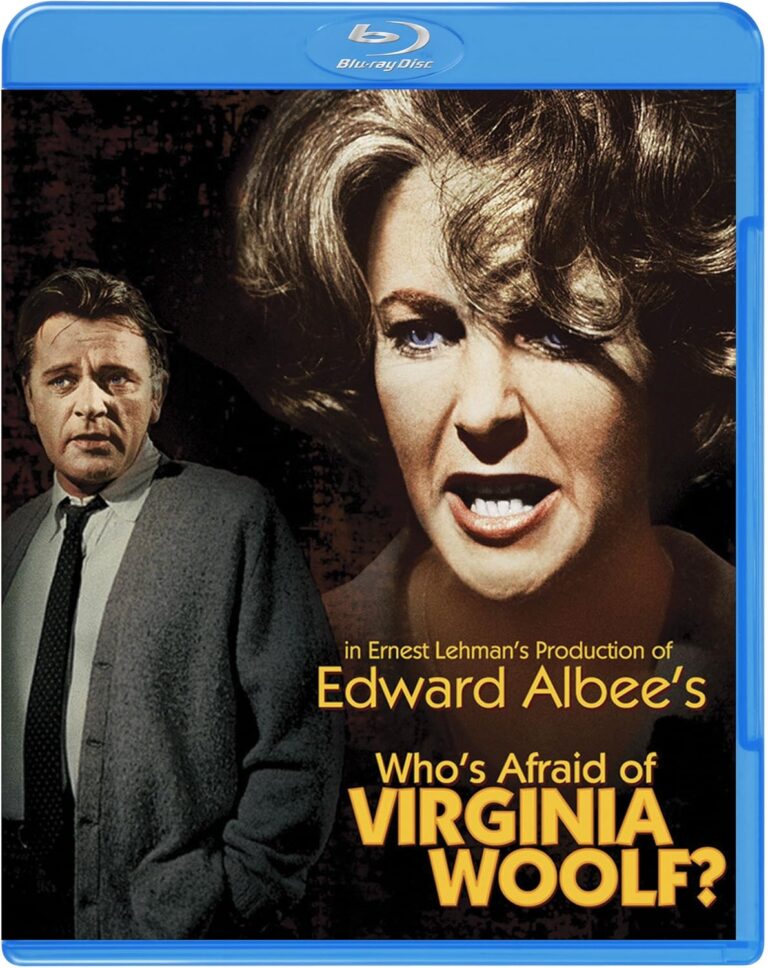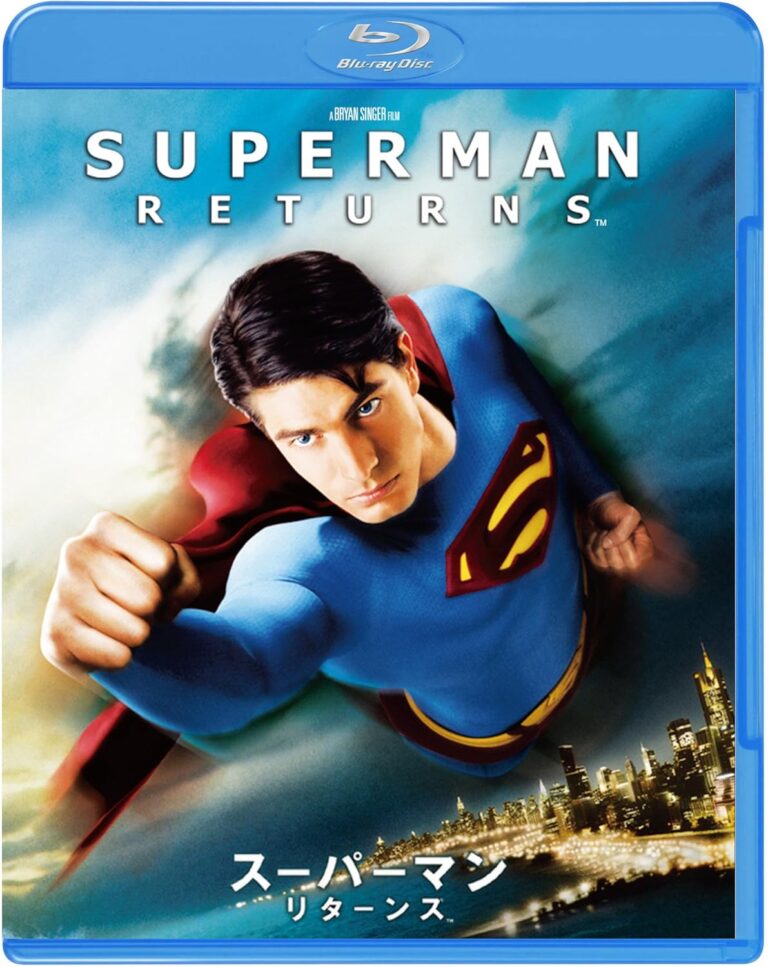『突入せよ! あさま山荘事件』──佐々淳行の自慢話を延々聞かされる“あさま山荘事件”
『突入せよ! あさま山荘事件』(2002年)は、原田眞人監督が佐々淳行の記録をもとに、1972年に長野県軽井沢で発生した立てこもり事件を描いたドラマ。連合赤軍のメンバーが山荘に侵入し、管理人の妻を人質に取ったまま籠城したことで、警視庁と長野県警が合同で救出作戦に当たる。指揮を執る警備企画課長・佐々淳行(役所広司)は、混乱する現場の調整と周辺警備の統括に追われ、県警側では本部長(伊武雅刀)や刑事部長(遠藤憲一)が状況判断に奔走する。人質救出の可否と突入時期が焦点となり、両組織の判断が事件の転機へつながっていく。
『突入せよ! あさま山荘事件』──国家装置と英雄性の絵空事をめぐる映画的構造
僕は1973年生まれで、当然あさま山荘事件が起きた1972年2月19日にはこの世にいなかった。ゆえに全共闘の熱や学園闘争のダイナミズムは、歴史の外側からしか想像できない。だからこそ、まず事件の概略へ立ち返らざるをえないだろう。
連合赤軍は京浜安保連合と共産主義者同盟赤軍派が統合して生まれた新左翼武装組織で、70年代初頭には学生運動の退潮とともに「武装闘争による革命」という理念だけが浮き彫りになり、その暴走は止まらなくなっていた。
メンバーは29人、そのうち12人が“総括”という名のもとに集団リンチで殺害され、榛名山ベースでは脱走の兆しや規律違反が即座に粛清へ結びつくという閉鎖的構造が形成されていた。
やがて5人にまで弱体化した彼らは追跡を逃れ、軽井沢のあさま山荘へ人質を取って立てこもる。破れかぶれの逃走線があの事件へ収斂したのであり、思想の理路はすでに崩壊し、行為そのものが自壊の延長として展開していく。
映画『突入せよ! あさま山荘事件』(2002年)は、この政治的背景や組織の思想性をほとんど説明しない。新左翼の文脈を削除するという判断は思い切りがよく、物語の効率化を徹底する試みでもある。
だが大胆な省略が、連合赤軍の思想的基盤への理解を断ち切った結果、観客は事件を“政治の物語”としてではなく“警察組織の物語”として受け取ることになる。
思想の枝葉が剥ぎ取られた後に残るのは、警視庁と長野県警の対立、組織内部のしがらみ、プライドの衝突といった力学であり、映画はその組織論的視点から加速していく。
一見すると事件を純化したように見えるが、実際には政治が消えることで逆に警察組織の独善的体質が強調され、権力機構の複雑な内部摩擦が物語の中心に据えられるのだ。
組織の物語化──国家装置の力学と英雄像の過剰さ
映画が描くのは、あくまで警察側の内部構造である。役所広司が演じる佐々淳行は、指揮官として困難を捌きながら前線を支配する人物として造形され、組織の混乱を統制し、命令系統を維持し、マスコミ対策を施し、部下の士気を鼓舞する。
だがその強固な英雄像は、原作者本人の経験に基づく物語であるがゆえに、自己顕示の匂いを排除しきれない。実際の佐々淳行が事件の中心で尽力したことは事実だとしても、映画の内部で“彼だけが突破口を切り開いた”という構図は、歴史の複雑さや他者の貢献を押し流し、視点の偏りを露骨に浮かび上がらせる。
言い換えれば、映画は組織の物語を描きながら、その中心に極端に理想化された英雄像を据えてしまい、歴史を単線化してしまう危うさを孕んでいる。
この単線化は映画の緊張を高める一方で、原田眞人の演出が状況の複雑さを抑制しすぎているようにも見える。捜査会議のシーンでは役者たちが新劇風のオーバーアクトで声を張り上げ、緊迫しているはずの空間が舞台劇のような過剰な熱量へ傾く。
事件のリアリティを薄めるこの演技合戦は、作品の緊張を別の方向へ逸らし、観客に“芝居を見せられている”という感触を生じさせる。映画が描くべきは国家装置の硬直した構造であり、職務と命の消耗戦であるはずなのに、演出の過度なドラマ化がその苦味を中和してしまう。
演出の速度と違和感──ハリウッド的構造を持つ日本映画
原田眞人の持ち味である高速カットと情報圧縮は、この作品にも強く表れている。だが、その速度は事件の政治性をえぐり出すためではなく、むしろ“事件がエンターテインメントとして処理される”という方向へ働く。
人質が危険に晒され、すでに民間人に犠牲者が出ているという緊迫した状況にもかかわらず、作戦決行前に明るいマーチ風の音楽が流れる場面は、事件の凄惨さと映画の調子の間に奇妙な断層を生む。
ここで示されるのは、ハリウッドアクション映画の構造に近い“死の軽量化”であり、死が物語進行の燃料として処理されてしまう状態だ。『ダイ・ハード』(1988年)のように、死や暴力が物語の機能として軽やかに回る世界観が日本の実在事件へそのまま転写されることで、事件の歴史的重層性が表層的な見せ場へと還元されてしまう。
原田の狙いを推測すれば、事件を政治的読み込みから解放し、純粋なサスペンスとして成立させようとしたのかもしれない。だが、その選択は“現実への距離”を取りすぎてしまい、逆に事件の痛みや複雑さを漂白してしまう。
高速編集、英雄化された中心人物、マーチによる昂揚──これらは確かに映画的興奮を生むが、同時に事件の悲惨さを“見せ場の一部”へ変換する危うい構造でもある。
歴史の圧力をどう受け止めるか──映画の限界と観客の視点
歴史的事件を映画が扱うとき、作品は常に“描くこと”と“削ること”の二重の選択を迫られる。『突入せよ! あさま山荘事件』は削る方へ大きく振り切り、政治・思想・葛藤を捨象し、事件を組織論と英雄譚の枠へ押し込めた。
その結果、映画としての躍動感は確かに生まれたが、歴史の複雑さはそぎ落とされ、事件の重力は驚くほど軽く扱われる。だからこそ僕は、映画を観ているというより、原作者の自慢話を延々と聞かされているような奇妙な感覚を抱いてしまう。
「最前線に立って事件を収拾したのは自分だ」という声が作品全体の裏側から響いてくるかのよう(うるせえ)。その語りは“英雄性の再演”としては機能するが、事件の全体像を照らすものではない。
映画はあらゆる暴力を“システムに還元する装置”として動いていく。原田眞人が目指したのは、事件の政治性を排し、ハリウッド的速度と構造で日本の歴史事件を語る試みだったのかもしれない。
だが、その試みが成立するためには、歴史的現実の重さと映画的速度の落差をどこかで調停する必要があり、その接合点がこの作品ではうまく機能していない。
事件の悲惨さ、暴力の構造、国家装置の硬直──それらがエンターテインメントの速度に溶かされてしまったとき、観客の視線は迷いの中へ放り出される。
- 製作年/2002年
- 製作国/日本
- 上映時間/130分
- 監督/原田眞人
- プロデュース/原正人
- 原作/佐々淳行
- 脚本/原田眞人
- 撮影/阪本善尚
- 美術/部谷京子
- 編集/上野聡一
- 音楽/村松崇継
- 照明/大久保武志
- 録音/中村淳
- 助監督/村上秀晃
- 役所広司
- 宇崎竜童
- 伊武雅刀
- 串田和美
- 松岡俊介
- 池内万作
- 矢島健一
- 豊原功補
- 篠原涼子
- 松尾スズキ
- 遠藤憲一
- 椎名桔平
- 天海祐希
- 藤田まこと

![突入せよ! あさま山荘事件/原田眞人[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/71Il2JeI6qL._AC_UL640_FMwebp_QL65_-e1763092842510.webp)