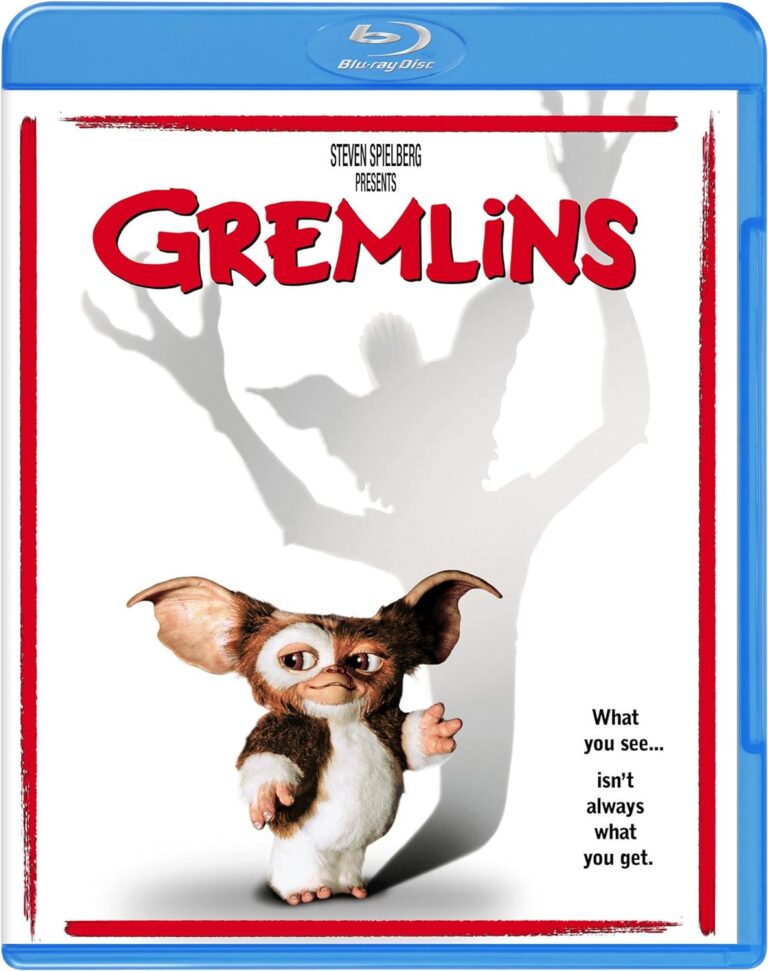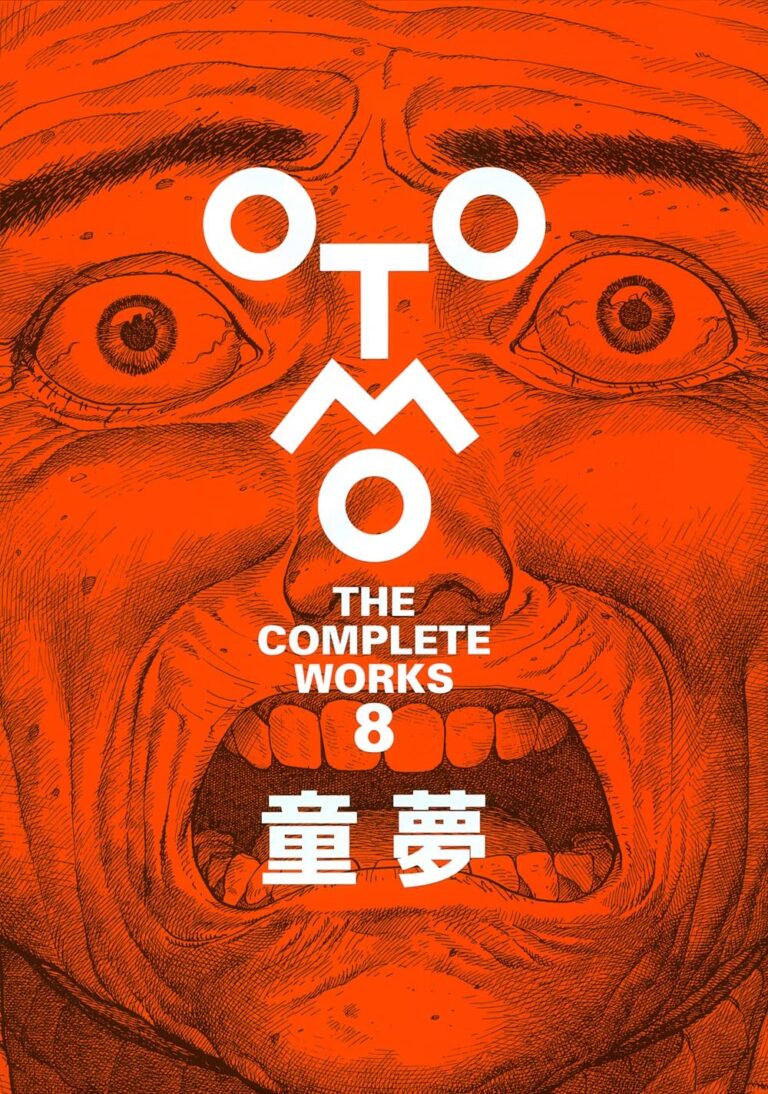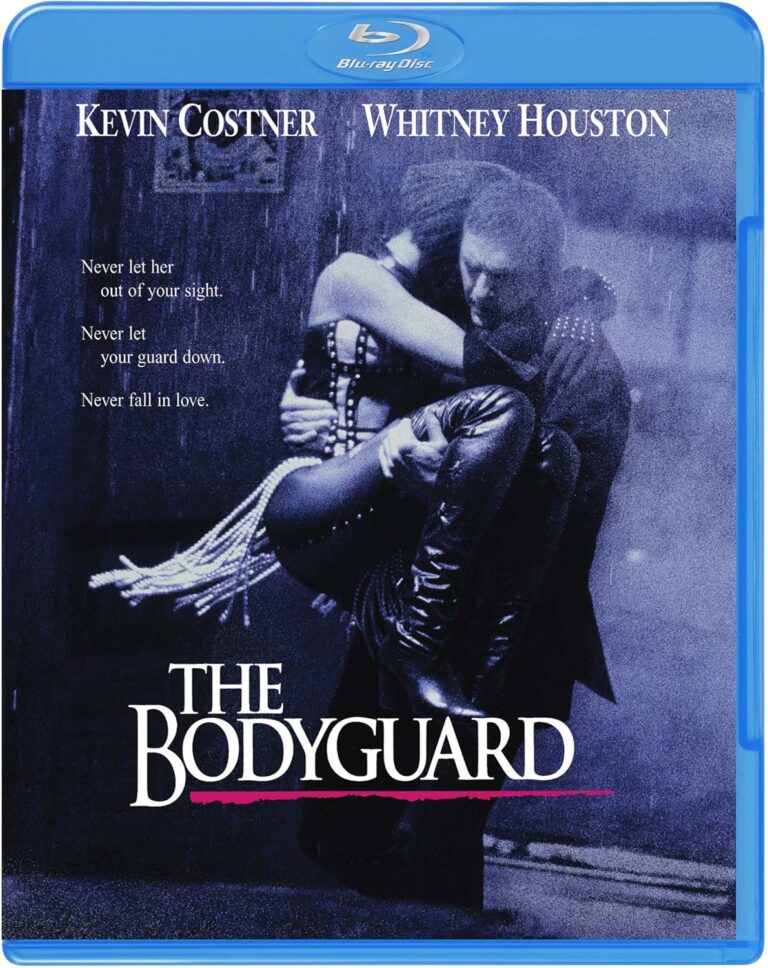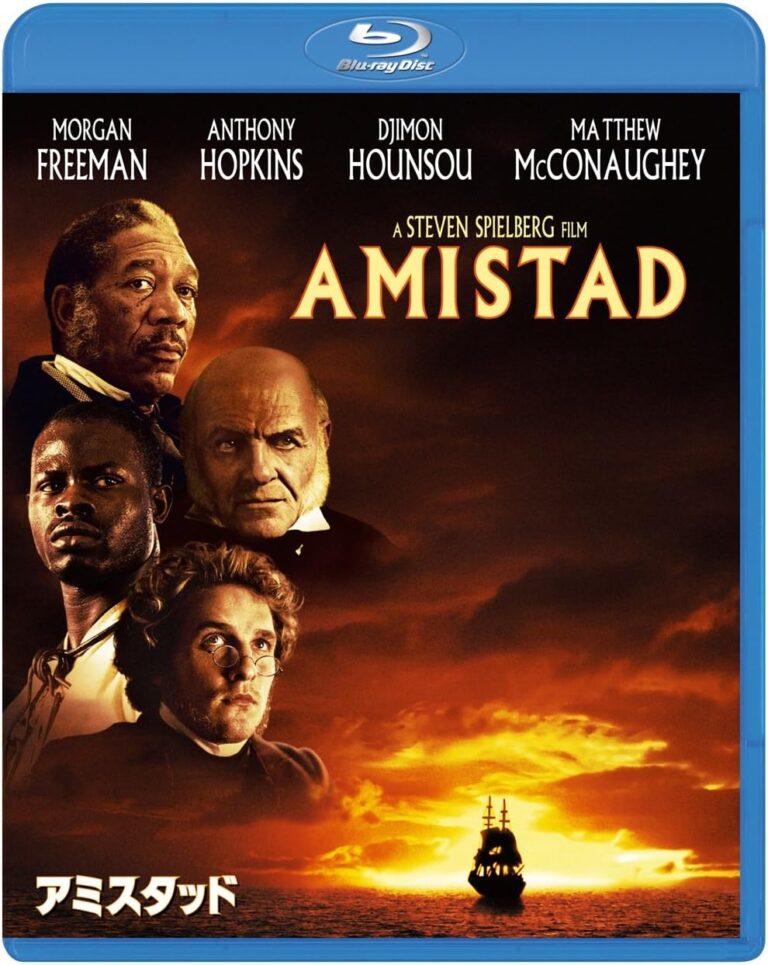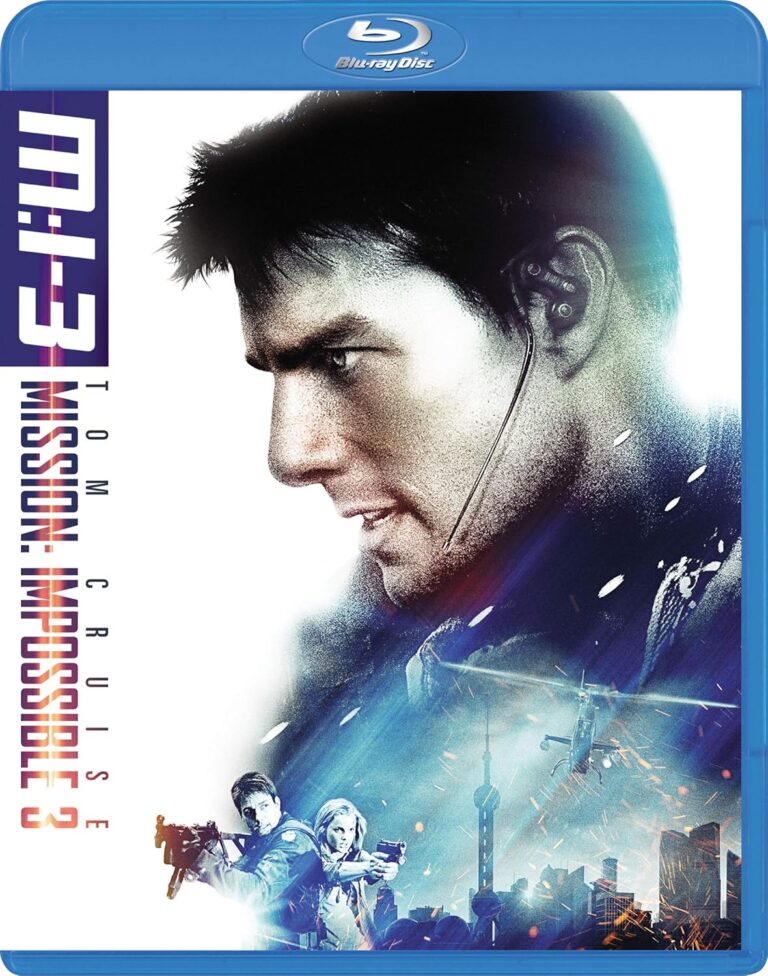『カリスマ』──なぜ一本の木が世界を揺るがすのか?
『カリスマ』(1999年)は、黒沢清が監督・脚本を務めたオリジナル作品で、主演は役所広司。人質事件のトラウマを抱える刑事・薮池が、山中で発見された一本の奇妙な木〈カリスマ〉をめぐる争いに巻き込まれていく。自然の秩序を守ろうとする者と、人間の支配を肯定する者が衝突し、彼は生と死、破壊と再生の境界に立たされる。第52回カンヌ国際映画祭・監督週間にも正式出品された。
光と風を操る映像作家
多義的な読みを許容する『カリスマ』(1999年)は、自然と文明、協調と弱肉強食といった主題的対立で語られることが多い。だが僕はまず、主題論以前にその圧倒的なビジュアルの豊饒さにひれ伏すべき映画ではないかと思う。
黒沢清が切り取るカットの一つひとつは、ただの「場面」を超えて、世界の裂け目をこちらに提示するかのようだ。暗がりの廃墟、水たまりを踏みしめる役所広司の靴を横から捉えたショットは、アンドレイ・タルコフスキーの『惑星ソラリス』(1972年)を想起させる。湿潤で、鉛色の空気が張り詰めた映像世界。黒沢映画の文脈を超えて、世界映画史の「映像美学」の系譜に接続している。
黒沢清はストーリーテリングのために映像を従属させない。むしろ映像それ自体が、観客を強烈に吸引する。カリスマの木の下に佇む役所広司の姿をとらえたショットだけで、僕はすでに降参だ。光の差し込み、風に揺れる木々、その佇まい。これだけで一本の映画を支えるだけの力がある。
彼の演出の特徴は、会話シーンにおいて特に際立つ。基本的に正対の構図を避け、窓ガラス越しや遮蔽物を間に挟むことで、不自然な間合いを生む。それが黒沢的な「異物感」の源泉だ。
ところが『カリスマ』では、寝たきりの院長夫人(目黒幸子)と薮池(役所広司)が雨のなかで差し向かいに話すシーンがある。黒沢映画にしては珍しく直球の構図だが、他のショットがすべて変化球であるため、逆に異様な強度を帯びている。ここにこそ黒沢の映像設計の巧みさがある。
白と闇のコントラスト
象徴的なのは、神保姉妹の居宅シーンだ。そよ風がカーテンを揺らし、白に満ちた静謐な空間が広がる。そのイメージは「自然と協調して生きるべきだ」と説く植物学者・神保美津子(風吹ジュン)の思想と共鳴する。
一方で、カリスマの木を「強いものが勝つ」というロジックで擁護する桐山(池内博之)は、薄暗い廃墟に住んでいる。
特別な木も森全体もない。あっちこっちに平凡な木が1本ずつ生えている。それだけだ
白と闇の対比が、思想の差異を視覚的に表現しているのだ。黒沢の映像は観念を超え、人物像そのものを彫刻する役割を担っている。
そしてその狭間に立つのが役所広司だ。人質事件のトラウマを抱え、協調も弱肉強食も受け入れたうえで「あるがままに」という境地に達する彼は、どちらの色にも染まらず、曖昧な中間に立ち続ける。
1999年という公開年も忘れてはならない。ミレニアム直前の不安と終末感は、作品全体を覆う湿度とともに観客を包み込む。真っ赤な炎に包まれた首都、旋回するヘリコプター。『CURE』(1997年)のカオスから、『カリスマ』を経て、『回路』(2001年)の黙示録へ。黒沢清のフィルモグラフィーは、まさに世紀末の影を刻印している。
その中で役所広司の身体性は特筆すべきだ。彼が「歩く」「佇む」「見つめる」だけで、映画の緊張感が変容する。台詞や筋立てを超えて、身体そのものが物語を語ってしまう。黒沢の映像は、この身体を媒介にして、観客を自然とカオスの境界へと導いていくのだ。
黒沢清フィルモグラフィーの転換点
『カリスマ』は『CURE』で開かれた扉をさらに押し広げ、黒沢映画をより抽象的かつ世界的な水準に押し上げた作品だ。特別な木と平凡な木、森と都市、協調と弱肉強食。観念的対立を超えて、「映像そのものが主題を語る映画」へと到達している。
巨木をピストルで撃ち抜いたあと、役所広司は風吹ジュンにこう語る――「たぶん、これが始まりです」。それは劇中人物の言葉であると同時に、黒沢清という稀代の映像作家の偉大なフィルモグラフィーの新章の始まりを告げるものでもあった。
- 製作年/1999年
- 製作国/日本
- 上映時間/104分
- 監督/黒沢清
- 脚本/黒沢清
- プロデューサー/神野智、下田淳行
- 製作総指揮/中村雅哉、池口頌夫
- 企画/吉田達、鵜野新一、有吉司
- 撮影/林淳一郎
- 編集/菊池純一
- 美術/丸尾知行
- 音楽/ゲイリー芦屋
- 役所広司
- 池内博之
- 大杉漣
- 風吹ジュン
- 洞口依子
- 松重豊
- 塩野谷正幸
- 大鷹明良
- 目黒幸子
- 戸田昌宏