ひっそりと佇む子供たちだけのユートピア、そしてその崩壊
第57回カンヌ国際映画祭で、『誰も知らない』(2004年)の演技が評価され、みごと最優秀男優賞を受賞した柳楽優弥クンが、尊敬する俳優を「以前ドラマで共演した押尾学さん」と公言したことは記憶に新しい。
そしてそれを聞いた誰しもが、「え、マジで?もうちょっとマシな役者の名前を挙げなよ」と総ツッコミを入れたのも、また記憶に新しいところである。もっと頑張れ、押尾学。
しかし、押尾学の話なんかどーでもよいので本題に入ろう。『誰も知らない』は、1988年に実際に起きた「巣鴨置き去り事件」がモチーフとなっている。
ここで、その事件の経過を簡単に振り返ってみよう。発端は、婚姻届を出していたと思っていたが、実は男が出しておらず、息子が産まれて出生届を出していたと思っていたが、これも実は男が出していなかったという事実を、女が知ることから始まる。(その時点で、男は女のもとから去ってしまっていた)。女は自分が未婚であり、息子が「戸籍上は存在しない子供」であることに愕然する。
しかし、彼女は区役所に足を運ぶことはしなかった。息子の存在を隠匿したまま、何人かの男と知り合っては妊娠、出産という行動を繰り返したのである。
彼女は合計5人の子供を産んだが、全員とも出生届は出されていなかった。後に次男が病死した際も、戸籍がないので埋葬届が出せず、女は死体をビニールでくるんで押入れに隠したという。
やがて女は新しい男をつくる。女は子供の世話を当時14歳だった長男に任せ、家を出てってしまう。子供たちは毎月約7万円の仕送りで、自分たち自身の力で生きていかざるを得ない状態に。
長男はまだ幼い妹たちの世話を一生懸命みていたが、やがて知り合った同年齢の友達と遊ぶことが多くなり、次第に家族を省みなくなるようになる。
悲劇は突如起きた。長男の家に居候のように居座るようになった友達の一人が、幼い三女を折檻して殺してしまったのだ(長男もその折檻に関与していたかどうかは不明だが、後日傷害致死・死体遺棄で起訴された際、情状酌量の余地があるとして保護観察で済んでいる)。
長男は母親を真似て三女をビニールでくるみ、押入れに隠しす。しかしたちまちのうちに異臭がたちこめるようになり、長男は三女の死体をボストンバッグに詰め、秩父市の公園にある駐車場脇の雑木林に死体を捨て、上を木の葉や枝で覆った…。
以上が、事件の大体の顛末である。後日事件は発覚し、女は執行猶予付きながら有罪判決を受けたらしい。これを踏まえて『誰も知らない』を鑑賞すると、監督の是枝裕和は、ひっそりと佇む子供たちだけのユートピアが崩壊した「その後」を描きたかったことがよく分かる。
突然の闖入者(長男の友達)によって乱されてしまった秩序が回復され、再生されたその向こうには何があるのか。子供達の辿り付くべき終着点を、是枝裕和はドキュメンタルなタッチで繊細に再現した。
アパートの一室に身を潜め、世界の片隅でサバイバルする子供たち。社会性を剥奪された彼らは、ホームレスではなく、アイデンティティーレスである。
母親の「ベランダに出てはいけない」「外に出ていいのは長男だけ」というルールを最初は追従するも、規範は次第に改変・拡張され、彼らは彼らなりのボーダーラインで世界と分け隔てようとする。それは例えば学校の校門であったり、登校拒否の少女の家のエントランスだったりする。
なぜ、彼らはその境界線を踏み越えないのか?なぜアイデンティティーレスとして生きようとするのか?なぜ長女は隔離されたアパートの一室の、さらに隔離された物入れの中に身を置くのか?映画では長男に、「(警察に行くと)皆で住めなくなっちゃうから」と言わせているが、それだけではないだろう。
万人を支えるはずだった共同体としての社会が崩壊し、まったりとした個人主義にシフトチェンジされた近現代において、円環の外で営みを続けようとする人間たちのドラマは、象徴的な現代論として機能する。
実際の事件が発覚すると、母親は嵐のようなマスコミの批判にさらされたと言う。曰く、「子供を顧みるどころか、男のもとに走って子供たちを置き去りにした鬼のような女」。
しかし映画でYOUが演じる母親は、彼女なりに子供たちを愛情をもって接している快活な女性であり、悪意は微塵も感じられない。
実は重要なのはココなのであって、彼女には社会への従属意識がごろんと欠落しているだけなのであって(もちろんそれが問題なのだが)、「なんで私だけ幸せになっちゃいけないの?」という無邪気な個人主義を貫いているだけに過ぎないのだ。
喜びもなければ哀しみもない。希望もなければ絶望もない。生きがいなどという言葉はすでに形骸化し、エンドレスな日常をただまったりとと生きていく。
GONNTITIの音楽が感傷的になりきらず、かといって乾ききってもいないのは、ドラマのレベルがあまりにも日常的すぎるからだ。その現実を直視しながら、是枝裕和もまた感傷的にも冷徹にもならない一定の距離で、彼らを見守っていく。
是枝裕和は母親をラストで登場させなかったし、子供達を警察へ連れて行かなかった。是非はともかくして、是枝裕和は未来を子供たちに託したかったのだと思う。彼らが、「誰も知らない」存在であり続けるとしても。
- 製作年/2004年
- 製作国/日本
- 上映時間/141分
- 監督/是枝裕和
- 脚本/是枝裕和
- プロデューサー/是枝裕和
- ゼネラルプロデューサー/重延清、川城和実
- アソシエイトプロデューサー/浦谷年良、河野聡
- 企画/安田匡裕
- 撮影/山崎裕
- 編集/是枝裕和
- 美術/磯見俊裕、三ツ松けいこ
- 録音/弦巻裕
- 音楽/ゴンチチ
- 柳楽優弥
- 北浦愛
- 木村飛影
- 清水萌々子
- 韓英恵
- YOU
- 串田和美
- 岡元夕紀子
- 平泉成
- 加瀬亮
- 木村祐一
- 遠藤憲一
- 寺島進
![誰も知らない [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41dQVi6WOrL.jpg)




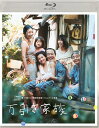





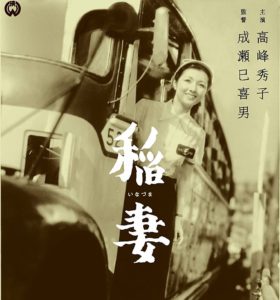
最近のコメント