一人の女性の“死と再生”を淡々と描く、是枝裕和の劇場映画デビュー作
今や世界的巨匠となった是枝裕和の劇場映画デビュー作、『幻の光』(1995年)。原作は1979年に発表された宮本輝の同名小説で、夫を自殺で失った一人の女性の“死と再生”を淡々と描いた、ポエティックなドラマである。
『しかし… 福祉切り捨ての時代に』(1991年)、『もう一つの教育』(1991年)、『公害はどこへ行った…』(1992年)など、それまで社会派のテーマを扱った作品を手がけてきた是枝裕和は、もともとテレビマンユニオンに所属するドキュメンタリー作家だった。
ドキュメンタリーにおいて何よりも重用視されるのは、まず“機動性”。鮮やかな色彩を産み出す高品質カメラよりも、偶発的な出来事にも対応できる手持ちカメラが重宝され、クリアーな画像を保証する単焦点レンズよりも、自由に対象へ寄れるズームレンズが選択される。
ところが、劇場用作品としての処女作『幻の光』(1995年)においては、フレーミングに細心の注意が払われたフィックス・ショットが多用され、ほとんどロングで固定されたカメラは、登場人物と適度な距離を保っている。
埠頭で江角マキコが内藤剛志に苦しみを打ち明けるクライマックス・シーンなんぞ、ほとんど人物が判然としないぐらいに極端なロング・ショットだ。
ドキュメンタリーでは、しばしばカメラが主題を前景化させるために人物に寄り、その内面に肉薄せんとする。しかし『幻の光』では、頑なまでに心象風景を排することによって、非感傷的・散文的な映像詩を紡いでいる。
おそらく是枝裕和には、「ポートレイトのように、計算し尽くされた構図」に対する飢餓があったのではないか。パンすら使用しないストイックなカメラ(移動撮影はいくつか使われている)には、今まで積み上げてきたドキュメンタリー的手法とは全く真逆な、「是枝裕和的フィクション説話法」が徹底されているのだ。
では、登場人物への内面的同一化を拒否するこの映画において、作品のリズムを形成する生活感はどのようにして生起されるのか。それは例えば音である。
侯孝賢(ホウ・シャオシェン)の『恋恋風塵』(1987年)や『戯夢人生』(1993年)などを手がけた、台湾のマエストロ陳明章が本作の音楽を担当しているが、物語をかたちづくっているのは、むしろ隣の部屋のラジオ、波の音、自転車の鈴といった自然音だ。「作為的に用いられた自然音が、自然らしさを強調する」という格好の例なんではないか。
大阪の貧困街で生活しているという設定にも関わらず、江角マキコはスタイリッシュ&ドレッシーな佇まいを見せているし、対象をフォトジェニックに撮りたいという欲望があったためか、照明は妙にダーク。日常をドキュメンタルに取り出すのではなく、あくまで虚構であることに自覚的な手つきで、日常的空間を装飾する。
『幻の光』は、“死”についてのテキストだ。しかも彼岸にある死ではなく、薄皮一枚で隔てられた、生と地続きにある死。祖母の失踪も夫の謎の自殺も、生への否定ではなく、漠然とした死への渇望として描かれる。
「日常のなかの死」は、計算し尽くされた構図、効果音、照明によって鮮明化するのだ。
- 製作年/1995年
- 製作国/日本
- 上映時間/110分
- 監督/是枝裕和
- 製作/重延浩
- プロデューサー/合津直枝
- 原作/宮本輝
- 脚色/荻田芳久
- 撮影/中堀正夫
- 音楽/陳明章
- 美術/部谷京子
- 編集/大島ともよ
- 衣装/北村道子
- 録音/横溝正俊
- 照明/丸山文雄
- 江角マキコ
- 浅野忠信
- 内藤剛志
- 木内みどり
- 柄本明
- 赤井英和
- 市田ひろみ
- 大杉漣
- 橋本菊子
- 吉野紗香
- 寺田農
![幻の光 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41vNWv7CSGL.jpg)

![恋恋風塵 -デジタルリマスター版- [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51n5gznt95L.jpg)
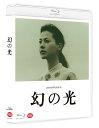








最近のコメント