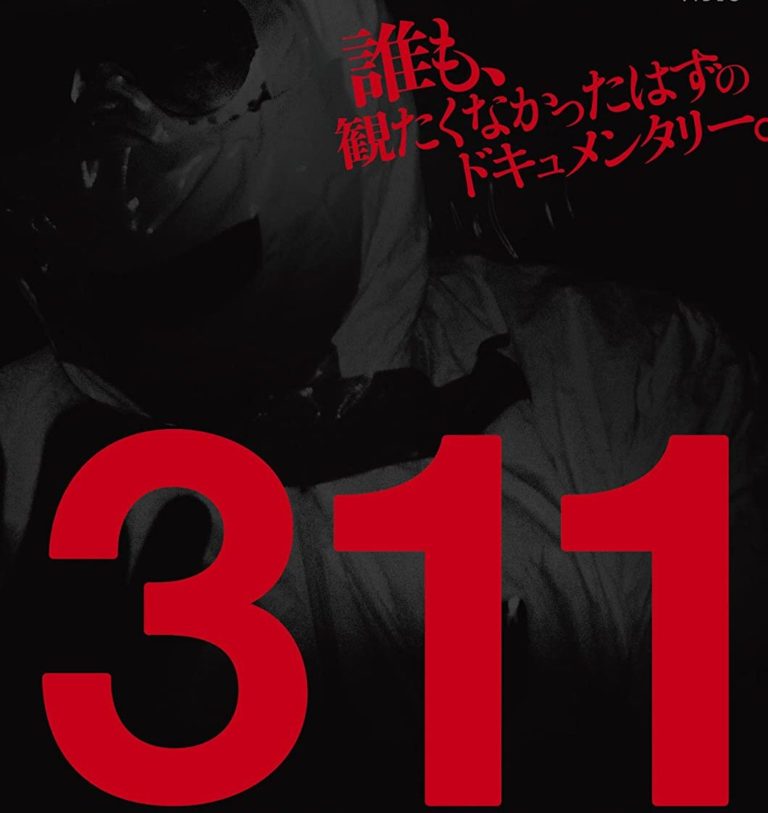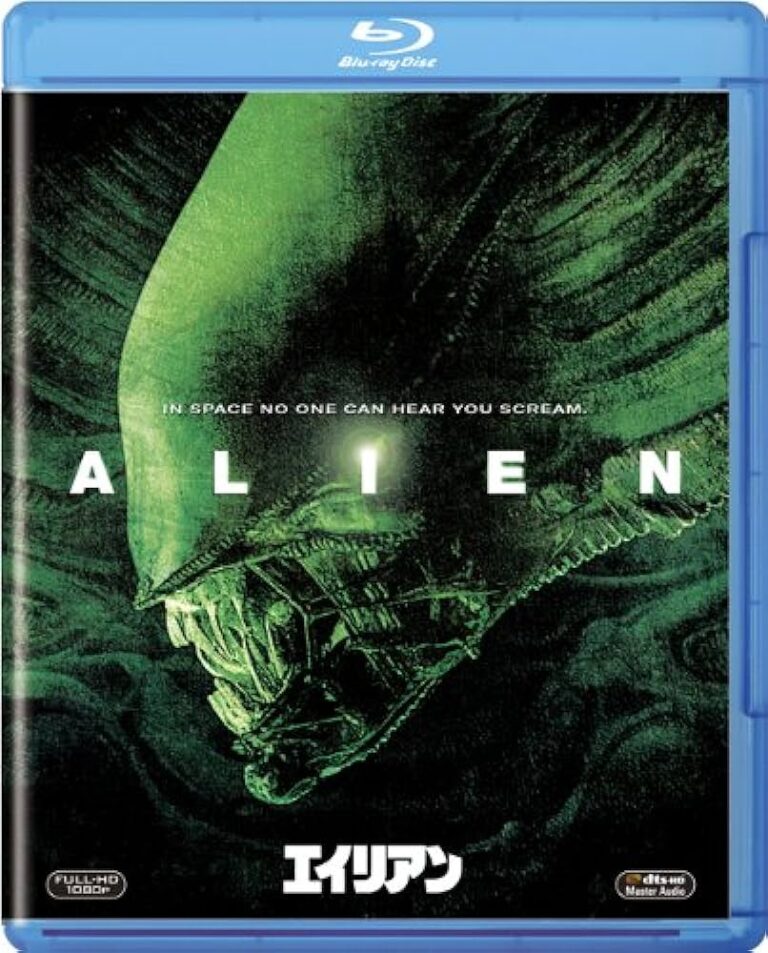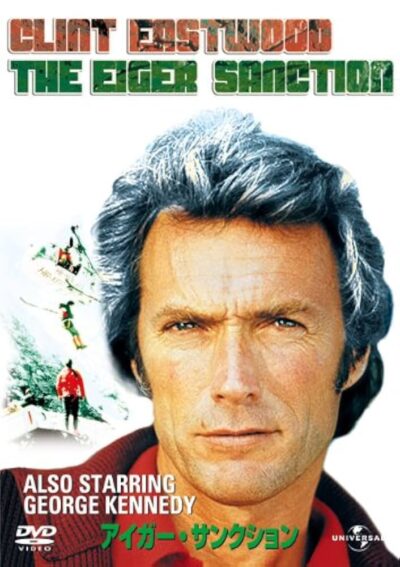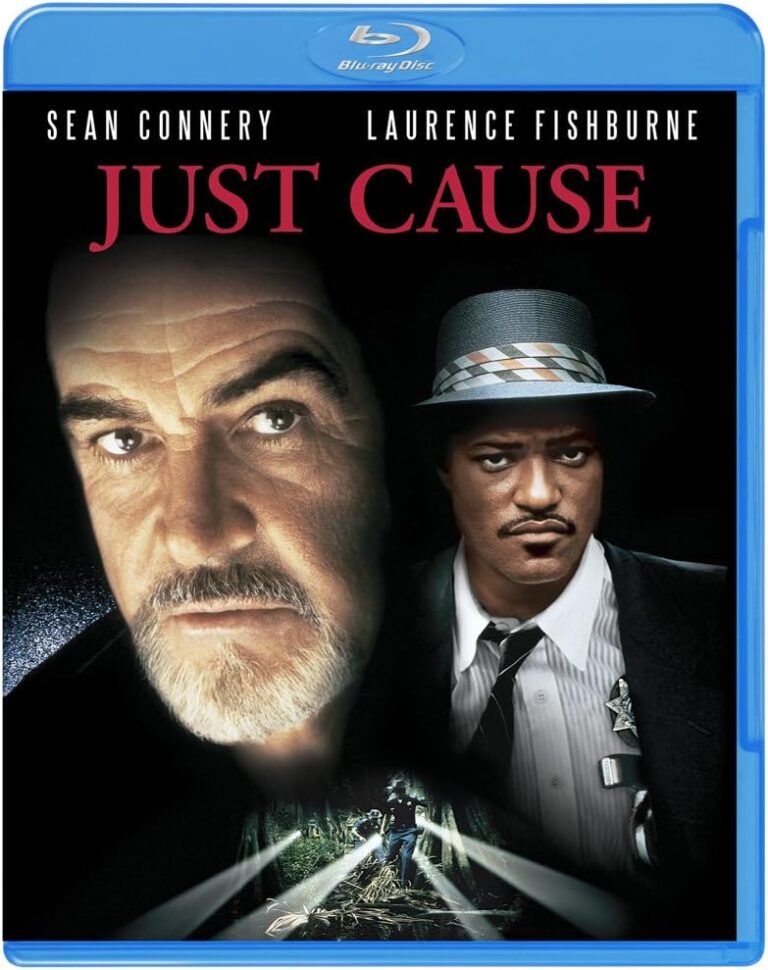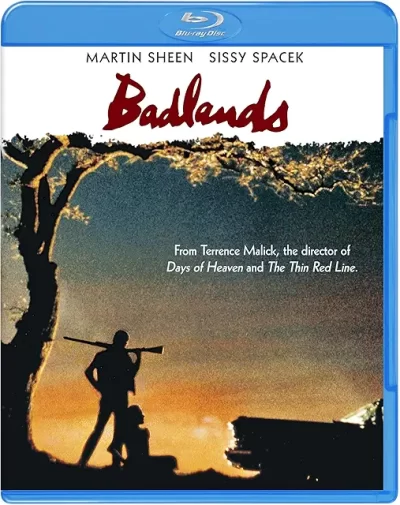『ドライヴ』(2011年)──沈黙と暴力の美学、光と孤独の神話
『ドライヴ』(原題:Drive/2011年)は、ニコラス・ウィンディング・レフン監督がジェイムズ・サリスの小説を映画化したクライム・サスペンス。ロサンゼルスを舞台に、昼は自動車修理工、夜は強盗の逃走を請け負う“逃がし屋”として生きる無名のドライバー(ライアン・ゴズリング)が、隣人アイリーン(キャリー・マリガン)とその息子を守ろうとしたことから抗争に巻き込まれる。沈黙と暴力、孤独と愛が交錯する夜の都市を、光と音楽が詩的に照らし出す。
夜の都市を走る“神話的ドライバー”
まるで宝石箱を覗き込むがごとく、無限の光を放つ都市の夜景。ビルとビルの間をすり抜けるように、エレクトリックな『Nightcall』のサウンドが鳴り響く。タイトルシーンだけで、「ヤバい!これジャスト好み!」と稲妻のように直感が働いた。
夜のLAを美しく撮るという才能ひとつだけでマイケル・マンを敬愛する僕としては、こんなツボすぎる映像を観させられたら即ノックアウト。かくして僕は、デンマーク生まれの若き鬼才ニコラス・ウィンディング・レフンと、『ドライヴ』(2011年)で幸福な邂逅を果たすことになる。
原作はジェイムズ・サリスの同名小説。強盗の逃走車を操る“逃がし屋”の孤独な男が、裏切りと暴力の渦に巻き込まれる物語だ。本来はヒュー・ジャックマン主演×ニール・マーシャル監督での企画だったが、ライアン・ゴズリングの強い要望によって監督が変更されたという経緯を持つ。かくしてレフンの美学とゴズリングの沈黙が結晶した結果、単なるカーアクションではなく“都市の孤独と暴力の寓話”として再構築された。
観客が予想していた『ワイルド・スピード』的スピード感とは無縁に、レフンは“止まること”によって映画を動かす。静寂と余白の中で、エンジン音だけが生の鼓動として響く。
夜のLAを走るドライバーの姿は、アメリカン・ニューシネマの亡霊であり、孤独な職人としての存在証明である。レフンは“沈黙の男”という神話を、80年代的シンセサウンドと共に再生産しているのだ。
沈黙の演技、視線の映画
この映画が傑作たりえる理由は、極端なダイアローグの省略にある。ドライバーはほとんど語らず、観客は彼の呼吸とまなざしによって物語を読み取る。
キャリー・マリガン演じるアイリーンとの恋愛も、会話より“見つめ合う沈黙”で進行していく。レフンはここで、感情の表現を台詞から完全に解放した。
彼女の頬に射す車窓の光、手と手が触れる一瞬、微笑みと呼吸。その断片の連続によって、ふたりの心の距離が映像的に可視化されていく。まさに“視線の映画”である。
ドライバーが抱く恋は、もはや恋愛ではなく儀式に近い。彼にとって暴力は仕事であり、愛は儚い幻影だ。キスシーンの演出はその象徴だ。エレベーターの中、唇が触れる瞬間、照明はスポットライトとなって二人を聖別し、カメラがスローモーションで回転する。
あの一瞬、彼らは暴力と救済の境界に立っている。その直後に訪れる残酷な殺人描写こそ、レフンの“神話的構造”を決定づけている。甘美と残酷、美と暴力が断ち切れない関係で共存する。
愛の瞬間に最も強く流れる死の予感。それはタルコフスキーが描いた“静止のなかの運動”にも通じ、映画という装置の根源的な快楽を呼び覚ます。レフンは暴力をスペクタクルとしてではなく、“存在の光”として描く稀有な映画作家なのだ。
光と影の建築──レフンの映像哲学
『ドライヴ』を貫く最大の美学は、照明設計と色彩構成にある。レフンは光を演出ではなく“物語そのもの”として扱う。車内のオレンジの灯が漂白された青白い夜景を照らすとき、観客は彼の内面を覗き込む。暗闇は単なる背景ではなく、彼の心の輪郭である。
高級クラブでのネオンピンク、車庫の無機質な蛍光灯、夜の街を包む紫のグラデーション──それらすべてが感情のスペクトラムとして機能している。レフンは映画を“光と音の建築”と定義しているが、その思想は『ドライヴ』において完璧なかたちで結実している。
光の演出は心理の可視化であり、暴力は光の到達点として配置される。照明の対比、構図のシンメトリー、そして音楽の呼吸。これらが融合して初めてこの映画は成立する。
ここで重要なのは、レフンがLAという都市を“人間の延長”として描いている点だ。夜の街は人工的で冷たく、しかしその光の下では人間だけが熱を持つ。彼のカメラは常に車の外と内を行き来し、都市と孤独の狭間を走り続ける。
まるで車が彼の肉体であり、エンジンが心臓であるかのように。走ることでしか存在できない人間。そこには、“静止すれば死ぬ”という現代の寓話が潜んでいる。
ドライバーは沈黙のまま光に包まれ、やがて闇に溶けていく。あのラストの長い夜道は、救済でも絶望でもない。ただひとりの男が、生の残響として走り続ける光景なのだ。
暴力の詩学とレフンの冷たい慈悲
『ドライヴ』の暴力は、決して娯楽的ではない。血飛沫の瞬間さえも、どこか祈りのような静謐さを湛えている。レフンは暴力を“神話の更新”として描く。
彼にとって暴力は罰ではなく浄化であり、愛と死の等価交換の儀式でもある。だからこの映画における残酷さは、沈黙の中に潜む痛覚を、光とリズムによって視覚化した結果なのだ。
ライアン・ゴズリングの無表情の奥には、自己犠牲と破壊衝動が同居している。彼は守るために殺し、愛するために孤立する。レフンはその矛盾を“冷たい慈悲”として描く。観客はドライバーに共感しながら、同時に彼の破滅を予感してしまう。そこにこそ、この映画の詩的な残酷さがある。
サントラの『A Real Hero』が流れる終盤、観客はようやく理解する。彼はヒーローではなく、愛の記憶を運ぶ亡霊なのだ。ハンドルを握る彼の横顔には、もはや生者の温度がない。
だがその孤独な走行の果てに、わずかな希望が灯る。人は光を求めて闇を走る──そのシンプルな命題を、レフンは誰よりもスタイリッシュに、誰よりも哀しく描ききった。
『ドライヴ』は暴力の映画であり、沈黙の映画である。そして、孤独を美しく撮るという一点で、永遠に“走り続ける映画”でもある。
- 原題/Drive
- 製作年/2011年
- 製作国/アメリカ
- 上映時間/100分
- 監督/ニコラス・ウィンディング・レフン
- 製作/マーク・プラット、アダム・シーゲル、ジジ・プリッツカー、ミシェル・リトヴァク、ジョン・パレルモ
- 製作総指揮/デヴィッド・ランカスター、ゲイリー・マイケル・ウォルターズ、ビル・リシャック、リンダ・マクドナフ、ジェフリー・ストット
- 原作/ジェイムズ・サリス
- 脚本/ホセイン・アミニ
- 撮影/ニュートン・トーマス・サイジェル
プロダクションデザイン/ベス・マイクル - 衣装/エリン・ベナッチ
- 編集/マット・ニューマン
- 音楽/クリフ・マルティネス
- ライアン・ゴズリング
- キャリー・マリガン
- ブライアン・クランストン
- クリスティナ・ヘンドリックス
- ロン・パールマン
- オスカー・アイザック
- アルバート・ブルックス

![ドライヴ/ニコラス・ウィンディング・レフン[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/91r79K105aL._AC_UL640_FMwebp_QL65_-e1762044853577.webp)