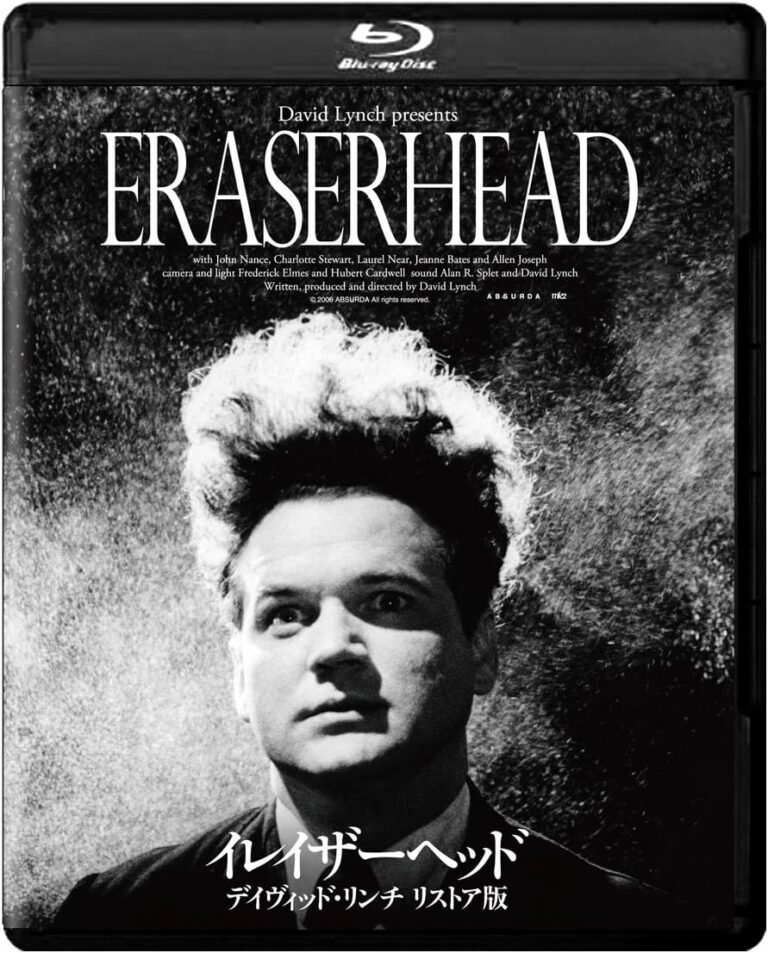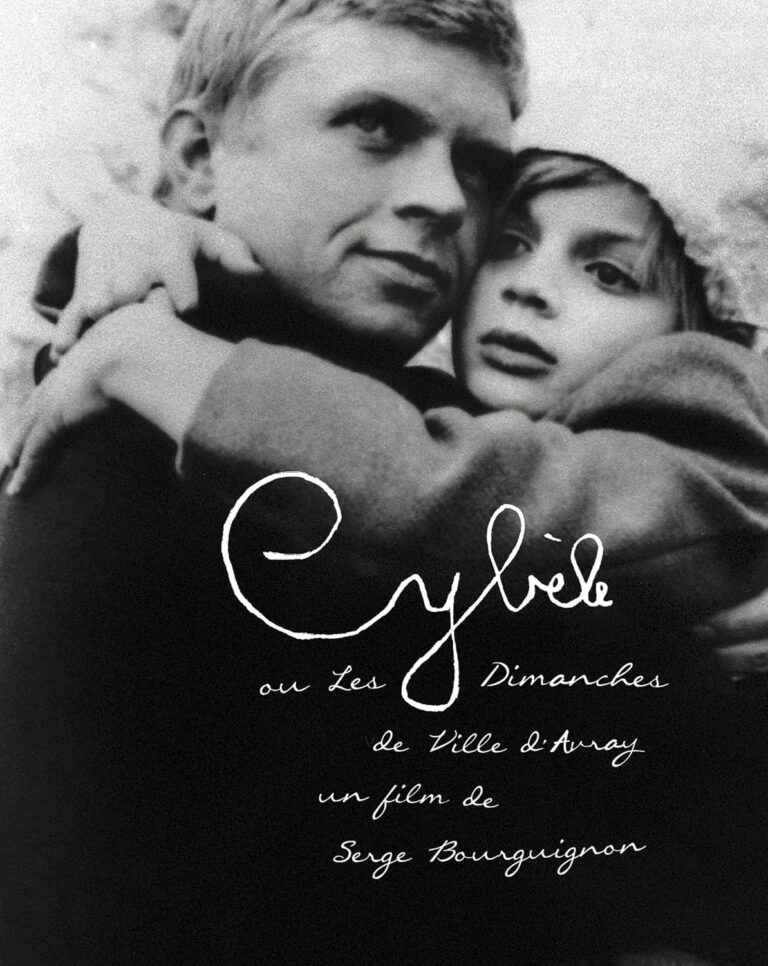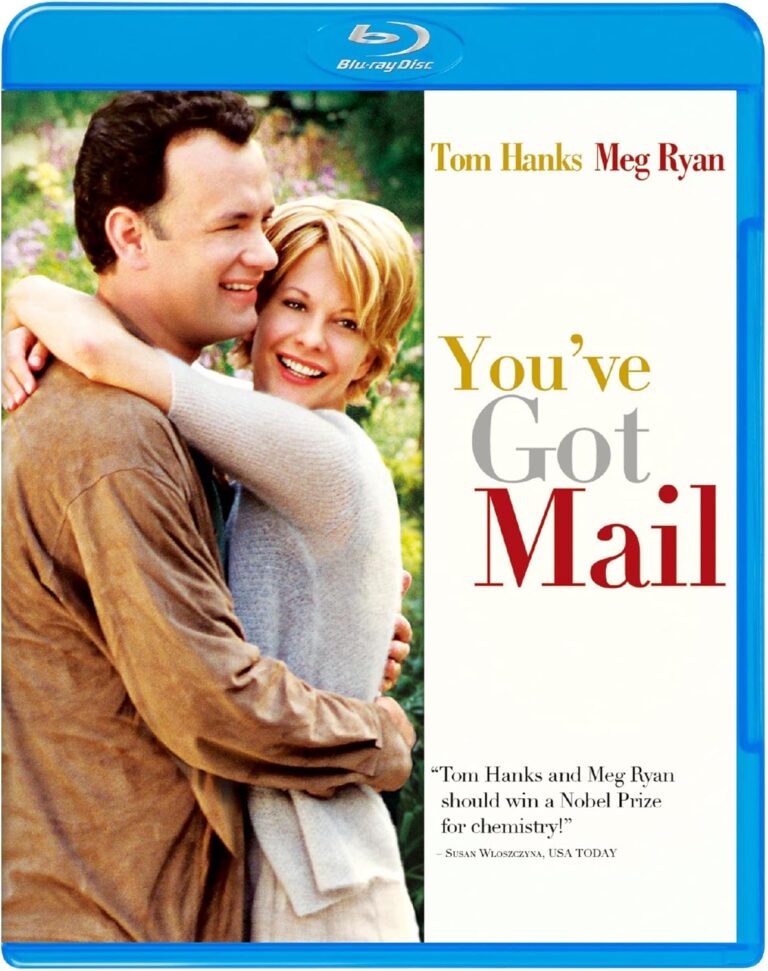『エクソシスト』(1973)
映画考察・解説・レビュー
『エクソシスト』(原題:The Exorcist/1973年)は、少女リーガンに取り憑いた悪霊と、信仰を失った神父カラスの再生を描く。母の苦悩、神父の罪、そして信仰の崩壊と再生──ホラーの枠を超え、祈りと赦しをめぐる人間ドラマが展開する。
ホラーではなく、信仰と再生の物語
私見だが、あくまで『エクソシスト』(1973年)は“悪魔払いについての映画”であって、ホラー映画ではない。
惨殺死体もなければ、スプラッター描写も存在しない。悪霊パズズが少女リーガンに取り憑くとはいえ、彼は他者に危害を加えることすらない。この映画には、観客を直接的に脅かす“恐怖の核”が存在しないのだ。
むしろ本作が描くのは、娘を失いつつある母の葛藤と、信仰を失った神父の再生である。つまりこれは、悪魔と戦う映画ではなく、信じる力を取り戻す映画だ。暴力と混乱の背後には、“救済の可能性”という静かなテーマが潜んでいる。
表層的には超常現象のドラマだが、構造的には家庭の崩壊と修復をめぐる人間劇。「口汚く罵り、暴力をふるう娘をどう治療するか」という物語は、むしろ80年代日本の家庭内ドラマ『積木くずし』(1983年)を思わせる。
リーガンは高部知子であり、母クリスは前田吟である──と言えば半ば冗談のようだが、比喩としては的を射ているはず(自画自賛)。『エクソシスト』とは、〈超常〉の形を借りた〈家族再生〉の物語なのだ。
信仰の崩壊──神父カラスの苦悩
物語の中心にいるのは、悪魔ではなく神父ダミアン・カラス(ジェーソン・ミラー)である。 彼は、母を看取れなかった罪悪感と、信仰の喪失に苦しむ。 バーで「僕は信仰さえ失ってしまった」と呟くその一言が、映画全体のトーンを決定づける。
彼の母は貧困の中で病に倒れ、息子は彼女を救えなかった。“神の言葉”を説く立場にありながら、“一番救いたい人”を救えない。その無力感こそが、彼を神から遠ざける。悪魔パズズとは、信仰を失った人間の内部から現れる“自己否定の化身”であり、外部の敵ではない。
だからこそ、リーガンの悪魔祓いはカラス自身の“信仰の儀式”でもある。悪魔を祓うことが、彼の贖罪であり、神への帰還の道となる。『エクソシスト』がホラーでありながらも倫理的カタルシスを持つのは、恐怖の対象が常に“人間の内部”に置かれているからだ。
信仰の不在──イラクからジョージタウンへ
原作は、1949年にメリーランド州で実際に起こった“悪魔憑き事件”をもとに、ウィリアム・ピーター・ブラッティが小説化したもの。彼はシナリオも自ら執筆し、アカデミー賞脚本賞を受賞した。 オカルトという題材でオスカーを制したこと自体、極めて異例である。
だがこの快挙は、“超常”を“人間ドラマ”として描ききったことによる。ブラッティの筆致には、宗教家でも心理学者でもない、人間観察者としての冷静さがある。悪魔は恐怖の象徴ではなく、人間の罪と赦しを映す鏡。この構図のリアリズムが、当時の映画芸術科学アカデミー会員たちの心を動かしたのだ。
映画はイラクの遺跡発掘シーンから始まる。 太古の神パズズの像を発見する神父メリン(マックス・フォン・シドー)。 この“異国の神”がなぜアメリカのジョージタウンに出現するのか。 その地理的断絶こそが、宗教的断絶の象徴である。
現代社会において、信仰はもはや“異国の遺物”にすぎない。フリードキンは、悪魔を異教の遺物として提示しながら、〈信じる力を失った文明〉を静かに告発する。
リーガンに宿るのはパズズではなく、“空洞化した信仰”そのものだ。だからこそ、彼女の絶叫は恐怖ではなく祈りの反転形として響く。それは、信仰を失った時代が生み出した“神なき救済”の叫びである。
ウィリアム・フリードキンの冷徹なる演出
『フレンチ・コネクション』(1971年)でアカデミー監督賞を受け、アメリカン・ニューシネマ世代の旗手と目されたウィリアム・フリードキン。 その冷徹なリアリズムは、『エクソシスト』にも息づいている。
ドキュメンタリー的撮影、自然光を活かした陰影、過剰なショック演出を排除したストイックな構図。彼は“恐怖の再現”ではなく、“信仰の不在”を映像化する。
セットを実際に冷凍庫並みに冷やし、俳優の吐息をリアルに撮影したという逸話は有名。ショットガンを持参して現場を緊張状態に置いたというエピソードも、もはや演出というよりも儀式に近い。
この狂気すれすれの方法論によって、映画は〈神聖と冒涜〉の境界に立つ。恐怖を人工的に作り出すのではなく、俳優たちの身体から直接“信仰の震え”を抽出する。フリードキンは、映画そのものを一種の“エクソシズム”に変えたのだ。
音楽が刻む不安──チューブラー・ベルズと現代音楽の魔
『エクソシスト』を語る上で、音楽の効果は決定的だ。マイク・オールドフィールドの『チューブラー・ベルズ』は、もはや映画音楽史に残る象徴的テーマとなった。 だが特筆すべきは、ウェーベルン、ペンデレツキ、ヘンツェら現代音楽の使用である。
調性を逸脱した弦のうねり、間歇的な沈黙、金属的残響。それらは悪魔の声ではなく、人間の理性が崩壊していく音だ。特にハンス・ヴェルナー・ヘンツェの『弦楽のためのファンタジア』(本来は『テルレスの青春』のための曲)が、エンドロールに流れるとき、我々は“恐怖の余韻”ではなく、“浄化の静けさ”に包まれる。
音楽は祈りの代替であり、音響は神への問いである。その沈黙こそ、最も宗教的な瞬間なのだ。
恐怖の彼方にある救済──信じる力の再生
『エクソシスト』の終盤、カラス神父は悪魔を自らの身に引き受け、窓から身を投げる。 それは殉教ではなく、信仰の回復の瞬間である。 彼は“悪魔を倒す”のではなく、“罪を引き受ける”ことで神へ帰還する。
この結末によって、映画はホラーの形式を超え、宗教的ドラマへと昇華する。悪魔とは、神を疑う人間自身のことだった。そして祓いとは、信じる力をもう一度取り戻すことだった。
フリードキンが描いたのは、恐怖ではなく信仰の再生である。『エクソシスト』は“恐怖の映画”ではなく、“信じることの難しさ”を描いた映画である。だからこそ半世紀を経ても、観る者の内側を静かに震わせ続ける。
- エクソシスト(1973年/アメリカ)
- エクソシスト(1973年/アメリカ)

![エクソシスト/ウィリアム・フリードキン[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/81lfvFXN1L._AC_SL1500_-e1707308841112.jpg)