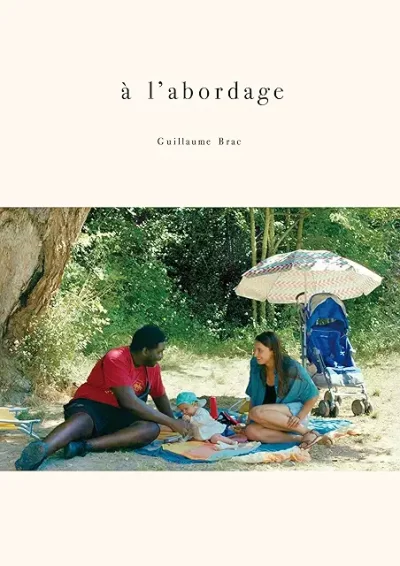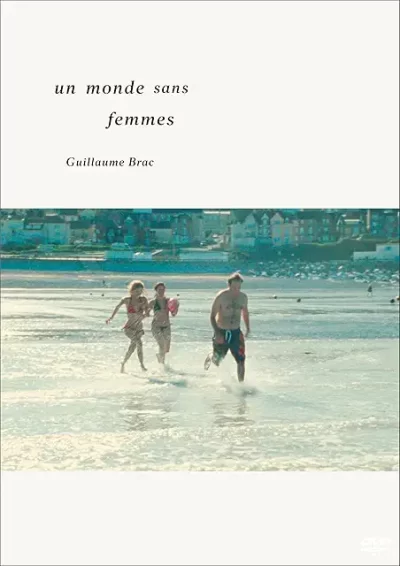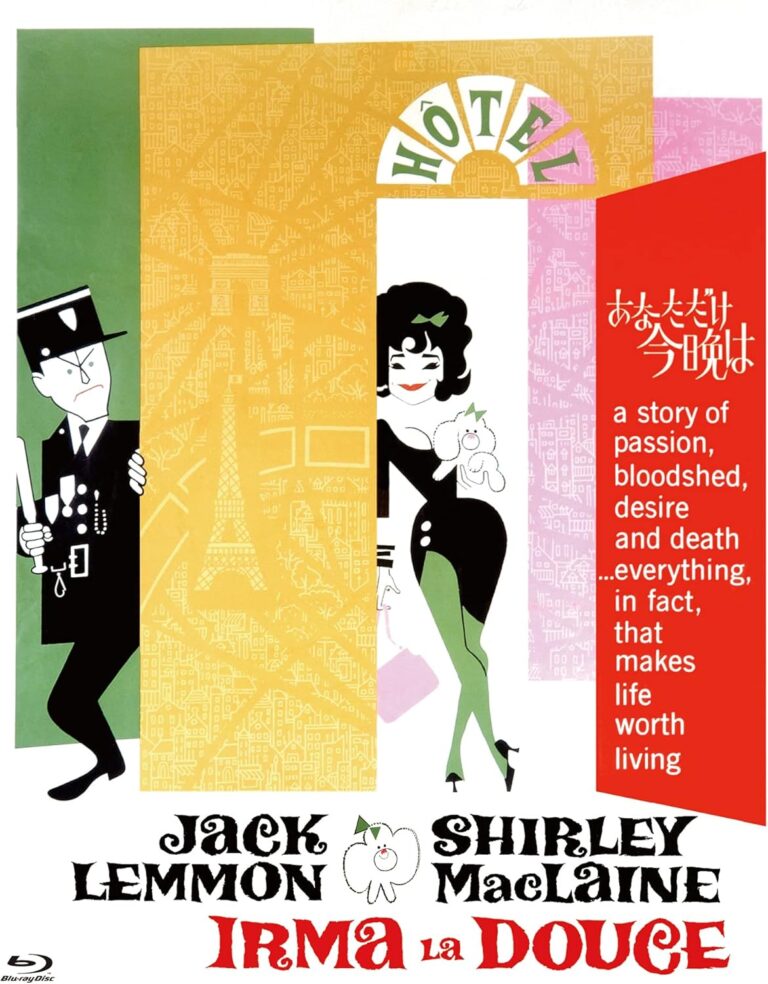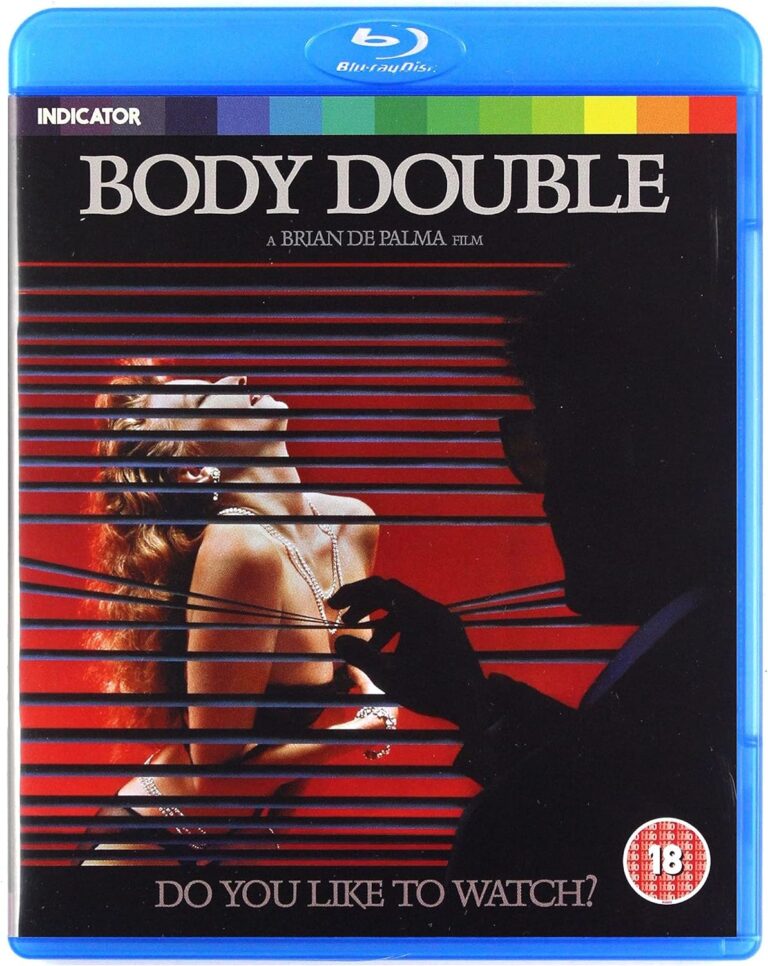『ジョジョ・ラビット』(2019)
映画考察・解説・レビュー
ジョジョ・ラビット(原題:Jojo Rabbit/2019年)は、鬼才タイカ・ワイティティ監督が、戦時下のドイツという重いテーマをポップな毒とユーモアで包み込んだ人間ドラマの傑作。第92回アカデミー賞で脚色賞を受賞し、世界中を笑いと涙で包み込んだ。空想のヒトラーを心の拠り所にする純真な少年ジョジョが、敵であるはずのユダヤ人少女との出会いを経て、自分自身の頭で考え「世界」を見つめ直すまでの成長を瑞々しく描く。スカーレット・ヨハンソン、サム・ロックウェルといった実力派の競演に加え、ローマン・グリフィン・デイヴィスら子役たちの熱演が光る、今こそ観るべき希望の一編。
「ヒトラーが親友」という狂気の設定が暴く、洗脳のカラクリと色彩の魔法
あのチョビ髭独裁者が、10歳の少年のイマジナリーフレンドって正気か!?
タイカ・ワイティティ監督が『ジョジョ・ラビット』(2019年)を引っ提げて現れたとき、世界中の映画ファンと批評家は、期待と不安で脳内がバグりかけたに違いない。
ホロコーストという人類史上もっともダークでセンシティブな案件を、コメディタッチで描くなんて、一歩間違えれば大炎上確定の綱渡りだからだ。
だが、断言しよう。この映画は、単なる不謹慎なパロディなんかじゃない。これは、憎悪という名の洗脳がいかにして完成し、そしていかにして解かれるかを描いた、極めてロックで、かつてないほど優しい解呪の物語なのだ。
度肝を抜かれるのは、映画のオープニング。記録映像の中、熱狂的に手を振るドイツ市民たち。そこに被さってくるのが、なんとビートルズの『抱きしめたい』ドイツ語ver.。
ワイティティ監督は、ナチズムの台頭を、60年代のビートルマニアのようなポップカルチャーの熱狂と重ね合わせてみせた。つまり、当時の少年たちにとって、ナチスの制服を着ることは、イケてるブランドの服を着るのと同じだし、ハーケンクロイツは推しのロゴだったのだ。
この視点の転換こそが、本作の最大の武器。だからこそ、画面は戦争映画特有のどんよりとした灰色ではない。鮮やかな緑、パステルカラーの街並み、陽光きらめく森。まるでウェス・アンダーソン監督の『グランド・ブダペスト・ホテル』(2014年)かと思うほど可愛らしい色彩設計だ。
だが、この不自然な明るさこそが、洗脳された10歳のジョジョ少年の目に見えている、歪んだ世界そのもの。世界はこんなにも美しく、ナチスは最高にクールだと思い込まされている子供の視点。その鮮やかさが、後半に訪れる現実の残酷さを、これでもかというほど際立たせる。
そして、監督自身が演じるイマジナリー・ヒトラーの破壊力!マオリ系ユダヤ人のワイティティが、青いコンタクトを入れて、あのアドルフを間抜けで幼稚な友人として演じる。チャップリンが『独裁者』(1940年)でヒトラーを笑い飛ばした系譜を受け継ぎつつ、本作はさらに「内面の怪物」へと踏み込む。
最初は愉快な相談相手だったヒトラーが、ジョジョが現実(=屋根裏のユダヤ人少女エルサ)を知るにつれて、支配的で醜悪な存在へと変貌していくグラデーションが見事だ。これは、少年が悪い父親(イデオロギー)を乗り越え、自立を獲得するための、痛みとユーモアを伴う父殺しの儀式でもある。
善きナチスは許されるのか?
この映画が単なるドタバタ劇で終わらないのは、脇を固める大人たちの描写があまりにも深淵だからだ。特に、スカーレット・ヨハンソン演じる母親ロージーの存在感は、映画全体の心臓部と言っても過言ではない。狂った世界で唯一、正気を保ち続ける彼女は、ジョジョにとっての太陽だ。
ワイティティはこの映画で、足元にとにかく執着する。彼女が履いている特徴的なツートーンの靴。映画全編を通して、カメラは執拗なまでに彼女の足元を映し出す。
そして、あの中盤の広場のシーン。顔を映さず、宙に浮いたあの靴だけをフレームに収めた瞬間、観客は言葉を失い、心臓を鷲掴みにされる。直接的な処刑シーンを見せるよりも遥かに雄弁で、残酷。この演出だけで、ワイティティ監督は映画史に名を刻んだと言ってもいいのではないか。
一方で、公開当時、批評家たちの間で賛否両論の嵐を巻き起こしたのが、サム・ロックウェル演じるキャプテンK(クレンツェンドルフ大尉)の存在だ。
ナチスの将校でありながら、どこかやる気がなく、部下とイチャつき、最後にはジョジョを救う男。一部の厳格な批評家からは「ナチスの制服を着た人間に、安易な救済を与えるべきではない」「歴史の修正だ」なんて厳しい意見も飛び交った。
確かにその通りだろう。だがその一方で、彼がジョジョを逃がす直前、彼が着ているナチス式軍服を荒々しく剥ぎ取り、罵倒して唾を吐きかけたシーンを忘れてはならない。
彼は、自分が犯した罪(=体制への加担)からは絶対に逃れられないことを悟っていた。だからこそ、未来ある子供であるジョジョからナチスの象徴である軍服を引き剥がし、一人の人間として送り出したのだ。
自分は軍服を着たまま死ぬことを選び、次世代にはその呪いを継承させない。これはナチスの肯定ではなく、イデオロギーと個人を切り離すことができるのかという、ギリギリの倫理的問いかけに対する、監督なりの魂の回答と受け止めるべきではないか。
『ライフ・イズ・ビューティフル』(1997年)が、父が嘘をついて子供を守る物語だったとすれば、『ジョジョ・ラビット』は、子供自身が嘘(プロパガンダ)を見破り、自分の足で立つ物語なのである。
瓦礫の中で鳴り響くデヴィッド・ボウイ
僕がこの映画を推す最大の理由、それはラストシーンにある。「2020年で一番好きだった映画のシーンを一つ挙げろ」と言われたら、僕は一瞬の躊躇もなく、食い気味にこの映画のラストシーンを挙げるだろう。それくらい、あのエンディングは最高にして至高、映画という芸術が到達した奇跡の瞬間だと確信している。
戦争が終わり、ナチスが崩壊し、街は瓦礫の山。そんな絶望的な状況で、ジョジョとエルサは言葉で愛を語り合う訳でもなく、未来への希望を演説する訳でもなく、ただ、踊る。玄関先で、ぎこちなく、しかし確かにリズムに身を任せて体を揺らす。
エルサを演じるトーマシン・マッケンジーの微細な表情の変化、そして指先の動き。自由という概念をこれほどまでに肉体的に、かつエモーショナルに表現したダンスが他にあるだろうか?
しかも、そこに流れてくるのがデヴィッド・ボウイの『ヒーローズ(Heroes)』、それもドイツ語版だ。ベルリンの壁について歌われたこの曲が、分断を超えた二人の若者の未来を祝福するように鳴り響く。
「自由になったら何をする?」「踊るのよ」──劇中で交わされたこの伏線が、最高のカタルシスと共に回収される。イデオロギーも、人種も、国境も、すべてのクソみたいなレッテルを吹き飛ばして、ただ人間として向き合い、音楽に合わせて体を揺らす。
これこそが、僕たちが映画を見る理由であり、生きる喜びそのものだ。
- 原題/Jojo Rabbit
- 製作年/2019年
- 製作国/アメリカ
- 上映時間/109分
- ジャンル/コメディ、歴史、戦争
- 監督/タイカ・ワイティティ
- 脚本/タイカ・ワイティティ
- 製作/カーシュー・ニール、タイカ・ワイティティ、チェルシー・ウィンスタンリー
- 製作総指揮/ケヴァン・ヴァン・トンプソン
- 制作会社/サーチライト・ピクチャーズ、TSGエンターテインメント、
- 原作/クリスティン・ルーネンズ
- 撮影/ミハイ・マライメア・Jr.
- 音楽/マイケル・ジアッチーノ
- 編集/トム・イーグルス
- 美術/ラ・ヴィンセント
- 衣装/マイェス・C・ルベオ
- ローマン・グリフィン・デイヴィス
- トーマシン・マッケンジー
- タイカ・ワイティティ
- レベル・ウィルソン
- スティーヴン・マーチャント
- アルフィー・アレン
- サム・ロックウェル
- スカーレット・ヨハンソン
- アーチー・イェーツ
- ブランドン・フィールド
- サム・ヘイガース
- ジョジョ・ラビット(2019年/アメリカ)

![ジョジョ・ラビット/タイカ・ワイティティ[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/718yz0t64VL._AC_UL640_FMwebp_QL65_-e1762675135153.webp)
![グランド・ブダペスト・ホテル/ウェス・アンダーソン[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/81QVAVbZivL._AC_UL640_FMwebp_QL65_-e1769326989108.webp)
![Heroes/デヴィッド・ボウイ[CD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/A1-PDo3Ep3L._AC_UL640_FMwebp_QL65_.webp)