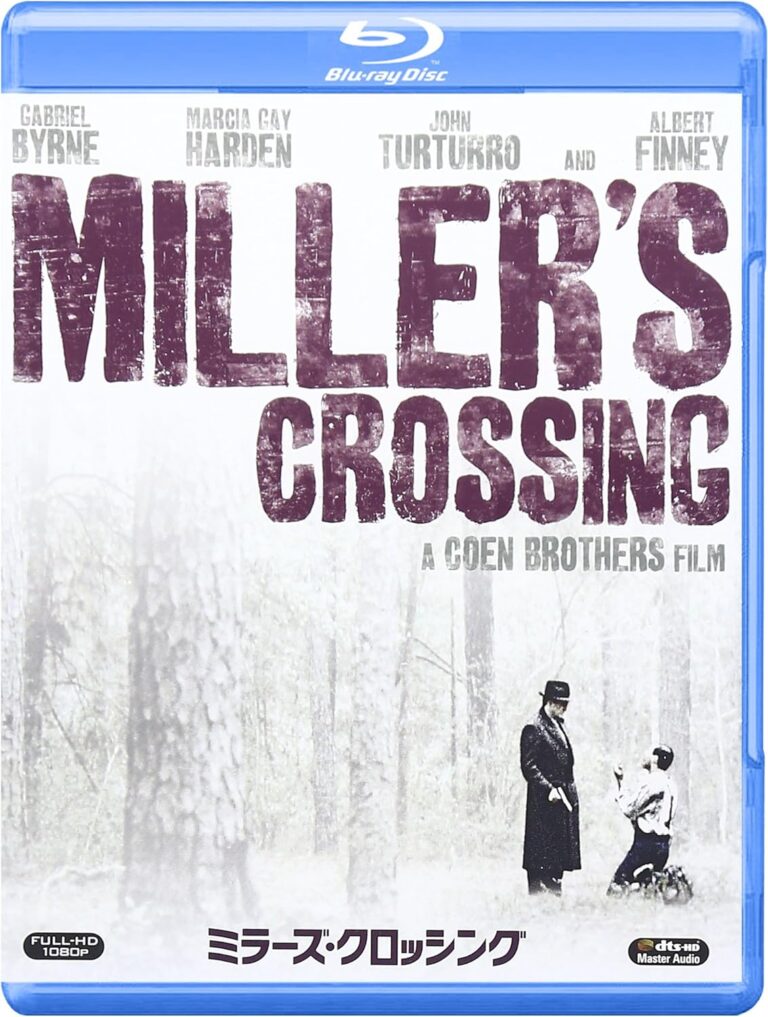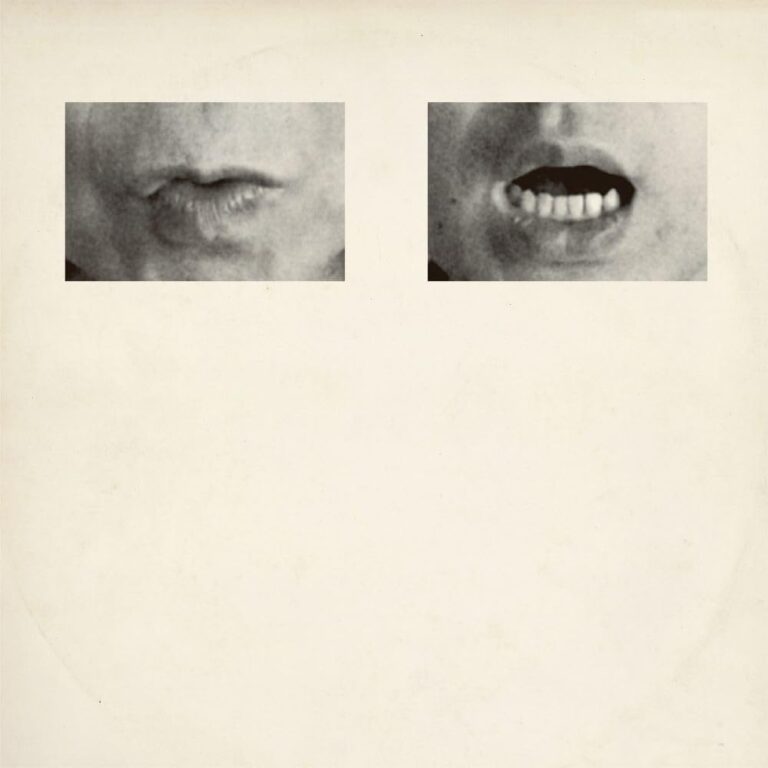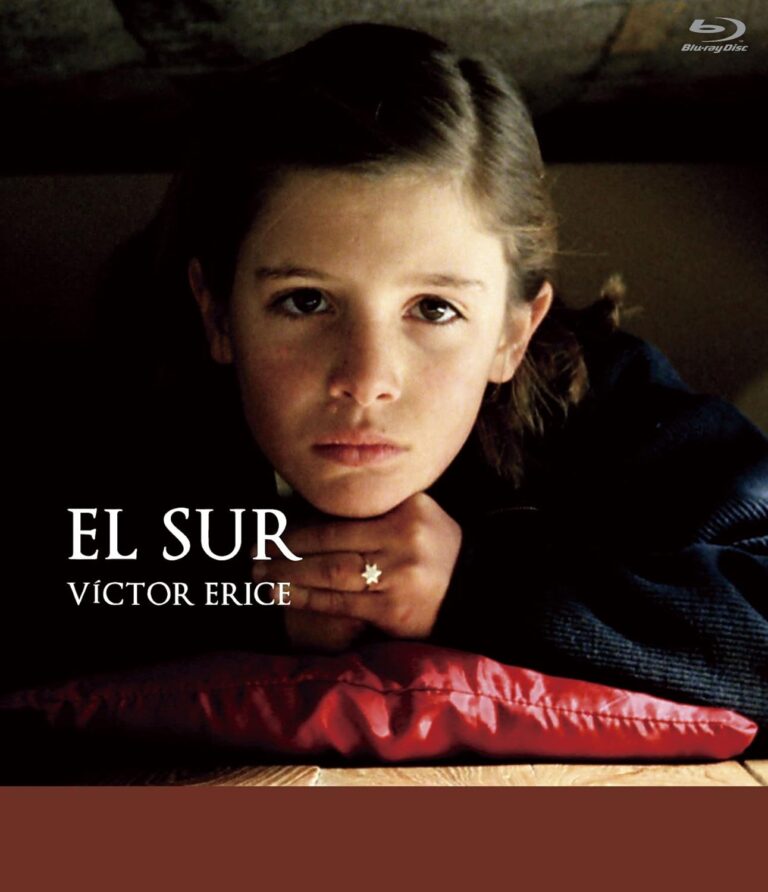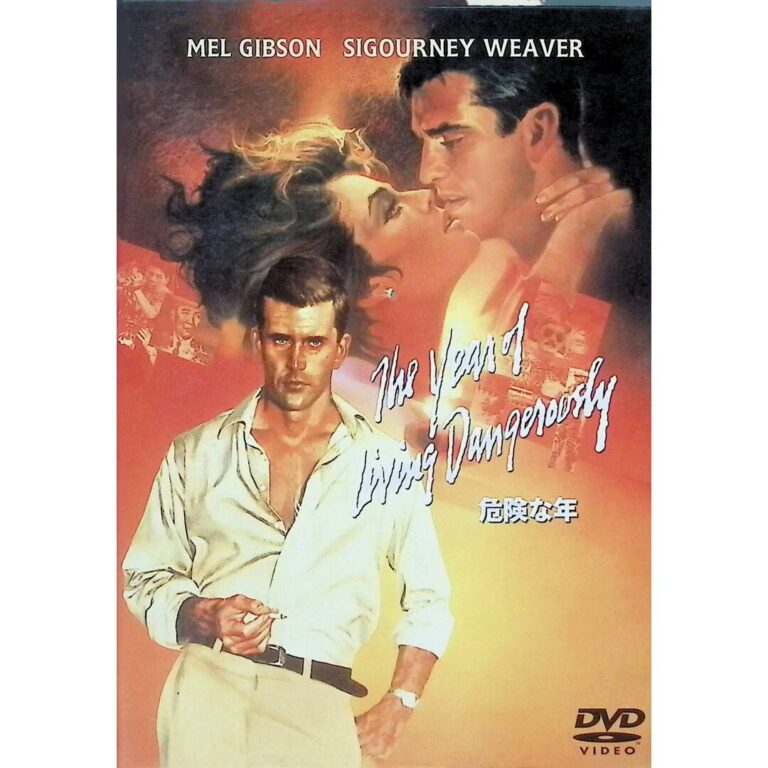『風立ちぬ』──“飛行機は美しい夢”に込められた老境の祈り
『風立ちぬ』(2013年)は、宮崎駿監督が実在の航空技師・堀越二郎をモデルに描いた長編アニメーション。少年時代から「美しい飛行機を作りたい」と夢見た青年が、戦争の時代に理想と現実の狭間でもがく姿を描く。結核に冒された菜穂子との恋、設計者としての葛藤、師カプローニとの夢の対話――宮崎自身の分身としての二郎が、創造の代償と生の意味を問いかける。
『風立ちぬ』の静謐
宮崎駿は、きわめて能弁な映画作家だ。
彼の政治的信条は、『紅の豚』(1992年)のポルコ・ロッソに仮託されてきたし、地球にとって“害虫”かもしれない人間という存在をどう肯定するかという命題は、『風の谷のナウシカ』(1984年)のナウシカや『もののけ姫』(1997年)のアシタカのセリフによって代弁されてきた。
その熱量たるや、まるで壇上から拳を握りしめて熱弁をふるう大先生のツバが、客席のこちらにまで飛んできそうなほどである。説教臭さが、宮崎アニメ特有の生理的快感を凌駕してしまったあたりから、僕自身のジブリ離れは加速していったのだ。
内包するテーマを大上段から語ってしまった作品の典型は、やはり『もののけ姫』だろう。宮崎駿はこの映画で、世界の抱える矛盾と自身の苦悩を余すところなくブチまけ、その混沌のただ中で「生きろ」という、ある種倒錯的なメッセージを火花のように散らした。
だが、15年の時が過ぎ、70代に突入した宮崎駿が手がけた新作『風立ちぬ』(2013年)には、その説教臭さはほとんど見当たらない。むしろ静謐で抑制された筆致が印象的だ。
主演に庵野秀明を据えたことも特筆すべきだろう。かつて『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Air/まごころを、君に』(1997年)で「だからみんな、死んでしまえばいいのに」と「生きろ」とは真逆のメッセージを突きつけた庵野の声が、今度は堀越二郎の肉声を担う。
このキャスティング自体が、作風の変化を強調している。
飛行機は夢
映画は、堀越二郎の夢から幕を開ける。朝日を浴びた小型飛行機が、美しい田園を渡り鳥のように駆け抜ける。モノローグもセリフもなく、ただ飛翔の運動的快感だけがスクリーンに刻まれる。このオープニングだけで、僕は本作を傑作と確信した。
プロデューサーの鈴木敏夫は「戦闘機が大好きで、戦争が大嫌い。宮崎駿は矛盾の人である」と喝破する。それは、平和を望みつつ原子爆弾の開発に加担してしまい、生涯葛藤に苛まれたアルバート・アインシュタインの姿を想起させる。
だが『風立ちぬ』には、その「もがき」は表層には描かれない。ゼロ戦を設計したことで多くの人命が失われた事実に対する悔恨も、直接的には表現されていないのだ。
むしろ「戦争責任」を描く代わりに、「飛行機の美しさ」という純粋な美意識のほうへ物語を収束させる。このすり替えこそが、宮崎駿の老境の選択であり、同時に最大の批評点にもなる。
さらに庵野秀明特有の声質と抑制された台詞回しが、観客を主人公の内面に容易に接続させない。そのため二郎の煩悶や憐憫は伝わりにくく、結果として彼は苦悩を超えた「達観者」のような相貌を帯びている。
興味深いのは、堀越二郎が眼鏡をかけた“4つの眼を持つ男”として描かれる点である。すなわち、より高次の俯瞰的視点=神の視点を体現しているかのようなのだ。
人間の業に囚われ、もがき苦しむ姿を微塵も見せない。育ちの良いボンボンで、正義感の強い快男児であり、しかも“史上最強のメガネ男子”として造形されたキャラクター。
こうした特異な主人公によって、『風立ちぬ』は従来のフィルモグラフィーとは一線を画すテイストを醸し出している。
夢と現実の交錯
同時に本作の中で繰り返されるカプローニとの夢の対話は重要だ。夢の場面は、現実の戦争責任からの逃避の場であると同時に、「飛行機は美しい夢」という理念を保証する舞台でもある。
夢と現実が交錯する二重構造の中で、宮崎駿は「罪」と「美」をどうしても切り離せない矛盾を処理しようとする。だが、夢でいかに純度を高めても、現実において機体は武器へと接続される以上、その結節点は消し去れない。この二重帳簿的な処理が、矛盾の正体。だからこそこの映画には、奇妙に透きとおった透明さを帯びるのだ。
物語展開も劇的な高揚を排除し、意識的にカタルシスを回避している。名機ゼロ戦の開発過程で描かれるのは失敗の連続であり、ようやくテスト飛行が成功した瞬間に、愛する女性=里見菜穂子はすでに遠くにいる。観客の溜飲を下げるような場面は一切用意されていない。
なぜなら、現実において機体が武器として接続され、人命を奪う道具に転化してしまう以上、「勝利の瞬間」に喝采を与えることは倫理的に不可能だからだ。
もしカタルシスを提供すれば、それは美しい夢の肯定と同時に戦争の加担を正当化することになってしまう。宮崎駿はその構造的矛盾を回避するために、あえて達成の歓喜を奪い取り、観客に「空を飛ぶ美しさ」と「殺戮に結びつく現実」との亀裂を突きつけるのである。
恋愛の宿命性
本作の骨格はラブストーリーに位置づけられるはずだが、そのプロセスは徹底して省略される。『未来少年コナン』(1978年)のコナンとラナ、『天空の城ラピュタ』(1986年)のパズーとシータのように、宮崎作品の男女は“一目で恋に落ちている”のが鉄則。
唐突に思えるプロポーズすら、宮崎駿にとっては必然の流れなのだ。しかし『風立ちぬ』の菜穂子は結核に侵され、愛は成就ではなく「喪失」へと収束していく。ここにおいて恋愛はプロセスではなく、最初から定められた宿命として描かれている。
むしろ宮崎駿作品において恋愛要素は、つねに「運動」と「職能」に従属する。働く/つくるという生のベクトルに、恋愛というファクターが吸い寄せられる。
コナンは走り、パズーは飛行石を掲げ、千尋は働き、キキは配達し、ソフィーは動く城の家事を整える。そこで育まれるのはデートや会話ではなく、共同作業だ。
『風立ちぬ』においても、紙飛行機を介したやりとり、避暑地での再会、病床を支える日々は、いずれも「ともに生きるための作業」として配置される。
プロポーズが唐突に見えるのは、心理の熟成が省かれているからではない。むしろ共同作業が十分に行われ、もはや言葉を要しない段階に達しているからである。
そのうえで宮崎は、恋愛を時間の圧縮装置に結びつける。『もののけ姫』のアシタカとサンは「世界の不一致」によって距離を保たれ、『ハウルの動く城』では時間のループがすでに二人の運命を先取りしている。
『千と千尋の神隠し』では忘却された幼時の記憶が「以前にすでに出会っていた」という事実として回収される。『風立ちぬ』では結核が時間を容赦なく縮め、恋は成就ではなく「別離」という終着点を最初から内包する。だから菜穂子は、恋人でありながら“生の有限性”そのものとして二郎の前に現れるのだ。
ゆえに宮崎の恋愛は、心理学的リアリズムではなく神話的リアリズムに属する。人物が互いを「好きになっていく」のではなく、世界の側が二人を結び、また引き裂くのだ。
その力は、自然(風)、災厄(地震・病)、あるいは時間(記憶・ループ)として立ち現れる。『風立ちぬ』で菜穂子が消えることは、恋が敗れることを意味しない。
むしろ、恋が生の継続(生きねば)へと昇華される瞬間であり、二郎の職能=飛行機の夢が、その喪失を背負うことで「大人の倫理」に到達する瞬間なのである。
老境の映画作家として
宮崎自身の企画書冒頭には「飛行機は美しい夢」と一文がある。戦闘機であるにもかかわらず、そう断言できる精神的境地が本作を貫いている。アインシュタイン的な葛藤を解き放たれ、少年のように一途な夢想に帰依した宮崎駿の姿が、映画全体をきらめかせているのだ。
この「業」を捨て「夢」に還る姿勢は、同時代の黒澤明が『夢』(1990年)や『八月の狂詩曲』(1991年)で到達した「老境の映画」とも響きあう。若き日に「生きろ」と叱咤し続けた映画作家が、老境に差し掛かって「生きねば」と囁くように問いかける――その変貌は、宮崎駿という作家の人生そのものを映し出す。
『風立ちぬ』は、いびつで奇妙な構造を有しながらも、宮崎フィルモグラフィーのなかで最も透明度の高い作品といえる。
- 製作年/2013年
- 製作国/日本
- 上映時間/126分
- 監督/宮崎駿
- 脚本/宮崎駿
- 原作/宮崎駿
- プロデューサー/鈴木敏夫
- 製作/奥田誠治、福山亮一、藤巻直哉
- 作画監督/高坂希太郎
- 動画検査/舘野仁美
- 美術監督/武重洋二
- 色彩設計/保田道世
- 音楽/久石譲
- 庵野秀明
- 瀧本美織
- 西島秀俊
- 西村雅彦
- スティーヴン・アルパート
- 風間杜夫
- 竹下景子
- 志田未来
- 國村隼
- 大竹しのぶ
- 野村萬斎