ヒッチお得意の巻き込まれ型サスぺンスを、スケールを拡大させて自己模倣した傑作
『北北西に進路を取れ』(1959年)といえば、何よりもあの都会的で洗練されたオープニング・タイトルが頭に浮かぶ。
バーナード・ハーマンの高揚感溢れるスコアにのせて、直線的に画面を横切りながら細いラインが入り、右上がりのロゴが飛び出してくる。やがてそのタイトルデザインが前面ガラス窓の高層ビルにフェードインするという、あのカッコ良さ!
『めまい』(1958年)や『サイコ』(1960年)を手がけた、ソウル・バスらしいグラフィカルなデザイン。このオープニング・タイトルを観るためだけに、僕は何度も『北北西に進路を取れ』のVHSをデッキに押し込んだ記憶あり。
内容といえば、これが転々奇を究めて簡単に要約できないぐらいのお話。主演のケイリー・グラントが、「なんてひどいシナリオだ。もう最初の三分の一の撮影が済んだというのに、何が何だかさっぱり分からん!」と漏らしたほど。
いい映画の条件は1分でストーリーを説明できることだ
とは、20世紀フォックスで辣腕をふるったかつての大プロデューサー、ダリル・F・ザナック氏のお言葉だが、『北北西に進路を取れ』はその条件と完全に真逆である。
ヒッチコックは同一のテーマを繰り返し変奏することで、映画をより洗練させていく映画作家だが、この『北北西に進路を取れ』も、『三十九夜』(1935年)や『海外特派員』(1940年)といった、ヒッチお得意の巻き込まれ型サスぺンスを、スケールを拡大させて自己模倣している。
この映画では、広告屋のケイリー・グラントがジョージ・キャプランなる諜報部員に間違えられたことからサスペンスが発動するのだが、そもそもそんな人物なんぞ存在しない、というのがミソ。
つまり『北北西に進路を取れ』とは、“間違えられた男”が次第にアイデンティティーを回復していく物語なのではなく、存在しない他者に自分を同一化させ、アイデンティティーを変容させていく物語なのだ。
「自分ではない誰かを演じる」ということによって生じる仮想現実感が、理由もなく命を狙われるという恐怖が前景化せず、どこか祝祭的な気分で物語が進行する最大の要因。キマジメすぎて物事を深刻に受け止めてしまいそうなジェームズ・スチュアートではなく、能天気で楽天家なプレイボーイのケイリー・グラントがキャスティングされたのは、必然だったのだ。
シカゴ行き特急20世紀号でのエヴァ・マリー・セイントとのロマンス、白昼堂々と展開されるトウモロコシ畑でのアクション・シーン、大統領の顔が刻まれたラシュモア山でのクライマックス・シーンと見所は多い。
個人的に唸らされたのは、ケイリー・グラントと諜報機関のボスである“教授”(レオ・G・キャロル)が、飛行場で「これまでの出来事を総括して語り合う」というシーンである。
フランソワ・トリュフォーも、自著『定本 映画術 ヒッチコック・トリュフォー』で指摘しているが、飛行機のプロペラ音に邪魔されて、実はその会話の後半は観客には聞こえない。
すでに観客が得ている情報をくどくど説明するのではなく、わざと会話をオフらせることによって、映画自体の時間の短縮をはかっているのだ。まさに映画的な「時間との戯れ」。映画における効率化の意味を突きつけられた思い。
ヒッチコック曰く、ケイリー・グラントとエヴァ・マリー・セイントが口づけをかわし、次のカットでトンネルに入る列車に切り替わるのは、自分の映画で最も猥褻なシーンだそうな。列車は男根の隠喩であり、トンネルに入る=性交するという暗喩だというのだ。
このオヤジはユング派夢解釈にまで自覚的だったのだ。脱帽!
- 原題/North by Northwest
- 製作年/1959年
- 製作国/アメリカ
- 上映時間/136分
- 監督/アルフレッド・ヒッチコック
- 製作/アルフレッド・ヒッチコック
- 脚本/アーネスト・レーマン
- 撮影/ロバート・バークス
- プロダクションデザイン/ロバート・ボイル
- 美術/メリル・パイ、ウィリアム・A・ホーニング
- 音楽/バーナード・ハーマン
- タイトルデザイン/ソウル・バス
- 編集/ジョージ・トマシーニ
- ケイリー・グラント
- エヴァ・マリー・セイント
- ジェームズ・メイソン
- ジェシー・ロイス・ランディス
- マーティン・ランドー
- レオ・G・キャロル
- エドワード・ビンズ
- ロバート・エレンスタイン
![北北西に進路を取れ [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51Qv55BkWrL.jpg)
![三十九夜 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51aIh0WK3iL.jpg)

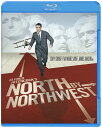








最近のコメント