華やかに’90年代を駆け抜けた、渋谷形の頂点
大学の時に好きだった女のコが「あたし、オザケンが好きなの」と発言してショックを受けたことがある。
東大に入学するやいなや高校の同級生・小山田圭吾とフリッパーズ・ギターを結成。一躍渋谷系の最右翼となり、解散後は『カローラ2にのって』、『ラブリー』などで王子様路線をまっしぐら。
う~む、どう逆立ちしたってこんなヤツにはかなわんだろ(っていうか俺は王子様にはなれんよ!)。だって彼女のことを「子猫ちゃん」とか言っちゃうんだぜ。
ポップ&スウィート!!そう、渋谷系のリリックってのはとにかくソフィスティケート感あふれる、等身大胸キュン・ラブストーリーなのである。
東京タワーを背に大きな花束を抱えたノンノ系男子が、外車で彼女とワインのコルクを開ける…。こんなバブリーな幻想を抱いた“恋愛”という神話を語る、これがオザケンワールドであると私は解釈する。
「プラダの靴が欲しいの」「何かいいコトはないか子猫チャン」などというオザケン語をまぶしながら、ホーン、オーケストラをフィーチャーしたサウンドは軽やかに、賑やかに駆け抜ける。
天下の「紅白歌合戦」でオザケンが楽しそうに『ラブリー』を熱唱していたのも記憶に新しい。渋谷系のトップランナー、’90年代のキング・ポップを彼は体現し続けてきたのだ。
しかし3rdアルバム『球体を奏でる音楽』(1996年)あたりからオザケンはジャジィなテイストをも取り込みはじめる。メロウな佳曲『大人になれば』では情感をたっぷりときかせて歌い上げ、新たなステップに突入。そして遂にはニューヨークに姿をくらましてしまう(おい!!)。
それから幾星霜、「オザケン」というワード自体が’90年代ノット・デッドな記号になってしまった2002年…、彼は帰ってきた。しかもユニセックスな王子様 「オザケン」としてではなく、男のホルモンを感じさせるアーティスト「小沢健二」として。
『Eclectic』(2002年)では、低音のベースがしずしずとサウンドを包み込み、官能的な世界観を造型する。音響系をも思わせるダヴ・アンビエント的なアレンジは、もはや「僕と君」とで繰り広げられる「恋愛ごっこ」ではない。
ここには、「僕とあなた」とで展開される、肉感的なラヴストーリーがある。ささやくような彼の歌声には、たしかに“男”としての獣を感じ図にはいられない。
30歳を過ぎ、小沢健二は照れ隠しをせずに赤裸々な「性」を語り始めた。少なくとも私はこのアルバムを聴いて、わずかながら引きずっていた「渋谷系」からの呪縛から解き放たれたような気がする。
- アーティスト/小沢健二
- 発売年/1994年
- レーベル/東芝EMI
- 愛し愛されて生きるのさ
- ラヴリー
- 東京恋愛専科・または恋は言ってみりゃボディ・ブロー
- いちょう並木のセレナーデ
- ドアをノックするのは誰だ?(ボーイズ・ライフ・パート1:クリスマス・ストーリー)
- 今夜はブギー・バック(ナイス・ヴォーカル)
- ぼくらが旅に出る理由
- おやすみなさい,仔猫ちゃん!
- いちょう並木のセレナーデ(リプライズ)
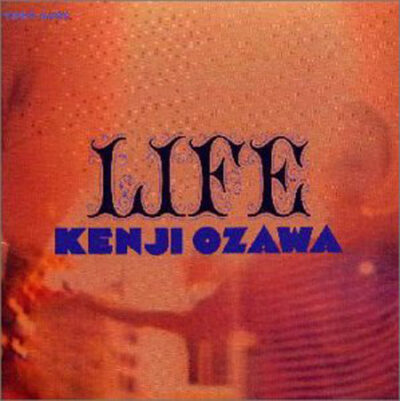

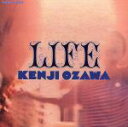








最近のコメント