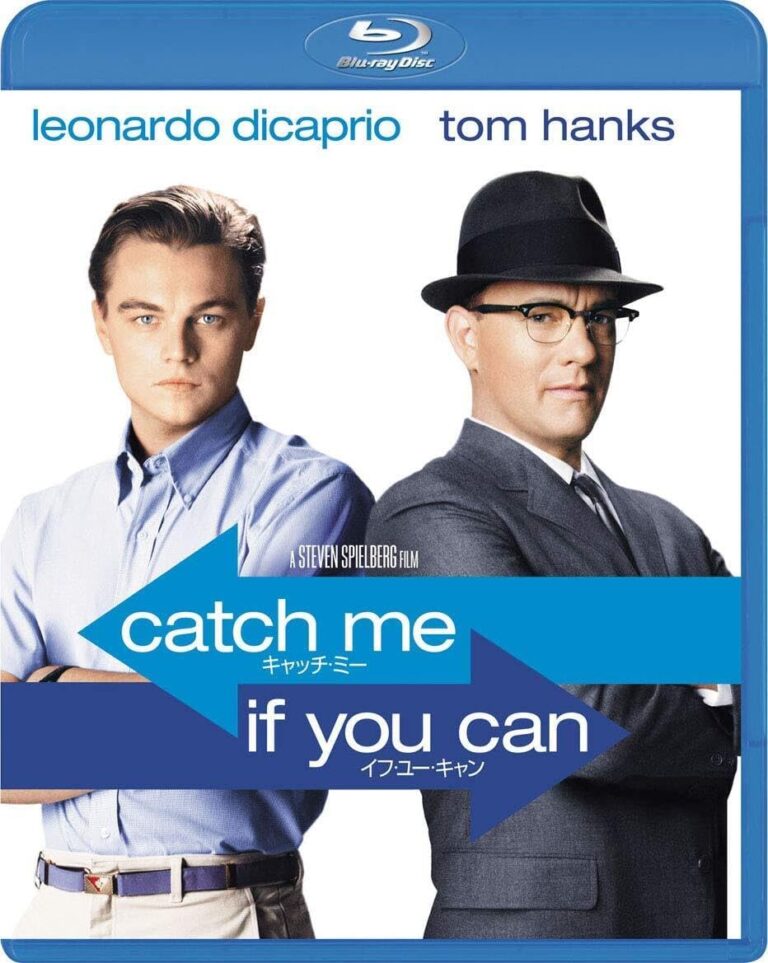『Superkilen』(2024)
アルバム考察・解説・レビュー
『Superkilen』(2024年)は、デンマークのデュオ、スヴェインボゥグ・カーディーブ(Svaneborg Kardyb)が現代ジャズ・シーンに「静寂」の衝撃を与えた決定的名盤。ウーリッツァーとドラムの極小編成で「聴く建築」を体現し、都市の喧騒と北欧の冷涼な空気を、温かな「余白」へと昇華させた、アンビエント・ミニマリズムの金字塔である。
聴く建築、あるいは都市のノイズを浄化する聖なる儀式
今、世界で最も美しい隙間をデザインする男たちは、デンマークにいる。
彼らの名はスヴェインボゥグ・カーディーブ(Svaneborg Kardyb)。ニコライ・スヴェインボゥグ(Key)とジョナス・カーディーブ(Dr)によるこのデュオが放った最新作『Superkilen』は、情報過多で窒息しそうな2026年の現代社会に打ち込まれた、あまりにも優しく、しかし強靭な“くさび”なのだ。
僕たちは日々、膨大なコンテンツの濁流に飲まれている。ショート動画の無限スクロール、AIが生成する大量のテキスト、絶え間ない通知音。
そんな加算ばかりの世界で、彼らの音楽は圧倒的な減算の美学を突きつけてくる。それはまるで、散らかり放題の部屋を一瞬で片付け、窓を全開にして冷たい風を迎え入れるような快感だ。
驚かされるのは、その楽器編成の簡素さ。基本にあるのは、ニコライが操るウーリッツァー(エレクトリック・ピアノの一種)と、ジョナスのドラムのみ。ベースもなければ、派手なサックスのソロもない。だが、そこには、驚くほど豊潤なノイズの小宇宙が広がっている。
スヴェインボゥグ・カーディーブのサウンドの核となるのは、間違いなくウーリッツァーの音色だ。今の時代、PCソフトを使えばどんな綺麗なピアノの音だって出せる。
だが、彼らはあえて、鍵盤を叩くときの「カタカタ」という物理的な打鍵音や、ペダルを踏む「ギシギシ」というきしみ音、そしてアナログ回路特有の「サーッ」というホワイトノイズさえも、愛おしい楽器の一部として録音しているのだ。
Lo-Fi(ローファイ)という安易な言葉じゃ、片付けられない。例えるなら、使い込まれた革張りのソファや、手触りの良い木のテーブルのような、テクスチャーへの執着。デジタル録音が「ツルツルしたプラスチック」だとしたら、彼らの音は「ザラついた木材」。その凹凸にこそ、魂が宿る。
僕が特に衝撃を受けたのは、ジョナスのドラミングだ。彼はリズムを刻むことを放棄しているようにさえ見える。通常のジャズドラマーが時間を管理する指揮官だとしたら、彼は空気を震わせる画家だ。シンバルを叩くのではなく、撫でる。スネアを叩くのではなく、置く。その所作は、まるで茶道の点前を見ているかのような静謐な緊張感に満ちている。
彼らのスタイルは、近年のジャズ界を席巻していた超絶技巧へのカウンターだ。速く弾くこと、複雑なコード進行を並べること、難解な変拍子で聴き手を圧倒すること。そんな筋肉質なジャズに疲れた僕たちの耳に、彼らの引き算の美学はあまりにも心地よく染み渡る。
これは、ジャズの顔をしたアンビエントであり、デンマークの伝統音楽(フォークロア)の魂を持ったミニマル・ミュージックだ。彼らは楽器を演奏しているのではなく、空間そのものを演奏している。
その証拠に、彼らのライブ映像を見てほしい。NPRの「Tiny Desk Concert」での彼らは、まるでお互いの呼吸を確かめ合うように、視線を交わしながら音を紡いでいる。
そこにあるのは、演奏というよりも「対話」であり、もっと言えば「生活」そのものだ。
多様性を縫い合わせる「赤い広場」の魔法
なぜ彼らは、このアルバムに『Superkilen』という奇妙なタイトルをつけたのだろう。ここにこそ、本作を読み解く最大の鍵がある。
「Superkilen(スーパーキーレン)」とは、デンマークのコペンハーゲン、ノアブロ地区に実在する公園の名前。この地区は、かつては治安が悪化し、暴動さえ起きたこともある移民街だった。そこに「多様性の共存」をテーマにして作られたのが、この公園だ。
建築家グループBIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)や芸術家集団Superflex、そしてランドスケープアーキテクトが手掛けたこの空間は、とにかく異様。
鮮烈な赤、真っ黒なアスファルト、そして緑。エリアごとに色が塗り分けられ、世界中から集められた遊具やベンチ、マンホールの蓋までもが展示されるように配置されている。
モロッコの噴水、日本のタコの滑り台、イラクのブランコ……。一見カオスに見えるその空間は、しかし不思議な調和を保ち、人々を繋いでいる。スタジオがすぐ隣ということもあって、ニコライは毎日窓からこの景色を眺めていたという。
「Superkilen」とは、、デンマーク語で「巨大なくさび」という意味。くさびとは、固い岩を割るための道具であり、同時に、ぐらつく二つのものを繋ぎ止めるための道具でもある。
スヴェインボゥグ・カーディーブの音楽は、まさにこの公園そのものだ。異なる文化、異なるリズム、異なるノイズが混在する都市の中で、彼らの音は「広場」のように機能する。ニコライもインタビューでこう語っている。
(Superkilenとは)くさびを使って木を割るように、突破口を開くエネルギーのことだ
アルバムを通して聴くと、曲ごとに表情がガラリと変わることに気づくだろう。ある曲は北欧の冷たい冬を思わせる厳かさを持ち、次の曲では中東のバザールのような熱気を帯びたループが顔を出す。
だが、それらは決してバラバラにはならない。ニコライのウーリッツァーとジョナスのドラムという「2つの色」だけで描かれることで、すべてが奇跡的な統一感を持って響くのだ。
これは、分断が進む世界に対する、彼らなりの回答なのだろう。 声高に平和を叫ぶのではなく、ただ異なるリズムを隣り合わせに置くこと。不協和音さえも肯定し、それをグルーヴに変えてしまうこと。
彼らの音楽が持つ包容力の正体は、この公園が持つ哲学と完全にリンクしている。彼らは音楽で、都市の隙間に「シェルター」を作ろうとしているのかもしれない。
マンチェスターから世界へ響く、静寂の轟音
本作を語る上で避けて通れないのが、彼らが所属するレーベル〈Gondwana Records(ゴンドワナ・レコーズ)〉の存在だ。イギリス・マンチェスターを拠点とするこのレーベルは、マシュー・ハルソールによって設立された、現代ジャズ・シーンにおける聖域である。
ゴーゴー・ペンギン、ママル・ハンズ、ポルティコ・カルテット…。彼らが輩出してきたバンドには、共通するDNAがある。それは、ミニマリズムへの傾倒と、エレクトロニック・ミュージックの構造をアコースティック楽器で再現するという、実験精神だ。スヴェインボゥグ・カーディーブは、このGondwanaの系譜における末っ子でありながら、最もラジカルな進化を遂げた存在だと言える。
先輩格であるゴーゴー・ペンギンが、テクノやドラムンベースのような機械的ビートを人力で再現するマシーン・ジャズだとしたら、スヴェインボゥグ・カーディーブはもっと有機的で、土着的。彼らの音楽には、テクノロジーへの憧れよりも、自然への回帰願望が強く感じられる。
とはいえ、彼らのサウンド・プロダクションは極めて現代的だ。反復されるフレーズの微妙なズレ、レイヤーの重ね方、そして空間系エフェクト(リバーブやディレイ)の処理。
これらは明らかに、ブライアン・イーノやエイフェックス・ツインといった電子音楽の巨匠たちが切り拓いた地平の上にある。彼らは古き良きジャズをやっているのではない。ジャズというフォーマットを借りて、現代的なアンビエント・ポップをやっているのだとも言える。
特筆すべきは、アルバム全体を貫く親密さ(Intimacy)。ストリーミングで音楽を聴くことが当たり前になった今、僕たちは「誰かが自分のために演奏してくれている」という感覚に飢えている。
彼らの音楽には、隣で演奏しているかのような体温がある。ウーリッツァーの鍵盤が戻る音、ドラムスティックが皮に触れる瞬間。それらの微細な音が、僕たちの孤独を埋めてくれるのだ。
世界がますます騒がしく複雑になり、AIが生成する音楽が溢れかえる中で、彼らの不完全な、しかし温かい音は、これまで以上に重要な意味を持つはずだ。
何より、ミニマルなジャケがいいじゃないですか。2024年にリリースされたアルバムのなかで、僕が一番好きなのはこのジャケかも。
- アーティスト/スヴェインボゥグ・カーディーブ
- 発売年/2024
- レーベル/Gondwana Records
- ジャンル/ジャズ,アンビエント
- プロデューサー/ニコライ・スヴェインボゥグ,ジョナス・カーディーブ
- Superkilen
- Cycles
- St. Pancras
- Vakler
- Balancen
- Tvillinger
- Tide
- Udsigten
- Arendal
- Superkilen(2024年/Gondwana Records)

![Superkilen/スヴェインボゥグ・カーディーブ[CD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/61R08AU7XL._AC_SL1500_-e1769082850637.jpg)