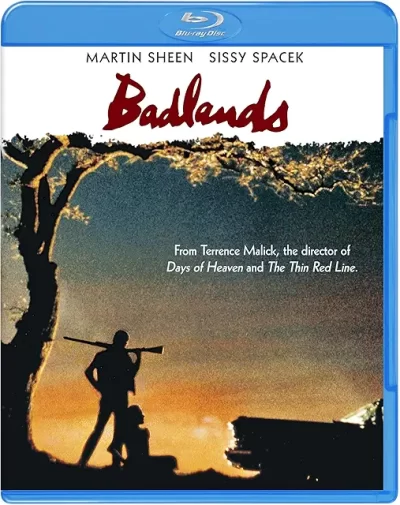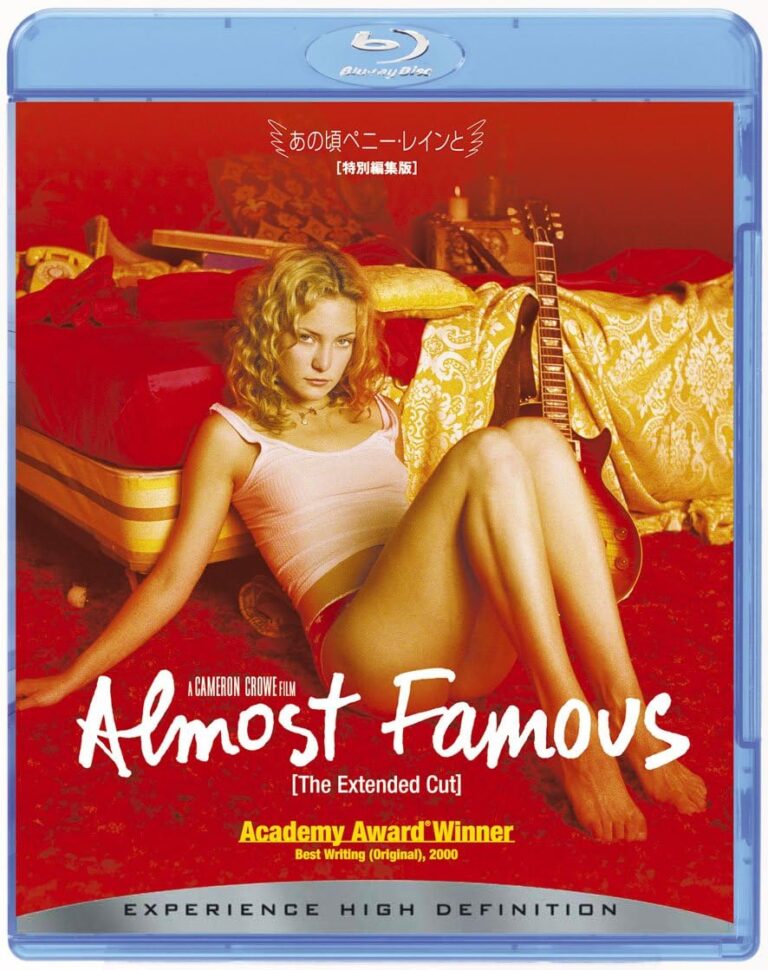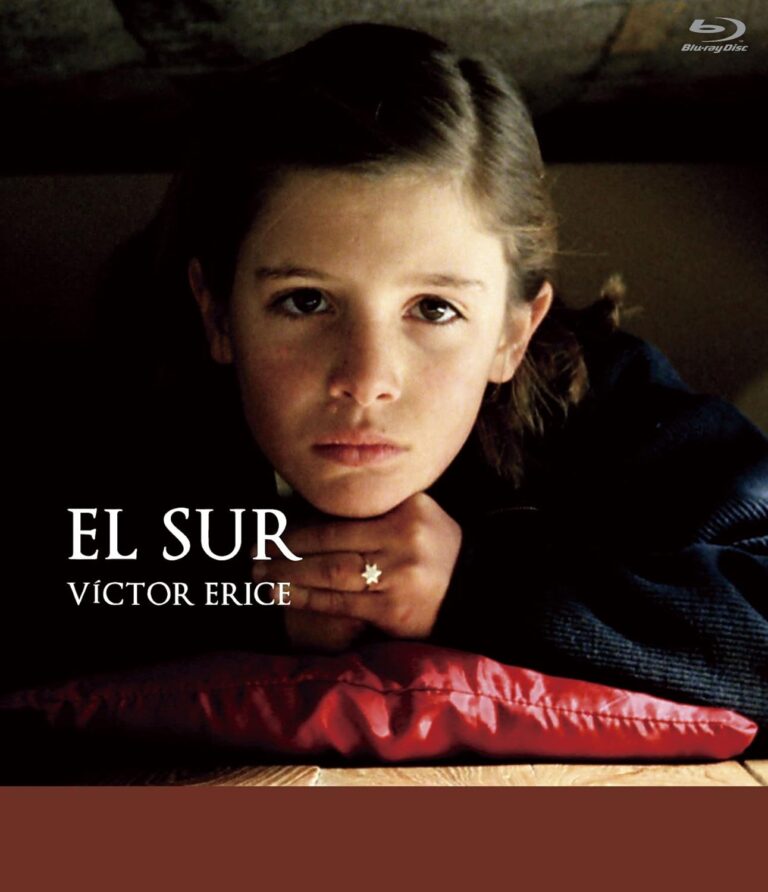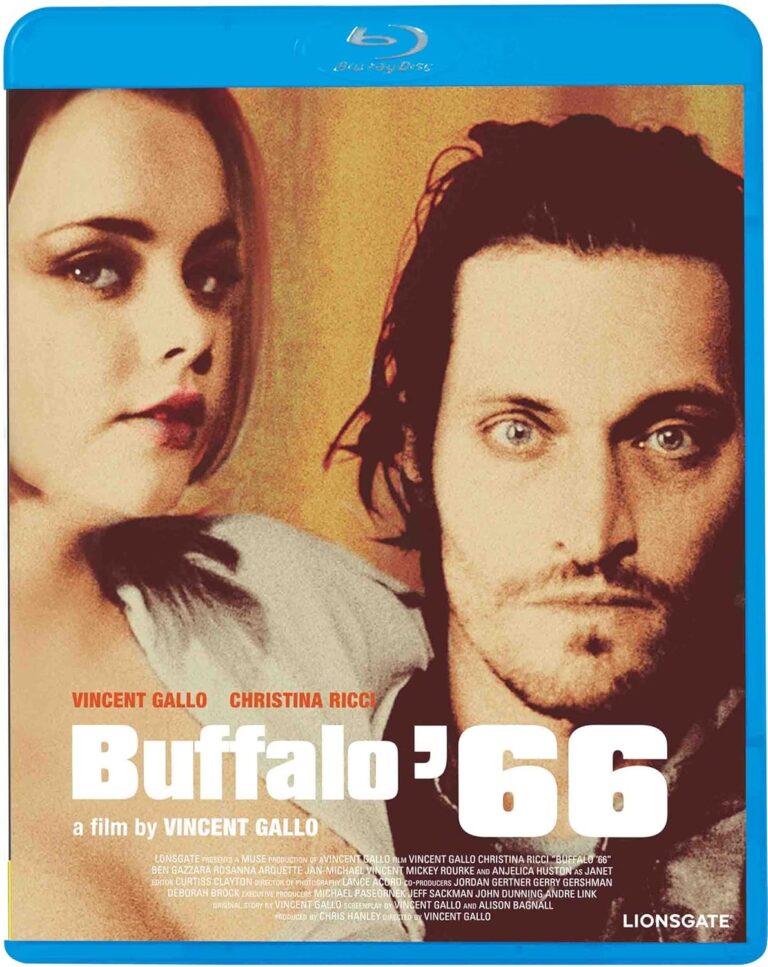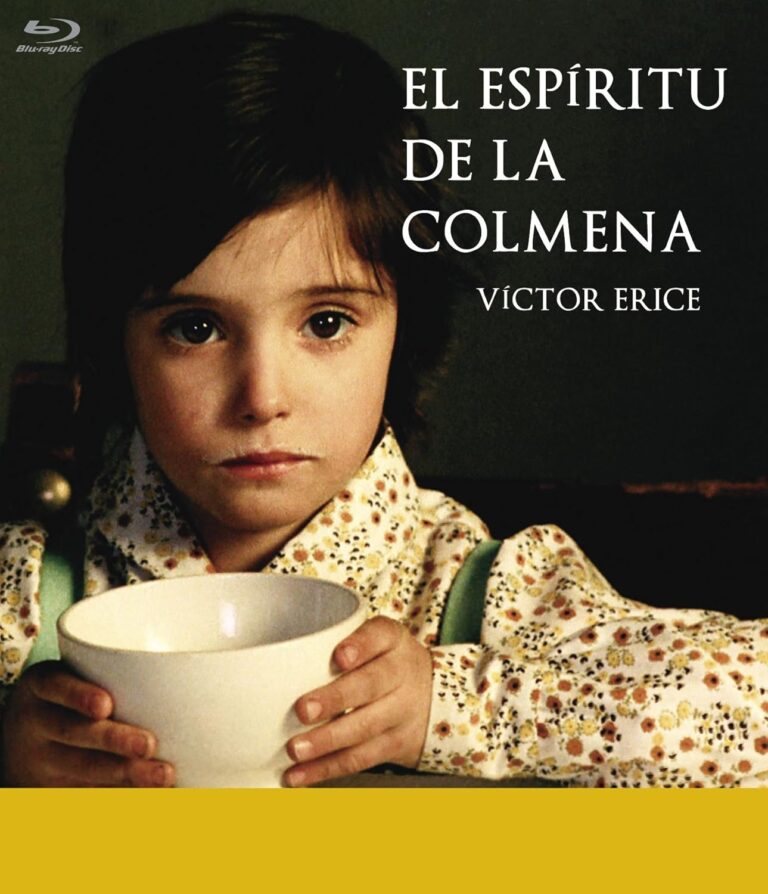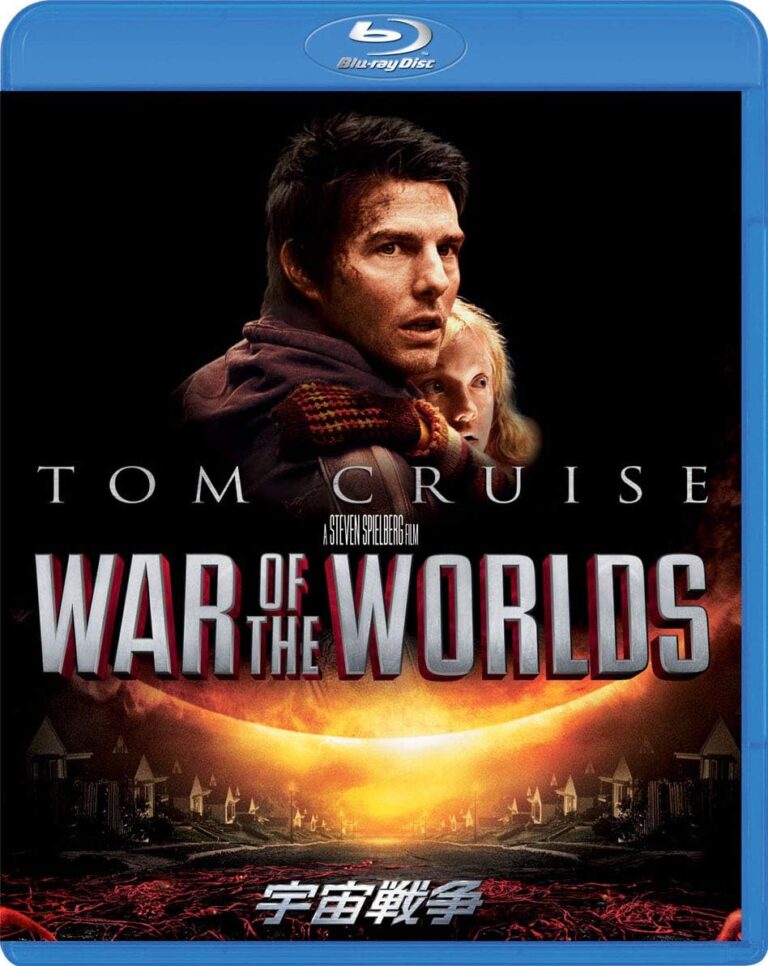『夜霧の恋人たち』(1968)
映画考察・解説・レビュー
『夜霧の恋人たち』(原題:Baisers volés、1968年)は、フランソワ・トリュフォー監督が軽快なテンポと洒脱な会話で綴る、アントワーヌ・ドワネルの冒険シリーズ第3作。兵役を終えたアントワーヌ・ドワネル(ジャン・ピエール・レオ)が職を転々とし、ホテル夜勤や探偵事務所での珍騒動を経て、クリスチーヌ(クロード・ジャド)やファビエンヌ(デルフィーヌ・セリッグ)との揺れる恋に翻弄されるパリ青春喜劇。
お調子者の身体──未成熟さと“母性”の設計図
『大人は判ってくれない』(1959年)から『逃げ去る恋』(1979年)まで、20年にわたって断続的に撮られたアントワーヌ・ドワネル・シリーズ。
その第3作にあたる『夜霧の恋人たち』(1968年)は、少年期の疎外と苦味を描いたモノクロの第1作とも、離婚劇としての苦さが前景化する『家庭』(1970年)とも違う、きわめて“宙吊り”な位相にある作品だ。
ジャン=ピエール・レオ演じるアントワーヌは、ここでようやく大人の社会へ足を踏み入れたかに見えながら、その実態は少年期と青年期の境界線の上で足踏みし続ける存在として描かれる。
不真面目さが祟って軍隊から除隊され、ホテルの夜勤仕事もトラブル続きであっさり解雇され、探偵事務所に就職しても依頼人の妻と関係を持ってしまう。
恋も仕事もあっちへフラフラ、こっちへフラフラ。ヘマはするがどうにも憎めないダメ男。『夜霧の恋人たち』は実にいきあたりばったり的な、正統派フレンチ・モラトリアム映画だ。
アントワーヌは、シリーズを通して一貫して“どこか不器用な青年”として描かれてきたが、『夜霧の恋人たち』ではその未成熟さがほとんど喜劇的なレベルまで前景化している。
ヘマを繰り返し、仕事にも人生にも集中しきれないその身振りは、一人前の男性としての自意識よりも、まだ少年の延長線上にいる存在として造形されているように見える。にもかかわらず、彼は妙に女性に対して吸引力を持つ。
これは単なる“ダメ男がなぜかモテる”という記号ではなく、未完成な存在に対して周囲の女性たちが自然と関わり方を変えてしまう構造として機能している。
アントワーヌの振る舞いは、社会的責任を引き受けきれない危うさと、保護本能を刺激する脆さのあいだを揺れ続ける。トリュフォーはその揺れを、悲劇ではなく軽やかなコメディとして配置することで、観客に安易な同情も断罪も許さない。
アントワーヌは“成長物語の主人公”というより、成長というプロットそのものをずらしてしまう撹乱要因として画面に居座るのだ。
女たちの布陣──クリスティーヌとファビエンヌの“技術”
本作において、トリュフォーの視線はアントワーヌの迷走と同じくらい、女性たちの立ち回りに向けられている。良家の娘として描かれるクリスティーヌと、成熟した魅力でアントワーヌを翻弄するファビエンヌ。
二人は性格も振る舞いも異なりながら、“男性主人公の周辺にいるヒロイン”として消費されるのではなく、むしろアントワーヌを翻弄し、配置し直し、時に操作する側として立ち上がってくる。
クリスティーヌは、テレビを自ら壊しておきながら、その修理を口実にアントワーヌを呼びつけ、結果として関係を回復してしまう。この“事故に見せかけた召喚”は、偶然や運命として処理されがちな恋愛映画の定番装置を、彼女自身の能動的な“技術”として描き直す試みだと言える。
ファビエンヌのストレートなアプローチも、アントワーヌを誘惑するというより、彼の未熟さを見抜いたうえで、その揺らぎを自分の側へ引き寄せる行為として機能している。
二人の女性は、いずれも“男性主人公に振り回される側”ではなく、アントワーヌの不安定さを見越したうえで関係の主導権を握ろうとする主体として存在している。
その結果、アントワーヌは関係を支配しているように見えながら、実際には彼女たちの掌の上から一歩も出られない。トリュフォーはここで、恋愛関係をロマンティックな物語として語るのではなく、視線や駆け引き、策略が交錯する場として描き出している。
コメディと伏線放棄──トリュフォー的シネフィル感覚の噴出
『夜霧の恋人たち』の面白さは、アントワーヌの迷走ぶりや女性たちの技術だけではなく、その語り口と映画的引用の重ね方にある。
クリスティーヌの尾行シーンは、サスペンスとしての緊張にはほとんど貢献せず、むしろコントのような間合いとぎこちなさによって観客の期待を裏切る。探偵事務所という設定も、物語をスリラー方向へ傾けるための装置に見えながら、最後まで本格的サスペンスへ移行することはない。
ミステリー映画のような“何かが起こりそうな予感”だけが持続し、結果的にはドタバタ恋愛劇としてのテンションが優先される。この“肩すかし”の感覚こそ、トリュフォーのシネフィル的な遊びだと言える。
観客が無意識に抱くジャンル映画の期待──探偵が出てくればサスペンスが始まるはずだ、尾行があれば謎が深まるはずだ──を巧妙に誘発しながら、その期待をあっさり裏切ることで、恋愛映画そのものの純度を上げてしまう。
色彩設計やファッションもまた、ゴダールを思わせる原色の使い方やコンチネンタルな衣装センスを通して、“60年代パリ映画”であることを強く自己主張している。
だがそれは単なるスタイリッシュな装飾ではなく、登場人物たちのモラトリアムな心性と呼応する“外側の仮装”として機能する。派手な色彩や流行のファッションは、大人になりきれない彼らがまとっている一種のペルソナであり、その華やかさと中身の不安定さのギャップによって、作品全体に独特の浮遊感が生まれている。
ラストに登場する“クリスティーヌを尾けていた謎の男”の処理も象徴的。観客は彼を探偵だと誤認するよう誘導されるが、物語は突然、彼の一方的な愛の告白と「頭がオカシイ人」という一蹴によって幕を閉じる。
この瞬間、それまでサスペンスの伏線のように見えていた事柄が、すべて恋愛映画の文脈へ吸収される。トリュフォーはここで、伏線を回収することよりも、“恋愛にとって不要な要素はあっさり切り捨てる”という決断を選ぶ。ある種乱暴なこの手つきの中に、物語の整合性よりも“恋愛映画としてのトーン”を優先するシネフィル的感覚が露出している。
『夜霧の恋人たち』は、シリーズ全体の中で見ると、アントワーヌという人物がいちばん“定まらない”地点で揺れている作品だ。その揺れを、トリュフォーは成長物語として収束させようとせず、むしろモラトリアムそのものの形として記録する。
ダメさと魅力が同時に立ち上がるアントワーヌ、主体性を持って彼を扱う女性たち、そしてジャンルの約束事を意識的に裏切る語り口。そこに見えるのは、恋愛というテーマを扱いながら、つねに“映画そのもののルール”をいじり続けるトリュフォーの遊び心と批評意識だ。
本作は、甘さに寄りかかることのない恋愛映画であり、同時に、映画で恋愛を描くこと自体への静かなコメントでもある。
- 監督/フランソワ・トリュフォー
- 脚本/フランソワ・トリュフォー、クロード・ド・ジヴレー、ベルナール・ルボン
- 撮影/デニス・クレルヴァル
- 音楽/アントワーヌ・デュアメル
- 編集/アニェス・ギユモ
- 美術/クロード・ピニョ
- 録音/ルネ・ルヴェール
- 大人は判ってくれない(1959年/フランス)
- ピアニストを撃て(1959年/フランス)
- 黒衣の花嫁(1968年/フランス、イタリア)
- 夜霧の恋人たち(1968年/フランス)
![夜霧の恋人たち/フランソワ・トリュフォー[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/baisersvoles-e1759052744716.webp)