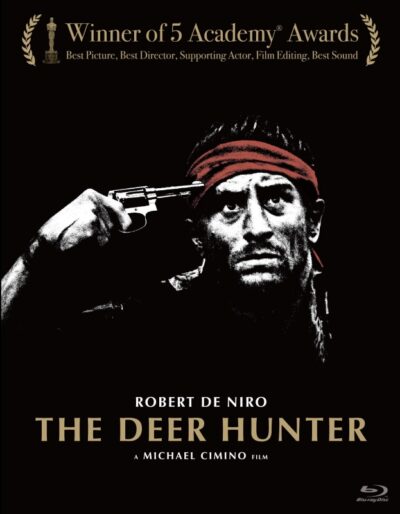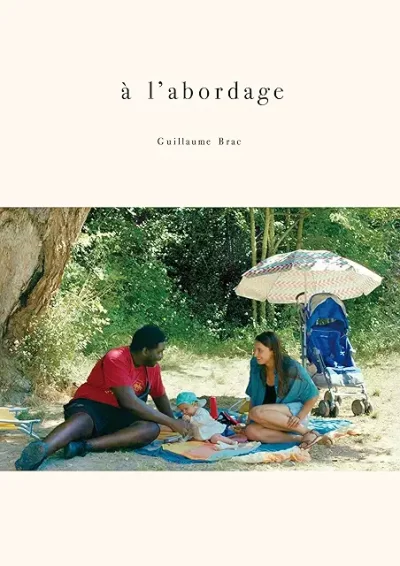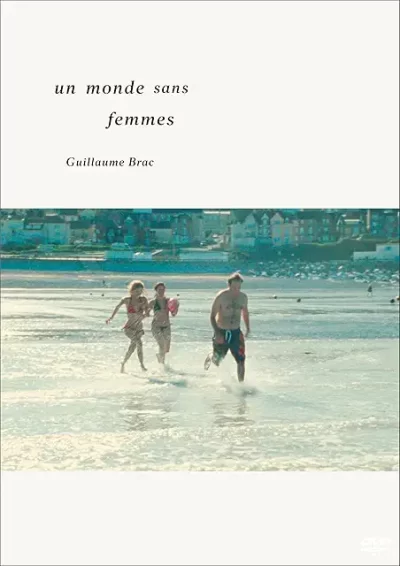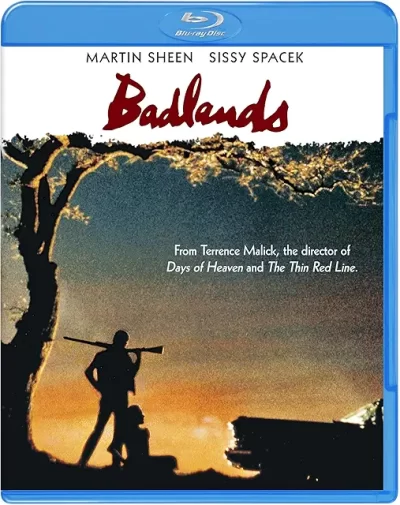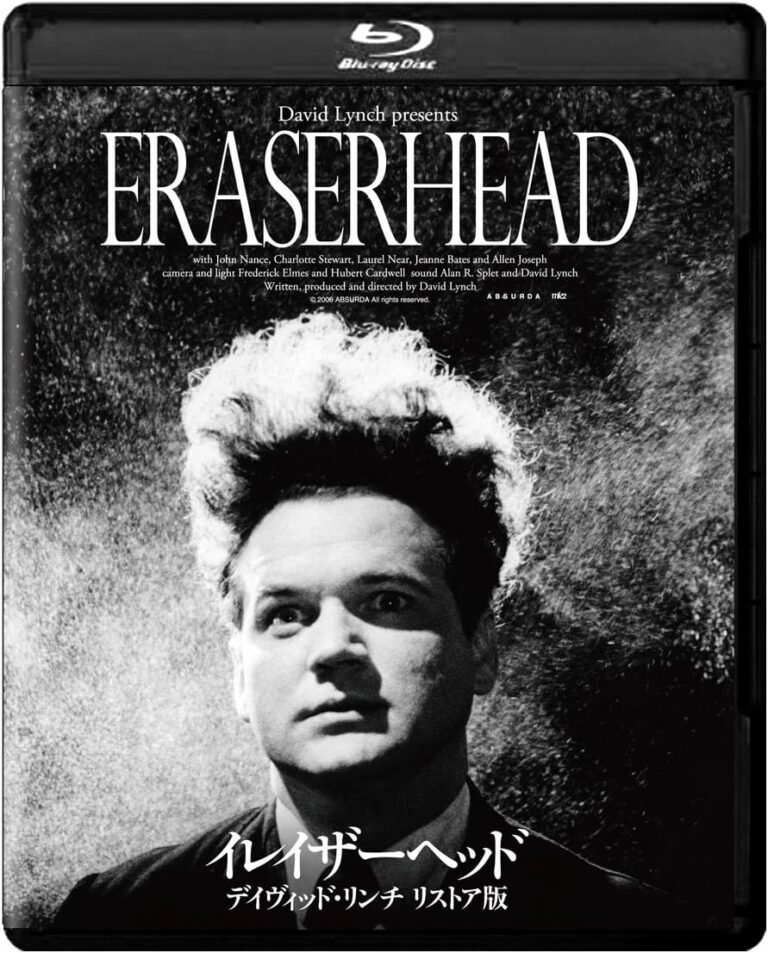『バリー・リンドン』(1975)
映画考察・解説・レビュー
『バリー・リンドン』(原題:Barry Lyndon/1975年)は、スタンリー・キューブリック監督が18世紀ヨーロッパを舞台に描いた歴史ドラマ。アイルランドの青年バリーが、恋と野心に突き動かされて成り上がり、やがて栄光から転落していく過程を、ロウソクと自然光のみで撮影した絵画的映像で綴る。静謐と退廃が共存する異色の叙事詩。
文芸映画の枠を逸脱する
スタンリー・キューブリックは過剰な作家だ。映画を構成するあらゆる要素を、常に目盛りいっぱいまで増幅させる。そしてその過剰さは、観客を畏怖させるだけでなく、時に滑稽にさえ転倒させる。
『2001年宇宙の旅』(1968年)における宇宙的沈黙、『時計じかけのオレンジ』(1971年)における暴力の戯画化──それらはいずれも、人間のイノセンスを嘲笑する冷徹な視線に貫かれている。1975年に公開された『バリー・リンドン』もまた、この過剰の美学を極限まで突き詰めた作品だ。
ウィリアム・メイクピース・サッカレーの小説を下敷きにしたこの映画は、一見すると典型的な文芸大作に見える。しかし、キューブリックの演出は、文芸映画の枠に収まらない奇妙な輝きを放つ。
豪奢なドレスをまとった貴婦人たち、重厚な軍服に身を包んだ兵士たち。照明器具を排し、屋外シーンは自然光、屋内はロウソクのみで撮影したという徹底ぶりは、あまりにも有名だ。
映像の様式美は、しばしばフェルメールの《真珠の耳飾りの少女》やレンブラントの《夜警》と比較される。前者に通じる柔らかい光の差し込みは、登場人物たちの肌や衣装を宝石のように浮かび上がらせ、後者を思わせる群像構図は、人物たちの動きと背景の緊張感を同時に刻印する。
こうした絵画的美学は、ただ単に「絵画の再現」にとどまらず、映像そのものを美術史的言語に翻訳する試みだった。だが、キューブリックは美の模倣を目的としたのではない。彼の意図はむしろ、「美を極限まで誇張することで、逆に滑稽さを浮かび上がらせる」ことにある。
イノセンスの嘲笑と転落
過剰な様式美の中で描かれるのは、イノセンスに対する徹底した嘲笑。ナイーヴなアイルランド青年バリーが、野心を胸に成り上がる物語は、やがて悲惨な転落劇へと変貌する。愛息を事故で失い、決闘で左足を切断し、最終的には家から追放される──まるで、運命が悪意をもって主人公を翻弄しているかのようだ。
だがここに重要なのは、この転落劇が決して「悲劇的感動」には回収されない点にある。観客が同情する間もなく、物語は淡々と進み、淡々と終幕する。
フェルメール的な光に照らされた静謐な室内や、レンブラント風の群像に紛れる主人公は、あくまで“観察対象”にすぎない。美の極点で描かれる人間の転落は、むしろ嘲笑と滑稽さを伴って提示される。ここにこそ、キューブリックが「文芸映画」を逸脱する所以があるのだ。
冷徹なカメラワークと音楽、誇張された演技
映像技法の面でも、キューブリックは独自の過剰さを追求する。特筆すべきは、ズームの多用だ。望遠レンズによる緩慢なズームイン/ズームアウトは、人物へ一定の距離感を示している。これにより、観客は登場人物に共感するのではなく、まるで博物館の展示物を眺めるように観察を強いられる。
多くのシーンが静止画のように構図化され、その中で人物だけがわずかに動く。この様式化されたカメラワークは、観客の没入を阻害し、むしろ「歴史を俯瞰する視点」を強制する。『バリー・リンドン』は、歴史映画である以前に、歴史そのものを冷徹に観察する映画なのだ。
音楽もまた、この冷笑を補強する。主題として繰り返されるのは、ヘンデルの「サラバンド」。荘重で陰鬱な旋律は、常に死の気配を漂わせ、バリーの成功も転落もすべて運命の鎖に縛られていることを告げる。
結婚式や舞踏会の場面でさえ、明るく軽快な音楽はほとんど登場せず、代わりに重苦しい旋律が支配する。音楽は物語を高揚させるどころか、抑圧し、冷笑的な距離感を与えるのだ。
役者の演技も過剰さの一部となる。厚化粧の貴族たち、誇張された仕草を見せる登場人物──いずれも様式化された舞台装置のよう。だが、主人公バリーを演じるライアン・オニールだけは異質。彼の凡庸でデクノボーのような演技は、周囲の過剰さを逆照射するゼロ地点の存在だ。凡庸さそのものが、演出上の構造的役割を果たしている。
幻の『ナポレオン』とリドリー・スコット
『バリー・リンドン』の背景には、キューブリックが準備していた幻の大作『ナポレオン』がある。何千ものカードにナポレオンの行動を記録し、ロケ地を調査し、膨大な衣装を準備していたが、予算の膨張と既存映画の失敗によって頓挫。この野心的プロジェクトのエネルギーが、『バリー・リンドン』に注ぎ込まれた。
そして半世紀後、リドリー・スコットが『ナポレオン』(2023年)を完成させる。スコットはスペクタクル描写を得意とする監督であり、戦場の群像や権力の劇をダイナミックに描き出した。
その作品には、キューブリックが収集した資料や構想の遺産が、明らかに継承されている。つまりキューブリックの未完の夢は、遠回りののちにスコットの手によって結実したのだ。
だが両者のスタイルはあまりにも違う。スコットは英雄の矛盾と壮大さを前景化したが、もしキューブリックがナポレオンを描いたなら、徹底的に猜疑心が強く、見栄っ張りで、独占欲の強いチビ男として描かれたに違いない。
そのタッチも、ナポレオンをめぐる人間たちの様々な欲望が交差する、ブルーチーズのように濃厚な映画になったことだろう。そこには人間嫌いの監督ならではの冷徹な視線が刻印されていただろう。『バリー・リンドン』はその“予行演習”だったのである。
現代映画への射程
近年の歴史映画──ノーランの『オッペンハイマー』(2023年)やスコットの『ナポレオン』──はいずれも個人と歴史の関係をテーマに据える。しかしキューブリックの歴史叙事は、より徹底した冷笑に貫かれていた。人間の欲望や愚かさを、絵画的様式美と過剰な美で包み込み、冷徹に観察する。『バリー・リンドン』はその極点にあり、現代映画にとっても参照すべき座標である。
『バリー・リンドン』は、文芸映画の様式を借りながら、それを逸脱し、過剰な美と退屈を武器に変えた異端の歴史映画だ。フェルメールやレンブラントの光と構図を参照しながら、その典雅を冷笑的に転倒させる。
人間嫌いの映画監督が描く人間模様ほど、辛辣なものはないのだ。
- 原題/Barry Lyndon
- 製作年/1975年
- 製作国/イギリス、アメリカ
- 上映時間/185分
- ジャンル/ドラマ、文芸
- 監督/スタンリー・キューブリック
- 脚本/スタンリー・キューブリック
- 製作/スタンリー・キューブリック、バーナード・ウィリアムズ
- 原作/ウィリアム・メイクピース・サッカレー
- 撮影/ジョン・オルコット
- 音楽/レナード・ローゼンマン
- 編集/トニー・ローソン
- 美術/ミレーナ・カノネロ、ウルラ=ブリット・ショダールンド
- ライアン・オニール
- マリサ・ベレンソン
- パトリック・マギー
- スティーヴン・バーコフ
- マーレイ・メルヴィン
- ハーディ・クリューガー
- レナード・ロシター
- アンドレ・モレル
- 時計じかけのオレンジ(1971年/アメリカ)
- バリー・リンドン(1975年/イギリス、アメリカ)
- シャイニング(1980年/アメリカ)

![バリー・リンドン/スタンリー・キューブリック[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/71osE55HOUL._AC_SL1500_-e1757809654131.jpg)