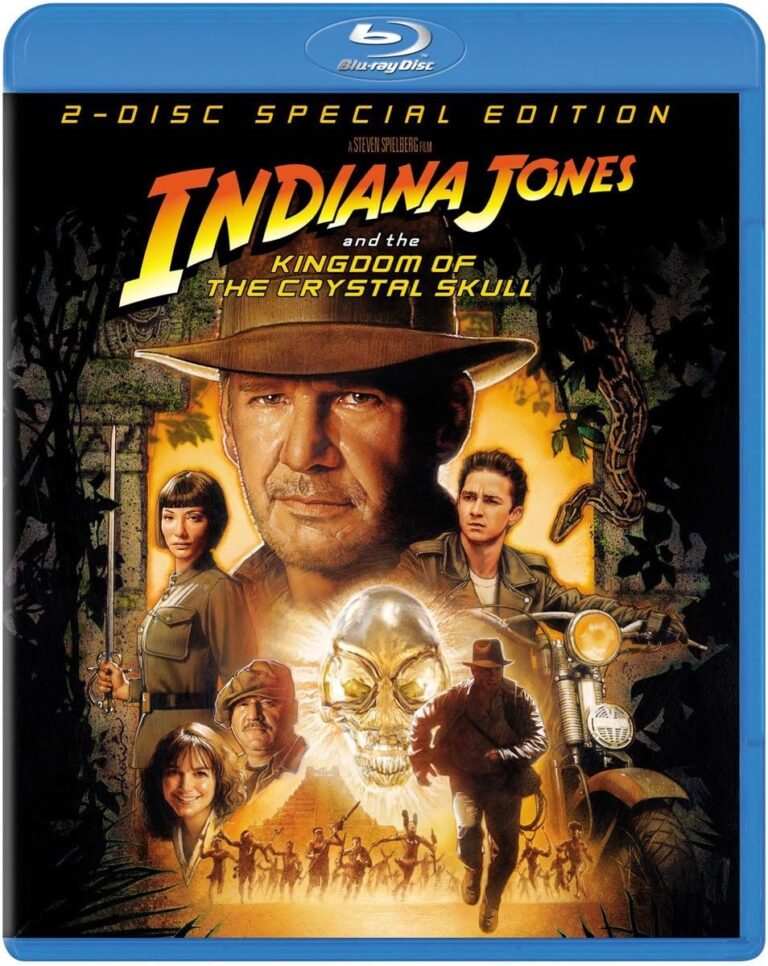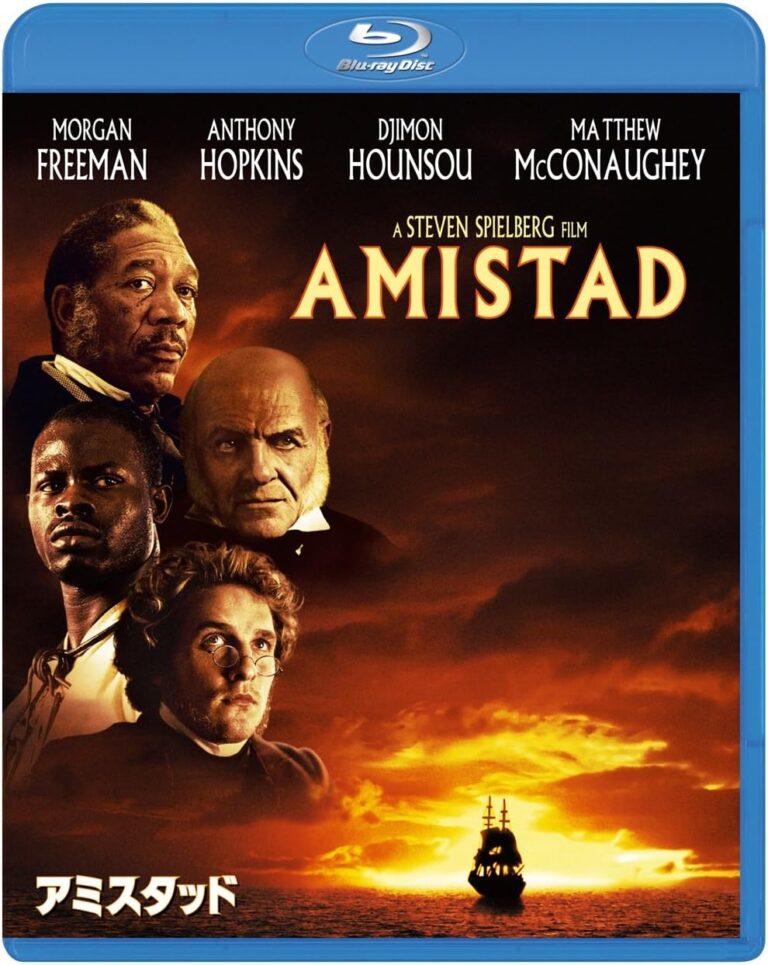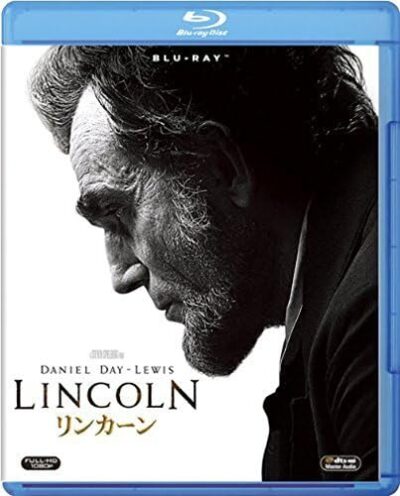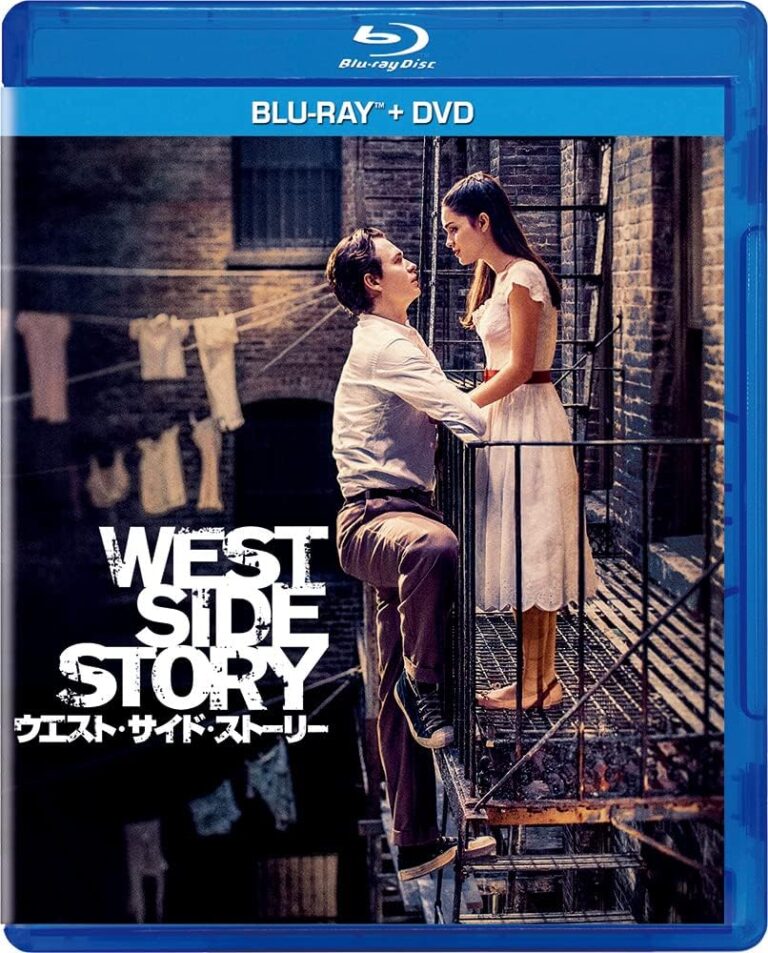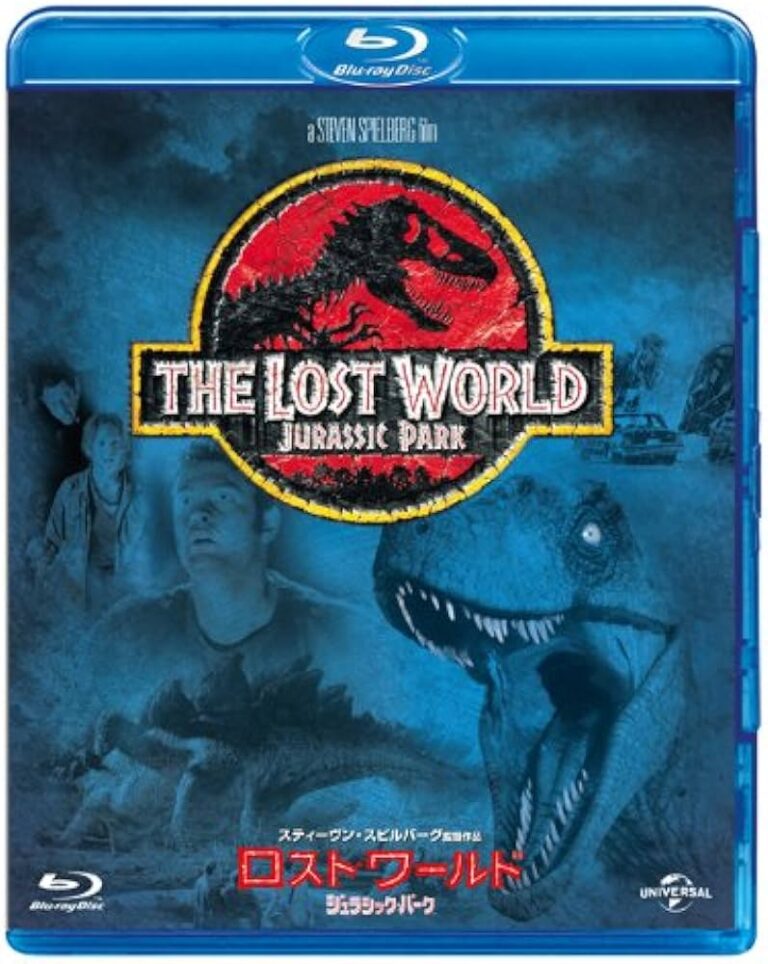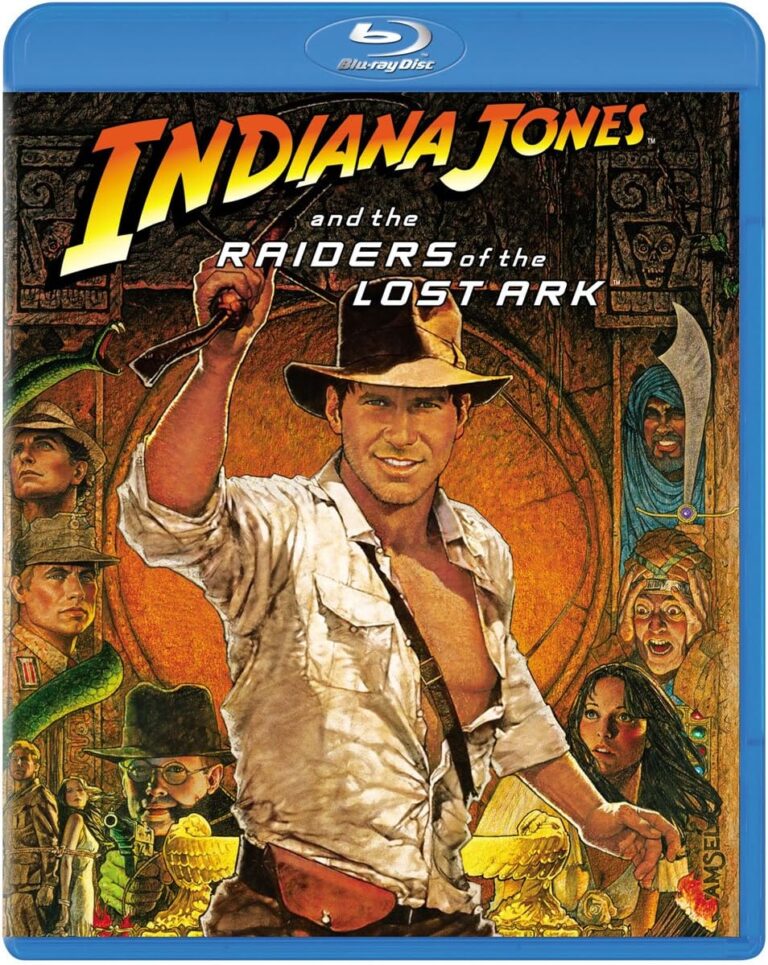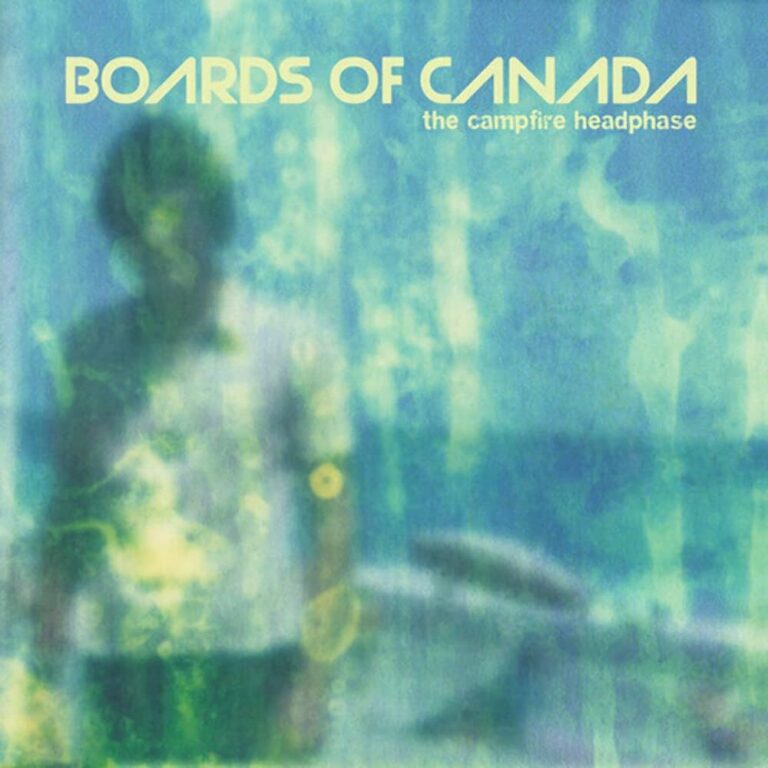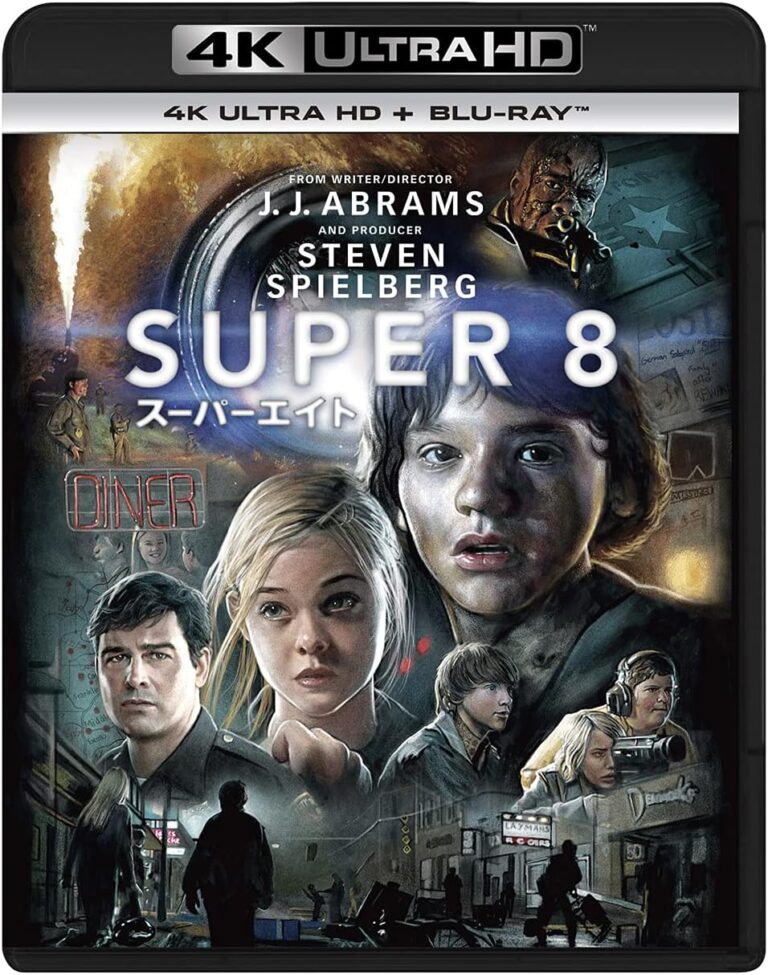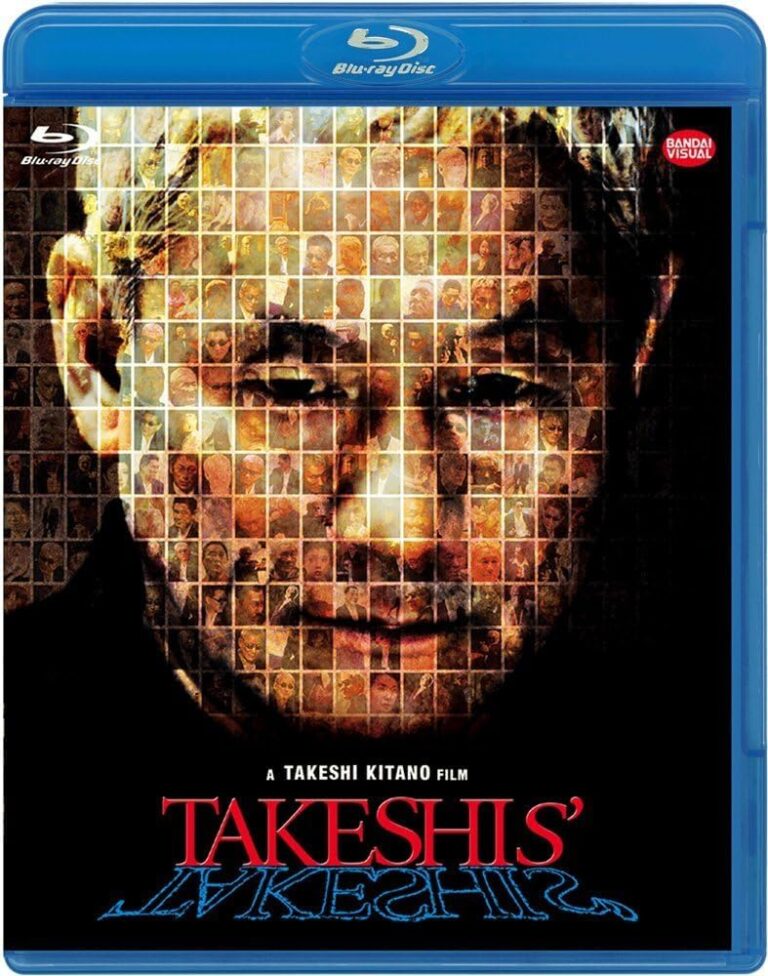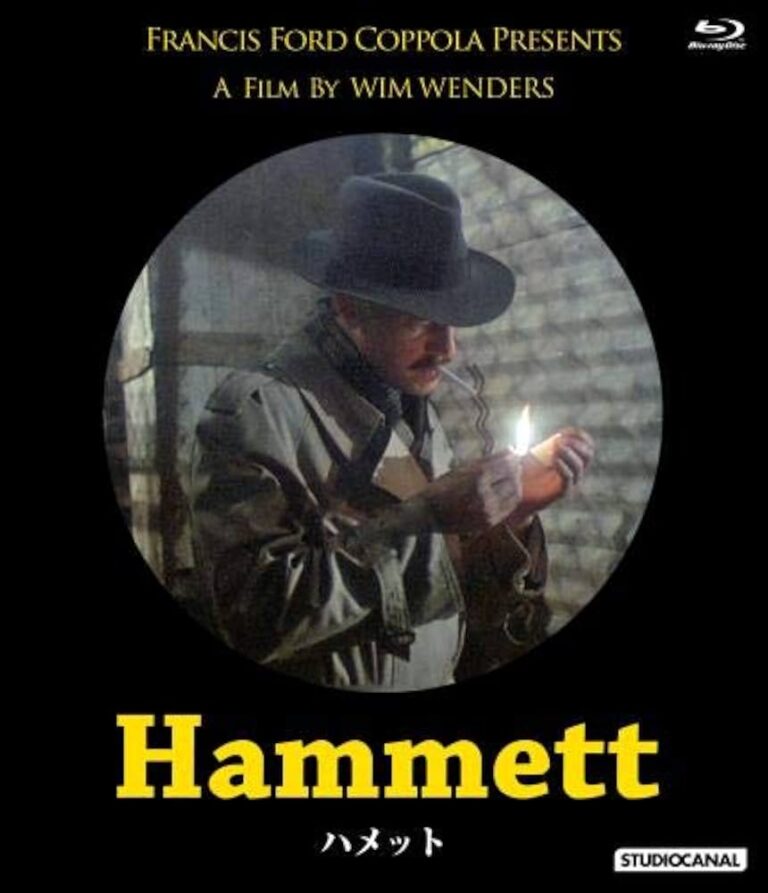『E.T.』(1982)
映画考察・解説・レビュー
『E.T.』(1982年)は、スティーヴン・スピルバーグが「子供の目線」で世界を描いたファンタジー映画。郊外に暮らす少年エリオットが、地球に取り残された宇宙人E.T.と心を通わせる。カメラのローアングル構図と光の演出が、子供と大人の断絶を鮮明に描き出す一方で、センチメンタルな寓話として80年代アメリカの家族神話を映し出した。
“白いスピルバーグ”──子供と未知へのアクセス装置
スティーヴン・スピルバーグは、キャリア初期から一貫して「子供」と「未知なるもの」をセットで描いてきた作家だ。そこでは子供は、単に守られるべき存在ではなく、“世界の向こう側”へアクセスできる特権的な媒体として機能している。
『ジョーズ』(1975年)でサメに襲われる少年アレックス・キントナーの場面は、その象徴だろう。あのビーチのシークエンスは、海水浴客の雑多な日常が続いているところに、突然“死”という異物が割り込んでくる構造になっている。
犠牲になるのが女性でも老人でもなく“少年”であることによって、観客は世界の残酷さを一気に突きつけられる。安全であるはずのリゾートと、制御不能な自然の暴力。その境界線上に、子供の小さな身体が置かれてしまうのだ。
『未知との遭遇』(1977年)では、その構図がさらに進化する。そこでは、異星人とのコミュニケーションを成立させるのは、官僚でも軍人でもなく、子供のような好奇心と開かれた感性を持つ人々だ。
小さな少年バリーが、光と音に誘われて家の外へ出ていく場面は、恐怖以上に“未知への陶酔”が強く刻印されている。彼は、UFOの存在を「おもちゃ」のように受け止めるモチーフでもあり、スピルバーグ自身が信じる「子供の無防備さ=世界への開口部」というイメージを代弁している。
こうした初期作を踏まえて『E.T.』を眺めると、スピルバーグがどれほど徹底して「子供の世界」に賭けていたかが見えてくる。彼は自らを“リアル・ピーター・パン”であろうとし、大人の論理から距離を取り続けた。
“白いスピルバーグ”というラベルは、そうした時期の彼のスタンス──光と驚異とイノセンスに賭ける作家性──を示す略号として機能していると言っていい。
『E.T.』が照らし出した到達点と、その限界
『E.T.』(1982年)は、その“白いスピルバーグ”の思想がもっとも純度高く結晶した作品だ。 カメラのアイ・レベルは徹底して子供に合わせられ、ローアングルで世界を見上げる視点が貫かれる。
エリオット少年の近しい大人以外は、基本的に腰から下しか映らない。大人は顔の見えない存在として画面外へ追いやられ、子供たちの世界だけがまとまった輪郭を持ち始める。
「E.T.は子供にしか見えないんだ」というエリオットの台詞は、まさにその構造の口頭での確認だ。母親は目の前にいるE.T.を認識しようとせず、その存在が“見える”のは子供たちだけ。
ここでスピルバーグは、「大人 VS 子供」という対立軸を、単なる世代間ギャップではなく、“世界の見え方の違い”として映画のフォーマットそのものに書き込んでいる。
問題は、この徹底がそのまま作品の限界にもなっているところだ。月を飛び越える自転車のショットは、文句なしに映画史級のイメージだが、あれをあえて二度挿入し、のちに製作会社アンブリンのロゴとして再利用するあたりに、スピルバーグの“記憶に焼き付けるための反復”というプロフェッショナルな計算が透けて見える。
「あざとい」は「巧い」の裏返しであり、「巧い」は「分かりやすい」とほぼ同義だ。『E.T.』の分かりやすさは、世界中の観客を巻き込むうえで決定的な武器だった。
一方で、その分かりやすさは、エリオットの内側にしか存在しないはずの“私的な神秘”を、最大公約数的な「良い話」へ翻訳してしまう作用も持ってしまう。
ここで振り返りたいのが、『ジョーズ』や『未知との遭遇』との微妙な差異である。『ジョーズ』の少年の死は、観客にとって決して“理解しやすい”ドラマではなく、むしろ世界の理不尽さの象徴として突き刺さる。『未知との遭遇』のラストも、主人公が家族を置いて宇宙船に乗り込むという、どこか倫理的にざらついた選択が残されていた。
だが『E.T.』では、そのざらつきが極力取り除かれている。レーガン政権下のアメリカで「家族の再生」や「郊外の共同体」が求めた安心感と、グローバル市場で通用する“普遍的メッセージ”を両立させるために、スピルバーグは物語から剥き出しの異物感を削いでしまった。
結果として、『E.T.』はスピルバーグが信じてきた子供の神秘性を、もっとも華やかに祝祭しつつ、同時にもっとも消費し尽くしてしまった作品になっている。
『太陽の帝国』が開けた“黒いスピルバーグ”の扉
そんな“白いスピルバーグ”のピークから数年後に撮られたのが、『太陽の帝国』(1987年)。 J・G・バラードの自伝的小説を原作にしたこの作品は、第二次世界大戦期の上海で暮らす少年ジェイミー(クリスチャン・ベイル)が、戦争によって両親と引き離され、日本軍の収容所で生き延びる物語である。
ここでも主人公は少年であり、スピルバーグ的な「子供の目で世界を見つめる」というモチーフは継続している。しかし、『E.T.』との決定的な違いは、世界の残酷さを“魔法のような奇跡”では上書きしない点にある。
ジェイミーは戦争のなかで生き残る術を身につけ、大人びたふるまいを身につけていくが、その過程で何かを取り返しのつかないかたちで失ってもいる。
批評家たちは『太陽の帝国』を、「子供時代の無垢さだけを描いてきたと批判されてきたスピルバーグが、その批判に応答するかたちで生み出した転換作」と位置づけている。
収容所の風景はしばしば“スペクタクル”として美しく撮られるが、その美しさは『E.T.』のように現実を忘却させるための装置ではなく、むしろ少年の視線が現実をどう誤読し、どう糧にしているかを見せるためのフィルターとして機能している。
同時に、『太陽の帝国』には『ジョーズ』以降のスピルバーグ作品に繰り返し現れる、「大人が子供を守りきれない世界」というモチーフも強く現れる。郊外の家で守られていたはずのエリオットとは異なり、ジェイミーは大人たちの無力さ/利己心の中に放り出される。
この作品を境に、“白いスピルバーグ”はすでに揺らぎ始めている。それでも、撮影監督はまだアレン・ダヴィオであり、画面はどこかしら輝度の高い光に満ちている。
子供の眼差しと戦争の残酷さ、その二つをどう両立させるか──その問いが、のちの“黒いスピルバーグ”の出発点として、ここで明確になっているように見える。
カミンスキー以後の光と影──歴史化されるスピルバーグ像
“白い/黒いスピルバーグ”という区分を本格的に語るうえで、撮影監督ヤヌス・カミンスキーの存在は欠かせない。スピルバーグは90年代に入って彼と出会い、『シンドラーのリスト』(1993年)で初めてタッグを組む。
そのモノクロームの映像は、子供時代の幻想を描いてきた監督が、歴史の暗部と真正面から向き合うために選んだ新しい“光の使い方”だった。
『シンドラーのリスト』『プライベート・ライアン』(1998年)以降、カミンスキーとのコラボレーションはスピルバーグ作品の標準装備になり、“白い”時代のふわりとしたライティングとはまったく違う、コントラストの強い、曇りガラス越しのようなビジュアルが定着していく。
そこには、もはやピーター・パンではいられないことを自覚した作家の、光とのつきあい方の変化がはっきり刻まれている。
その意味で、『E.T.』は単に“子供映画の金字塔”というだけでなく、スピルバーグ史の中で「光のピーク」であり、同時に「そこから先へ進めなくなる限界点」でもある。
『太陽の帝国』がその限界を意識化し、『フック』(1991年)が“永遠の子供ではいられない”という自己言及的な物語を通じて“白いスピルバーグ”との決別を宣言する。そこから先に、『シンドラーのリスト』や『ミュンヘン』(2005年)といった“黒いスピルバーグ”の時代が続いていく。
振り返ってみると、『ジョーズ』で子供を容赦なくサメの餌食とし、『未知との遭遇』で父親を宇宙船へ送り出し、『E.T.』で子供と異星人の友情を世界共通の寓話へ翻訳し、『太陽の帝国』で戦争が子供の内面を変質させる様を描いた──そうした一連の作品は、すべて「子供が世界とどう接続されるか」をめぐる変奏でもあった。
かつてスピルバーグにとって子供は“未知へのアクセス装置”だったが、『E.T.』以降、その装置はあまりにもよく機能しすぎて、世界標準のエモーションを供給するシステムになってしまった。
だからこそ彼は、カミンスキーとの出会いを足がかりに、今度は“大人として歴史の暗闇を見る映画”へと舵を切らざるを得なかったのだ。
『E.T.』は、そうした長いスピルバーグ史のなかで、ひとつの眩しい通過点として立っている。子供の神秘を祝福しつつ、その神秘を商品として使い切ってしまった映画。
だからこそ、この作品は単なるノスタルジーではなく、“白い/黒いスピルバーグ”という二つの像を往復しながら、何度でも語り直す価値があるのだ。
- 原題/E.T. The Extra Terrestrial
- 製作年/1982年
- 製作国/アメリカ
- 上映時間/115分
- ジャンル/SF、ヒューマン
- 監督/スティーヴン・スピルバーグ
- 脚本/メリッサ・マシスン
- 製作/スティーヴン・スピルバーグ、キャスリーン・ケネディ
- 撮影/アレン・ダヴィオー
- 音楽/ジョン・ウィリアムズ
- 編集/キャロル・リトルトン
- 美術/ジェームズ・D・ビッセル、フランク・マーシャル
- SFX/デニス・ミューレン
- ディー・ウォーレス
- ヘンリー・トーマス
- ロバート・マクノートン
- ドリュー・バリモア
- ピーター・コヨーテ
- K・C・マーテル
- ショーン・フライ
- トム・ハウエル
- エリカ・エレニアック
- レイダース/失われたアーク《聖櫃》(1981年/アメリカ)
- E.T.(1982年/アメリカ)
- ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク(1997年/アメリカ)
- アミスタッド(1998年/アメリカ)
- プライベート・ライアン(1998年/アメリカ)
- マイノリティ・リポート(2002年/アメリカ)
- ミュンヘン(2005年/アメリカ)
- インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国(2008年/アメリカ)
- タンタンの冒険 ユニコーン号の秘密(2011年/アメリカ)
- リンカーン(2012年/アメリカ)
- レディ・プレイヤー1(2018年/アメリカ)
- ウエスト・サイド・ストーリー(2021年/アメリカ)

![E.T. [Blu-ray]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/51YCjb0tLxL._AC_-e1758175514300.jpg)