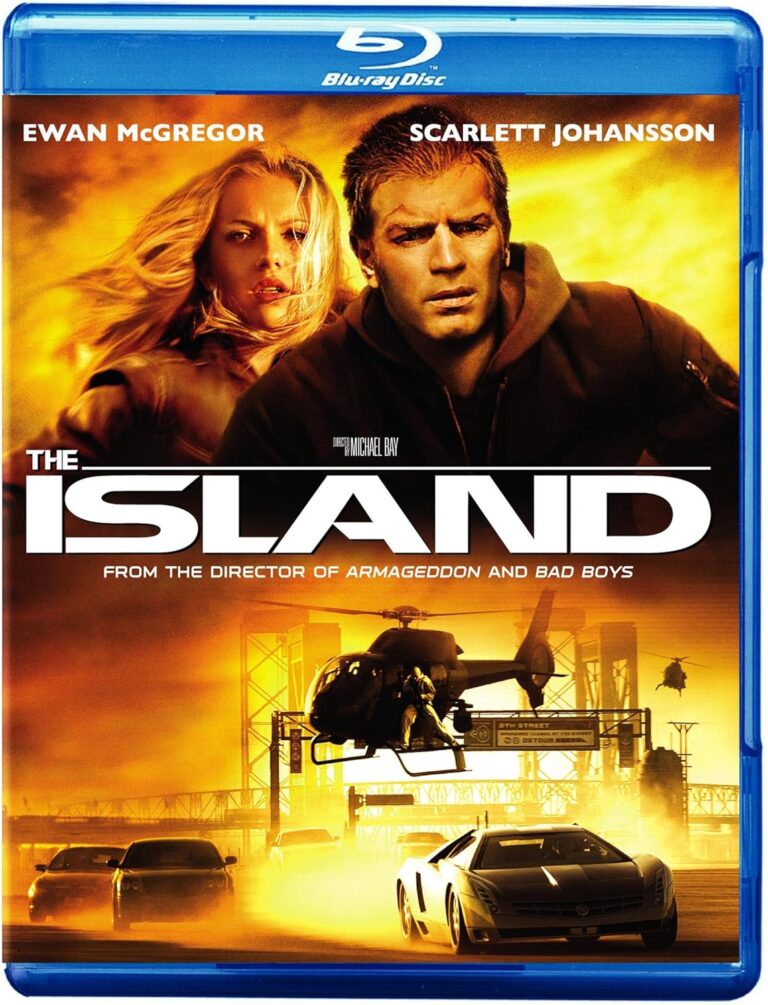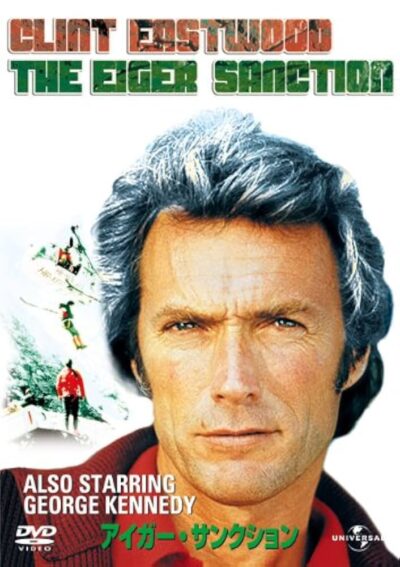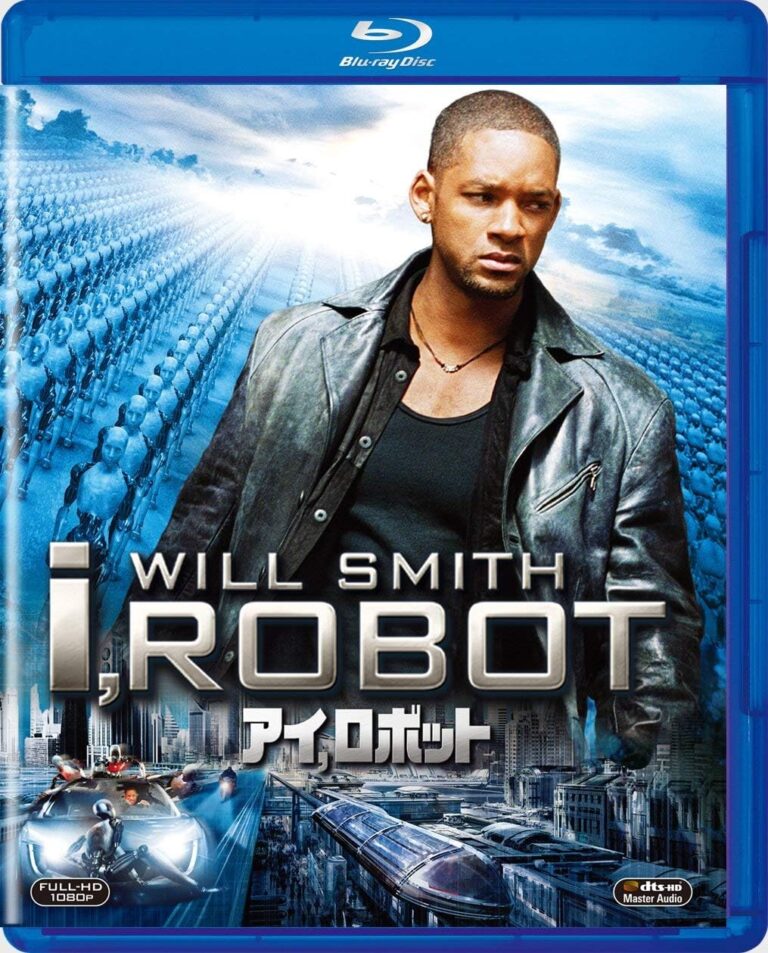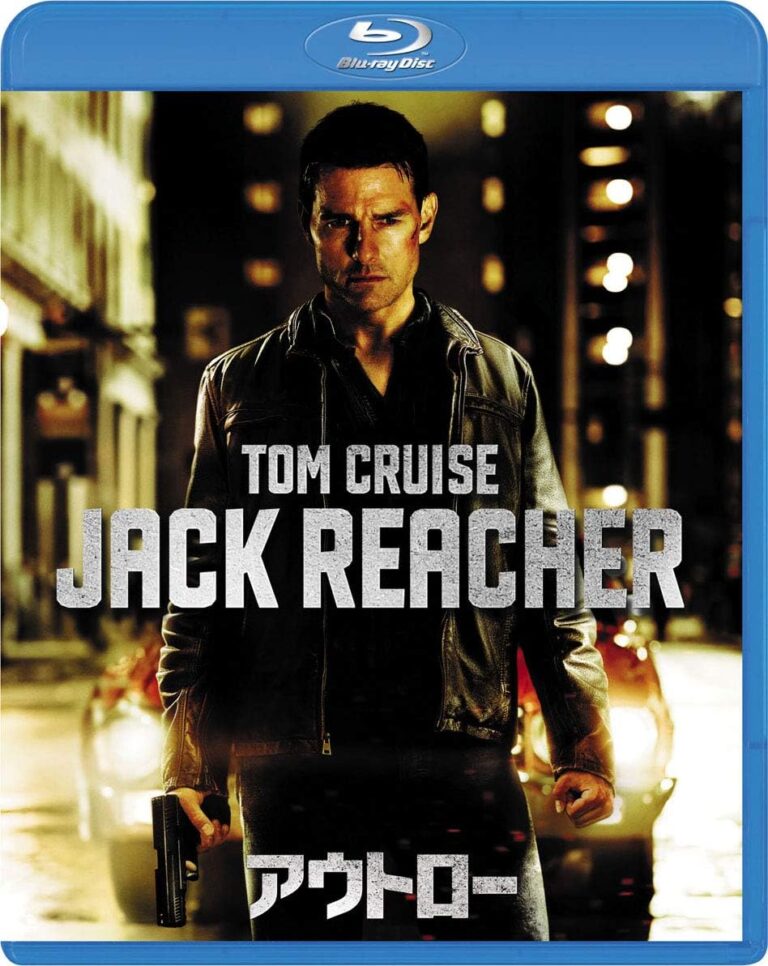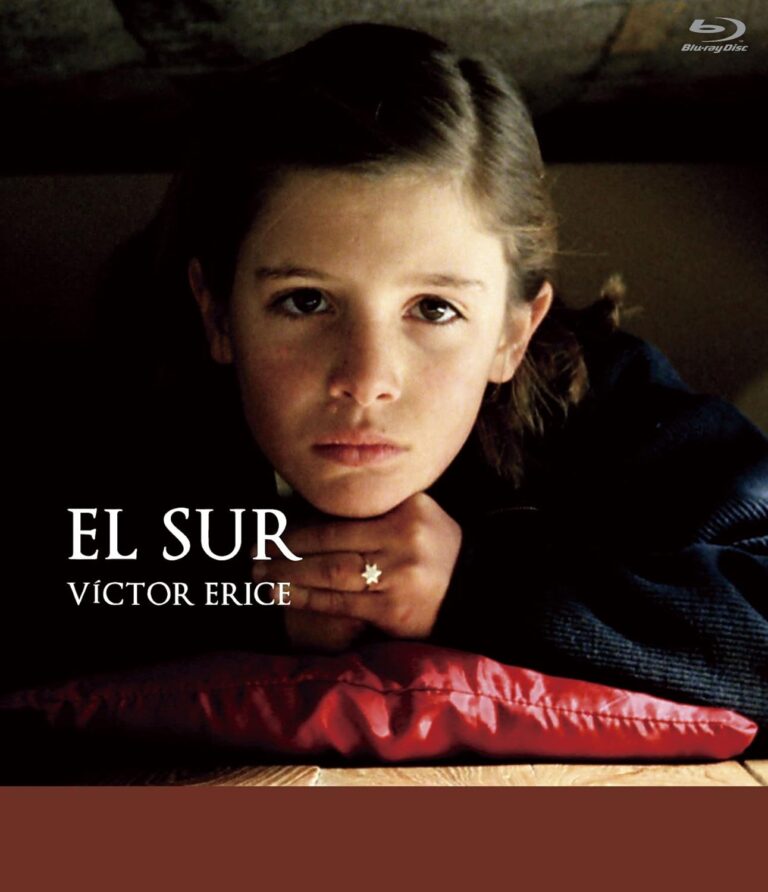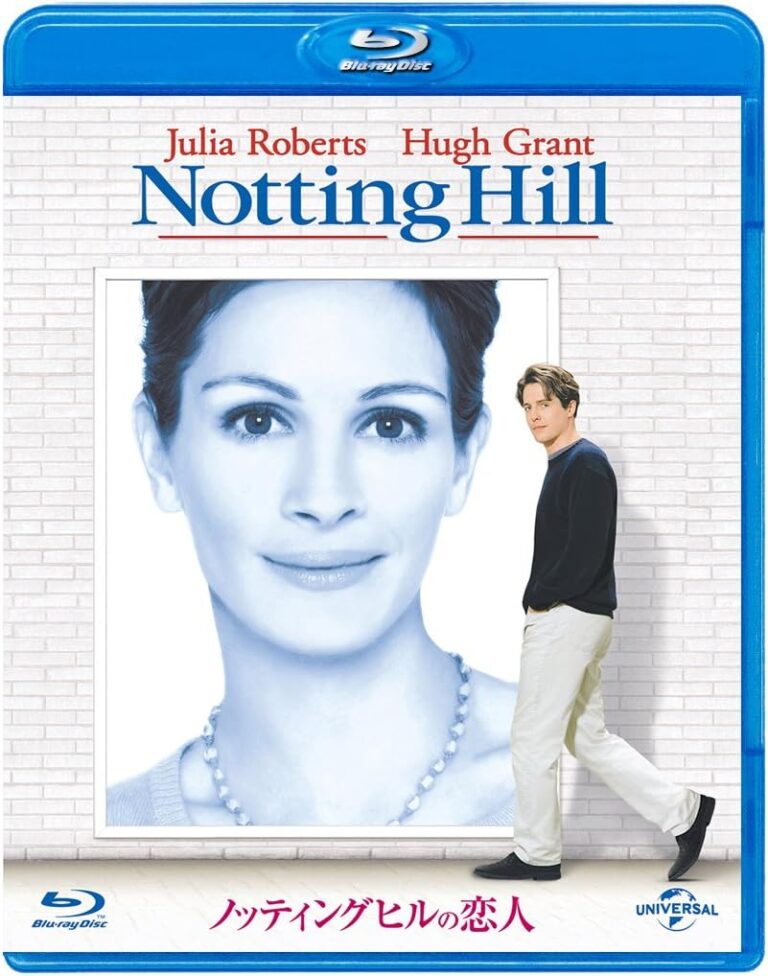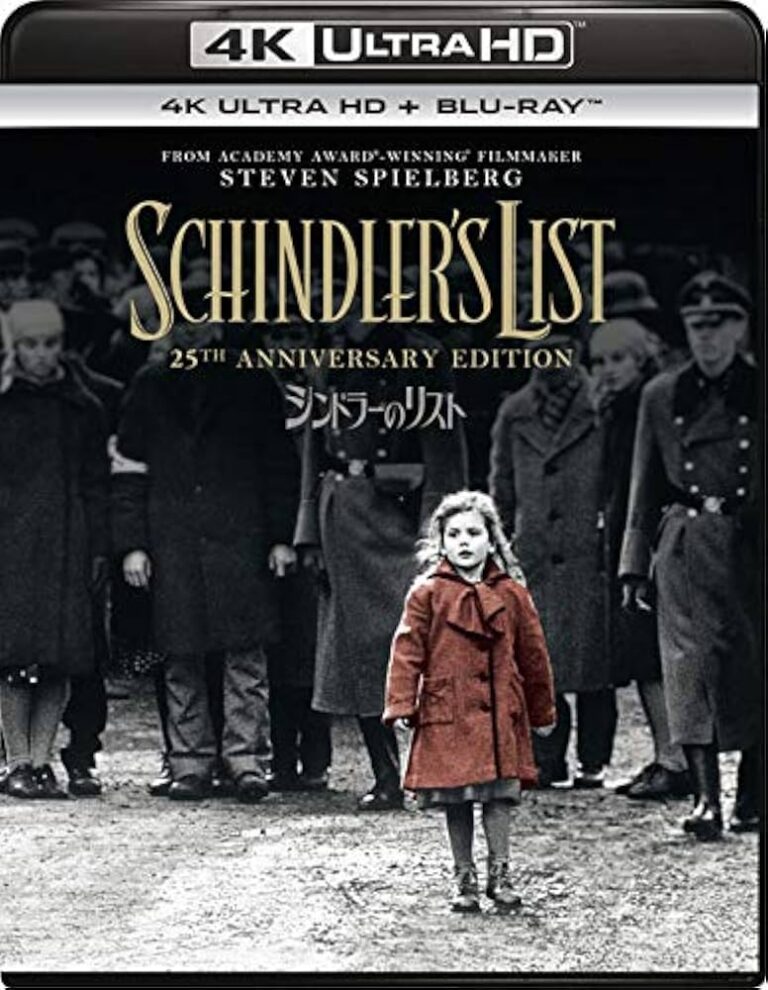『レオン』(1994)
映画考察・解説・レビュー
『レオン』(原題:Léon: The Professional/1994年)は、孤独な殺し屋レオン(ジャン・レノ)と、家族を失った少女マチルダ(ナタリー・ポートマン)の出会いを描く物語。犯罪と日常、暴力と愛が交錯するニューヨークの街で、二人は共に逃避行を続ける中で互いの存在に救われていく。滅びを運命づけられた関係が、破滅の中に一瞬の輝きを放つ。
硝煙とミルクの匂いが混ざり合う、90年代が生んだ奇跡
「凶暴な純愛」。このあまりにも有名なキャッチコピーは、『レオン』(1994年)という映画が内包する倒錯的かつロマンティックな罠を、恐ろしいほど正確に言い当てている。
リュック・ベッソンは、すでに前作『ニキータ』(1990年)で、社会システムから逸脱した個人の悲哀と、暴力の中に咲く徒花のような純粋さを描いていた。
だが、この『レオン』において、彼はそのアクセルを床まで踏み抜く。愛と暴力。本来であれば対極にあるはずの二つのベクトルが、まったく同じ方向を向いて噴出する瞬間を、我々は目撃することになる。
まず耳を劈くのは、エリック・セラの音楽だ。あの金属的で、どこか地下鉄の風圧を感じさせるような不穏なスコアが、観る者の皮膚をヒリヒリと焦がしていく。
そして、名手ティエリー・アルボガストのカメラワーク。彼のレンズを通すと、血なまぐさい銃撃戦さえもが、ある種の「抱擁」へと変貌を遂げるから不思議だ。
弾丸が肉体を貫く衝撃と、愛する者を抱き寄せる強さが、映像の中で等価交換されているかのような錯覚。アクション映画の文法を使いながら、そこで描かれているのはアクションではない。弾丸が交錯する空間に立ち上がっているのは、あまりにも切実で、混濁した「祈り」なのだ。粗暴さと繊細さが悪魔合体したようなその温度感こそが、この映画だけが持つ特有の“逆説”を生み出していると言っていい。
舞台となるニューヨークは、生き馬の目を抜くような戦場でありながら、同時にレオンとマチルダにとって、誰にも邪魔されない「子ども部屋」でもある。
コンクリートジャングルの無機質さの中に、ミルクの白さや観葉植物の緑といった、妙な「柔らかさ」が紛れ込む。この視覚的なギャップが、物語全体のワールドラインを決定づけている。
我々観客がなぜ、これほどまでに胸を締めつけられるのか? それは、レオンとマチルダの関係が、始まった瞬間から「消滅」を孕んでいることを直感的に理解してしまうからだ。
殺し屋と少女。その組み合わせ自体が社会的な倫理コードの完全に外側に位置しており、彼らが手を取り合って安全圏へ到達する未来など、どうあがいても想像できない。
破滅は約束されている。それでもなお、我々はスクリーンを見つめながら、かすかな希望の影を必死でつかみ取ろうとしてしまうのだ。
二人がミルクを飲み、不器用にリハビリをするかのように植木鉢を移し替える短い時間。それは、死へと向かう滑走路の上に奇跡的に出現した、小さな楽園(エデン)だ。
ベッソンはこのハッピー・サッドな振幅を意図的に、残酷なほど長く引き伸ばす。観客を、居心地の良さと破滅の予感が同居する、静かな緊張状態に閉じ込めるために。
レオンが見せる微かな微笑には、単純な幸福よりも、死を受け入れた者だけが持つ「覚悟」が宿っている。終盤、彼が廊下を歩くテンポは、すでに自身の運命を飲み込んだ者のそれだ。
純愛が暴力へと転化し、暴力が祈りへと滑り込むあの一瞬に、映画そのものが息を止める。これほど美しい窒息体験が、他にあるだろうか?
20世紀最後のシネマ・ロリータ、あるいは聖母
間違いなく、ナタリー・ポートマンという存在がいなければ、この映画は成立しなかった。いや、作品の条件そのものが彼女だったと言っても過言ではない。
撮影当時12歳。単なる子どもではないし、かといって小さな大人という陳腐な言葉でも片付けられない。彼女は、“子ども”と“成熟”の境界線を、パスポートも持たずに自在に横断してみせる。
かつてブルック・シールズが体現した「子どもの身体に大人の魂」という背徳的な図式を超え、マチルダの眼差しには、あろうことか「母性」までもが滑り込んでいる。
レオンという、社会的には大人だが精神的には発育不全の男。彼を守られる対象(子ども)として扱いながら、同時に彼を包み込む聖母のような存在としても君臨する。
この「保護者であり、被保護者でもある」という複雑怪奇な二重性こそが、『レオン』を単なるロリータ的倒錯の物語から引きはがし、一種の聖性へと押し上げているエンジンなのだ。
もちろん、2020年代以降の視座、いわゆるコンプライアンスやポリティカル・コレクトネスのフィルターを通せば、その危うさは無視できないノイズとして浮上する。
ポートマン本人ですら、近年のインタビューで「複雑な心境だ」「今見ると居心地が悪い部分もある」と吐露している通り、かつてはロマンとされた描写が、現代では深刻な倫理的問いを招いてしまうことも事実だ。その危うさを含めて記録されていることこそが、映画というメディアの業ともいえる。
そして、この奇妙なバランスを支えているのが、ジャン・レノの圧倒的な感情の不器用さだ。身長190センチ近い巨体に、丸いサングラスとニット帽。
暴力というコミュニケーション手段しか持たない殺し屋でありながら、彼が住むアパートの一室は、まるで独りぼっちの子ども部屋のような寂寥感を湛えている。
彼が飲むミルク、大切に拭く観葉植物の葉。それらのアイテムに滲むのは、レオン自身の幼さだ。彼が発する沈黙がこれほどまでに詩的に響くのは、その肉体に強さと脆さという矛盾が刻み込まれているからに他ならない。
そこへ、劇薬として投入されるのがゲイリー・オールドマン演じるスタンフィールドだ。彼はこの映画の均衡を破壊するために召喚された、「暴力化した芸術」の象徴である。
ベートーヴェンを浴びるように聴きながら、恍惚の表情で殺戮を行うその姿。あれはもう、演技というよりは憑依、あるいはカルト的な儀式だ。
「エヴリワン!!」と絶叫するシーンの、あの歪んだ顔面を見よ! 彼の演技は映画のリアリティラインを激しく揺さぶり、物語を漫画的な領域へと引きずり込もうとする。
だが、そのオールドマンの「過剰さ」が作品世界を一度破壊することで、逆にレオンとマチルダの静謐な世界が際立つという、とんでもない構造バグが発生しているのだ。
彼の狂気が高まれば高まるほど、二人の純愛はより透明度を増していく。まさに役者同士のケミストリーが起こした奇跡と言えるだろう。
“愛の銃弾”が撃ち抜いたもの
映画ファンならご存知だろうが、この作品には一般公開されたアメリカ版と、後に公開された長尺の「完全版(インターナショナル版)」が存在する。
この完全版には、マチルダがレオンの仕事に同行して訓練を受けるシーンや、命を賭けたロシアンルーレット的な「愛か死か」の遊び、そしてマチルダがレオンに「一緒に寝て」と迫る、極めて際どいシーンが収録されている。
これらは二人の関係性をより濃密に、より共依存的なものとして描写する一方で、ロリータ性への批判を呼び起こす火種にもなった。アメリカ公開時にこれらのシーンがバッサリとカットされたのは、当時の倫理コードや、試写会での観客の反応(ドン引きされたという逸話もある)を考慮したマーケティング上の「安全策」であったことは疑いようがない。
この編集の違い、そして文化による受容の差こそが、そのまま『レオン』という作品が孕む「危うさ」を測るリトマス試験紙になっている。さらに言えば、近年における監督リュック・ベッソン自身への告発やスキャンダルは、作品と作家の人格を切り離して評価することを難しくし、我々に映画の「読み直し」を強制するようになった。「傑作だが、問題作」。そんなレッテルが貼られることも増えた。
それでもなお、この作品が映画史の中心にドカっと居座り続けている理由は明白だ。それは、ラストシーンに集約されている。マチルダが学校の庭に植えるあの鉢植え。あれは単なる植物ではない。レオンの墓標であり、同時に、根無し草だった彼の愛が、ついに大地に根を張ったことの証明なのだ。
暴力しか知らなかった男の人生が、少女の手によって「生」へと変換される。死んで終わりではない。その魂が循環していくというこの転換こそが、本作に永遠性を与えている。
制作費は中規模、公開当時の興行収入も決して記録的な大ヒットというわけではなかった。だが、ビデオ、DVD、配信とメディアが変わるたびに、新たな世代に見つかり、熱狂的に支持され続けてきた。いわゆるロングテールの極みである。
時代が変わろうと、倫理観がアップデートされようと、孤独な魂同士が寄り添う姿には、理屈を超えた引力がある。「純愛」とは、時に社会への挑発であり、既存の価値観の破壊であり、そして切実な祈りでもあること。それを教えてくれる教科書として、『レオン』は機能し続けている。
エンドロールで流れるスティングの「Shape of My Heart」が聴こえてくる頃、我々は確信する。この映画は、古びないのではない。そのあまりの純度の高さゆえに、時間の風化作用を受け付けないのだと。
『レオン』は、その「凶暴な純愛」という一点突破だけで、永遠に若いままなのである。
- 原題/Leon
- 製作年/1993年
- 製作国/フランス、アメリカ
- 上映時間/111分
- ジャンル/アクション
- 監督/リュック・ベッソン
- 脚本/リュック・ベッソン
- 製作総指揮/クロード・ベッソン
- 撮影/ティエリー・アルボガスト
- 音楽/エリック・セラ
- 編集/シルヴィ・ランドラ
- 美術/ダン・ウェイル
- ジャン・レノ
- ナタリー・ポートマン
- ゲーリー・オールドマン
- ダニー・アイエロ
- ピーター・アペル
- マイケル・バダルコ
- エレン・グリーン
- サミー・ナセリ
- レオン(1993年/フランス、アメリカ)

![レオン/リュック・ベッソン[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/81q2-Jr72yL._AC_SL1500_-e1707309053993.jpg)
![ニキータ/リュック・ベッソン[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/61x8g2cE9SL._AC_UL640_FMwebp_QL65_-1-e1768200949696.webp)