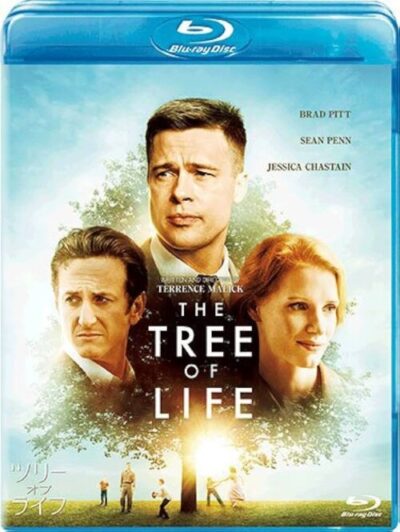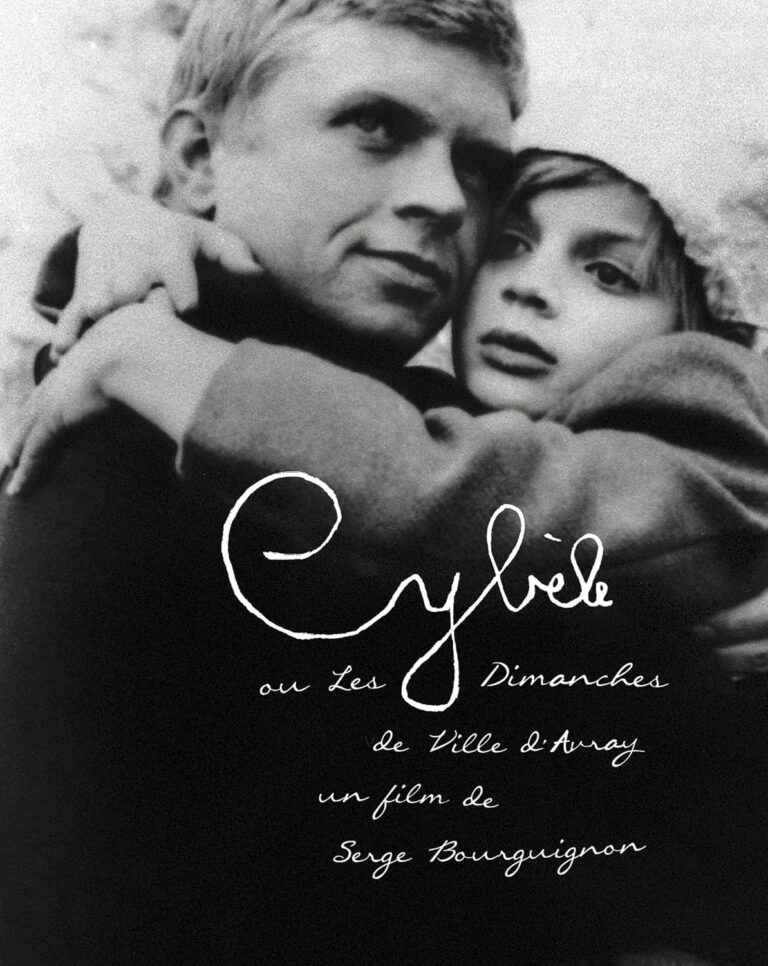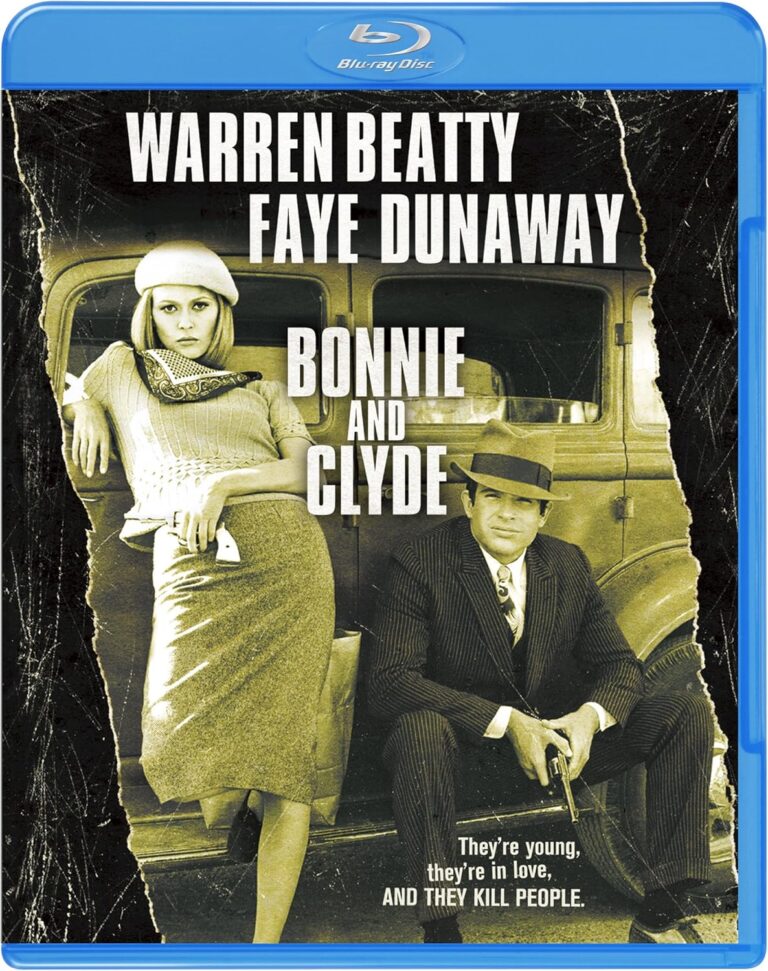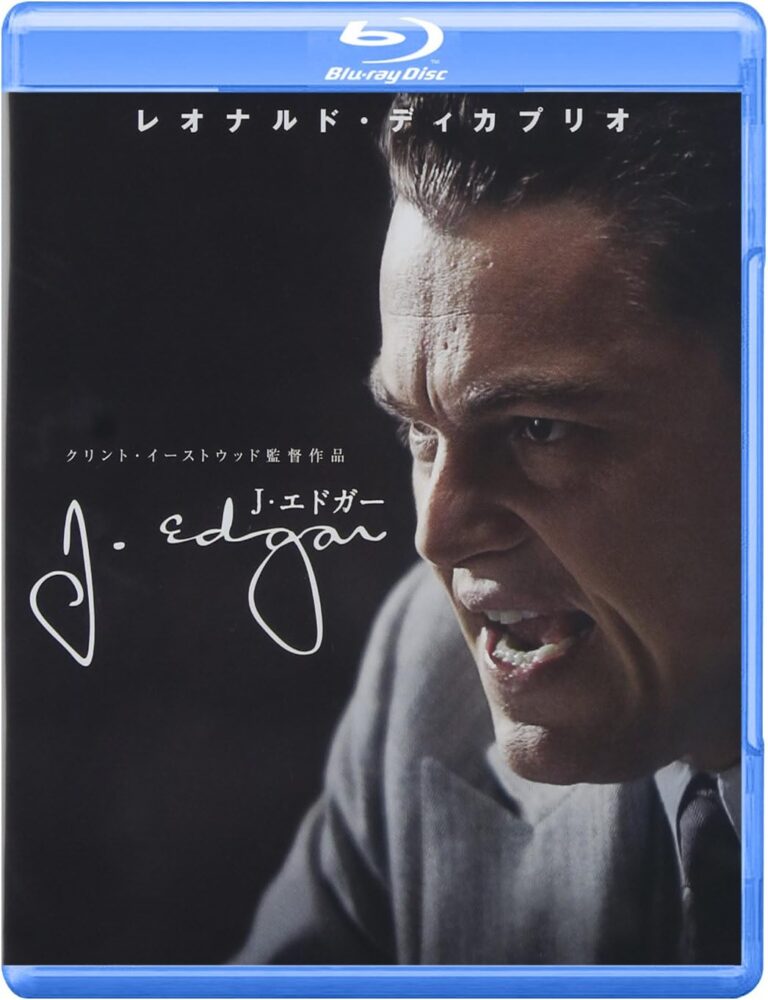『ザ・ピーナッツバター・ファルコン』(2019)
映画考察・解説・レビュー
『ザ・ピーナッツバター・ファルコン』(原題:The Peanut Butter Falcon/2019年)は、養護施設を脱走しプロレスラーを目指すダウン症の青年ザックと、兄を亡くし逃亡中の漁師タイラーの旅を描いたロードムービー。主演のザック・ゴッツァーゲン自身の人生を投影した脚本は、シャイア・ラブーフやダコタ・ジョンソンといった実力派俳優たちを惹きつけ、彼らがノーギャラに近い形で出演を熱望したことで実現。マーク・トウェインの古典的名作を現代のジョージア州へと移植した物語は、インディーズ作品ながら口コミで全米を席巻し、2019年度の単館系映画として最大のヒット作となった。
スコープサイズを選んだ理由
映画には時として、理屈や分析をすべて置き去りにして、ただ「その瞬間の美しさ」だけで観客の涙腺を決壊させる魔力が宿ることがある。『ザ・ピーナッツバター・ファルコン』(2019年)は、まさにそんな魔法がかかった一本だ。
ポスターを見れば、ダウン症の青年と荒くれた漁師の逃避行という、いかにも「心温まるヒューマンドラマ」的な装いをしている。だがこの映画の正体は、映画製作の常識をすべてぶん投げ、人生を賭けた男たちが作り上げた、「パンク・ロック」な魂の結晶なのだ。
まず、映画冒頭から映画ファンの脳裏にはある「違和感」が浮かぶはず。それは画面のアスペクト比だ。本作は、ダウン症の青年ザック、逃亡中の漁師タイラー、そして彼らを追う看護師エレノアという、たった三人の登場人物の心の交流を描く、極めてミニマムな人間ドラマ。
通常、こうした親密な物語を撮るなら、キャラクターの表情に寄り添いやすいビスタサイズ(1.85:1)や、あるいは閉塞感を強調するスタンダードサイズ(4:3)を選ぶのがセオリーだろう。
ところが、監督のタイラー・ニルソンとマイケル・シュワルツは、あえて横に長いシネマスコープサイズ(2.39:1)を選択した。たった三人の徒歩旅行を撮るのに、そんな広大なキャンバスが必要なのか?と、最初は誰もが首をかしげるだろう。
だが、物語中盤、その疑問は稲妻に打たれたように氷解することになる。ダコタ・ジョンソン演じるエレノアの長く美しい髪が、風に煽られて真横になびくショット。その髪は、画面の端から端まで優雅に流れていく。
謎は解けた!おそらくこのスコープサイズは、アメリカ南部の湿地帯を支配する「空気」や「風」、そして彼らを取り巻く世界の「広大さ」そのものを捉えるための器だったのだろう。
もしこれがビスタサイズなら、なびく髪は画面の外に切れてしまう。あの横長のフレームがあったからこそ、彼女の髪は自由の象徴として、その美しさを完全な形で我々の網膜に焼き付けることができたのだ。
この一瞬の映像美へのこだわりこそが、本作を単なるインディーズ映画から、普遍的なクラシック映画の風格へと押し上げている最大の要因なのではないか。
ただ「一人の俳優の夢」に賭けた狂気の制作秘話
この映画の凄みは、画面の中だけではない。むしろ、カメラの外で起きていたドラマこそが、本作を「奇跡」と呼ぶにふさわしいものにしている。
すべては、主演俳優ザック・ゴッツァーゲンの「一言」から始まった。監督二人は、障害者のためのキャンプで当時無名だったザックと出会う。「映画スターになりたい」と語るザックに対し、監督たちは残酷な現実を告げる。「ハリウッドには、ダウン症の俳優が主演できる脚本なんて存在しないんだよ」。
普通の人間ならここで諦めるだろう。しかし、ザックは違った。「だったら、君たちが僕のために書いてよ。僕らだけでやればいいじゃないか!」。
この純粋で強烈な直談判に心を撃ち抜かれた監督たちは、なんと自分たちの家を引き払い、テントや車で寝泊まりするホームレス同然の極貧生活を送りながら、脚本を書き上げた。
さらにドラマは続く。完成した脚本を持って資金集めに奔走した彼らに、あるプロデューサーから悪魔の囁きが届く。「素晴らしい脚本だ。主演を有名な(ダウン症ではない)俳優に替えるなら、数百万ドルの予算を出そう」。
喉から手が出るほど金が必要な状況。テント生活から抜け出し、安定した制作環境を手に入れるチャンスだ。だが、彼らは即答で拒否。「ザックが主演でなければ、この映画を作る意味がない」。
彼らは「感動的な映画を作って儲けよう」としたのではない。「ザックという友人の夢を叶える」ためだけに、人生のすべてをベットしたのだ。この狂気じみた純粋さが、フィルムの端々にまで浸透しているからこそ、本作は決して説教臭くならず、ただひたすらに熱く、優しい。
その熱量は、共演者であるシャイア・ラブーフにも伝染した。当時、シャイアは私生活でのトラブル続きで、ハリウッドの問題児としてキャリアのどん底にいた。
彼が演じるタイラーもまた、過去の過ちから逃げる男。撮影中、あろうことかシャイアは現地で酒気帯び運転による逮捕劇を起こしてしまう。「映画が終わるかもしれない」という最悪の空気の中、釈放された彼を待っていたのは、怒りに震えるザックだった。
「君はもう有名なスターだろう。でも僕はこれが初めてのチャンスなんだ。僕の夢を台無しにしないでくれ!」。ザックのこの魂の叫びが、シャイアの目を覚まさせた。彼はその日から酒を断ち、撮影に没頭したという。
劇中でタイラーとザックが心を通わせていくプロセスは、演技ではない。あれは、傷ついた二人の男が、現実世界で互いを救済し合っていくドキュメンタリーそのもの。だからこそ、二人が焚き火を囲むシーンには、どんな名優の演技も及ばない「本物の親密さ」が宿っているのである。
現代版ハックルベリー・フィンの冒険
本作を批評的に語る上で外せないのが、マーク・トウェインの名作『ハックルベリー・フィンの冒険』へのオマージュと、障害の描き方における革新性だ。
従来の映画では、障害者はしばしば「守られるべき無垢な天使」や「健常者が優しさを学ぶための道具」として描かれがちだった。だが、この映画のタイラーは、ザックを絶対に子供扱いしない。彼にショットガンの撃ち方を教え、ウイスキーを飲ませ、危険なイカダ旅に連れ出す。
エレノアが「彼はそんなことできない、危ない」と制止すると、タイラーはこう言い放つ。「あんたは彼をかわいがることで、彼の能力を奪っているんだ」と。
これこそが、本作の核心!過剰な保護は、時としてその人の可能性や「失敗する権利」さえも奪ってしまう。タイラーとザックの関係は、父と子でもなければ、保護者と被保護者でもない。対等なブラザー(兄弟)なのだ。
物語の終盤、ザックが憧れのプロレスラーとリングで対峙するシーンについて、「リアリティがない」「あんな体格差で勝てるわけがない」と批判する批評家もいた。
だがこの映画は、物理法則に基づいたドキュメンタリーじゃない。ザックが見ている「世界はこうあってほしい」という願いを具現化した、現代の神話なのだ。
ザックが必殺技「アトミック・スロー」で巨漢を投げ飛ばすとき、単に相手レスラーを倒しているのではなく、彼を「施設」という鳥籠に閉じ込め、「お前には無理だ」と決めつけてきた社会の偏見そのものを、リングの外へ放り投げている。
あの瞬間、映画はリアリズムを超越し、純粋なカタルシスへと昇華される。「ご都合主義」と切り捨てるのは、映画という芸術が持つ「夢を見る力」を否定する野暮な行為でしかないだろう。
結局のところ『ザ・ピーナッツバター・ファルコン』とは、持たざる者たちが集まり、互いの欠落を埋め合わせながら、「ルールその1:パーティー!」を合言葉に人生を祝福するロードムービーだ。
ダコタ・ジョンソンの髪が風になびく、あの美しすぎる瞬間、僕たちは理屈抜きで理解する。「ああ、彼らは自由なんだ」と。スコープサイズの広い広い画面は、彼らの行く手に待っている未来の広さそのものだ。
- 監督/タイラー・ニルソン、マイケル・シュワルツ
- 脚本/タイラー・ニルソン、マイケル・シュワルツ
- 製作/ロン・イェルザ、アルバート・バーガー、クリストファー・ルモール、ティム・ザジャロフ、リイェ・サルキ、デヴィッド・ティース
- 製作総指揮/マニュ・ガルギ、アーロン・スコッティ、ティモシー・シュライヴァー、アンソニー・K・シュライヴァー、ミシェル・シー・ウィッテン、カーメラ・カシネリ
- 撮影/ナイジェル・ブラック
- 音楽/ザカリー・ドーズ、ジョナサン・サドフ
- 編集/ナット・フラー、ケヴィン・テント
- 美術/ガブリエル・ウィルソン
- 衣装/メリッサ・ウォーカー
- ザ・ピーナッツバター・ファルコン(2019年/アメリカ)
![ザ・ピーナッツバター・ファルコン[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/81iYZWb-m7L._AC_UL640_FMwebp_QL65_-e1764897490888.webp)
![ハックルベリー・フィンの冒けん/マーク・トウェイン (著)、柴田元幸 (翻訳)[本]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/71hQ5maj0NL._AC_UL640_FMwebp_QL65_-e1768182895330.webp)