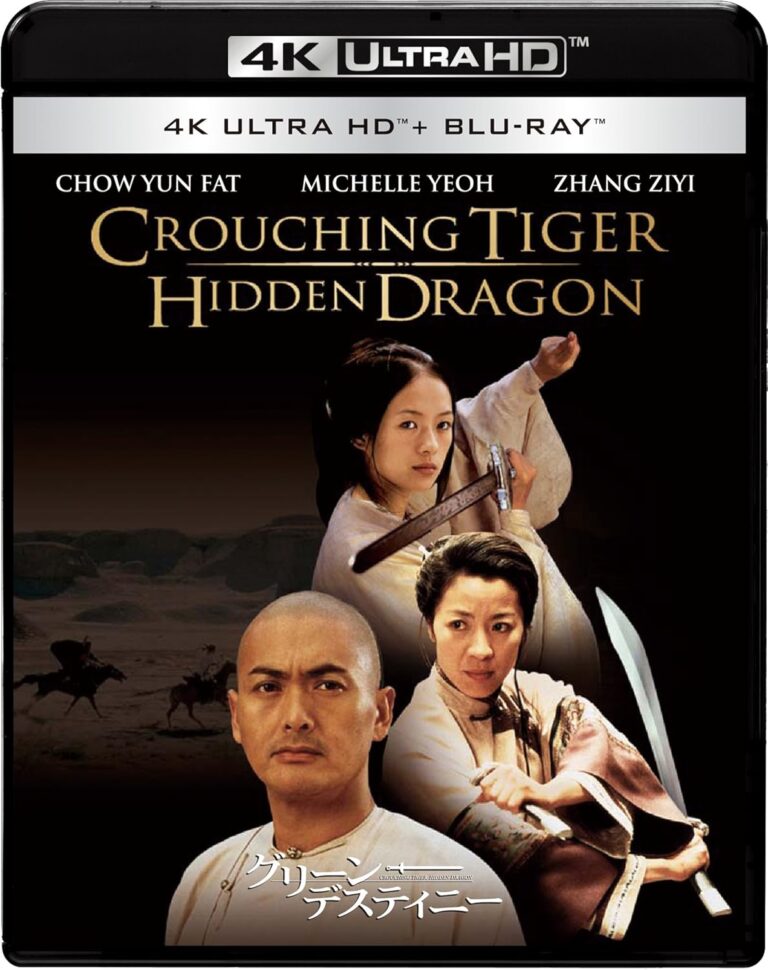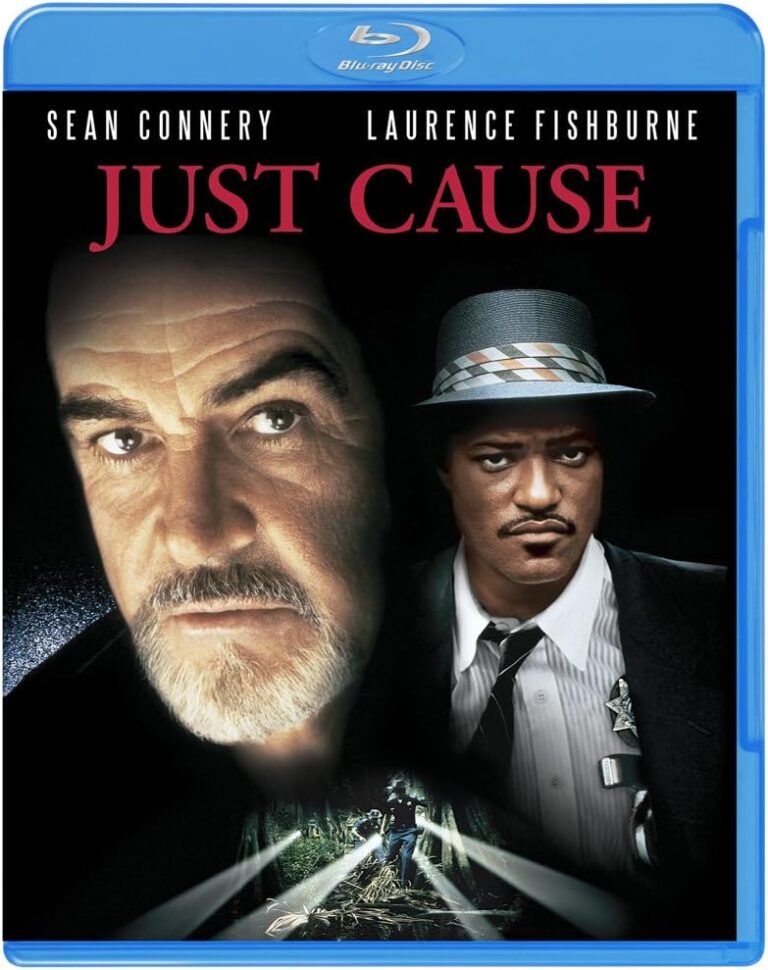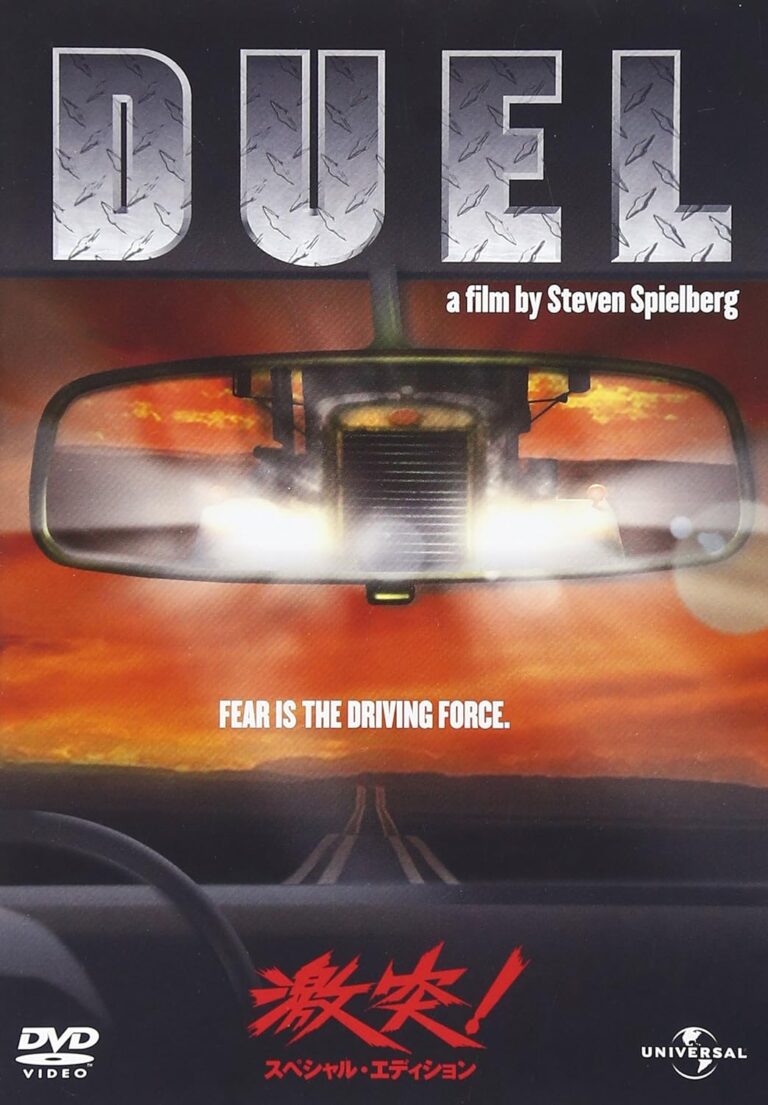『気狂いピエロ』──色彩と快楽のモンタージュ
『気狂いピエロ』(原題:Pierrot le Fou/1965年)は、ジャン・リュック・ゴダール監督がベルモンドとアンナ・カリーナを主演に迎えた逃避行の物語である。退屈な日常に飽いたフェルディナンが、恋人マリアンヌとともに犯罪に手を染め、海辺をさまよう。旅の果てで二人は裏切りと破滅を迎えるが、そこに描かれるのは愛でも絶望でもなく、色彩と音楽の奔流による自由の幻影である。
ポスト・モダンとしてのゴダール──理屈を超えた映画的存在
ポスト・モダン、ヌーヴェルヴァーグ、政治、ソニマージュ──。
ジャン・リュック・ゴダールという名のもとに無数のキーワードが渦を巻く。しかしそれらは、古典的映画文法に慣れ親しんだ私たちが、ゴダールという“異物”を理解するための仮設装置にすぎない。
彼の映画を観るためには、論理ではなく、感性の可塑性が求められる。観客は柔らかく、しなやかでなければならないのだ。
デビューから半世紀を経た今なお、その本質が掴みがたい映画作家ジャン・リュック・ゴダールとは何者か。ある音楽評論家は「音楽を聴くようにゴダールを観よ」と言い、鈴木慶一は「何だかわかんないけどカッコイイ」と評した。
まさにそれこそが正鵠を射ている。アンディ・ウォーホルのキャンベル・スープ缶を前に、意味よりも質感を味わうように。ゴダールは理屈ではなく、感覚で咀嚼されるべき作家なのだ。
『気狂いピエロ』の快楽原則──生理と詩情のあいだで
『気狂いピエロ』(1965年)は、その快楽原則のもっとも純粋な結晶だろう。ベルモンドの奔放な存在感、アンナ・カリーナの愛らしさ、そして全編を貫くリズミカルな編集は、PV的感覚で疾走する。観ていて“気持ちがいい”映画──それこそが本作の本質だ。
多くの映画が〈面白さ〉や〈感動〉を志向するのに対し、『気狂いピエロ』は〈気持ちよさ〉を目的とする。音楽的構造、映像的リズム、カットの呼吸までもが、生理的快楽の波動として観客に届く。
ゴダール自身が語った「映画は万人のためのものではない」という言葉は、この作品の根底を流れるエゴイスティックな美学の宣言である。
ライオネル・ホワイトの犯罪小説『オブセッション』を下敷きにした物語は、男女の逃避行という単純な枠を持ちながら、その内実は反物語的である。フェルディナンとマリアンヌは愛し合い、裏切り、現実と幻想のあわいを漂流する。
だがその逃避は悲劇でも冒険でもなく、“日常の一断片”として描かれる。JLGのカメラは、刹那の破滅すらも日常に吸収してしまうのだ。
そこには政治の比喩も潜む。ベトナム戦争を風刺する芝居の挿入や、ニュース映像の断片は、世界と映画の境界を溶解させる装置として機能する。
だがそれらは決して説教的ではない。政治すらもゴダールの映画では〈形式〉の一部に還元される。彼の革命は叫びではなく、スタイルそのものの中にある。
“色”のモンタージュ──赤と青の詩学
『気狂いピエロ』の最大の発明は、色彩が物語を超えて“意味を持つ”瞬間にある。赤と青という原色が画面全体を支配し、映像を構成するリズムとして機能している。
ラストシーン、フェルディナンが顔に青いペンキを塗り、ダイナマイトで自爆。カメラはその青を引き継ぐように地中海の深い青へパンしていく。色が論理的に連鎖し、死が“色のモンタージュ”として表現される。
この〈青の継承〉こそ、ゴダールの映画が言葉ではなく、視覚的記号で構築されている証だ。 赤は情熱と血、青は理性と静寂。その二つが衝突し、混ざり合い、やがて白い光に溶けていくとき、映画は宗教画的な美しさを帯びる。
『気狂いピエロ』は、恋愛映画の形式を借りた“色彩の神話”である。
理屈の外側で──ゴダール的快楽主義の系譜
ランボーの詩の引用、海辺での歌唱『私の運命線』、不条理劇としての戦争風刺。これらすべてが知的でありながら、同時に感覚的だ。ゴダールは思索家であると同時に、快楽主義者である。彼の映画は「考える映画」である前に、「感じる映画」なのだ。
観客に求められるのは、理解ではなく共振。彼の映像が放射するオーガズムをただ浴び、彼とともに恋し、嫉妬し、絶望すればよい。理屈はその後に来る。
『気狂いピエロ』は、映画という言語が“意味”を手放したときに到達しうる、最初の歓喜であり、最後の祈りである。
- 原題/Pierrot Le Fou
- 製作年/1967年
- 製作国/フランス、イタリア
- 上映時間/109分
- 監督/ジャン・リュック・ゴダール
- 脚本/ジャン・リュック・ゴダール
- 原作/ライオネル・ホワイト
- 音楽/アントワーヌ・デュアメル
- 製作/ジョルジュ・ド・ボールガール、ディノ・デ・ラウレンティス
- 撮影/ラウール・クタール
- 美術:ピエール・ギュフロワ
- ジャン・ポール・ベルモンド
- アンナ・カリーナ
- グラツィエッラ・ガルヴァーニ
- レイモン・ドボス
- ダーク・サンダース
- ジミー・カルービ
- ロジェ・デュトワ
- ハンス・メイヤー
- アレクシアス・ポリアコフ