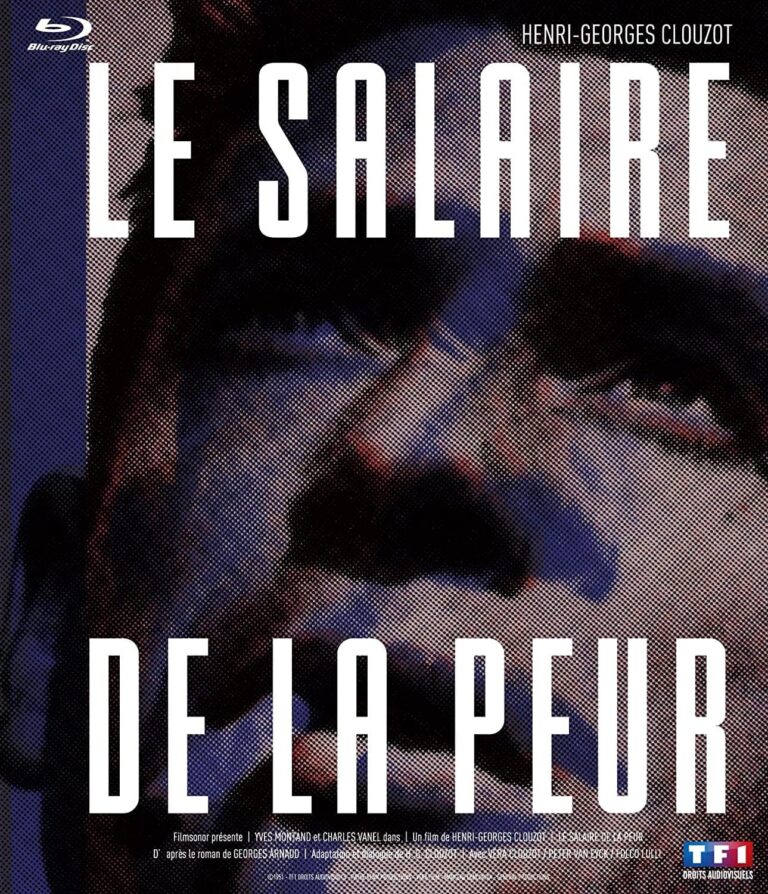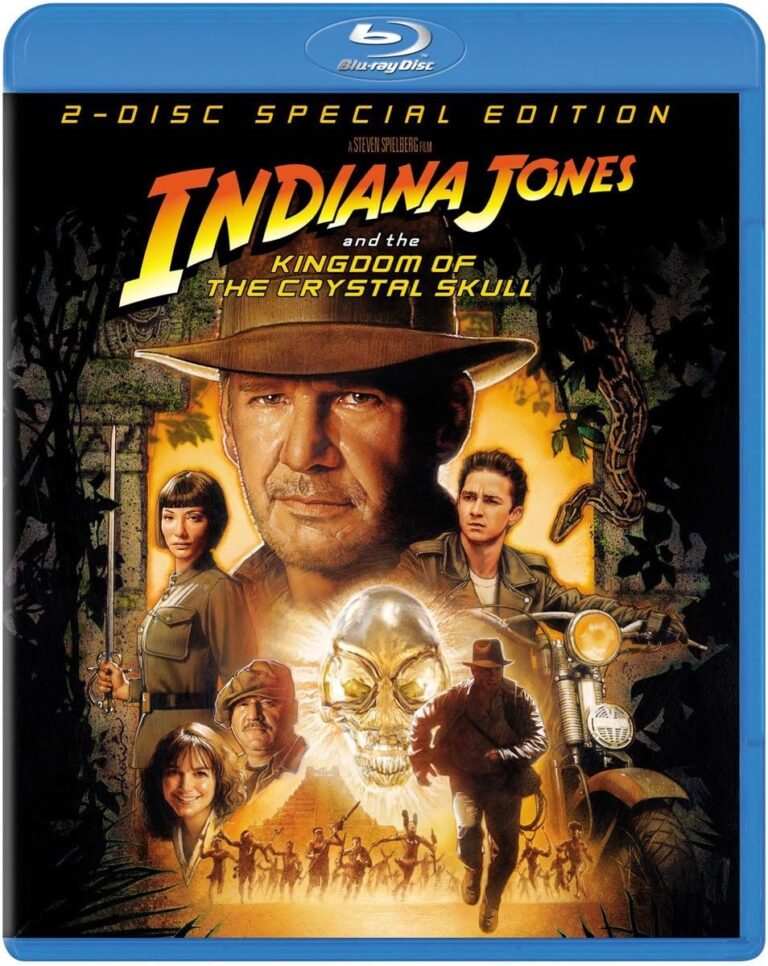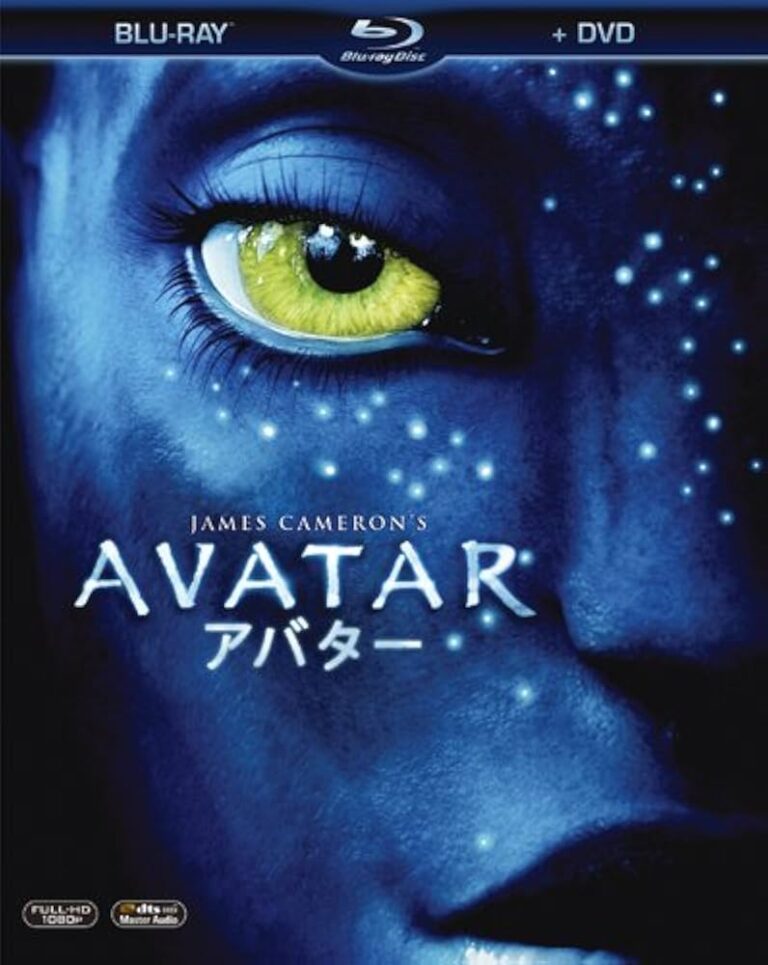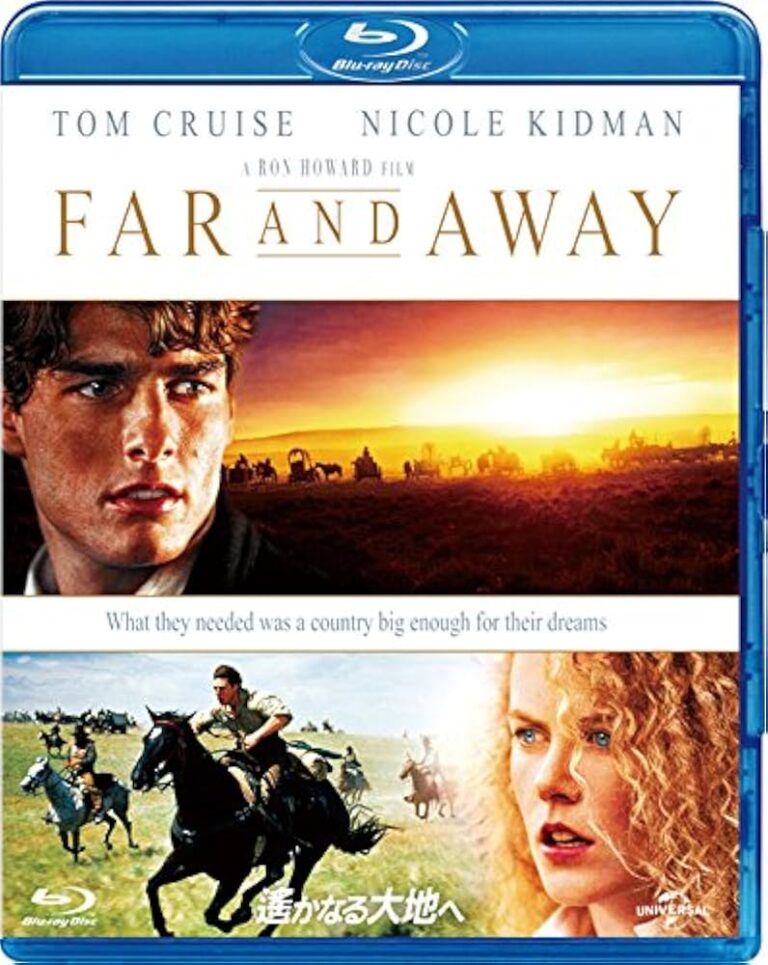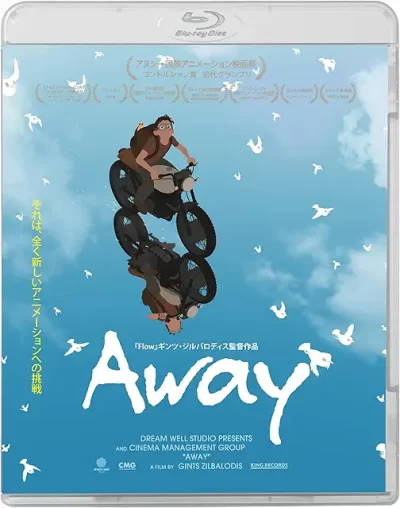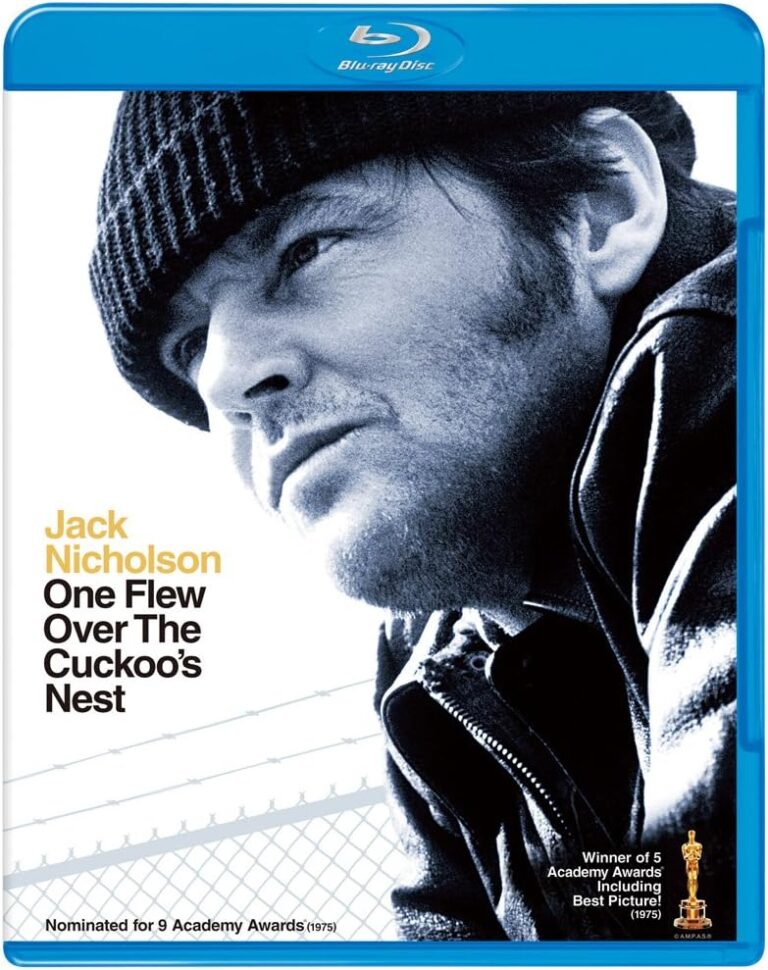『リトル・ワンダーズ』(2023)
映画考察・解説・レビュー
『リトル・ワンダーズ』(原題:Riddle of Fire/2023年)は、新鋭ウェストン・ラズーリ監督が16ミリフィルムの魔法を駆使し、どこか懐かしいおとぎ話の世界を現代に鮮やかに現出させた、インディーズ・ファンタジーの快作。ゲームをするためにブルーベリーパイの材料を探すという些細な日常のミッションが、謎の魔女集団との抗争という壮大な冒険へと変貌していく、痛快な活劇。
ジョー・ダンテの悪戯心とショーン・ベイカーの路上リアリズム
2023年のカンヌ国際映画祭監督週間でプレミア上映されるや否や、世界中のシネフィルと映画祭を熱狂の渦に巻き込んだウェストン・ラズーリ監督の長編デビュー作『リトル・ワンダーズ』(2023年)。
現代のインディーズ映画界に突如として現れたこのフィルムは、まるでジョー・ダンテとショーン・ベイカーの感性をミックスしたような快作だ。
『グレムリン』(1984年)や『エクスプロラーズ』(1985年)で、子供たちの無邪気な悪戯心が未知の怪物やオカルト現象と衝突するジョー・ダンテ。『フロリダ・プロジェクト 真夏の魔法』(2017年)で、子供たちの無垢で残酷な視点から極彩色のトーンで切り取ったショーン・ベイカー。
本作は、この全くベクトルが異なるはずの二つの映画的美学が、ワイオミング州の広大な自然を舞台に、一切の縫い目を感じさせないほど奇跡的なハイブリッドを果たしている。
主人公は、ミニバイクにまたがり、ペイント銃で武装した悪ガキ3人組「不死身のワニ団」。彼らの行動原理は、母親が設定したパスワードを解除して、どうしてもテレビゲームがしたいという、極めて卑小でリアルな現代っ子の欲望だ。
大人の監視の目が届かないところで、彼らはスーパーで万引きをし、森を駆け回り、ちょっと危険な大人たちと平気で遭遇する。この徹底して放任された子供たちの路上リアリズムと、倫理観の欠如が生み出すスリルは、まさにショーン・ベイカー的だ。
しかし、物語が進むにつれて、彼らの周囲にはジョー・ダンテ的なB級ファンタジーの気配が濃厚に漂い始める。カルト集団のような怪しげな大人たち、森の奥深くの不気味な洋館、そして魔法の力。
現代のリアルな貧困や機能不全家族の匂いを漂わせながらも、いつの間にか物語は極上のジュブナイル・ファンタジーへと変貌を遂げていく。この二つのレイヤーをシームレスに縫い合わせたウェストン・ラズーリの圧倒的なバランス感覚は、新人離れした狂気すら感じさせる。
病の女王、魔女、そしてまだらの卵
この映画の素晴らしさは、その深層に張り巡らされたプロットの構造にある。
「ゲームをするためのパスワードを教えてもらう代わりに、風邪で寝込んでいる母親にブルーベリーパイを作って届ける」という、たったそれだけのお使いミッションが、子供たちの主観という無敵のフィルターを通すことで、壮大なアーサー王伝説やグリム童話さながらの神話的構造へとトランスフォームしていくのだ。この見立ての錬金術が、本作の文学的・神話的な強度を支えている。
ベッドから起き上がれない母親は、彼らにとって絶対的な権力を持つ、病に伏せた女王だ。彼女を救う(=パイを焼く)ための特効薬として、3人の若き騎士たちは過酷な冒険へと旅立つ。そして、彼らの前に立ちはだかるのは、パイの必須材料であるまだらの卵を不当に独占するカルト集団、魔女と黒騎士たちだ。
リオ・ティプトン演じる一味のリーダーの造形がまた素晴らしい。彼女たちは決してハリウッド的なわかりやすい悪役ではなく、アメリカの田舎町に実在しそうなヒッピー的カルトの生々しさを持ちながら、同時に童話の中の森の魔女としての恐ろしさを完璧に体現している。
子供たちの視点を通せば、ただのスーパーマーケットのバックヤードは城の宝物庫であり、ペイント銃での撃ち合いは命を懸けた魔法の戦争となる。
彼らは現実世界から逃避しているのではない。機能不全の家庭、貧困、大人の身勝手さといった現実の過酷を乗り越えるために、自分たちの手で世界を神話へとたくましく書き換えているのだ。
子供による現実の神話化というテーマにおいて、本作は『グーニーズ』(1985年)や『スタンド・バイ・ミー』(1986年)といった過去のキッズ・アドベンチャーの正統な後継者でありながら、その解像度を現代インディペンデント映画の極北まで引き上げている。
彼らがついに、まだらの卵を奪還した瞬間のカタルシスは、神話の勇者が聖杯を手にした瞬間のそれと全く同じなのだ。
コダック16mmが焼き付ける永遠の夏
そして、本作を単なるノスタルジーのパッチワークから真の映画的魔法へと昇華させている決定打が、全編コダック16mmフィルムによる撮影である。
ウェストン・ラズーリ監督と撮影監督のジェイク・ミッチェルは、デジタル全盛の現代において、あえてARRI 416カメラとKODAK VISION3(50Dおよび200T)フィルムを選択した。この狂信的とも言えるアナログへの回帰が、映画全体に計り知れない恩恵をもたらしている。
16mmフィルム特有の粗い粒子は、画面にザラついた物質感を与え、ワイオミングの広大な森や眩しい陽光を、まるで70年代〜80年代の忘れ去られたおとぎ話の1ページのように美しく焼き付けている。
デジタルカメラのクリアすぎる画質では、この映画が持つおとぎ話と現実の境界線がシームレスに溶け合う感覚は絶対に表現できなかったはずだ。
強い光源の周りに発生するハレーション、森の緑の深い沈み込み、そして子供たちの泥だらけの頬に反射する柔らかな光。これらすべてが、フィルムという化学反応の魔法によって生み出された奇跡のテクスチャーである。
さらに、シンセサイザーを多用したレトロフューチャーなサウンドトラックや、サウンドデザインにおいてもラズーリ監督の偏執狂的なこだわりが光る。
彼は、かつて私たちが子供時代にたしかに感じていた「夏休みの終わらない冒険の匂い」と「日が暮れる前の焦燥感」を、フィルムの粒子と電子音の振動の中に完全に封じ込めたのだ。
『リトル・ワンダーズ』は、映画というメディアが本来持っていた遊び心と神話創造の力を、最もピュアな形で現代に蘇らせた比類なきマスターピースである。
ウェストン・ラズーリという圧倒的な才能の出現を、我々は映画史の新たなページがめくられた瞬間として、深く記憶に刻み込むべきだろう。
- 監督/ウェストン・ラズーリ
- 脚本/ウェストン・ラズーリ
- 製作/ウェストン・ラズーリ、リオ・ティプトン、デヴィッド・アトラッキ
- 撮影/ジェイク・ミッチェル
- 編集/ウェストン・ラズーリ
- 美術/メグ・キャベル
- 衣装/ウェストン・ラズーリ
- リトル・ワンダーズ(2023年/アメリカ)
![リトル・ワンダーズ/ウェストン・ラズーリ[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/81ULQdTUdyL._AC_SL1500_-e1760266396172.jpg)
![グレムリン/ジョー・ダンテ[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/81rkN9mWx4L._AC_SL1500_-e1707222242726.jpg)
![アーサー王物語[本]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/91FXIGNu1ML._SY522_.jpg)
![グーニーズ/リチャード・ドナー[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/81Liv-t1RAS._AC_UL640_FMwebp_QL65_-e1771549424216.webp)