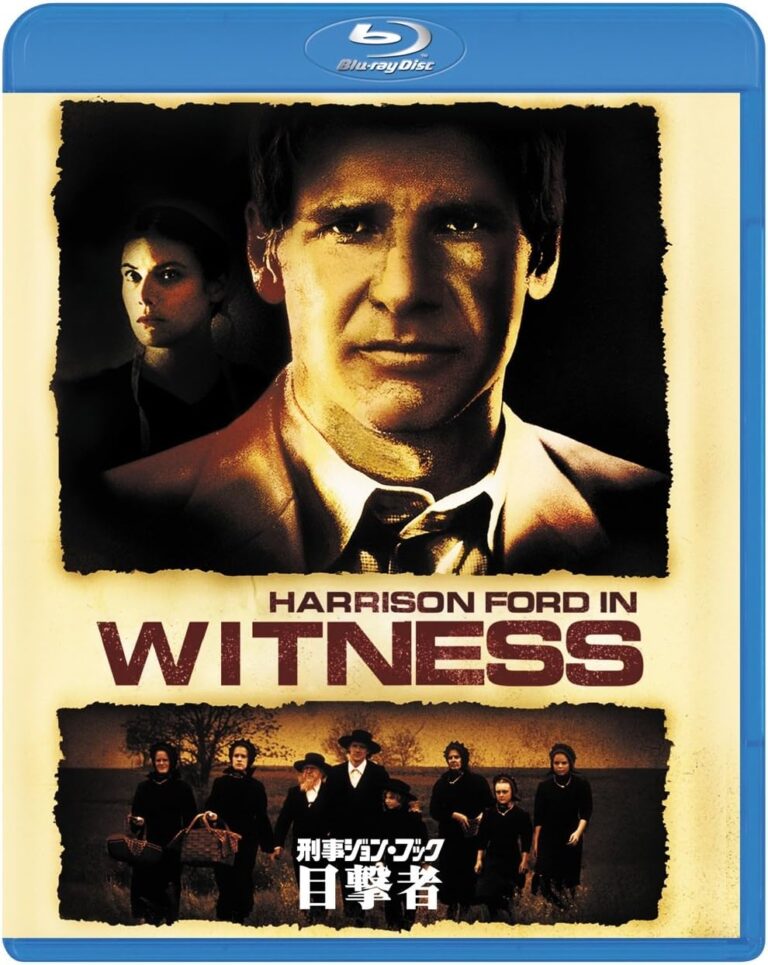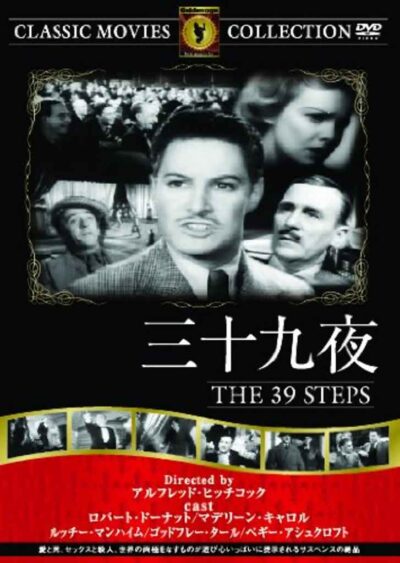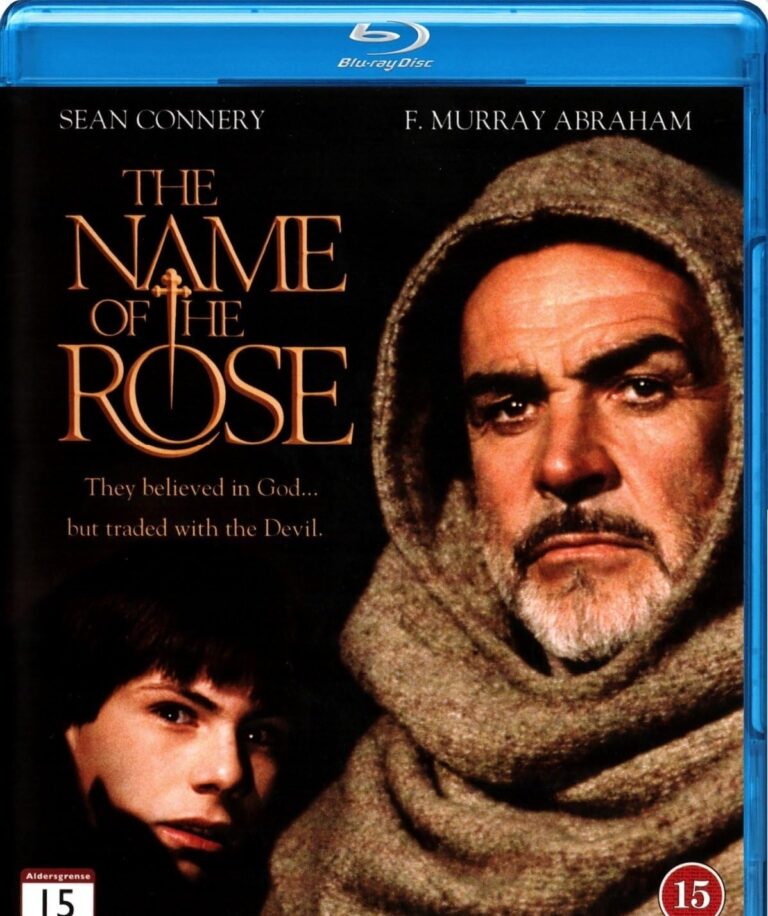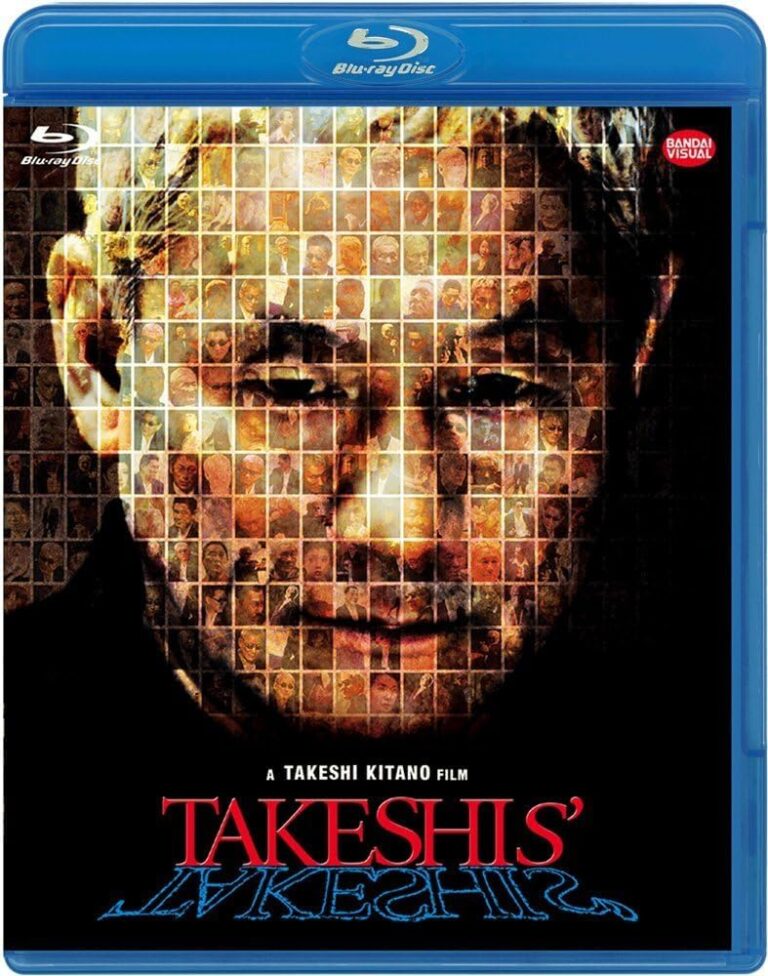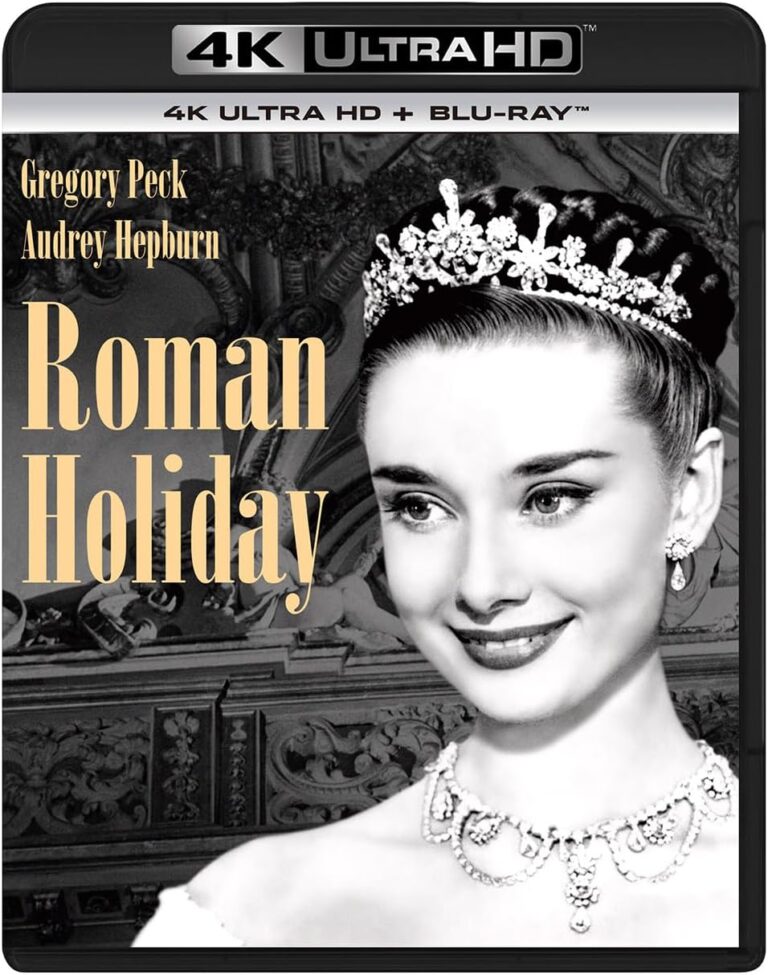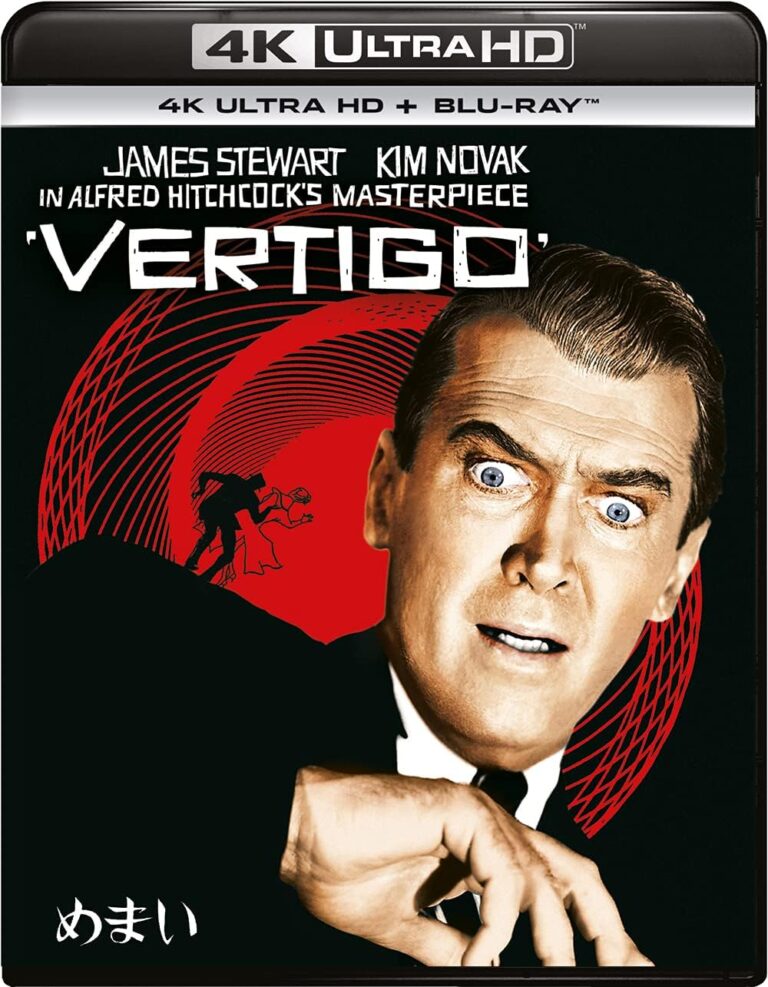『殺人の追憶』(2003)
映画考察・解説・レビュー
映画『殺人の追憶』(2003年)は、韓国を震撼させた華城連続殺人事件を題材に、軍事政権下の社会不安と正義の不在を描いたボン・ジュノ監督の代表作。未解決事件がもたらす持続的な恐怖と、不条理を映像言語で可視化する演出によって、サスペンスの枠を超えた社会派スリラーとして映画史に刻まれた。
軍事政権下の闇!「国家の無能」を笑い飛ばすブラックコメディの極北
ボン・ジュノ監督の『殺人の追憶』(2003年)ほど、1980年代後半の韓国、軍事政権下の息の詰まるような社会の空気を、完璧な解像度でフィルムに封じ込めた映画があっただろうか。
題材となったのは、1986年から1991年にかけて実際に発生した、韓国犯罪史に残る最悪の未解決事件「華城連続殺人事件」である。当時の韓国は強権的な軍事独裁政権の只中にあり、メディアの報道は厳しく検閲され、防空演習のサイレンが不気味に鳴り響き、女性たちは夜間の外出を恐れて息を潜めていた。
犯人が一向に捕まらないという現実は、単なる警察の怠慢や治安の問題を超え、「国家権力は一般市民の命を守る能力すら持っていない」という絶望的な無力感を、社会全体に蔓延させていた。
この映画に生々しく描かれる警察の暴力や拷問は、当時の血塗られた現実そのもの。証拠よりも自白を優先し、ドロップキックで容疑者を蹴り飛ばして無理やり調書をでっち上げようとする。
ソン・ガンホ演じるパク刑事は、まるでガキ大将がそのまま大人になったかのような傍若無人なジャイアン的存在であり、そのあまりにも拙い捜査や、サッパリ分からない迷信や占いに頼る姿は、強烈なコメディリリーフとして画面に屹立している。
さらに、低アングルやミディアムショットで滑稽に切り取られる、署長たちのポンコツぶりはどうだ。ボン・ジュノはコメディにすることで、権力というものの脆弱性と、国家機構の恐るべき不条理さを、観客の脳裏に強烈に焼き付ける。
笑いは安心を生むどころか、逆に我々の心底に冷たい恐怖を植え付けるのだ。
日常と暴力が交錯する振り子の演出
ソウルから赴任してきたインテリのソ刑事(キム・サンギョン)が意気揚々と持ち込んだ科学捜査やプロファイリングは、このドロドロの田舎町では決定的な成果に何一つ結びつかない。必死の捜査も空しく、事件は結局未解決のまま残酷に時効を迎えて幕を閉じる。
ここで観客が味わわされるのは、スリラー映画が本来提供するはずの謎解きの快感ではなく、答えの不在と解決不能の不条理さ。映画は観客を刑事たちと同じように無力な立場に強制的に縛り付け、証言を追い、証拠を探し、容疑者に迫らせる。しかし最後に我々の両手に残るのは、真実に永遠に到達できないという、空虚な絶望感だけなのだ。
さらにヤバいのが、ボン・ジュノの専売特許であり、のちの『母なる証明』(2009年)や『パラサイト 半地下の家族』(2019年)でも遺憾なく発揮される、日常と暴力の振り子構造。
スヒョンのウジの湧いた腐乱死体を検分した直後に、刑事たちが平然と美味そうに焼肉を貪り食うシーンがもたらす、あの強烈な倫理的違和感と不快感ったら!
ソ刑事と女子中学生が田んぼ道で絆を深めるシーンでは、逆光を用いた柔らかな映像で牧歌的な雰囲気を高めておきながら、その直後に彼女が無惨な死体となって発見される場面では、手持ちカメラの不安定な揺れと低アングルのクローズアップで、生々しい暴力を叩きつけてくる。
光から闇へ、笑いから恐怖へ。我々はこの急激な転換に情緒をグチャグチャに揺さぶられ続け、平穏な日常がいかに脆弱な氷の上に成り立っているかを骨の髄まで思い知らされる。
雨は証拠を洗い流し、黄金色の田園風景は死体を隠す。自然そのものが人間に敵対し、すべてを隠蔽していく風景の敵対性の前に、我々はただ立ち尽くすしかない。
現実を侵食する「真犯人の視線」
『殺人の追憶』を、映画史における決定的な転換点へと昇華させた最大の理由は、あの狂気に満ちた戦慄のラスト・シークエンスだろう。
事件から十数年が経過し、すっかり時効も成立して警察を辞め、平凡なセールスマンとなったパク刑事。彼はふと、かつて最初の犠牲者が発見されたあの用水路を訪れ、排水溝の奥深くを覗き込む。
そこへ通りすがりの見知らぬ少女が声をかける。「この間も、別の男の人がここを覗き込んでいたよ。自分が昔ここでやったことを思い出しに来たって言ってた」。全身の血が凍りつくようなその言葉に対し、パク刑事は震える声で男の顔の特徴を問いただす。
しかし少女から返ってくるのは、「普通の人だった」という平凡な答え。その瞬間、パク刑事の顔が画面いっぱいにクローズアップされ、彼は血走った目でカメラのレンズを、いや、スクリーンの向こう側の暗闇に座っている我々観客を、真っ直ぐに射抜くように見つめ返す。
ディープ・フォーカスによって、のどかな村と彼の絶望的な表情が同時に鮮明に映し出されるこのラスト・カットは、「犯人は今、この映画館の客席でこの映画を観ているかもしれない」という、映画の虚構が現実に直接侵食してくるような、究極の恐怖体験を突きつける。
2019年、DNA鑑定の劇的な進化によって、ついに現実の真犯人であるイ・チュンジェが特定されたというニュースは世界中を震撼させた。だが、現実の事件が解決したからといって、この映画の価値が1ミリでも下がることは絶対にない。
むしろ、軍事政権下の不条理、国家権力の暴力、そして日常の背後にヌメヌメと潜む悪を完璧に映し出した本作は、現実のアップデートを経た今だからこそ、人間の正義の限界と執念を突きつけるマスターピースとして、我々の心臓を鷲掴みにし続けている。
![殺人の追憶/ポン・ジュノ[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/91M5j-gVcL._AC_SL1500_-e1758389593892.jpg)
![パラサイト 半地下の家族/ポン・ジュノ[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/91LFZYCGzL._AC_UL640_FMwebp_QL65_-e1762675437250.webp)