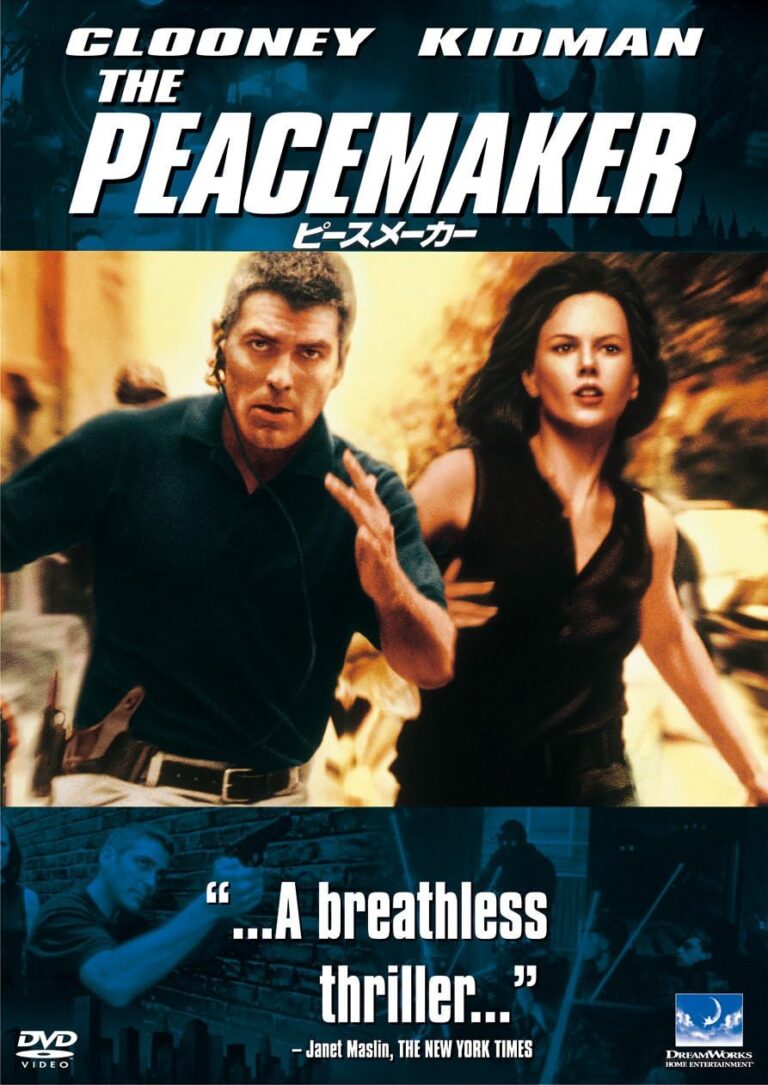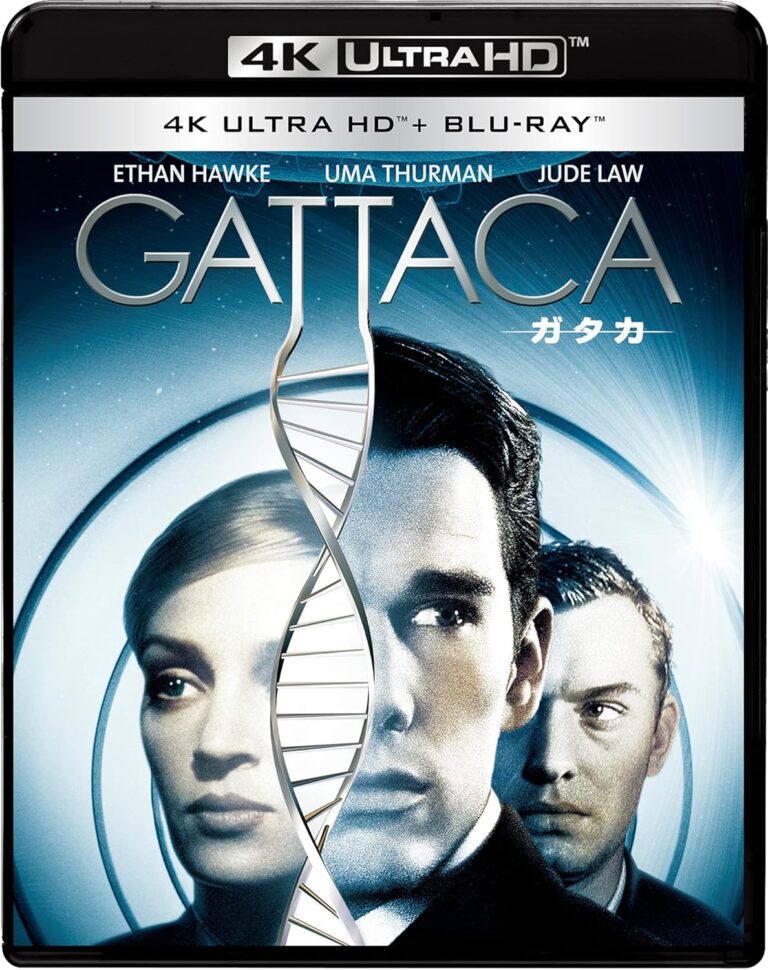『yanokami』(2007)
アルバム考察・解説・レビュー
『yanokami』(2007年)は、矢野顕子とレイ・ハラカミによるコラボレーション・ユニットであり、J-POPにおける電子音と声の幸福な融合を実現した作品である。矢野が歌とピアノを、ハラカミがエレクトロニクスを担当し、「>恋は桃色」などのカバーを収録。アコースティックとデジタルが呼吸するように溶け合い、人間とテクノロジーの共生を音楽として体現した。
暴力的なピアノ──矢野顕子という異能
ここ数年、NHKホールで行われる矢野顕子の「さとがえるコンサート」に足げく通っているが、そのたびに感じるのは、壮絶としか言いようのないミュージシャンとしての圧倒的な凄みである。
矢野顕子というミュージシャンの真の本質は、あのおっとりとしたチャイルディッシュな詩世界や、天空を舞うようなチャーミングなヴォーカリゼーションの奥底でギラギラと牙を剥く、壮絶で暴力的なまでのピアノの打鍵にこそ宿る。
歴史的デビューアルバム『JAPANESE GIRL』(1976年)から現在に至るまで、彼女は常に日本のポップミュージックの最前線を独走してきた。かつてイエロー・マジック・オーケストラ(YMO)のワールドツアーにサポート・メンバーとして帯同し、世界中のオーディエンスを驚愕させたその圧倒的なグルーヴ感。
ジャズ・ピアニストの山下洋輔ばりに鍵盤を叩き潰すかのような凶暴なスウィングと、神懸かり的で予測不能の跳躍!転調に次ぐ転調、常軌を逸した独特のテンション・コード。彼女の紡ぐ音楽は、幼子の無邪気さを装いながら、常に聴く者の感情の臨界点を軽々と、そして問答無用に突破して襲い掛かってくるのである。
恐るべきは、カバー曲に対するアプローチだ。日本のポップス史を彩る幾多の名曲たちを、その面影を木っ端微塵に粉砕し、完全なる矢野顕子の曲として再構築してしまう。
THE BOOMの「中央線」(1996年)、ムーンライダーズの「ニットキャップマン」(2006年)、くるりの「ばらの花」(2004年)、ELLEGARDENの「右手」(2006年)、そして細野晴臣の「恋は桃色」(1993年)…。
メロディーもコードもリズムも、矢野顕子という巨大な宇宙のフィルターを通過することでDNAレベルから組み替えられ、全く別の生態系として強烈に立ち上がる。
原曲の魂を一度飲み込み、自らの血肉として吐き出す“再誕”。これはもう、カバーという形式を借りた新曲だ。この過剰なまでの人間力と、ピアノ一台で世界をねじ伏せる生命力。これこそが矢野顕子という、日本音楽界に君臨する絶対的な異能の正体なのである。
ハラカミの非人称的ランドスケープ
過剰な人間性の塊である矢野顕子に対し、全く対極のベクトルから日本のエレクトロニカ・シーンに静かなる革命を起こした男がいる。京都が生んだ天才トラックメイカー、レイ・ハラカミだ。
彼の音楽制作のスタイルは、高価なビンテージ機材やプラグインが跋扈するテクノ界隈にあって、異常なくらいストイック。彼は何百万円もするアナログ・シンセサイザーや最新鋭のDAWソフトを並べるたのではない。
1996年に発売されたSC-88Pro(通称ハチプロ)と、古いMacに入ったEZ Visionという化石のようなシーケンスソフトだけで、ほぼすべての楽曲を構築していたのだ。
ハチプロといえば、当時のパソコン音楽初心者がMIDIでカラオケデータを作るために使っていたような、めちゃめちゃ大衆的でチープな機材。
だが、ハラカミはこの不自由さに自らをあえて閉じ込め、内蔵されたプリセット音色のアタックやリリース、ディレイ、そして滑らかなピッチベンドを偏執狂的なまでにエディットし倒すことで、誰も聴いたことのない魔法のサウンドを生み出したのである。
『Unrest』(1998年)や大傑作『Red Curb』(2001年)を聴けばわかるだろう。レイ・ハラカミの音楽には、ポップス特有の核が存在しない。
明確なメロディラインが主役を張るのではなく、電子の粒そのものが有機的に空間を漂い、時間とともにゆったりと呼吸を繰り返す。彼自身の言葉を借りれば、それはまさに「主役のいない風景」なのだ。
矢野顕子が音楽を血の通った“生き物”として奏でるなら、ハラカミは音楽を透明な“気配”として空間に描く。徹底的にパーソナルで限定された機材環境から生み出された、非人称的なランドスケープ。
その無重力の電子空間は、聴く者の記憶の底を静かに揺り起こすように、あまりにも美しく、孤独なのだ。
エレクトロニカと体温の奇跡
本来ならば絶対に交わるはずのない過剰な人間性と、非人称的な風景。この二つの極端なベクトルが衝突ではなく、奇跡の共鳴を果たしたのが、矢野顕子とレイ・ハラカミによる伝説のユニットyanokamiである。
事の発端は、レイ・ハラカミが大胆極まりないダブ的アプローチで再構築した、くるりの大名曲「ばらの花」リミックス音源。矢野顕子は、ハラカミの構築した無重力のエレクトロニカに強烈な衝撃を受け、熱烈なラブコールを送る。
矢野のアルバム『ホントのきもち』(2004年)での共同作業を経て、ついに生み出されたデビューアルバム『yanokami』(2007年)は、日本のポップ・ミュージック史において、電子音と人間の声の最も幸福な融合を成し遂げた歴史的マスターピースとなった。
同作に収録された矢野自身のセルフカバー「David」や、細野晴臣のカバー「終りの季節」を聴いてほしい。ハラカミが精緻に設計した主役のいない無重力空間に、矢野という絶対的主役が飛び込み、ドクドクと脈打つ血と体温を流し込んでいく。
矢野の暴力的なまでに自由なピアノの間を、ハラカミが柔らかな電子の粒で埋め尽くし、ハラカミの冷徹な無音の間に、矢野の温かな歌声がふわりと降り立つ。
それは人間と機械、即興と構築、アナログの声とデジタルの残響といった相反する要素が、互いを一切否定することなく見事に共在する、奇跡の空間。
2008年には全編英語詞の『yanokamick』をリリースし世界を見据えた彼らだったが、2011年、レイ・ハラカミは40歳という若さで急逝し、セカンドアルバム『遠くは近い』(2011年)が彼らの遺作となってしまった。
だが、yanokamiの残した音楽を聴くと、テクノでもジャズでもポップでもない、得体の知れない“新しい生命体”が今もなおそこで呼吸しているのを確かに感じるはず。
彼らが見出した「音の呼吸=共生の音楽」は、現代社会のノイズを静かに調律し直す祈りのようであり、21世紀の音楽が到達した最も美しく、最も気高い“うた”の形なのである。
- 1. 気球にのって
- 2. David
- 3. 終りの季節
- 4. おおきいあい
- 5. Too Good to be True
- 6. You Showed Me
- 7. La La Means I Love You
- 8. Night Train Home
- 9. Full Moon Tomorrow
- 10. 恋は桃色
- yanokami(2007年/ヤマハミュージックコミュニケーションズ)
![yanokami/yanokami[CD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/419uxwLXaGL-e1707317500705.jpg)
![JAPANESE GIRL/矢野顕子[CD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/51eg58r6cfL._AC_UL640_FMwebp_QL65_-e1771701790448.webp)
![Red Curb/レイ・ハラカミ[CD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/419Tn50h12L._AC_UL640_FMwebp_QL65_-e1771702509696.webp)