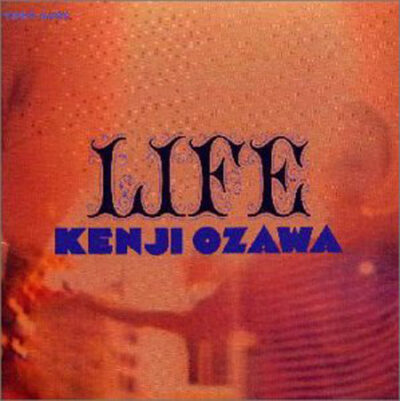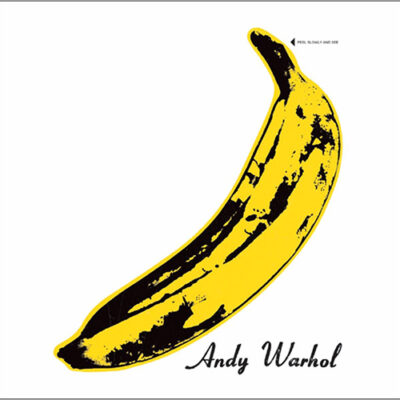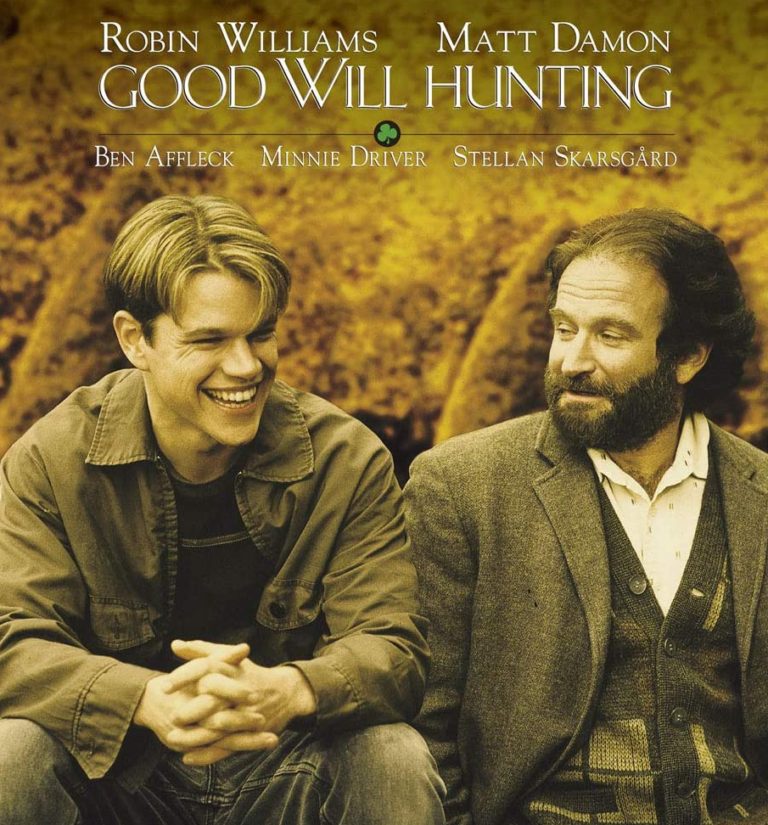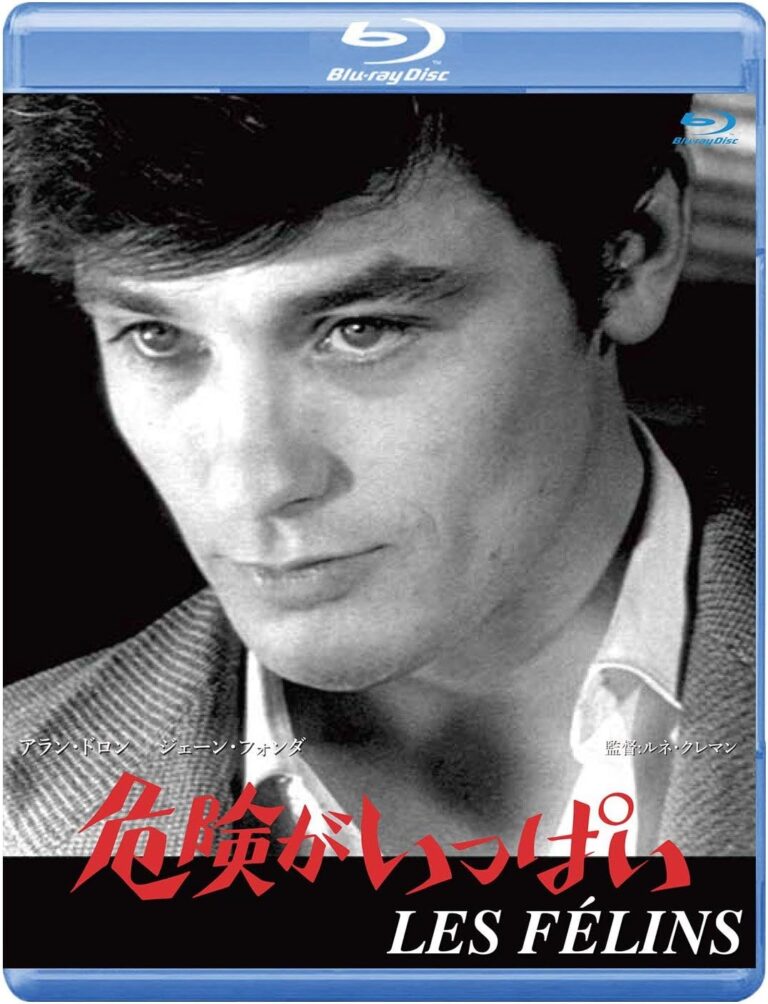『童夢』──構築と破壊のテクノロジー
『童夢』(1980年)は、大友克洋が週刊『アクションデラックス』で発表した長編漫画。東京の団地を舞台に、超能力を持つ老人と少女の対決を軸に、均質化された都市空間と人間の暴力を描く。緻密な建築描写と冷徹な構成で漫画表現の可能性を拡張し、第4回日本SF大賞を受賞。後の『AKIRA』(1982–1990年)へと連なる“構築と崩壊”の原点として、世界中のクリエイターに影響を与えた。
体温のない物語──ヒューマニズムを拒絶する作家
大友克洋の漫画は冷めている。体温が低いとでも言うべきだろうか。一切のヒューマニズムを排したその作風は、熱狂とは無縁の冷徹な平熱を保っている。
だが、静的なストーリーの底で蠢くのは、異常なまでに昂ぶった作画の熱量だ。冷たい物語の内部で、ペン線だけが灼けるように熱い──この乖離こそが大友克洋の本質である。
『童夢』(1980年)は、その冷たさと熱のバランスが極限まで高まった作品だ。マンモス団地で連続する住民の変死事件。自殺か、他殺か、事故か。
ミステリードラマの装いで始まった物語は、やがてエスパーたちの戦いへと転じ、団地そのものが崩壊していく。だがそこに人間的な悲劇はない。死や暴力が感情の発露ではなく、構造の結果として描かれる。
その冷たさは、キャラクターの表情にさえ宿る。怒りも涙も、彼らの顔にはほとんど浮かばない。世界はただ淡々と進行し、破壊の瞬間さえも無感動に処理される。大友の漫画における暴力は、倫理的な問題ではなく、構築された世界の必然的崩壊である。
描線の快楽──「構築」に憑かれた職人
短編集『彼女の思いで』を読んでも明らかなように、大友克洋の創作欲を駆動するのは「構築」と「破壊」である。特に「構築」への偏執は異常なほどだ。団地、配管、車、信号、埃、電線──それらを一つ一つ丁寧にペンで立ち上げる。作画の工程自体が、世界の生成そのものとして機能している。
漫画を描いた経験のある者なら、この「構築」がどれほど地味で、報われない作業であるかを知っているだろう。だが大友はその苦行を快楽に変える。一本の線を引くたびに、世界が更新されていく。描く行為そのものが、物語を駆動させる。
『童夢』の背景で特筆すべきは、団地という舞台装置だ。大量生産された住宅群は、個の喪失と社会の均質化を象徴する。大友はそれを単なる背景ではなく、人格を持った構造体として描いた。窓の一つ一つに明かりが灯り、ベランダの洗濯物が風に揺れる。そこに住む人間たちは、まるで建築物に吸い込まれた細胞のように見える。
団地の屋上から人間が落下する場面を、見開き2ページで描くという手法も、その構築的美学の延長線上にある。人が死ぬ瞬間を「読ませる」のではなく、「見ることの構造」として提示する。まるで映像の一時停止のような冷静さ。漫画という“読むメディア”の性質を反転させ、純粋な視覚体験へと昇華している。
物語が終盤に向かうにつれ、『童夢』は理性を失ったように加速する。ビルは崩壊し、人間は吹き飛び、街は瓦解する。破壊がクライマックスに達する瞬間、ページ全体が音になる。これは漫画的というよりも、映画的・音楽的なリズムだ。
大友のカット構成は、映画のモンタージュ理論に近い。俯瞰・煽り・広角・クローズアップを駆使し、読者の視点を自在にコントロールする。コマ割りはリズムを持ち、破壊の連続がドラム・ループのような反復ビートとして響く。
その意味で『童夢』は、テクノミュージックに最も近い漫画である。冷たい構造と精密な反復。人間的情緒を排した“メカニカルな快楽”。そこには、音楽におけるテクノロジーの美学がそのまま映し出されている。大友克洋が実際にテクノを好んで聴いていたという逸話は、単なる趣味ではなく、彼の作風そのものを説明する証左である。
テクノが「人間の不在」を前提にした音楽であるように、大友の漫画も「作家の不在」を前提にしている。感情を挿入せず、構築物として作品を完成させる。そこに宿るのは冷たさではなく、純度の高い快楽だ。
『童夢』から『AKIRA』へ──冷たさの進化
『童夢』で芽吹いた構築と破壊のバランスは、『AKIRA』(1982–1990年)で臨界点に達する。都市規模の破壊、群衆の暴走、軍事と神話の融合──すべてが拡張され、熱狂的なビジュアルへと転化する。だが根底に流れる体温の低さは変わらない。
『AKIRA』の爆発は、『童夢』の延長線上にある“構築物の崩壊”の極大化だ。そこでは人間が物語の中心ではなく、システムの中のノイズとして描かれる。超能力というモチーフも、人間的な救済ではなく、構造の歪みを暴くための装置に過ぎない。
『老人Z』(1991年)に至るまで、大友の物語は常に「追いかけっこ」の形をとる。逃げる者と追う者、破壊する者と構築する者。その単純な構造を、彼は異常なまでの密度で再構築する。これは反復そのものであり、音楽的でもある。ビートを刻みながらエントロピーが上昇していく構造──まさにテクノの構文だ。
冷たいストーリー、熱い描線。無感情なキャラクター、過剰なディテール。大友克洋の漫画はその矛盾の中で美を形成する。熱量と冷却のあいだで均衡を保つその世界は、読者に快楽と不安を同時に与える。
大友克洋の偉大さは、描くことそのものを生の証明へと昇華した点にある。マンモス団地を描くことが苦行であることを知りながら、彼はそこに幸福を見いだした。無数の窓、均質な壁、無機質な光。世界を再構築するためにペンを走らせる──その姿は宗教的ですらある。
彼の作品には、創作における祈りの構造がある。人間の感情を排した結果、残るのは“描くという行為そのもの”だけだ。構築すること、描き続けること。それが破壊の衝動を制御し、世界を再び形づくる。
『童夢』とは、創作という名の宗教に取り憑かれた作家の記録である。感情を冷却し、線を積み重ね、世界を再構築する──その静かな狂気こそが、大友克洋の“体温”なのだ。
- 著者/大友克洋
- 発売年/1983年
- 出版社/双葉社