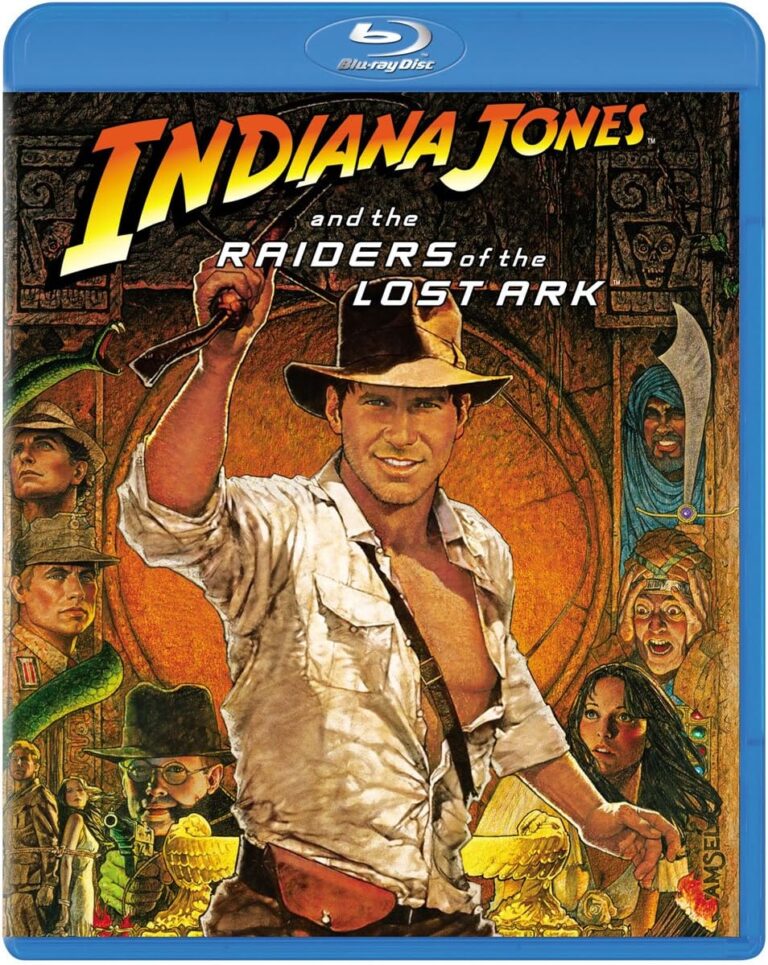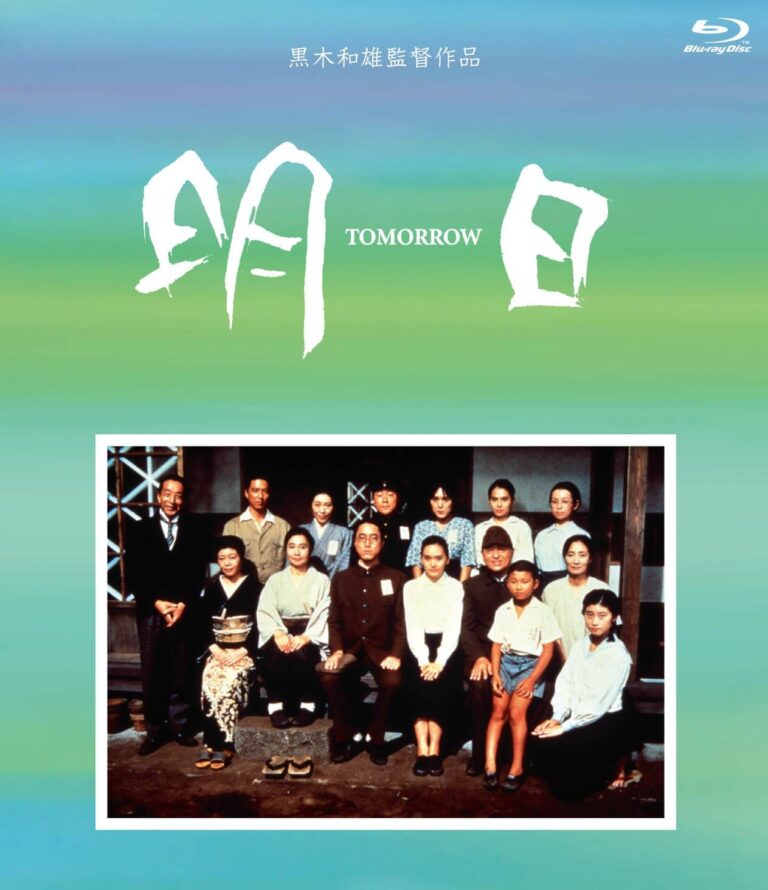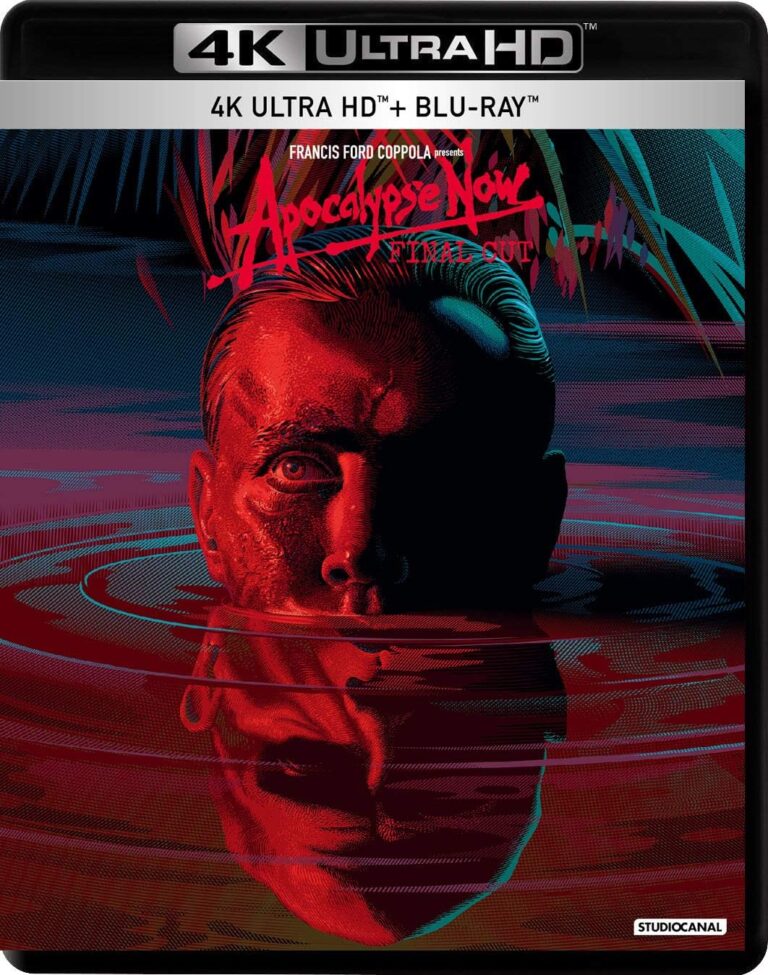『アメリ』(2001)
映画考察・解説・レビュー
『アメリ』(原題:Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain/2001年)は、パリのモンマルトルに暮らす孤独な女性アメリが、偶然の連鎖の中で出会った人々に小さな奇跡をもたらしていく物語である。幼少期の環境から自分の世界に閉じこもってきた彼女は、ひそやかな善意の行動を重ねることで日常の風景を変えていき、やがて一人の青年ニノとの出会いを通じて、自らの幸福と向き合う勇気を見つけようとする。街に広がる色彩と出来事の連なりが、彼女の心の変化をそっと導いていく。
“幸福の映画監督”という誤解
2001年、『アメリ』が公開されるや否や、フランス大統領が絶賛し、日本でもスペイン坂周辺はオシャレ系女子で大混雑した(それに混じって僕も駆けつけた)。
だが、彼女たちに告げておきたい。ジャン・ピエール・ジュネとは、もともと『デリカテッセン』(1991年)や『ロスト・チルドレン』(1995年)といった、異形と倒錯の世界を好む、キッチュな闇の職人なのであるぞ。わかっとんのか、そのへん。
『アメリ』のキャッチコピー──“人生は小さな奇跡の連続”──をそのまま受け取ると、幸福とロマンに満ちたヒーリング・ムービーと誤解されがちだ。
しかし、ジュネのフィルモグラフィーを辿れば、そこに常に毒が流れていたことに気づく。彼の幸福とは、社会的規範の裏側に潜む異物をも愛でる「歪んだ快楽」なのだ。
『デリカテッセン』での食人アパート、『ロスト・チルドレン』での悪夢のような人工都市──これらの閉鎖的世界から一転、『アメリ』はパリの街角を舞台にする。
しかし、世界が明るくなっても、ジュネの視線は決して健全ではない。むしろ、彼は初めて“光の中に毒を溶かす”という試みに挑戦したのである。
『アメリ』の最も劇的な変化は、撮影監督がダリウス・コンジからブリュノ・デルボネルに交代した点にある。
『セブン』(1995年)などで知られるコンジの映像は、密閉空間と退廃的光線によって構成されていた。それに対し、デルボネルの映像は、飴色に輝く陽光と、柔らかく拡散する陰影に満ちている。
ジュネがこの変更を行ったのは、単なる技術的転換ではなく、作家としての自己脱皮の表明だろう。閉鎖された“部屋”から、開かれた“街”へ。毒の光から、幸福の光へ。
言い換えれば、『アメリ』はジャン・ピエール・ジュネにとっての「外界デビュー」であり、アメリ自身が外の世界へ踏み出す物語構造と並行している。
パリのモンマルトルを、過剰な彩度と温度で包み込む画面は、まるでベル・エポック期の絵画のように装飾的である。そこに漂うのは、デジタル処理の人工的光彩と、19世紀絵画的ノスタルジアが融合した独自のフランス的バロック。
ジュネは写実ではなく、あくまで人工的幸福の絵画を描いている。
オドレイ・トトゥ──幸福の女神、もしくは孤独の巫女
当初『奇跡の海』(1996年)のエミリー・ワトソンが主演予定だったという逸話は有名だが、もし彼女が演じていたら『アメリ』はもっと内省的で神経症的な映画になっていただろう。ワトソンの内的な痛みを可視化する演技は、ジュネの幸福の寓話とは化学反応を起こさない。
オドレイ・トトゥのキャスティングこそ、この映画の魔法である。彼女の笑顔は、単なるチャーミングではなく、幸福の代行者として機能する。
観客は彼女を愛するのではなく、彼女の笑顔を通じて「自分の幸福」を投影するのだ。つまり、オドレイ・トトゥは媒介としての女優なのである。
その存在の軽やかさは、同時に危うさも孕む。アメリの行動は、他者の幸福に介入する善意のストーカー的性質を帯びており、ジュネの倒錯的嗜好がここでも微妙に顔を覗かせる。幸福の物語に見えて、実は〈他人の人生を操作する快楽〉というブラックユーモアが潜んでいるのだ。
そして、アンドレ・デュソリエによるナレーション。彼の穏やかで理知的な声は、奇天烈な登場人物たちの過剰な世界を客観化し、観客の感情を中庸に保つ。これは『ちびまる子ちゃん』のキートン山田的手法に近い。ユーモラスな断絶こそが、映画のテンポを軽やかにしている。
ジュネの脚本構造は、フランス的な物語の枝分かれに満ちている。小さな出来事が別の人物に伝播し、偶然が幸福を導くというモチーフは、ジャック・タチの『ぼくの叔父さん』(1958年)に通じるもの。ここでの幸福は計画されたものではなく、編集とナレーションのリズムが生む構成上の偶然によって生成されるのだ。
映像的にも、極端なワイドレンズと過剰な動きによって、都市の空間そのものが呼吸しているように感じられる。ジュネの画面は静止せず、常に脈動している。幸福とは動きの中にしか存在しない。それが『アメリ』の映画的命題である。
幸福の形式、もしくは毒の形式
『アメリ』は一見すると“癒し映画”だが、ジュネのブラックな資質は完全には消えていない。性的倒錯の匂い、変人たちの異常なこだわり、日常に潜む軽い不条理。それらが、明るくポップな光彩の裏で蠢いている。
つまり本作は、幸福の顔をしたグロテスクなのだ。画面の彩度が高ければ高いほど、その裏に潜む陰影が深くなる。ジュネはその逆説を誰よりもよく理解している。幸福とは、毒を完全に除去した清潔な状態ではなく、毒と幸福が同居する“危ういバランス”にこそ宿るのだ。
『アメリ』は、ジャン・ピエール・ジュネが“幸福”というモチーフを使って自らの暗黒性を浄化した作品である。だが、完全な変容ではない。『デリカテッセン』の閉塞的世界を開放的に反転させただけで、その根幹にある倒錯的美意識は変わっていない。
オドレイ・トトゥの笑顔、デルボネルの光、デュソリエの声、そしてパリの街並み。それらすべては幸福の装置として精密に設計された“映画的構築物”だ。ジュネは人間を救うためにではなく、映画を救うために“幸福”を撮ったのである。
『アメリ』とは、ジャン・ピエール・ジュネ版『白スピルバーグ映画』のようなものだ。だがスピルバーグが「光」を純粋に信じるのに対し、ジュネは「光に混ざる闇」を信じている。その違いが、彼の映画を単なる癒し映画ではなく、“幸福のメタ映画”たらしめているのだ。
- 原題/Le Fabuleux Destin d'Ame'lie Poulain
- 製作年/2001年
- 製作国/フランス
- 上映時間/120分
- 監督/ジャン・ピエール・ジュネ
- 脚本/ジャン・ピエール・ジュネ、ギョーム・ローラン
- 製作/クローディー・オサール
- 撮影/ブリュノ・デルボロル
- 音楽/ヤン・ティルセン
- 編集/ハーヴ・シュナイド
- 美術/アリーヌ・ボネット
- 衣装/マドリン・フォンテーヌ
- オドレイ・トトゥ
- マチュー・カソヴィッツ
- ヨランド・モロー
- リュフュ
- アルチュス・ド・パンゲルン
- ウルバン・カンセリエ
- ドミニク・ピノン
- クロード・ペロン
- ミシェル・ロバン
- アメリ(2001年/フランス)

![アメリ/ジャン・ピエール・ジュネ[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/811-IAVo22L._AC_SL1500_-e1707310562408.jpg)