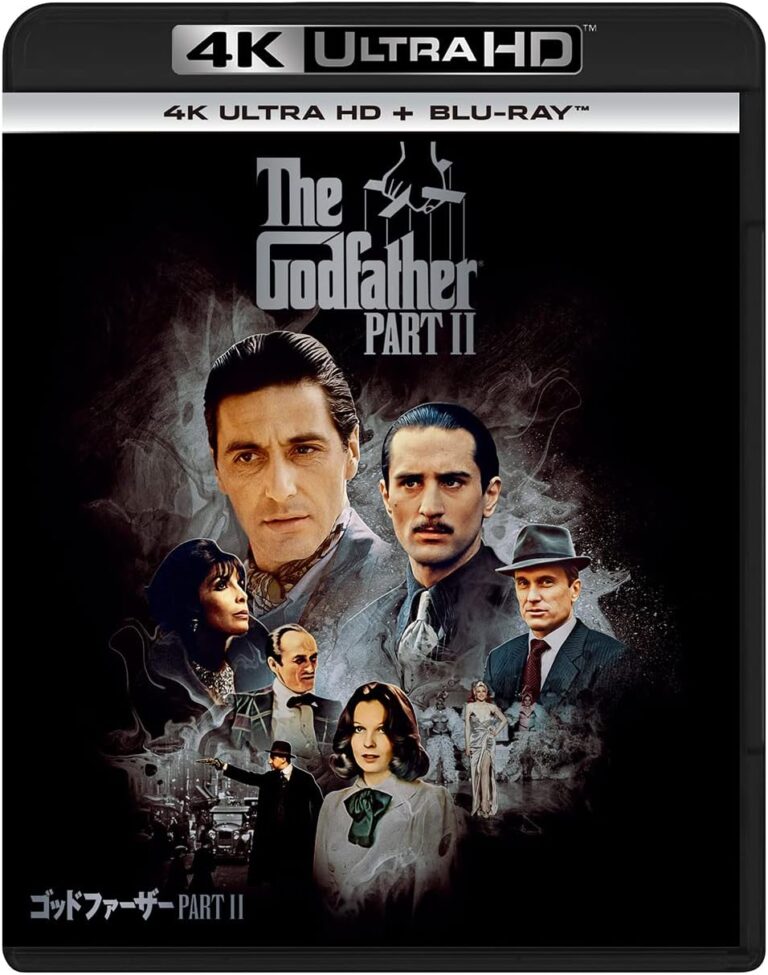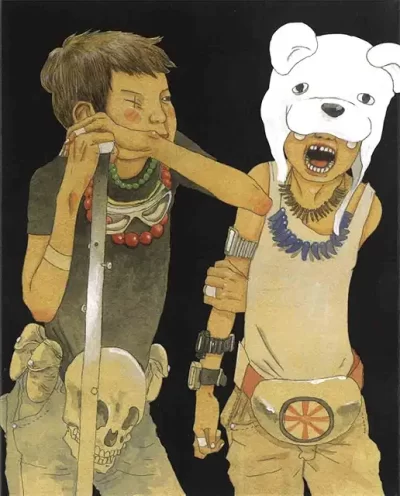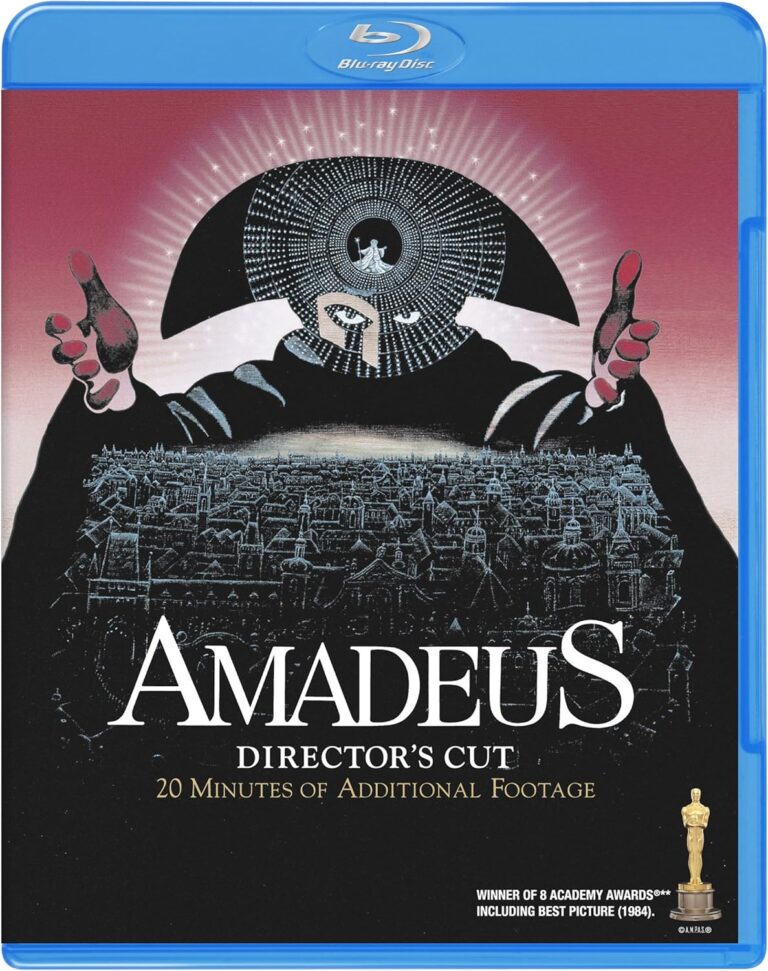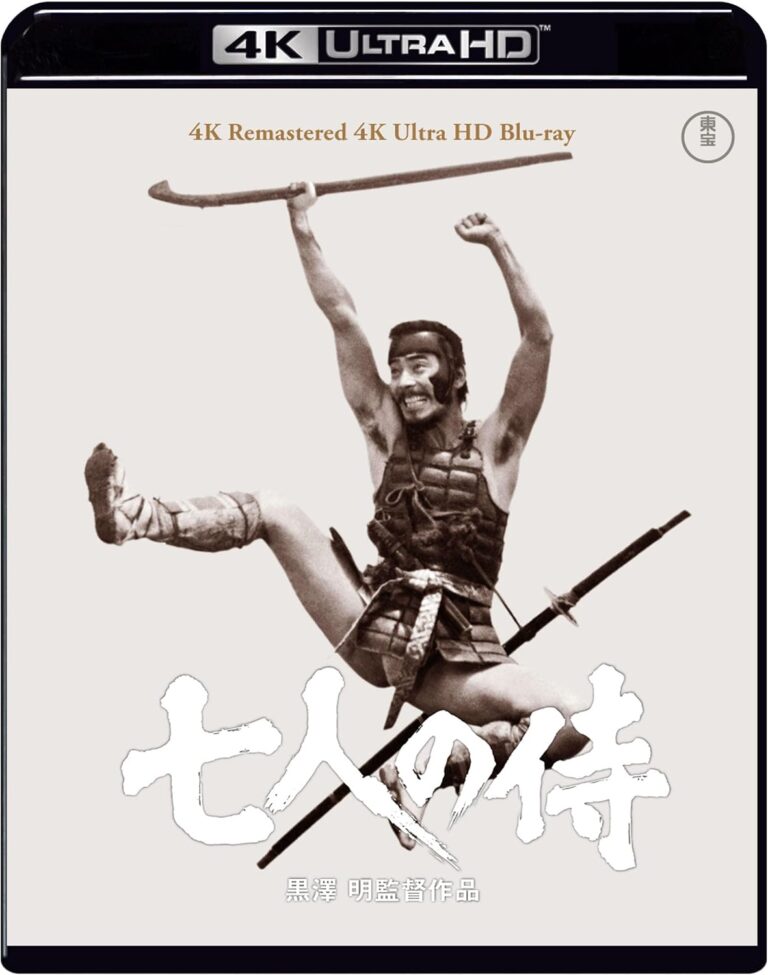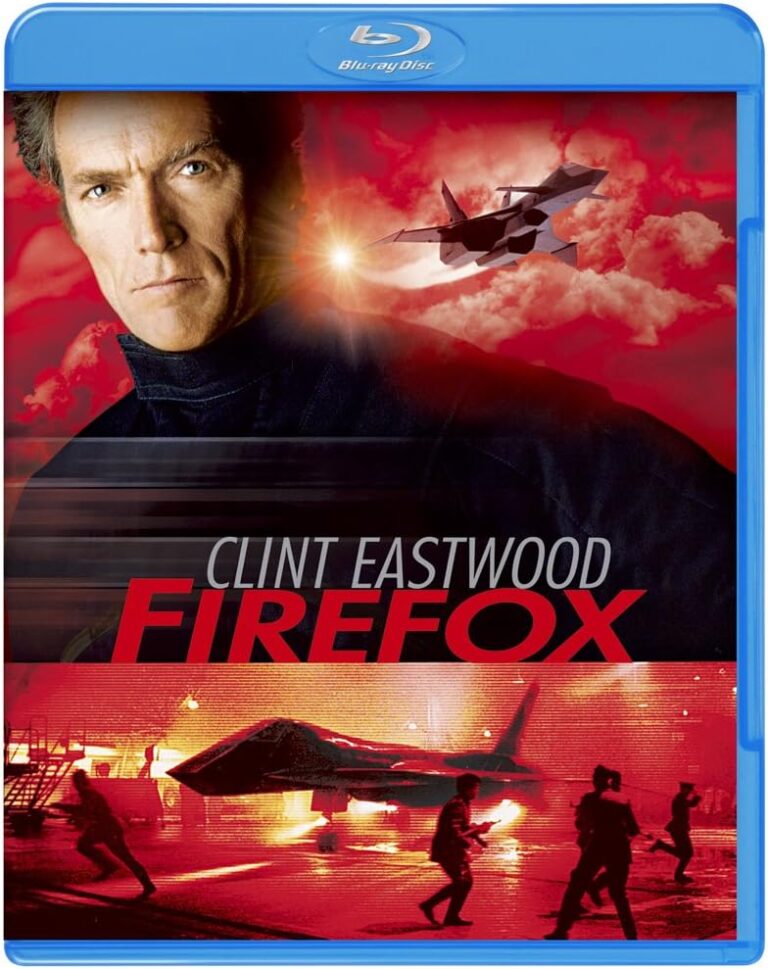『ブルー・ベルベット』(1986)
映画考察・解説・レビュー
『ブルー・ベルベット』(原題:Blue Velvet/1986年)は、デヴィッド・リンチ監督がアメリカ郊外の表と裏を描いたサスペンス映画。青年ジェフリー(カイル・マクラクラン)が草むらで見つけた“切断された耳”をきっかけに、歌手ドロシー(イザベラ・ロッセリーニ)と悪漢フランク(デニス・ホッパー)が支配する闇の世界へと迷い込む。青空とチューリップの牧歌的風景の下で、暴力と欲望が蠢く異形のアメリカが露わになっていく。
郊外神話を切り裂く「耳」
青い空、赤いチューリップ、白いフェンス、そしてロイ・オービンソンの歌う『Blue Velvet』の甘美なメロディー。
『ブルー・ベルベット』(1986年)は、とてつもなく牧歌的な風景から始まる。戦後アメリカが夢見た理想的な郊外生活のステレオタイプを映し出し、幸福と安定を約束するかのような映像美で観客を安心させる。
だがその直後、芝生の中にうごめく虫や切断された耳が映し出され、我々はその幸福像が幻想であることを思い知らされる。リンチは郊外神話を「切り裂かれた耳」という異物で破壊し、アメリカ的幸福の裏に腐敗と暴力が潜んでいることを暴き出すのだ。
「郊外に潜む悪夢」というモチーフは、20世紀以降のアメリカ文化に繰り返し登場してきた。ダグラス・サークの『天はすべて許し給う』(1955年)は理想的家庭の裏に欲望と抑圧を映し出し、サム・メンデスの『アメリカン・ビューティー』(1999年)は白いフェンスと緑の芝生の向こう側に虚無と崩壊を描いた。
絵画では、エドワード・ホッパーが整然とした郊外の家並みに漂う孤独と不安を定着させ、音楽では、ブルース・スプリングスティーンの『Born in the U.S.A.』(1984年)が郊外的幸福のイメージとその裏側にある挫折や不満を歌う。
さらに文学においても、ジョン・チーヴァーやリチャード・ヨーツといった作家たちは、郊外生活の華やかさの奥に潜む倦怠や破綻を描き出している。
つまりリンチの『ブルー・ベルベット』が切り裂いたのは、映画だけでなく、アメリカ文化全体が繰り返し問い続けてきた「郊外の幸福神話」という傷口だったのである。
覗き見の快楽と共犯としての観客
主人公ジェフリー(カイル・マクラクラン)は、切断された耳をきっかけに闇の世界へ足を踏み入れる。ここで重要なのは、彼の行為が単なる探偵的好奇心ではなく「覗き見」という背徳的快楽であることだ。
暗い部屋でカーテンの隙間から他人の秘密を覗き見るジェフリーの姿は、そのままスクリーンを覗き込む観客自身の行為と重なっていく。リンチは「覗いてはいけないものを覗く」衝動を物語の推進力に仕立て、観客に「自分もまた共犯だ」と気づかせるのである。
この仕掛けは映画史的に見れば、ヒッチコックの『裏窓』(1954年)やブライアン・デ・パルマの『ボディ・ダブル』(1984年)といった、覗き見映画(そんなジャンルないけど)の系譜に連なる。
『裏窓』ではカメラマンのジェフ(ジェームズ・スチュワート)が窓越しに隣人の生活を盗み見し、殺人の可能性に気づく。観客は彼と同じ位置に座らされ、覗くことのスリルと罪悪感を同時に味わわされる。
『ボディ・ダブル』では、双眼鏡越しに女性を盗み見る行為がプロットの起点となり、同時に映画という装置そのものが「覗き」のメタファーであることをデ・パルマはあからさまに示す。
リンチは、覗き見映画の伝統を継承しつつも、その快楽をさらに露骨で暴力的な領域へと押し広げた。ヒッチコックがサスペンスと倫理的揺らぎに収めたものを、リンチは性愛と残酷さを交差させてエスカレートさせる。
覗き見はもはや単なる「見てしまった事件」ではなく、観客が自らの欲望と向き合わざるを得ない実存的な問題に転化するのだ。
ヒッチコック的な「犯罪を見抜く視線」と、デ・パルマ的な「映画=覗き装置」という自己言及的な視線。『ブルー・ベルベット』はその両方を内包し、性的快楽と暴力の文脈に組み替えている。
しかもリンチは観客をサスペンスの共犯者にとどめず、彼らの奥底に潜む欲望そのものを暴露してしまう。だからこそ、この映画を観終えたあと、私たちは「覗き込んだのは他人の秘密ではなく、自分自身の暗部だったのではないか」と感じざるを得ないのだ。
光と闇の二重性――二人のファム・ファタール
ジェフリーは二人の女性に出会う。光を象徴するローラ・ダーンと、闇を象徴するイザベラ・ロッセリーニ。ダーン演じる少女は、平和と愛に満ちた未来を夢見て熱弁する。
「突然、たくさんのコマドリたちが舞い降りてきて、愛の光が闇を変えるの…」
この無垢な理想主義は新興宗教めいたヤバさを帯び、観客に違和感を覚えさせる。一方で、ロッセリーニ演じる歌手はデニス・ホッパー演じる悪漢に支配され、暴力と性欲の狭間で崩壊している。
彼女の「Hit me!」というマゾヒスティックな懇願に応じる瞬間、ジェフリーは理性のタガを外し、加虐者としての自分を発見してしまう。だが同時に、彼自身もホッパーに痛めつけられる被虐の立場に追い込まれる。
かくして『ブルー・ベルベット』では、サディズムとマゾヒズム、支配と服従がめまぐるしく反転し、観客に「人間の欲望とは常に矛盾を孕んでいる」ことを突きつける。リンチ作品全体を見渡せば、この「支配と服従」のねじれは繰り返し現れるテーマだ。
『イレイザーヘッド』(1977年)では、主人公が“赤ん坊”のような異形に支配される構図があり、父性を装いながらも、むしろ彼の方が恐怖と責務に従属させられていく。
『ツイン・ピークス』ではローラ・パーマーが一見「犠牲者」として描かれるが、実際には彼女自身が周囲を翻弄し、欲望の磁場を作り出す力を持っている。支配者と被支配者の役割は固定されず、視点を変えるごとに反転していくのだ。
さらに『マルホランド・ドライブ』(2001年)では、恋愛関係の中における服従と支配が濃密に描かれる。夢の中で優位に立っていたベティ(ナオミ・ワッツ)は、現実に戻るとダイアンとして絶望的に従属する側に転落する。愛の関係が権力の関係に転化する瞬間をリンチは鋭利に描写し、支配/服従の揺らぎを「夢と現実の落差」として映し出した。
リンチにとって「支配」とは単純な暴力ではなく、しばしば愛や欲望と表裏一体のものとして現れる。支配する者は同時に自らの欲望に囚われており、服従する者はその関係の中で奇妙な主体性を獲得してしまう。『ブルー・ベルベット』のフランクがロッセリーニ演じるドロシーを支配する一方で、彼自身も快楽と依存の虜囚となっているのと同じ構造だ。
リンチ映画における支配/服従の構図は、権力の一方的な関係を暴露するのではなく、欲望に絡め取られた人間同士の相互依存として描出される。よって観客は加害者にも被害者にも感情移入しきれず、むしろそのねじれそのものの不気味さに囚われてしまうのだ。
リンチはそんな「光と闇」を単純に分け隔てるのではなく、むしろ同一のフレームに共存させる。デニス・ホッパーに殴られるジェフリーの背後でくたびれた娼婦がゴーゴーダンスを踊り、ホッパーは「ママ、ママ」と絶叫しながらロッセリーニを犯す。
甘美なものと暴力的なものが同居する異様な映像は、倫理的な二項対立を無効化し、人間の欲望がいかに雑多で矛盾に満ちているかを可視化している。ローラ・ダーンを愛すると同時にロッセリーニも愛してしまうジェフリーの姿は、まさにその欲望のグレーゾーンを体現している。
そんな異様空間を支えるのは音響だ。ロイ・オービンソンの『Blue Velvet』や『In Dreams』は甘美な旋律の裏に不気味さを忍ばせ、観客を不穏な感情に包み込む。
さらにホッパーが吸うガスの「シュコー」という呼吸音は、性的興奮と死の気配を同時に呼び込み、画面に漂う異常性を強調する。音は単なる背景ではなく、光と闇の境界を可聴化する重要な装置として機能しているのだ。
汚染されたハッピーエンド――帰還の意味
やがて物語は光の世界へと帰還する。ジェフリーは再び郊外の家庭に戻り、平和な日常を取り戻したかに見える。しかしその「光」はもはや純粋ではない。闇を知った後にかろうじて残った、汚染された希望だ。
リンチ流のハッピーエンドは常にアイロニカルで、決して安心を与えない。『ツイン・ピークス』のブラックロッジが示すように、闇は常に日常のすぐ隣に潜んでいるからだ。
光から闇へ、そして再び光へ――しかしその光はもはや穢れなきものではない。闇を受け入れたとき、観客はリンチ・ワールドの住人となり、二度と“表のアメリカ”を無邪気に信じることはできなくなるのだ。

![ブルーベルベット/デヴィッド・リンチ[DVD]](https://popmaster.jp/wp-content/uploads/71RZYNe9mQL._AC_SL1082_-e1754913639259.jpg)